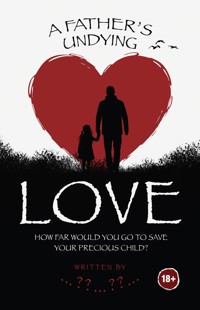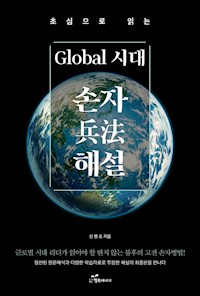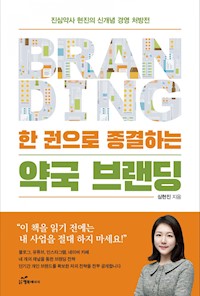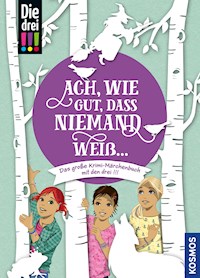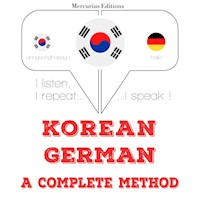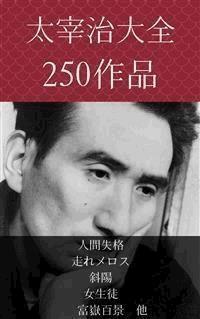
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: micpub.com
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: ja
最新の太宰治の作品を集めた大全です。 太宰治の代表作である人間失格、走れメロス、斜陽、女生徒、富嶽百景などを全て掲載しています。 太宰治の世界をご堪能ください。 「太宰治は、日本の小説家である。自殺未遂や薬物中毒を克服し戦前から戦後にかけて多くの作品を発表。没落した華族の女性を主人公にした『斜陽』はベストセラーとなる。その作風から坂口安吾、織田作之助、石川淳らとともに新戯作派、無頼派と称された。主な作品に『走れメロス』『津軽』『お伽草紙』『人間失格』がある。」 (Wikipediaより抜粋) <掲載作品一覧> 雨の玉川心中 愛と美について 兄たち 青森 老ハイデルベルヒ 『老ハイデルベルヒ』序 或る忠告 朝 あさましきもの 新しい形の個人主義 ア、秋 「晩年」に就いて 「晩年」と「女生徒」 美男子と煙草 美少女 眉山 チャンス 父 小さいアルバム 畜犬談 竹青 地球図 「地球圖」序 千代女 地図 大恩は語らず 断崖の錯覚 男女同権 檀君の近業について 誰 誰も知らぬ ダス・ゲマイネ デカダン抗議 道化の華 貪婪禍 炎天汗談 『富嶽百景』序 富嶽百景 富士に就いて 服装に就いて 不審庵 冬の花火 玩具 『玩具』あとがき 芸術ぎらい 義務 グッド・バイ 「グッド・バイ」作者の言葉 五所川原 逆行 魚服記 魚服記に就て 葉 八十八夜 母 恥 薄明 花火 花吹雪 犯人 春 春の枯葉 春の盗賊 走ラヌ名馬 走れメロス 葉桜と魔笛 碧眼托鉢 返事 皮膚と心 火の鳥 一つの約束 HUMAN LOST 『井伏鱒二選集』後記 一問一答 一日の労苦 田舎者 陰火 一歩前進二歩退却 一燈 I can speak 弱者の糧 人物に就いて 自作を語る 自信の無さ 女類 女生徒 『女性』あとがき 十五年間 十二月八日 純真 貨幣 佳日 駈込み訴え かくめい 鴎 彼は昔の彼ならず 花燭 喝采 かすかな声 家庭の幸福 川端康成へ 風の便り 『風の便り』あとがき 帰去来 金錢の話 禁酒の心 きりぎりす 校長三代 乞食学生 心の王者 國技館 故郷 このごろ 困惑の弁 古典風 古典竜頭蛇尾 九月十月十一月 苦悩の年鑑 黒石の人たち 狂言の神 虚構の春 饗応夫人 郷愁 リイズ 砂子屋 満願 待つ 女神 『女神』あとがき めくら草紙 メリイクリスマス 雌に就いて 未帰還の友に みみずく通信 男女川と羽左衛門 盲人独笑 悶悶日記 文盲自嘲 もの思う葦 無題 無趣味 二十世紀旗手 「人間キリスト記」その他 人間失格 庭 女人訓戒 女人創造 如是我聞 織田君の死 緒方氏を殺した者 黄金風景 思ひ出 『思ひ出』序 同じ星 女の決闘 おさん おしゃれ童子 黄村先生言行録 桜桃 お伽草紙 音に就いて 親という二字 パンドラの匣 『パンドラの匣』あとがき パウロの混乱 フォスフォレッスセンス 懶惰の歌留多 ラロシフコー 令嬢アユ 列車 律子と貞子 六月十九日 ロマネスク ろまん燈籠 『ろまん燈籠』序 佐渡 酒ぎらい 酒の追憶 作家の手帖 作家の像 三月三十日 散華 猿ヶ島 『猿面冠者』あとがき 猿面冠者 正義と微笑 清貧譚 政治家と家庭 世界的 惜別 「惜別」の意圖 先生三人 斜陽 思案の敗北 親友交歓 新樹の言葉 新郎 新ハムレット 新釈諸国噺 失敗園 知らない人 市井喧争 私信 正直ノオト 諸君の位置 食通 小説の面白さ 小志 小照 秋風記 春晝 創作余談 創生記 水仙 雀 雀こ 豊島與志雄著『高尾ざんげ』解説 田中君に就いて 多頭蛇哲学 たずねびと 天狗 鉄面皮 答案落第 トカトントン 東京だより 東京八景 『東京八景』あとがき 燈籠 當選の日 徒党について 津軽 津輕地方とチエホフ 姥捨 『姥捨』あとがき 右大臣実朝 鬱屈禍 海 嘘 ヴィヨンの妻 わが半生を語る わが愛好する言葉 渡り鳥 私の著作集 やんぬる哉 容貌 横綱 雪の夜の話 座興に非ず 善蔵を思う 俗天使
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Guide
表紙
目次
扉
本文
目 次
雨の玉川心中
愛と美について
兄たち
青森
老ハイデルベルヒ
『老ハイデルベルヒ』序
或る忠告
朝
あさましきもの
新しい形の個人主義
ア、秋
「晩年」に就いて
「晩年」と「女生徒」
美男子と煙草
美少女
眉山
チャンス
父
小さいアルバム
畜犬談
竹青
地球図
「地球圖」序
千代女
地図
大恩は語らず
断崖の錯覚
男女同権
檀君の近業について
誰
誰も知らぬ
ダス・ゲマイネ
デカダン抗議
道化の華
貪婪禍
炎天汗談
『富嶽百景』序
富嶽百景
富士に就いて
服装に就いて
不審庵
冬の花火
玩具
『玩具』あとがき
芸術ぎらい
義務
グッド・バイ
「グッド・バイ」作者の言葉
五所川原
逆行
魚服記
魚服記に就て
葉
八十八夜
母
恥
薄明
花火
花吹雪
犯人
春
春の枯葉
春の盗賊
走ラヌ名馬
走れメロス
葉桜と魔笛
碧眼托鉢
返事
皮膚と心
火の鳥
一つの約束
HUMAN LOST
『井伏鱒二選集』後記
一問一答
一日の労苦
田舎者
陰火
一歩前進二歩退却
一燈
I can speak
弱者の糧
人物に就いて
自作を語る
自信の無さ
女類
女生徒
『女性』あとがき
十五年間
十二月八日
純真
貨幣
佳日
駈込み訴え
かくめい
鴎
彼は昔の彼ならず
花燭
喝采
かすかな声
家庭の幸福
川端康成へ
風の便り
『風の便り』あとがき
帰去来
金錢の話
禁酒の心
きりぎりす
校長三代
乞食学生
心の王者
國技館
故郷
このごろ
困惑の弁
古典風
古典竜頭蛇尾
九月十月十一月
苦悩の年鑑
黒石の人たち
狂言の神
虚構の春
饗応夫人
郷愁
リイズ
砂子屋
満願
待つ
女神
『女神』あとがき
めくら草紙
メリイクリスマス
雌に就いて
未帰還の友に
みみずく通信
男女川と羽左衛門
盲人独笑
悶悶日記
文盲自嘲
もの思う葦
無題
無趣味
二十世紀旗手
「人間キリスト記」その他
人間失格
庭
女人訓戒
女人創造
如是我聞
織田君の死
緒方氏を殺した者
黄金風景
思ひ出
『思ひ出』序
同じ星
女の決闘
おさん
おしゃれ童子
黄村先生言行録
桜桃
お伽草紙
音に就いて
親という二字
パンドラの匣
『パンドラの匣』あとがき
パウロの混乱
フォスフォレッスセンス
懶惰の歌留多
ラロシフコー
令嬢アユ
列車
律子と貞子
六月十九日
ロマネスク
ろまん燈籠
『ろまん燈籠』序
佐渡
酒ぎらい
酒の追憶
作家の手帖
作家の像
三月三十日
散華
猿ヶ島
『猿面冠者』あとがき
猿面冠者
正義と微笑
清貧譚
政治家と家庭
世界的
惜別
「惜別」の意圖
先生三人
斜陽
思案の敗北
親友交歓
新樹の言葉
新郎
新ハムレット
新釈諸国噺
失敗園
知らない人
市井喧争
私信
正直ノオト
諸君の位置
食通
小説の面白さ
小志
小照
秋風記
春晝
創作余談
創生記
水仙
雀
雀こ
豊島與志雄著『高尾ざんげ』解説
田中君に就いて
多頭蛇哲学
たずねびと
天狗
鉄面皮
答案落第
トカトントン
東京だより
東京八景
『東京八景』あとがき
燈籠
當選の日
徒党について
津軽
津輕地方とチエホフ
姥捨
『姥捨』あとがき
右大臣実朝
鬱屈禍
海
嘘
ヴィヨンの妻
わが半生を語る
わが愛好する言葉
渡り鳥
私の著作集
やんぬる哉
容貌
横綱
雪の夜の話
座興に非ず
善蔵を思う
俗天使
雨の玉川心中
遺書
太宰治・山崎富栄
私ばかりしあわせな死に方をしてすみません。奥名とすこし長い生活ができて、愛情でもふえてきましたらこんな結果ともならずにすんだかもわかりません。山崎の姓に返ってから死にたいと願っていましたが……、骨は本当は太宰さんのお隣りにでも入れて頂ければ本望なのですけれど、それは余りにも虫のよい願いだと知っております。太宰さんと初めてお目もじしたとき他に二、三人のお友達と御一緒でいらっしゃいましたが、お話を伺っておりますときに私の心にピンピン触れるものがありました。奥名以上の愛情を感じてしまいました。御家庭を持っていらっしゃるお方で私も考えましたけれど、女として生き女として死にとうございます。あの世へ行ったら太宰さんの御両親様にも御あいさつしてきっと信じて頂くつもりです。愛して愛して治さんを幸せにしてみせます。
せめてもう一、二年生きていようと思ったのですが、妻は夫と共にどこ迄も歩みとうございますもの。ただ御両親のお悲しみと今後が気掛りです。
(注・この遺書は昭和二十二年八月二十九日付となっている)
永いあいだ、いろいろと身近く親切にして下さいました。忘れません。おやじにも世話になった。おまえたち夫婦は、商売をはなれて僕たちにつくして下さった。お金のことは石井に
泣いたり笑ったり、みんな御存知のこと、末までおふたりとも御身大切に、あとのこと御ねがいいたします。誰もおねがい申し上げるかたがございません。あちらこちらから、いろいろなおひとが、みえると思いますが、いつものように、おとりなし下さいまし。
このあいだ、拝借しました着物、まだ水洗いもしてございませんの。おゆるし下さいまし、着物と共にありますお薬は、胸の病いによいもので、石井さんから太宰さんがお求めになりましたもの、御使用下さいませ。田舎から父母が上京いたしましたら、どうぞ、よろしくおはなし下さいませ。勝手な願いごと、おゆるし下さいませ。
お部屋に重要なもの、置いてございます。おじさま、奥様、お開けになって、野川さんと御相談下さいまして、暫くのあいだおあずかり下さいまし。それから、父と、姉に、それから、お友達に(ウナ電)お知らせ下さいまし。
姉 神奈川県鎌倉市長谷通り二五六
マ・ソアール美容院友達
本郷区森川町九〇底本:「雨の玉川心中」真善美研究所
1977(昭和52)年6月13日初版発行
※表題、副題は、底本編集時に与えられたものです。
※底本巻末の編者による注記は省略しました。
※(注・)ではじまる注記は編集部によるものです。
※底本巻末の編者による語注は省略しました。
入力:江村秀之
校正:酒井和郎
2017年4月3日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
愛と美について
太宰治
兄妹、五人あって、みんなロマンスが好きだった。長男は二十九歳。法学士である。ひとに接するとき、少し尊大ぶる悪癖があるけれども、これは彼自身の弱さを庇かばう鬼の面めんであって、まことは弱く、とても優しい。弟妹たちと映画を見にいって、これは駄作だ、愚劣だと言いながら、その映画のさむらいの義理人情にまいって、まず、まっさきに泣いてしまうのは、いつも、この長兄である。それにきまっていた。映画館を出てからは、急に尊大に、むっと不気嫌になって、みちみち一言も口をきかない。生れて、いまだ一度も嘘言うそというものをついたことがないと、躊躇ちゅうちょせず公言している。それは、どうかと思われるけれど、しかし、剛直、潔白の一面は、たしかに具有していた。学校の成績は、あまりよくなかった。卒業後は、どこへも勤めず、固く一家を守っている。イプセンを研究している。このごろ人形の家をまた読み返し、重大な発見をして、頗すこぶる興奮した。ノラが、あのとき恋をしていた。お医者のランクに恋をしていたのだ。それを発見した。弟妹たちを呼び集めて、そのところを指摘し、大声叱咤しった、説明に努力したが、徒労であった。弟妹たちは、どうだか、と首をかしげて、にやにや笑っているだけで、一向に興奮の色を示さぬ。いったいに、弟妹たちは、この兄を甘く見ている。なめている風ふうがある。長女は、二十六歳。いまだ嫁がず、鉄道省に通勤している。フランス語が、かなりよくできた。脊丈せたけが、五尺三寸あった。すごく、痩やせている。弟妹たちに、馬、と呼ばれることがある。髪を短く切って、ロイド眼鏡をかけている。心が派手で、誰とでもすぐ友達になり、一生懸命に奉仕して、捨てられる。それが、趣味である。憂愁、寂寥せきりょうの感を、ひそかに楽しむのである。けれどもいちど、同じ課に勤務している若い官吏に夢中になり、そうして、やはり捨てられたときには、そのときだけは、流石さすがに、しんからげっそりして、間まの悪さもあり、肺が悪くなったと嘘をついて、一週間も寝て、それから頸くびに繃帯ほうたいを巻いて、やたらに咳せきをしながら、お医者に見せに行ったら、レントゲンで精細にしらべられ、稀まれに見る頑強の肺臓であるといって医者にほめられた。文学鑑賞は、本格的であった。実によく読む。洋の東西を問わない。ちから余って自分でも何やら、こっそり書いている。それは本箱の右の引き出しに隠して在る。逝去せいきょ二年後に発表のこと、と書き認したためられた紙片が、その蓄積された作品の上に、きちんと載せられているのである。二年後が、十年後と書き改められたり、二カ月後と書き直されたり、ときには、百年後、となっていたりするのである。次男は、二十四歳。これは、俗物であった。帝大の医学部に在籍。けれども、あまり学校へは行かなかった。からだが弱いのである。これは、ほんものの病人である。おどろくほど、美しい顔をしていた。吝嗇りんしょくである。長兄が、ひとにだまされて、モンテエニュの使ったラケットと称する、へんてつもない古ぼけたラケットを五十円に値切って買って来て、得々とくとくとしていたときなど、次男は、陰でひとり、余りの痛憤に、大熱を発した。その熱のために、とうとう腎臓じんぞうをわるくした。ひとを、どんなひとをも、蔑視べっししたがる傾向が在る。ひとが何かいうと、けッという奇怪な、からす天狗てんぐの笑い声に似た不愉快きわまる笑い声を、はばからず発するのである。ゲエテ一点張りである。これとても、ゲエテの素朴な詩精神に敬服しているのではなく、ゲエテの高位高官に傾倒しているらしい、ふしが、無いでもない。あやしいものである。けれども、兄妹みんなで、即興の詩など、競作する場合には、いつでも一ばんである。できている。俗物だけに、謂いわば情熱の客観的把握はあくが、はっきりしている。自身その気で精進すれば、あるいは一流作家になれるかも知れない。この家の、足のわるい十七の女中に、死ぬほど好かれている。次女は、二十一歳。ナルシッサスである。ある新聞社が、ミス・日本を募っていたとき、あのときには、よほど自己推薦しようかと、三夜身悶みもだえした。大声あげて、わめき散らしたかった。けれども、三夜の身悶えの果、自分の身長が足りないことに気がつき、断念した。兄妹のうちで、ひとり目立って小さかった。四尺七寸である。けれども、決して、みっともないものではなかった。なかなかである。深夜、裸形で鏡に向い、にっと可愛く微笑してみたり、ふっくらした白い両足を、ヘチマコロンで洗って、その指先にそっと自身で接吻して、うっとり眼をつぶってみたり、いちど、鼻の先に、針で突いたような小さい吹出物して、憂鬱のあまり、自殺を計ったことがある。読書の撰定に特色がある。明治初年の、佳人之奇遇、経国美談などを、古本屋から捜して来て、ひとりで、くすくす笑いながら読んでいる。黒岩涙香るいこう、森田思軒しけんなどの、飜訳物をも、好んで読む。どこから手に入れて来るのか、名の知れぬ同人雑誌をたくさん集めて、面白いなあ、うまいなあ、と真顔で呟つぶやきながら、端から端まで、たんねんに読破している。ほんとうは、鏡花をひそかに、最も愛読していた。末弟は、十八歳である。ことし一高の、理科甲類に入学したばかりである。高等学校へはいってから、かれの態度が俄然がぜんかわった。兄たち、姉たちには、それが可笑おかしくてならない。けれども末弟は、大まじめである。家庭内のどんなささやかな紛争にでも、必ず末弟は、ぬっと顔を出し、たのまれもせぬのに思案深げに審判を下して、これには、母をはじめ一家中、閉口している。いきおい末弟は、一家中から敬遠の形である。末弟には、それが不満でならない。長女は、かれのぶっとふくれた不気嫌の顔を見かねて、ひとりでは大人おとなになった気でいても、誰も大人と見ぬぞかなしき、という和歌を一首つくって末弟に与え、かれの在野遺賢の無聊ぶりょうをなぐさめてやった。顔が熊の子のようで、愛くるしいので、きょうだいたちが、何かとかれにかまいすぎて、それがために、かれは多少おっちょこちょいのところがある。探偵小説を好む。ときどきひとり部屋の中で、変装してみたりなどしている。語学の勉強と称して、和文対訳のドイルのものを買って来て、和文のところばかり読んでいる。きょうだい中で、母のことを心配しているのは自分だけだと、ひそかに悲壮の感に打たれている。
父は、五年まえに死んでいる。けれども、くらしの不安はない。要するに、いい家庭だ。ときどき皆、一様におそろしく退屈することがあるので、これには閉口である。きょうは、曇天、日曜である。セルの季節で、この陰鬱の梅雨が過ぎると、夏がやって来るのである。みんな客間に集って、母は、林檎りんごの果汁をこしらえて、五人の子供に飲ませている。末弟ひとり、特別に大きいコップで飲んでいる。
退屈したときには、皆で、物語の連作をはじめるのが、この家のならわしである。たまには母も、そのお仲間入りすることがある。
「何か、無いかねえ。」長兄は、尊大に、あたりを見まわす。「きょうは、ちょっと、ふうがわりの主人公を出してみたいのだが。」
「老人がいいな。」次女は、卓の上に頬杖ほおづえついて、それも人さし指一本で片頬を支えているという、どうにも気障きざな形で、「ゆうべ私は、つくづく考えてみたのだけれど、」なに、たったいま、ふと思いついただけのことなのである。「人間のうちで、一ばんロマンチックな種属は老人である、ということがわかったの。老婆は、だめ。おじいさんで無くちゃ、だめ。おじいさんが、こう、縁側にじっとして坐っていると、もう、それだけで、ロマンチックじゃないの。素晴らしいわ。」
「老人か。」長兄は、ちょっと考える振りをして、「よし、それにしよう。なるべく、甘い愛情ゆたかな、綺麗きれいな物語がいいな。こないだのガリヴァ後日物語は、少し陰惨すぎた。僕は、このごろまた、ブランドを読み返しているのだが、どうも肩が凝る。むずかしすぎる。」率直に白状してしまった。
「僕にやらせて下さい。僕に、」ろくろく考えもせず、すぐに大声あげて名乗り出たのは末弟である。がぶがぶ大コップの果汁を飲んで、やおら御意見開陳。「僕は、僕は、こう思いますねえ。」いやに、老成ぶった口調だったので、みんな苦笑した。次兄も、れいのけッという怪しい笑声を発した。末弟は、ぶうっとふくれて、
"「僕は、そのおじいさんは、きっと大数学者じゃないか、と思うのです。きっと、そうだ。偉い数学者なんだ。もちろん博士さ。世界的なんだ。いまは、数学が急激に、どんどん変っているときなんだ。過渡期が、はじまっている。世界大戦の終りごろ、一九二〇年ごろから今日まで、約十年の間にそれは、起りつつある。」きのう学校で聞いて来たばかりの講義をそのまま口真似してはじめるのだから、たまったものでない。「数学の歴史も、振りかえって見れば、いろいろ時代と共に変遷して来たことは確かです。まず、最初の段階は、微積分学の発見時代に相当する。それからがギリシャ伝来の数学に対する広い意味の近代的数学であります。こうして新しい領分が開けたわけですから、その開けた直後は高まるというよりも寧むしろ広まる時代、拡張の時代です。それが十八世紀の数学であります。十九世紀に移るあたりに、矢張りかかる階段があります。すなわち、この時も急激に変った時代です。一人の代表者を選ぶならば、例えば Gauss. g、a、u、ssです。急激に、どんどん変化している時代を過渡期というならば、現代などは、まさに大過渡期であります。」てんで、物語にもなんにもなってやしない。それでも末弟は、得意である。調子が出て来た、と内心ほくほくしている。「やたらに煩瑣はんさで、そうして定理ばかり氾濫はんらんして、いままでの数学は、完全に行きづまっている。一つの暗記物に堕してしまった。このとき、数学の自由性を叫んで敢然立ったのは、いまのその、おじいさんの博士であります。えらいやつなんだ。もし探偵にでもなったら、どんな奇怪な難事件でも、ちょっと現場を一まわりして、たちまちぽんと、解決してしまうにちがいない。そんな頭のいい、おじいさんなのだ。とにかく、Cantor の言うたように、」また、はじまった。「数学の本質は、その自由性に在る。たしかに、そうだ。自由性とは、Freiheit の訳です。日本語では、自由という言葉は、はじめ政治的の意味に使われたのだそうですから、Freiheit の本来の意味と、しっくり合わないかも知れない。Freiheit とは、とらわれない、拘束されない、素朴のものを指していうのです。frei でない例は、卑近な所に沢山あるが、多すぎてかえって挙げにくい。たとえば、僕のうちの電話番号はご存じの通り4823ですが、この三桁けたと四桁けたの間に、コンマをいれて、4,823と書いている。巴里パリのように48 | 23とすれば、まだしも少しわかりよいのに、何でもかでも三桁けたおきにコンマを附けなければならぬ、というのは、これはすでに一つの囚とらわれであります。老博士はこのようなすべての陋習ろうしゅうを打破しようと、努めているのであります。えらいものだ。真なるもののみが愛すべきものである、とポアンカレが言っている。然り。真なるものを、簡潔に、直接とらえ来ったならば、それでよい。それに越したことがない。」もう、物語も何もあったものでない。きょうだいたちも、流石に顔を見合せて、閉口している。末弟は、更にがくがくの論を続ける。「空論をお話して一向とりとめがないけれど、それは恐縮でありますが、丁度このごろ解析概論をやっているので、ちょっと覚えているのですが、一つの例として級数についてお話したい。二重もしくは、二重以上の無限級数の定義には、二種類あるのではないか、と思われる。画を書いてお目にかけると、よくわかるのですが、謂わば、フランス式とドイツ式と二つある。結果は同じ様なことになるのだが、フランス式のほうは、すべての人に納得の行くように、いかにも合理的な立場である。けれども、いまの解析の本すべてが、不思議に、言い合せたように、平気でドイツ式一方である。伝統というものは、何か宗教心をさえ起させるらしい。数学界にも、そろそろこの宗教心がはいりこんで来ている。これは、絶対に排撃しなければならない。老博士は、この伝統の打破に立ったわけであります。」意気いよいよあがった。みんなは、一向に面白くない。末弟ひとり、まさにその老博士の如くふるいたって、さらにがくがくの論をつづける。"
「このごろでは、解析学の始めに集合論を述べる習慣があります。これについても、不審があります。たとえば、絶対収斂しゅうれんの場合、昔は順序に無関係に和が定るという意味に用いられていました。それに対して条件的という語がある。今では、絶対値の級数が収斂する意味に使うのです。級数が収斂し、絶対値の級数が収斂しないときには項の順序をかえて、任意の limit に tend させることができるということから、絶対値の級数が収斂しなければならぬということになるから、それでいいわけだ。」少し、あやしくなって来た。心細い。ああ、僕の部屋の机の上に、高木先生の、あの本が載せてあるんだがなあ、と思っても、いまさら、それを取りに行って来るわけにもゆくまい。あの本には、なんでも皆、書かれて在るんだけれど、いまは泣きたくなって、舌もつれ、胴ふるえて、悲鳴に似たかん高い声を挙げ、
「要するに。」きょうだいたちは、みな一様にうつむいて、くすと笑った。
「要するに、」こんどは、ほとんど泣き声である。「伝統、ということになりますると、よほどのあやまちも、気がつかずに見逃してしまうが、問題は、微細なところに沢山あるのです。もっと自由な立場で、極く初等的な万人むきの解析概論の出ることを、切に、希望している次第であります。」めちゃめちゃである。これで末弟の物語は、終ったのである。
座が少し白けたほどである。どうにも、話の、つぎほが無かった。皆、まじめになってしまった。長女は、思いやりの深い子であるから、末弟のこの失敗を救済すべく、噴き出したいのを我慢して、気を押し沈め、しずかに語った。
「ただいまお話ございましたように、その老博士は、たいへん高邁こうまいのお志を持って居られます。高邁のお志には、いつも逆境がつきまといます。これは、もう、絶対に正確の定理のようでございます。老博士も、やはり世に容れられず、奇人よ、変人よ、と近所のひとたちに言われて、ときどきは、流石に侘わびしく、今夜もひとり、ステッキ持って新宿へ散歩に出ました。夏のころの、これは、お話でございます。新宿は、たいへんな人出ひとででございます。博士は、よれよれの浴衣に、帯を胸高むなだかにしめ、そうして帯の結び目を長くうしろに、垂れさげて、まるで鼠の尻尾しっぽのよう、いかにもお気の毒の風采ふうさいでございます。それに博士は、ひどい汗かきなのに、今夜は、ハンカチを忘れて出て来たので、いっそう惨めなことになりました。はじめは掌てのひらで、お顔の汗を拭い払って居りましたが、とてもそんなことで間に合うような汗ではございませぬ。それこそ、まるで滝のよう、額から流れ落ちる汗は、一方は鼻筋を伝い、一方はこめかみを伝い、ざあざあ顔中を洗いつくして、そうしてみんな顎あごを伝って胸に滑り込み、その気持のわるさったら、ちょうど油壺あぶらつぼ一ぱいの椿油つばきあぶらを頭からどろどろ浴びせかけられる思いで、老博士も、これには参ってしまいました。とうとう浴衣の袖で、素早く顔の汗を拭い、また少し歩いては、人に見つからぬよう、さっと袖で拭い拭いしているうちに、もう、その両袖ながら、夕立に打たれたように、びしょ濡れになってしまいました。博士は、もともと無頓着むとんじゃくなお方でございましたけれども、このおびただしい汗には困惑しちゃいまして、ついに一軒のビヤホールに逃げ込むことに致しました。ビヤホールにはいって、扇風器のなまぬるい風に吹かれていたら、それでも少し、汗が収りました。ビヤホールのラジオは、そのとき、大声で時局講話をやっていました。ふと、その声に耳をすまして考えてみると、どうも、これは聞き覚えのある声でございます。あいつでは無いかな? と思っていたら、果して、その講話のおわりにアナウンサアが、その、あいつの名前を、閣下という尊称を附して報告いたしました。老博士は、耳を洗いすすぎたい気持になりました。その、あいつというのは、博士と高等学校、大学、ともにともに、机を並べて勉強して来た男なのですが、何かにつけて要領よく、いまは文部省の、立派な地位にいて、ときどき博士も、その、あいつと、同窓会などで顔を合せることがございまして、そのたびごとに、あいつは、博士を無用に嘲弄ちょうろうするのでございます。気のきかない、げびた、ちっともなっていない陳腐な駄洒落だじゃれを連発して、取り巻きのものもまた、可笑しくもないのに、手を拍うたんばかりに、そのあいつの一言一言に笑い興じて、いちどは博士も、席を蹴けって憤然と立ちあがりましたが、そのとき、卓上から床にころげ落ちて在った一箇の蜜柑みかんをぐしゃと踏みつぶして、おどろきの余り、ひッという貧乏くさい悲鳴を挙げたので、満座抱腹絶倒して、博士のせっかくの正義の怒りも、悲しい結果になりました。けれども、博士は、あきらめません。いつかは、あいつを、ぶんなぐるつもりで居ります。そいつの、いやな、だみ声を、たったいまラジオで聞いて、博士は、不愉快でたまりませぬ。ビイルを、がぶ、がぶ、飲みました。もともと博士は、お酒には、あまり強いほうでは、ございません。たちまち酩酊めいていいたしました。辻占売つじうらうりの女の子が、ビヤホールにはいって来ました。博士は、これ、これ、と小さい声で、やさしく呼んで、おまえ、としはいくつだい? 十三か。そうか。すると、もう五年、いや、四年、いや三年たてば、およめに行けますよ。いいかね。十三に三を足せば、いくつだ。え? などと、数学博士も、酔うと、いくらかいやらしくなります。少し、しつこく女の子を、からかいすぎたので、とうとう博士は、女の子の辻占を買わなければならない仕儀にたちいたりました。博士は、もともと迷信を信じません。けれども今夜は、先刻のラジオのせいもあり、気が弱っているところもございましたので、ふいとその辻占で、自分の研究、運命の行く末をためしてみたくなりました。人は、生活に破れかけて来ると、どうしても何かの予言に、すがりつきたくなるものでございます。悲しいことでございます。その辻占は、あぶり出し式になって居ります。博士はマッチの火で、とろとろ辻占の紙を焙あぶり、酔眼をかっと見ひらいて、注視しますと、はじめは、なんだか模様のようで、心もとなく思われましたが、そのうちに、だんだん明確に、古風な字体の、ひら仮名が、ありありと紙に現われました。読んでみます。
おのぞみどおり
博士は莞爾かんじと笑いました。いいえ、莞爾どころではございませぬ。博士ほどのお方が、えへへへと、それは下品な笑い声を発して、ぐっと頸を伸ばしてあたりの酔客を見廻しましたが、酔客たちは、格別相手になっては呉くれませぬ。それでも博士は、意に介しなさることなく、酔客ひとりひとりに、はは、おのぞみどおり、へへへへ、すみません、ほほほ、なぞと、それは複雑な笑い声を、若々しく笑いわけ、撒まきちらして皆に挨拶いたし、いまは全く自信を恢復かいふくなされて、悠々とそのビヤホールをお出ましになりました。
外はぞろぞろ人の流れ、たいへんでございます。押し合い、へし合い、みんな一様に汗ばんで、それでもすまして、歩いています。歩いていても、何ひとつ、これという目的は無いのでございますが、けれども、みなさん、その日常が侘びしいから、何やら、ひそかな期待を抱懐していらして、そうして、すまして夜の新宿を歩いてみるのでございます。いくら、新宿の街を行きつ戻りつ歩いてみても、いいことは、ございませぬ。それは、もうきまって居ります。けれども幸福は、それをほのかに期待できるだけでも、それは幸福なのでございます。いまのこの世の中では、そう思わなければ、なりませぬ。老博士は、ビヤホールの廻転ドアから、くるりと排出され、よろめき、その都会の侘びしい旅雁りょがんの列に身を投じ、たちまち、もまれ押されて、泳ぐような恰好で旅雁と共に流れて行きます。けれども、今夜の老博士は、この新宿の大群衆の中で、おそらくは一ばん自信のある人物なのでございます。幸福をつかむ確率が最も大きいのでございます。博士は、ときどき、思い出しては、にやにや笑い、また、ひとり、ひそかにこっくり首肯して、もっともらしく眉を上げて吃きっとなってみたり、あるいは全くの不良青少年のように、ひゅうひゅう下手な口笛をこころみたりなどして歩いているうちに、どしんと、博士にぶつかった学生があります。けれども、それは、あたりまえです。こんな人ごみでは、ぶつかるのがあたりまえでございます。なんということもございません。学生は、そのまま通りすぎて行きます。しばらくして、また、どしんと博士にぶつかった美しい令嬢があります。けれども、これもあたりまえです。こんな混雑では、ぶつかるのは、あたりまえのことでございます。なんということも、ございませぬ。令嬢は、通りすぎて行きます。幸福は、まだまだ、おあずけでございます。変化は、背後から、やって来ました。とんとん、博士の脊中を軽く叩いたひとがございます。こんどは、ほんとう。」
長女は伏目がちに、そこまで語って、それからあわてて眼鏡をはずし、ハンケチで眼鏡の玉をせっせと拭きはじめた。これは、長女の多少てれくさい思いのときに、きっとはじめる習癖である。
次男が、つづけた。
「どうも、僕には、描写が、うまくできんので、──いや、できんこともないが、きょうは、少しめんどうくさい。簡潔に、やってしまいましょう。」生意気である。「博士が、うしろを振りむくと、四十ちかい、ふとったマダムが立って居ります。いかにも奇妙な顔の、小さい犬を一匹だいている。
ふたりは、こんな話をした。
──御幸福?
──ああ、仕合せだ。おまえがいなくなってから、すべてが、よろしく、すべてが、つまり、おのぞみどおりだ。
──ちぇっ、若いのをおもらいになったんでしょう?
──わるいかね。
──ええ、わるいわ。あたしが犬の道楽さえ、よしたら、いつでも、また、あなたのところへ帰っていいって、そうちゃんと約束があったじゃないの。
──よしてやしないじゃないか。なんだ、こんどの犬は、またひどいじゃないか。これは、ひどいね。蛹さなぎでも食って生きているような感じだ。妖怪ようかいじみている。ああ、胸がわるい。
──そんなにわざわざ蒼あおい顔して見せなくたっていいのよ。ねえ、プロや。おまえの悪口言ってるのよ。吠えて、おやり。わん、と言って吠えておやり。
──よせ、よせ。おまえは、相変らず厭味いやみな女だ。おまえと話をしていると、私は、いつでも脊筋が寒い。プロ。なにがプロだ。も少し気のきいた名前を、つけんかね。無智だ。たまらん。
──いいじゃないの。プロフェッサアのプロよ。あなたを、おしたい申しているのよ。いじらしいじゃないの。
──たまらん。
──おや、おや。やっぱり、お汗が多いのねえ。あら、お袖なんかで拭いちゃ、みっともないわよ。ハンケチないの? こんどの奥さん、気がきかないのね。夏の外出には、ハンケチ三枚と、扇子、あたしは、いちどだってそれを忘れたことがない。
──神聖な家庭に、けちをつけちゃ困るね。不愉快だ。
──おそれいります。ほら、ハンケチ、あげるわよ。
──ありがとう。借りて置きます。
──すっかり、他人におなりなすったのねえ。
──別れたら、他人だ。このハンケチ、やっぱり昔のままの、いや、犬のにおいがするね。
──まけおしみ言わなくっていいの。思い出すでしょう? どう?
──くだらんことを言うな。たしなみの無い女だ。
──あら、どっちが? やっぱり、こんどの奥さんにも、あんなに子供みたいに甘えかかっていらっしゃるの? およしなさいよ、いいとしをして、みっともない。きらわれますよ。朝、寝たまま足袋をはかせてもらったりして。
──神聖な家庭に、けちをつけちゃ、こまるね。私は、いま、仕合せなんだからね。すべてが、うまくいっている。
──そうして、やっぱり、朝はスウプ? 卵を一つ入れるの? 二つ入れるの?
──二つだ。三つのときもある。すべて、おまえのときより、豊富だ。どうも、私は、いまになって考えてみるに、おまえほど口やかましい女は、世の中に、そんなに無いような気がする。おまえは、どうして私を、あんなにひどく叱ったのだろう。私は、わが家にいながら、まるで居候いそうろうの気持だった。三杯目には、そっと出していた。それは、たしかだ。私は、あのじぶんには、ずいぶん重大な研究に着手していたんだぜ。おまえには、そんなこと、ちっともわかってやしない。ただ、もう、私のチョッキのボタンがどうのこうの煙草の吸殻がどうのこうの、そんなこと、朝から晩まで、がみがみ言って、おかげで私は、研究も何も、めちゃめちゃだ。おまえとわかれて、たちどころに私は、チョッキのボタンを全部、むしり取ってしまって、それから煙草の吸殻を、かたっぱしから、ぽんぽんコーヒー茶碗にほうりこんでやった。あれは、愉快だった。実に、痛快であった。ひとりで、涙の出るほど、大笑いした。私は、考えれば、考えるほど、おまえには、ひどいめにあっていたのだ。あとから、あとから、腹が立つ。いまでも、私は、充分に怒っている。おまえは、いったいに、ひとをいたわることを知らない女だ。
──すみません。あたし、若かったのよ。かんにんしてね。もう、もう、あたし、判ったわ。犬なんか、問題じゃなかったのね。
──また、泣く。おまえは、いつでも、その手を用いた。だが、もう、だめさ。私は、いま、万事が、おのぞみどおりなのだからね。どこかで、お茶でも飲むか。
──だめ。あたし、いま、はっきり、わかったわ。あなたと、あたしは、他人なのね。いいえ、むかしから他人なのよ。心の住んでいる世界が、千里も万里も、はなれていたのよ。一緒にいたって、お互い不幸の思いをするだけよ。もう、きれいにおわかれしたいの。あたし、ね、ちかく神聖な家庭を持つのよ。
──うまく行きそうかね。
──大丈夫。そのかたは、ね、職工さんよ。職工長。そのかたがいなければ、工場の機械が動かないんですって。大きい、山みたいな感じの、しっかりした方かた。
──私とは、ちがうね。
──ええ、学問は無いの。研究なんか、なさらないわ。けれども、なかなか、腕がいいの。
──うまく行くだろう。さようなら。ハンケチ借りて置くよ。
──さようなら。あ、帯がほどけそうよ。むすんであげましょう。ほんとうに、いつまでも、いつまでも、世話を焼かせて。……奥さんに、よろしくね。
──うん。機会があれば、ね。」
次男は、ふっと口をつぐんだ。そうして、けッと自嘲した。二十四歳にしては、流石に着想が大人おとなびている。
「あたし、もう、結末が、わかっちゃった。」次女は、したり顔して、あとを引きとる。「それは、きっと、こうなのよ。博士が、そのマダムとわかれてから、沛然はいぜんと夕立ち。どうりで、むしむし暑かった。散歩の人たちは、蜘蛛くもの子を散らすように、ぱあっと飛び散り、どこへどう消え失せたのか、お化けみたい、たったいままで、あんなにたくさん人がいたのに、須臾しゅゆにして、巷ちまたは閑散、新宿の舗道には、雨あしだけが白くしぶいて居りました。博士は、花屋さんの軒下に、肩をすくめて小さくなって雨宿りしています。ときどき、先刻のハンケチを取り出して、ちょっと見て、また、あわてて、袂たもとにしまいこみます。ふと、花を買おうか、と思います。お宅で待っていらっしゃる奥さんへ、お土産に持って行けば、きっと、奥さんが、よろこんでくれるだろうと思いました。博士が、花を買うなど、これは、全く、生れてはじめてのことでございます。今夜は、ちょっと調子が変なの。ラジオ、辻占、先夫人、犬、ハンケチ、いろいろのことがございました。博士は、花屋へ、たいへんな決意を以もって突入して、それから、まごつき、まごつき、大汗かいて、それでも、薔薇ばらの大輪、三本買いました。ずいぶん高いのには、おどろきました。逃げるようにして花屋から躍り出て、それから、円タク拾って、お宅へ、まっしぐら。郊外の博士のお宅には、電燈が、あかあかと灯って居ります。たのしいわが家や。いつも、あたたかく、博士をいたわり、すべてが、うまくいって居ります。玄関へはいるなり、
──ただいま! と大きい声で言って、たいへんなお元気です。家の中は、しんとして居ります。それでも、博士は、委細かまわず、花束持って、どんどん部屋へ上っていって、奥の六畳の書斎へはいり、
──ただいま。雨にやられて、困ったよ。どうです。薔薇の花です。すべてが、おのぞみどおり行くそうです。
机の上に飾られて在る写真に向って、話かけているのです。先刻、きれいにわかれたばかりのマダムの写真でございます。いいえ、でも、いまより十年わかいときの写真でございます。美しく微笑ほほえんでいました。」まず、ざっと、こんなものだ、と言わぬばかりに、ナルシッサスは、再び、人さし指で気障な頬杖やらかして、満座をきょろと眺め渡した。
「うん。だいたい、」長兄は、もったいぶって、「そんなところで、よろしかろう。けれども、──」長兄は、長兄としての威厳を保っていなければならぬ。長兄は、弟妹たちに較べて、あまり空想力は、豊富でなかった。物語は、いたって下手くそである。才能が、貧弱なのである。けれども、長兄は、それ故に、弟妹たちから、あなどられるのも心外でならぬ。必ず、最後に、何か一言、蛇足だそくを加える。「けれども、だね、君たちは、一つ重要な点を、語り落している。それは、その博士の、容貌についてである。」たいしたことでもなかった。「物語には容貌が、重大である。容貌を語ることに依って、その主人公に肉体感を与え、また聞き手に、その近親の誰かの顔を思い出させ、物語全体に、インチメートな、ひとごとでない思いを抱かせることができるものです。僕の考えるところに依れば、その老博士は、身長五尺二寸、体重十三貫弱、たいへんな小男である。容貌について言うなれば、額は広く高く、眉は薄く、鼻は小さく、口が大きくひきしまり、眉間みけんに皺しわ、白い頬ひげは、ふさふさと伸び、銀ぶちの老眼鏡をかけ、まず、丸顔である。」なんのことはない、長兄の尊敬しているイプセン先生の顔である。長兄の想像力は、このように他愛がない。やはり、蛇足の感があった。
これで物語が、すんだのであるが、すんだ、とたんに、また、かれらは、一層すごく、退屈した。ひとつの、ささやかな興奮のあとに来る、倦怠けんたい、荒涼、やりきれない思いである。兄妹五人、一ことでも、ものを言い出せば、すぐに殴り合いでもはじまりそうな、険悪な気まずさに、閉口し切った。
母は、ひとり離れて坐って、兄妹五人の、それぞれの性格のあらわれている語りかたを、始終にこにこ微笑んで、たのしみ、うっとりしていたのであるが、このとき、そっと立って障子をあけ、はっと顔色かえて、
「おや。家の門のところに、フロック着たへんなおじいさん立っています。」
兄妹五人、ぎょっとして立ち上った。
母は、ひとり笑い崩れた。
底本:「新樹の言葉」新潮文庫、新潮社
1982(昭和57)年7月25日初版発行
1992(平成4)年11月15日17刷
初出:「愛と美について」竹村書房
1939(昭和14)年5月
入力:田中久太郎
校正:鈴木厚司
2001年11月1日公開
2016年2月1日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
兄たち
太宰治
父がなくなったときは、長兄は大学を出たばかりの二十五歳、次兄は二十三歳、三男は二十歳、私が十四歳でありました。兄たちは、みんな優しく、そうして大人びていましたので、私は、父に死なれても、少しも心細く感じませんでした。長兄を、父と全く同じことに思い、次兄を苦労した伯父さんの様に思い、甘えてばかりいました。私が、どんなひねこびた我儘わがままいっても、兄たちは、いつも笑って許してくれました。私には、なんにも知らせず、それこそ私の好きなように振舞わせて置いてくれましたが、兄たちは、なかなか、それどころでは無く、きっと、百万以上はあったのでしょう、その遺産と、亡父の政治上の諸勢力とを守るのに、眼に見えぬ努力をしていたにちがいありませぬ。たよりにする伯父さんというような人も無かったし、すべては、二十五歳の長兄と、二十三歳の次兄と、力を合せてやって行くより他に仕方がなかったのでした。長兄は、二十五歳で町長さんになり、少し政治の実際を練習して、それから三十一歳で、県会議員になりました。全国で一ばん若年の県会議員だったそうで、新聞には、A県の近衛このえ公とされて、漫画なども出てたいへん人気がありました。
長兄は、それでも、いつも暗い気持のようでした。長兄の望みは、そんなところに無かったのです。長兄の書棚には、ワイルド全集、イプセン全集、それから日本の戯曲家の著書が、いっぱい、つまって在りました。長兄自身も、戯曲を書いて、ときどき弟妹たちを一室に呼び集め、読んで聞かせてくれることがあって、そんな時の長兄の顔は、しんから嬉しそうに見えました。私は幼く、よくわかりませんでしたけれど、長兄の戯曲は、たいてい、宿命の悲しさをテエマにしているような気がいたしました。なかでも、「奪い合い」という長編戯曲に就ついては私は、いまでも、その中の人物の表情までも、はっきり思い出すことができるのであります。
長兄が三十歳のとき、私たち一家で、「青んぼ」という可笑おかしな名前の同人雑誌を発行したことがあります。そのころ美術学校の塑像そぞう科に在籍中だった三男が、それを編輯へんしゅういたしました。
「青んぼ」という名前も、三男がひとりで考案して得意らしく、表紙も、その三男が画かいたのですけれども、シュウル式の出鱈目でたらめのもので、銀粉をやたらに使用した、わからない絵でありました。長兄は、創刊号に随筆を発表しました。
「めし」という題で、長兄が、それを私に口述筆記させました。いまでも覚えて居ります。二階の西洋間で、長兄は、両手をうしろに組んで天井を見つめながら、ゆっくり歩きまわり、
「いいかね、いいかね、はじめるぞ。」
「はい。」
「おれは、ことし三十になる。孔子は、三十にして立つ、と言ったが、おれは、立つどころでは無い。倒れそうになった。生き甲斐がいを、身にしみて感じることが無くなった。強いて言えば、おれは、めしを食うとき以外は、生きていないのである。ここに言う『めし』とは、生活形態の抽象でもなければ、生活意慾の概念でもない。直接に、あの茶碗一ぱいのめしのことを指して言っているのだ。あのめしを噛かむ、その瞬間の感じのことだ。動物的な、満足である。下品な話だ。……」
私は、未だ中学生であったけれども、長兄のそんな述懐を、せっせと筆記しながら、兄を、たまらなく可哀想に思いました。A県の近衛公だなぞと無智なおだてかたはしても、兄のほんとうの淋しさは、誰も知らないのだと思いました。
次兄は、この創刊号には、何も発表なさらなかったようですが、この兄は、谷崎潤一郎の初期からの愛読者でありました。それから、また、吉井勇の人柄を、とても好いていました。次兄は、酒にも強く、親分気質の豪快な心を持っていて、けれども、決して酒に負けず、いつでも長兄の相談相手になって、まじめに物事を処理し、謙遜な人でありました。そうしてひそかに、吉井勇の、「紅燈に行きてふたたび帰らざる人をまことのわれと思ふや。」というような鬱勃うつぼつの雄心を愛して居られたのではないかと思われます。いつか鳩はとに就いての随筆を、地方の新聞に発表して、それに次兄の近影も掲載されて在りましたがその時、どうだ、この写真で見ると、おれも、ちょっとした文士だね、吉井勇に似ているね、と冗談に威張って見せました。顔も、左団次みたいな、立派な顔をしていました。長兄の顔は、線が細く、松蔦しょうちょうのようだと、これも家中の評判でありました。ふたり共、それをちゃんと意識していて、お酒に酔ったとき、掛合いで左団次松蔦の鳥辺山とりべやま心中や皿屋敷などの声色を、はじめることさえ、たまにはありました。
そんなとき、二階の西洋間のソファにひとり寝ころんで、遠く兄たち二人の声色を聞き、けッと毒笑しているのが、三男でありました。この兄は美術学校にはいっていたのですが、からだが弱いので、あまり塑像のほうへは精を出さず、小説に夢中になって居りました。文学の友だちもたくさんあって、その友人たちと「十字街」という同人雑誌を発行し、ご自身は、その表紙の絵をかいたり、また、たまには「苦笑に終る」などという淡彩の小説を書いて発表したりしていました。夢川利一という筆名だったので、兄や姉たちは、ひどい名前だといって閉口し、笑っていました。RIICHI UMEKAWA とロオマ字でもって印刷した名刺を作らせ、少し気取って私にも一枚くださいましたが、読んでみると、リイチ・ウメカワとなっているので、私まで、ひやっとして、兄さんは、ユメカワでしょう? わざと、こう刷らせたの? とたずねたら、兄は、
「やあ、しまった。おれは、ウメカワじゃ無いんだ。」と言って、顔を真赤になさいました。もう、名刺を、友人や先輩、または馴染なじみの喫茶店に差し上げてしまっていたのです。印刷所の手落ちでは無く、兄がちゃんと UMEKAWA と指定してやったものらしく、uという字を、英語読みにユウと読んでしまうことは、誰でも犯し易い間違いであります。家中、いよいよ大笑いになって、それからは私の家では、梅川先生だの、忠兵衛先生だのと呼ばれるようになりました。この兄は、からだが弱くて、十年まえ、二十八歳で死にました。顔が、不思議なくらい美しく、そのころ姉たちが読んでいた少女雑誌に、フキヤ・コウジとかいう人の画いた、眼の大きい、からだの細い少女の口絵が毎月出ていましたけれど、兄の顔は、あの少女の顔にそっくりで、私は時々ぼんやり、その兄の顔を眺めていて、ねたましさでは無く、へんにくすぐったいような楽しさを感じていました。
性質はまじめな、たいへん厳格で律儀なものをさえ、どこかに隠し持っていましたが、それでも趣味として、むかしフランスに流行したとかいう粋紳士風プレッシュウ、または鬼面毒笑風ビュルレスクを信奉している様子らしく、むやみやたらに人を軽蔑し、孤高を装って居りました。長兄は、もう結婚していて、当時、小さい女の子がひとり生れていましたが、夏休みになると、東京から、A市から、H市から、ほうぼうの学校から、若い叔父や叔母が家へ帰って来て、それが皆一室に集り、おいで東京の叔父さんのとこへ、おいでA叔母さんのとこへ、とわいわい言って小さい姪めいひとりを奪い合うのですけれど、そんなときには、この兄は、みんなから少し離れて立っていて、なんだ、まだ赤いじゃないか、気味がわるい、などと、生れたばかりの小さい姪の悪口を言い、それから、仕方なさそうに、ちょっと両手を差し伸べ、おいでフランスの叔父さんのとこへ、と言うのでした。また、晩ごはんのときには、ひとり、ひとりお膳に向って坐り、祖母、母、長兄、次兄、三兄、私という順序に並び、向う側は、帳場さん、嫂あによめ、姉たちが並んで、長兄と次兄は、夏、どんなに暑いときでも日本酒を固執し、二人とも、その傍に大型のタオルを用意させて置いて、だらだら流れる汗を、それでもって拭い拭い熱燗あつかんのお酒を呑みつづけるのでした。ふたりで毎晩一升以上も呑むようでしたが、どちらも酒に強いので、座の乱れるようなことは、いちどもありませんでした。三兄は、決してそのお仲間に加わらず、知らんふりして自分の席に坐って、凝こったグラスに葡萄酒をひとりで注いで颯さっと呑みほし、それから大急ぎでごはんをすまして、ごゆっくり、と真面目にお辞儀して、もう掻かき消すように、いなくなってしまいます。とても、水際立ったものでした。
「青んぼ」という雑誌を発行したときも、この兄は編輯長という格で、私に言いつけて、一家中から、あれこれと原稿を集めさせ、そうして集った原稿を読んでは、けッと毒笑していました。私が、やっと、長兄から「めし」という随筆を、口述筆記させてもらって、編輯長のところへ少し得意で呈出したら、編輯長はそれを読むなりけッと笑って、
「なんだいこれは。号令口調というんだね。孔子曰いわく、はひどいね。」と、さんざ悪口言いました。ちゃんと長兄の侘わびしさを解していながら、それでも自身の趣味のために、いつも三兄は、こんな悪口を言うのでした。人の作品を、そんなに悪く言いながら、この兄ご自身の作品は、どうかということになれば、そうなると、なんだか心細いものでした。この「青んぼ」という変な名前の雑誌の創刊号には、編輯長は自重して小説を発表せず、叙情詩を二篇、発表いたしましたが、どうも、それは、いま、いくら考えてみても傑作とは思えないものなのであります。あの、兄ともあろうお人が、どうしてこんなものを発表する気になったか、私は、いまは残念にさえ思います。甚はなはだ、書きにくいのでありますが、それは、こんな詩なのであります。「あかいカンナ」というのと、「矢車の花いとし」というのと、二つでありますが、前者は「あかいカンナの花でした。私の心に似ています。云々。」なんだか、とても、書きにくい思いなのですが、後者は、「矢車の花いとし。一つ、二つ、三つ、私のたもとに入れました。云々。」というのであります。どういうものでしょうか。やはり、之これは、大事に筐底きょうてい深く蔵して置いたほうが、よかったのでは無かったかと、私は、あのお洒落しゃれな粋いき紳士の兄のために、いまになって、そう思うのでありますが、当時は、私は兄の徹底したビュルレスクを尊敬し、それに東京の「十字街」というかなり有名らしい同人雑誌の仲間ではあり、それにまた兄には、その詩がとても自慢のものらしく、町の印刷所で、その詩の校正をしながら、「あかいカンナの花でした。私の心に似ています。」と、変な節をつけて歌い出す仕末なので、私にもなんだか傑作のような気がして参ったのであります。この「青んぼ」という雑誌については、いろいろと、なつかしく、また噴き出すような思い出が、あるのですけれど、きょうは、なんだか、めんどうくさく、この三番目の兄が、なくなった頃の話をして、それでおわかれ致したく思います。
この兄は、なくなる二、三年まえから、もう寝たり起きたりでありました。結核菌が、からだのあちこちを虫食いはじめていたのでした。それでも、ずいぶん元気で、田舎にもあまり帰りたがらず、入院もせず、戸山が原のちかくに一軒、家を借りて、同郷のWさん夫婦にその家の一間にはいってもらって、あとの部屋は全部、自分で使って、のんきに暮していました。私は、高等学校へはいってからは、休暇になっても田舎へ帰らず、たいてい東京の戸塚の、兄の家へ遊びに行って、そうして兄と一緒に東京のまちを歩きまわりました。兄は、ずいぶん嘘をつきました。銀座を歩きながら、
「あッ、菊池寛だ。」と小さく叫んで、ふとったおじいさんを指さします。とても、まじめな顔して、そういうのですから、私も、信じないわけには、いかなかったのです。銀座の不二屋でお茶を飲んでいたときにも、肘ひじで私をそっとつついて、佐々木茂索がいるぞ、そら、おまえのうしろのテエブルだ、と小声で言って教えてくれたことがありますけれど、ずっとあとになって、私が直接、菊池先生や佐々木さんにお目にかかり、兄が私に嘘ばかり教えていたことを知りました。兄の所蔵の「感情装飾」という川端康成氏の短篇集の扉には、夢川利一様、著者、と毛筆で書かれて在って、それは兄が、伊豆かどこかの温泉宿で川端さんと知り合いになり、そのとき川端さんから戴いただいた本だ、ということになっていたのですが、いま思えば、これもどうだか、こんど川端さんにお逢いしたとき、お伺いしてみようと思って居ります。ほんとうであって、くれたらいいと思います。けれども私が川端さんから戴いているお手紙の字体と、それから思い出の中の、夢川利一様、著者、という字体とは、少し違うようにも思われるのです。兄は、いつでも、無邪気に人を、かつぎます。まったく油断が、できないのです。ミステフィカシオンが、フランスのプレッシュウたちの、お道楽の一つであったそうですから、兄にも、やっぱり、この神秘捏造ミステフィカシオンの悪癖が、争われなかったのであろうと思います。
兄がなくなったのは、私が大学へはいったとしの初夏でありましたが、そのとしのお正月には、応接室の床の間に自筆の掛軸を飾りました。半折に、「この春は、仏心なども出で、酒もあり、肴さかなもあるをよろこばぬなり。」と書かれていて、訪問客は、みんな大笑いして、兄もにやにや笑っていましたが、それは、れいの兄のミステフィカシオンでは無く、本心からのものだったのでしょうけれど、いつも、みんなを、かつぐものだから、訪問客たちも、ただ笑って、兄のいのちを懸念しようとはしないのでした。兄は、やがて小さい珠数じゅずを手首にはめて歩いて、そうして自分のことを、愚僧、と呼称することを案出しました。愚僧は、愚僧は、とまじめに言うので、兄のお友だちも、みんな真似して、愚僧は、愚僧は、と言い合い、一時は大流行いたしました。兄にとっては、ただ冗談だけでそんなことをしていたのでは無く、自身の肉体消滅の日時が、すぐ間近に迫っていることを、ひそかに知っていて、けれども兄の鬼面毒笑風の趣味が、それを素直に悲しむことを妨げ、かえって懸命に茶化して、しさいらしく珠数を爪繰つまぐっては人を笑わせ、愚僧もあの婦人には心が乱れ申したわい、お恥かしいが、まだ枯れて居らん証拠じゃのう、などと言い、私たちを誘って、高田の馬場の喫茶店へ蹌踉そうろうと乗り込むのでした。この愚僧は、たいへんおしゃれで、喫茶店へ行く途中、ふっと、指輪をはめて出るのを忘れて来たことに気がつき、躊躇ちゅうちょなくくるりと廻れ右して家へ引きかえし、そうしてきちんと指輪をはめて、出直し、やあ、お待ちどおさま、と澄ましていました。
私は大学へはいってからは、戸塚の、兄の家のすぐ近くの下宿屋に住み、それでも、お互い勉強の邪魔をせぬよう、三日にいちどか、一週間にいちど顔を合せて、そのときには必ず一緒にまちへ出て、落語を聞いたり、喫茶店をまわって歩いたりして、そのうちに兄は、ささやかな恋をしました。兄は、その粋紳士風の趣味のために、おそろしく気取ってばかりいて、女のひとには、さっぱり好かれないようでした。そのころ高田の馬場の喫茶店に、兄が内心好いている女の子がありましたが、あまり旗色がよくないようで、兄は困って居りました。それでも、兄は誇プライドの高いお人でありますから、その女の子に、いやらしい色目を使ったり、下等にふざけたりすることは絶対にせず、すっとはいって、コーヒー一ぱい飲んで、すっと帰るということばかり続けて居りました。或る晩、私とふたりで、その喫茶店へ行き、コーヒー一ぱい飲んで、やっぱり旗色がわるく、そのまま、すっと帰って、その帰途、兄は、花屋へ寄ってカーネーションと薔薇ばらとを組合せた十円ちかくの大きな花束をこしらえさせ、それを抱えて花屋から出て、何だかもじもじしていましたので、私には兄の気持が全部わかり、身を躍らしてその花束をひったくり脱兎だっとの如くいま来た道を駈け戻り喫茶店の扉かげに、ついと隠れて、あの子を呼びました。
「おじさん(私は兄を、そう呼んでいました。)を知ってるだろう? おじさんを忘れちゃいけない。はい、これはおじさんから。」口早に言って花束を手渡してやっても、あの子はぼんやりしていますので、私は、矢庭にあの子をぶん殴りたく思いました。私まで、すっかり元気がなくなり、それから、ぶらぶら兄の家へ行ってみましたら、兄は、もうベッドにもぐっていて、なんだか、ひどく不機嫌でした。兄は、そのとき、二十八歳でした。私は六つ下の二十二歳でありました。
そのとしの、四月ごろから、兄は異常の情熱を以もって、制作を開始いたしました。モデルを家に呼んで、大きいトルソオに取りかかった様子でありました。私は、兄の仕事の邪魔をしたくないので、そのころは、あまり兄の家を訪ねませんでした。いつか夜、ちょっと訪ねてみたら兄は、ベッドにもぐっていて、少し頬が赤く、「もう夢川利一なんて名前は、よすことにした。堂々、辻馬桂治(兄の本名)でやってみるつもりだ。」と兄にしては、全く珍らしく、少しも茶化さず、むきになって言って聞かせましたので、私は急に泣きそうになりました。
それから、二月ふたつき経って、兄は仕事を完成させずに死んでしまいました。様子が変だとWさん御夫妻も言い、私も、そう思いましたので、かかりのお医者に相談してみましたら、もう四五日とお医者は平気で言うので、私は仰天いたしました。すぐに、田舎の長兄へ電報を打ちました。長兄が来るまでは、私が兄の傍に寝て二晩、のどにからまる痰たんを指で除去してあげました。長兄が来て、すぐに看護婦を雇い、お友だちもだんだん集り、私も心強くなりましたが、長兄が見えるまでの二晩は、いま思っても地獄のような気がいたします。暗い電気の下で兄は、私にあちこちの引き出しをあけさせ、いろいろの手紙や、ノオトブックを破り棄てさせ、私が、言いつけられたとおり、それをばりばり破りながらめそめそ泣いているのを、兄は不思議そうに眺めているのでした。私は、世の中に、たった私たち二人しかいないような気がいたしました。
長兄や、お友だちに、とりかこまれて、息をひきとるまえに、私が、
「兄さん!」と呼ぶと、兄は、はっきりした言葉で、ダイヤのネクタイピンとプラチナの鎖があるから、おまえにあげるよ、と言いました。それは嘘なのです。兄は、きっと死ぬる際まで、粋紳士風プレッシュウの趣味を捨てず、そんなはいからのこと言って、私をかつごうとしていたのでしょう。無意識に、お得意の神秘捏造ミステフィカシオンをやっていたのでありましょう。ダイヤのネクタイピンなど、無いのを私は知って居りますので、なおのこと、兄の伊達だての気持ちが悲しく、わあわあ泣いてしまいました。なんにも作品残さなかったけれど、それでも水際立って一流の芸術家だったお兄さん。世界で一ばんの美貌を持っていたくせに、ちっとも女に好かれなかったお兄さん。
死んだ直後のことも、あれこれ書いてお知らせするつもりでありましたが、ふと考えてみれば、そんな悲しさは、私に限らず、誰だって肉親に死なれたときには味うものにちがいないので、なんだか私の特権みたいに書き誇るのは、読者にすまないことみたいで、気持ちが急に萎縮いしゅくしてしまいました。ケイジ、ケサ四ジ、セイキョセリ。という電文を、田舎の家にあてて頼信紙に書きしたためながら、当時三十三歳の長兄が、何を思ったか、急に手放しで慟哭どうこくをはじめたその姿が、いまでも私の痩せひからびた胸をゆすぶります。父に早く死なれた兄弟は、なんぼうお金はあっても、可哀想なものだと思います。
底本:「太宰治全集3」ちくま文庫、筑摩書房
1988(昭和63)年10月25日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月刊行
入力:柴田卓治
校正:小林繁雄
1999年11月10日公開
2005年10月23日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
青森
太宰治
青森には、四年いました。青森中学に通っていたのです。親戚の豊田様のお家に、ずっと世話になっていました。寺町の呉服屋の、豊田様であります。豊田の、なくなった「お父どさ」は、私にずいぶん力こぶを入れて、何かとはげまして下さいました。私も、「おどさ」に、ずいぶん甘えていました。
「おどさ」は、いい人でした。私が馬鹿な事ばかりやらかして、ちっとも立派な仕事をせぬうちになくなって、残念でなりません。もう五年、十年生きていてもらって、私が多少でもいい仕事をして、お父どさに喜んでもらいたかった、とそればかり思います。いま考えると「おどさ」の有難いところばかり思い出され、残念でなりません。私が中学校で少しでも佳よい成績をとると、おどさは、世界中の誰よりも喜んで下さいました。
私が中学の二年生の頃、寺町の小さい花屋に洋画が五、六枚かざられていて、私は子供心にも、その画に少し感心しました。そのうちの一枚を、二円で買いました。この画はいまにきっと高くなります、と生意気な事を言って、豊田の「おどさ」にあげました。おどさは笑っていました。あの画は、今も豊田様のお家に、あると思います。いまでは百円でも安すぎるでしょう。棟方志功氏の、初期の傑作でした。
棟方志功氏の姿は、東京で時折、見かけますが、あんまり颯爽さっそうと歩いているので、私はいつでも知らぬ振りをしています。けれども、あの頃の志功氏の画は、なかなか佳かったと思っています。もう、二十年ちかく昔の話になりました。豊田様のお家の、あの画が、もっと、うんと、高くなってくれたらいいと思って居ります。
底本:「もの思う葦」新潮文庫、新潮社
1980(昭和55)年9月25日発行
1998(平成10)年10月15日39刷
入力:蒋龍
校正:土屋隆
2006年11月15日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
老ハイデルベルヒ
太宰治
八年まえの事でありました。当時、私は極めて懶惰らんだな帝国大学生でありました。一夏を、東海道三島の宿で過したことがあります。五十円を故郷の姉から、これが最後だと言って、やっと送って戴いただき、私は学生鞄かばんに着更の浴衣ゆかたやらシャツやらを詰め込み、それを持ってふらと、下宿を立ち出で、そのまま汽車に乗りこめばよかったものを、方角を間違え、馴染なじみのおでんやにとびこみました。其処そこには友達が三人来合わせて居ました。やあ、やあ、めかして何処どこへ行くのだと、既に酔っぱらっている友人達は、私をからかいました。私は気弱く狼狽ろうばいして、いや何処ということもないんだけど、君たちも、行かないかね、と心にも無い勧誘がふいと口から辷すべり出て、それからは騎虎きこの勢で、僕にね、五十円あるんだ、故郷の姉から貰ったのさ、これから、みんなで旅行に出ようよ、なに、仕度なんか要らない、そのままでいいじゃないか、行こう、行こう、とやけくそになり、しぶる友人達を引張るようにして連れ出してしまいました。あとは、どうなることか、私自身にさえわかりませんでした。あの頃は私も、随分、呑気のんきなところのある子供でした。世の中も亦また、私達を呑気に甘えさせてくれていました。私は、三島に行って小説を書こうと思って居たのでした。三島には高部佐吉さんという、私より二つ年下の青年が酒屋を開いて居たのです。佐吉さんの兄さんは沼津で大きい造酒屋を営み、佐吉さんは其その家の末っ子で、私とふとした事から知合いになり、私も同様に末弟であるし、また同様に早くから父に死なれている身の上なので、佐吉さんとは、何かと話が合うのでした。佐吉さんの兄さんとは私も逢ったことがあり、なかなか太っ腹の佳い方かただし、佐吉さんは家中の愛を独占して居るくせに、それでも何かと不平が多い様で、家を飛出し、東京の私の下宿へ、にこにこ笑ってやって来た事もありました。さまざま駄々をこねて居たようですが、どうにか落ち附き、三島の町はずれに小ぢんまりした家を持ち、兄さんの家の酒樽さかだるを店に並べ、酒の小売を始めたのです。二十歳の妹さんと二人で住んで居ました。私は、其の家へ行くつもりであったのです。佐吉さんから、手紙で様子を聞いているだけで、まだ其の家を見た事も無かったので、行ってみて具合が悪いようだったらすぐ帰ろう、具合がいいようだったら一夏置いて貰って、小説を一篇書こう、そう思って居たのでありましたが、心ならずも三人の友人を招待してしまったので、私は、とにかく三島迄の切符を四枚買い、自信あり気に友人達を汽車に乗せたものの、さてこんなに大勢で佐吉さんの小さい酒店に御厄介になっていいものかどうか、汽車の進むにつれて私の不安は増大し、そのうちに日も暮れて、三島駅近くなる頃には、あまりの心細さに全身こまかにふるえ始め、幾度となく涙ぐみました。私は自身のこの不安を、友人に知らせたくなかったので、懸命に佐吉さんの人柄の良さを語り、三島に着いたらしめたものだ、三島に着いたらしめたものだと、自分でもイヤになる程、その間の抜けた無意味な言葉を幾度も幾度も繰返して言うのでした。あらかじめ佐吉さんに電報を打って置いたのですが、はたして三島の駅に迎えに来てくれて居るかどうか、若もし迎えに来て居てくれなかったら、私は此この三人の友人を抱えて、一体どうしたらいいでしょう。私の面目は、まるつぶれになるのではないでしょうか。三島駅に降りて改札口を出ると、構内はがらんとして誰も居りませぬ。ああ、やはり駄目だ。私は泣きべそかきました。駅は田畑の真中に在って、三島の町の灯さえ見えず、どちらを見廻しても真暗闇、稲田を撫なでる風の音がさやさや聞え、蛙かえるの声も胸にしみて、私は全く途方にくれました。佐吉さんでも居なければ、私にはどうにも始末がつかなかったのです。汽車賃や何かで、姉から貰った五十円も、そろそろ減って居りますし、友人達には勿論もちろん持合せのある筈はずは無し、私がそれを承知で、おでんやからそのまま引張り出して来たのだし、そうして友人達は私を十分に信用している様子なのだから、いきおい私も自信ある態度を装わねばならず、なかなか苦しい立場でした。無理に笑って私は、大声で言いました。
「佐吉さん、呑気だなあ。時間を間違えたんだよ。歩くよりほかは無い。この駅にはもとからバスも何も無いのだ。」と知ったかぶりして鞄を持直し、さっさと歩き出したら、其のとき、闇のなかから、ぽっかり黄色いヘッドライトが浮び、ゆらゆらこちらへ泳いで来ます。
「あ、バスだ。今は、バスもあるのか。」と私はてれ隠しに呟つぶやき、「おい、バスが来たようだ。あれに乗ろう!」と勇んで友人達に号令し、みな道端に寄って並び立ち、速力の遅いバスを待って居ました。やがてバスは駅前の広場に止り、ぞろぞろ人が降りて、と見ると佐吉さんが白浴衣ゆかた着てすまして降りました。私は、唸うなるほどほっとしました。
佐吉さんが来たので、助かりました。その夜は佐吉さんの案内で、三島からハイヤーで三十分、古奈温泉に行きました。三人の友人と、佐吉さんと、私と五人、古奈でも一番いい方の宿屋に落ちつき、いろいろ飲んだり、食べたり、友人達も大いに満足の様子で、あくる日東京へ、有難う、有難うと朗らかに言って帰って行きました。宿屋の勘定も佐吉さんの口利きで特別に安くして貰い、私の貧しい懐中からでも十分に支払うことが出来ましたけれど、友人達に帰りの切符を買ってやったら、あと、五十銭も残りませんでした。
「佐吉さん。僕、貧乏になってしまったよ。君の三島の家には僕の寝る部屋があるかい。」
佐吉さんは何も言わず、私の背中をどんと叩きました。そのまま一夏を、私は三島の佐吉さんの家で暮しました。三島は取残された、美しい町であります。町中を水量たっぷりの澄んだ小川が、それこそ蜘蛛くもの巣のように縦横無尽に残る隈くまなく駈けめぐり、清冽の流れの底には水藻みずもが青々と生えて居て、家々の庭先を流れ、縁の下をくぐり、台所の岸をちゃぷちゃぷ洗い流れて、三島の人は台所に座ったままで清潔なお洗濯が出来るのでした。昔は東海道でも有名な宿場であったようですが、だんだん寂さびれて、町の古い住民だけが依怙地いこじに伝統を誇り、寂れても派手な風習を失わず、謂いわば、滅亡の民の、名誉ある懶惰に耽っている有様でありました。実に遊び人が多いのです。佐吉さんの家の裏に、時々糶市せりいちが立ちますが、私もいちど見に行って、つい目をそむけてしまいました。何でも彼でも売っちゃうのです。乗って来た自転車を、其のまま売り払うのは、まだよい方で、おじいさんが懐からハアモニカを取り出して、五銭に売ったなどは奇怪でありました。古い達磨だるまの軸物、銀鍍金メッキの時計の鎖、襟垢えりあかの着いた女の半纏はんてん、玩具の汽車、蚊帳かや、ペンキ絵、碁石、鉋かんな、子供の産衣うぶぎまで、十七銭だ、二十銭だと言って笑いもせずに売り買いするのでした。集る者は大抵四十から五十、六十の相当年輩の男ばかりで、いずれは道楽の果、五合の濁酒が欲しくて、取縋とりすがる女房子供を蹴飛ばし張りとばし、家中の最後の一物まで持ち込んで来たという感じでありました。或いは又、孫のハアモニカを、爺じいに借せと騙だまして取上げ、こっそり裏口から抜け出し、あたふた此こ所こへやって来たというような感じでありました。珠数じゅずを二銭に売り払った老爺ろうやもありました。わけてもひどいのは、半分ほどきかけの、女の汚れた袷あわせをそのまま丸めて懐へつっこんで来た頭の禿はげた上品な顔の御隠居でした。殆ほとんど破れかぶれに其の布を、(もはや着物ではありません。)拡げて、さあ、なんぼだ、なんぼだと自嘲の笑を浮べながら値を張らせて居ました。頽廃たいはいの町なのであります。町へ出て飲み屋へ行っても、昔の、宿場のときのままに、軒の低い、油障子を張った汚い家でお酒を頼むと、必ずそこの老主人が自らお燗かんをつけるのです。五十年間お客にお燗をつけてやったと自慢して居ました。酒がうまいもまずいも、すべてお燗のつけよう一つだと意気込んで居ました。としよりがその始末なので、若い者は尚なおの事、遊び馴れて華奢きゃしゃな身体をして居ます。毎日朝から、いろいろ大小の与太者が佐吉さんの家に集ります。佐吉さんは、そんなに見掛けは頑丈でありませんが、それでも喧嘩けんかが強いのでしょうか、みんな佐吉さんに心服しているようでした。私が二階で小説を書いて居ると、下のお店で朝からみんながわあわあ騒いでいて、佐吉さんは一際高い声で、
「なにせ、二階の客人はすごいのだ。東京の銀座を歩いたって、あれ位の男っぷりは、まず無いね。喧嘩もやけに強くて、牢に入ったこともあるんだよ。唐手からてを知って居るんだ。見ろ、この柱を。へこんで居るずら。これは、二階の客人がちょいとぶん殴って見せた跡だよ。」と、とんでも無い嘘を言って居ます。私は、頗すこぶる落ちつきません。二階から降りて行って梯子段はしごだんの上り口から小声で佐吉さんを呼び、
「あんな出鱈目でたらめを言ってはいけないよ。僕が顔を出されなくなるじゃないか。」そう口を尖らせて不服を言うと、佐吉さんはにこにこ笑い、
「誰も本気に聞いちゃ居ません。始めから嘘だと思って聞いて居るのですよ。話が面白ければ、きゃつら喜んで居るんです。」
「そうかね。芸術家ばかり居るんだね。でもこれからは、あんな嘘はつくなよ。僕は落ちつかないんだ。」そう言い捨てて又二階へ上り、其の「ロマネスク」という小説を書き続けて居ると、又も、佐吉さんの一際高い声が聞えて、
「酒が強いと言ったら、何と言ったって、二階の客人にかなう者はあるまい。毎晩二合徳利で三本飲んで、ちょっと頬っぺたが赤くなる位だ。それから、気軽に立って、おい佐吉さん、銭湯へ行こうよと言い出すのだから、相当だろう。風呂へ入って、悠々と日本剃刀かみそりで髯ひげを剃そるんだ。傷一つつけたことが無い。俺の髯まで、時々剃られるんだ。それで帰って来たら、又一仕事だ。落ちついたもんだよ。」
これも亦また、嘘であります。毎晩、私が黙って居ても、夕食のお膳に大きい二合徳利がつけてあって、好意を無にするのもどうかと思い、私は大急ぎで飲むのでありますが、何せ醸造元から直接持って来て居るお酒なので、水など割ってある筈は無し、頗る純粋度が高く、普通のお酒の五合分位に酔うのでした。佐吉さんは自分の家のお酒は飲みません。兄貴が造こしらえて不当の利益を貪むさぼって居るのを、此の眼で見て知って居ながら、そんな酒とても飲まれません。げろが出そうだ、と言って、お酒を飲むときは、外へ出てよその酒を飲みます。佐吉さんが何も飲まないのだから、私一人で酔っぱらって居るのも体裁ていさいが悪く、頭がぐらぐらして居ながらも、二合飲みほしてすぐに御飯にとりかかり、御飯がすんでほっとする間もなく、佐吉さんが風呂へ行こうと私を誘うのです。断るのも我儘わがままのような気がして、私も、行こうと応じて、連れ立って銭湯へ出かけるのです。私は風呂へ入って呼吸が苦しく死にそうになります。ふらふらして流し場から脱衣場へ逃れ出ようとすると、佐吉さんは私を掴つかまえ、髯がのびて居ます。剃ってあげましょう、と親切に言って下さるので、私は又も断り切れず、ええ、お願いします、と頼んでしまうのでした。くたくたになり、よろめいて家へ帰り、ちょっと仕事をしようかな、と呟いて二階へ這い上り、そのまま寝ころんで眠ってしまうのであります。佐吉さんだって、それを知って居るに違いないのに、何だってあんな嘘の自慢をしたのでしょう。三島には、有名な三島大社があります。年に一度のお祭は、次第に近づいて参りました。佐吉さんの店先に集って来る若者達も、それぞれお祭の役員であって、様々の計画を、はしゃいで相談し合って居ました。踊り屋台、手古舞、山車だし、花火、三島の花火は昔から伝統のあるものらしく、水花火というものもあって、それは大社の池の真中で仕掛花火を行い、その花火が池面に映り、花火がもくもく池の底から涌わいて出るように見える趣向になって居るのだそうであります。凡およそ百種くらいの仕掛花火の名称が順序を追うて記されてある大きい番附が、各家毎に配布されて、日一日とお祭気分が、寂れた町の隅々まで、へんに悲しくときめき浮き立たせて居りました。お祭の当日は朝からよく晴れていて私が顔を洗いに井戸端へ出たら、佐吉さんの妹さんは頭の手拭いを取って、おめでとうございます、と私に挨拶いたしました。ああ、おめでとう、と私も不自然でなくお祝いの言葉を返す事が出来ました。佐吉さんは、超然として、べつにお祭の晴着を着るわけでなし、ふだん着のままで、店の用事をして居ましたが、やがて、来る若者、来る若者、すべて派手な大浪模様のお揃いの浴衣ゆかたを着て、腰に団扇うちわを差し、やはり揃いの手拭いを首に巻きつけ、やあ、おめでとうございます、やあ、こんにちはおめでとうございますと、晴々した笑顔で、私と佐吉さんとに挨拶しました。其の日は私も、朝から何となく落ちつかず、さればといって、あの若者達と一緒に山車を引張り廻して遊ぶことも出来ず、仕事をちょっと仕掛けては、また立ち上り、二階の部屋をただうろうろ歩き廻って居ました。窓に倚よりかかり、庭を見下せば、無花果いちじくの樹蔭で、何事も無さそうに妹さんが佐吉さんのズボンやら、私のシャツやらを洗濯して居ました。
「さいちゃん。お祭を見に行ったらいい。」
と私が大声で話しかけると、さいちゃんは振り向いて笑い、
「私は男はきらいじゃ。」とやはり大声で答えて、それから、またじゃぶじゃぶ洗濯をつづけ、
「酒好きの人は、酒屋の前を通ると、ぞっとするほど、いやな気がするもんでしょう? あれと同じじゃ。」と普通の声で言って、笑って居るらしく、少しいかっている肩がひくひく動いて居ました。妹さんは、たった二十歳でも、二十二歳の佐吉さんより、また二十四歳の私よりも大人びて、いつも、態度が清潔にはきはきして、まるで私達の監督者のようでありました。佐吉さんも亦また、其の日はいらいらして居る様子で、町の若者達と共に遊びたくても、派手な大浪の浴衣などを着るのは、断然自尊心が許さず、逆に、ことさらにお祭に反撥して、ああ、つまらぬ。今日はお店は休みだ、もう誰にも酒は売ってやらない、とひとりで僻ひがんで、自転車に乗り、何処どこかへ行ってしまいました。やがて佐吉さんから私に電話がかかって来て、れいの所へ来いということだったので、私はほっと救われた気持で新しい浴衣に着更え、家を飛んで出ました。れいの所とは、お酒のお燗を五十年間やって居るのが御自慢の老爺の飲み屋でありました。そこへ行ったら佐吉さんと、もう一人江島という青年が、にこりともせず大不機嫌で酒を飲んで居ました。江島さんとはその前にも二三度遊んだことがありましたが、佐吉さんと同じで、お金持の家に育ち、それが不平で、何もせずに、ただ世を怒ってばかりいる青年でありました。佐吉さんに負けない位、美しい顔をして居ました。やはり今日のお祭の騒ぎに、一人で僻んで反抗し、わざと汚いふだん着のままで、その薄暗い飲み屋で、酒をまずそうに飲んで居るのでありました。それに私も加わり、暫しばらく、黙って酒を飲んで居ると、表はぞろぞろ人の行列の足音、花火が上り、物売りの声、たまりかねたか江島さんは立ち上り、行こう、狩野川へ行こうよ、と言い出し、私達の返事も待たずに店から出てしまいました。三人が、町の裏通りばかりをわざと選んで歩いて、ちえっ! 何だいあれあ、と口々にお祭を意味なく軽蔑しながら、三島の町から逃れ出て沼津をさしてどんどん歩き、日の暮れる頃、狩野川のほとり、江島さんの別荘に到着することが出来ました。裏口から入って行くと、客間に一人おじいさんが、シャツ一枚で寝ころんで居ました。江島さんは大声で、
「なあんだ、何時いつ来たんだい。ゆうべまた徹夜でばくちだな? 帰れ、帰れ。お客さんを連れて来たんだ。」
老人は起き上り、私達にそっと愛想笑いを浮べ、佐吉さんはその老人に、おそろしく丁寧なお辞儀をしました。江島さんは平気で、
「早く着物を着た方がいい。風邪を引くぜ。ああ、帰りしなに電話をかけてビイルとそれから何か料理を此所へすぐに届けさせてくれよ。お祭が面白くないから、此所で死ぬほど飲むんだ。」
「へえ。」と剽軽ひょうきんに返事して、老人はそそくさ着物を着込んで、消えるように居なくなってしまいました。佐吉さんは急に大声出して笑い、
「江島のお父さんですよ。江島を可愛くって仕様が無いんですよ。へえ、と言いましたね。」
やがてビイルが届き、様々の料理も来て、私達は何だか意味のわからない歌を合唱したように覚えて居ます。夕靄ゆうもやにつつまれた、眼前の狩野川は満々と水を湛たたえ、岸の青葉を嘗なめてゆるゆると流れて居ました。おそろしい程深い蒼い川で、ライン川とはこんなのではないかしら、と私は頗すこぶる唐突ながら、そう思いました。ビイルが無くなってしまったので、私達は又、三島の町へ引返して来ました。随分遠い道のりだったので、私は歩きながら、何度も何度も、こくりと居眠りしました。あわててしぶい眼を開くと蛍がすいと額ひたいを横ぎります。佐吉さんの家へ辿り着いたら、佐吉さんの家には沼津の実家のお母さんがやって来て居ました。私は御免蒙って二階へ上り、蚊帳かやを三角に釣って寝てしまいました。言い争うような声が聞えたので眼を覚まし、窓の方を見ると、佐吉さんは長い梯子はしごを屋根に立てかけ、その梯子の下でお母さんと美しい言い争いをして居たのでありました。今夜、揚花火あげはなびの結びとして、二尺玉が上るということになって居て、町の若者達もその直径二尺の揚花火の玉については、よほど前から興奮して話し合っていたのです。その二尺玉の花火がもう上る時刻なので、それをどうしてもお母さんに見せると言ってきかないのです。佐吉さんも相当酔って居りました。
「見せるったら、見ねえのか。屋根へ上ればよく見えるんだ。おれが負おぶってやるっていうのに、さ、負さりなよ、ぐずぐずして居ないで負さりなよ。」
お母さんはためらって居る様子でした。妹さんも傍にほの白く立って居て、くすくす笑って居る様子でした。お母さんは誰も居ぬのにそっとあたりを見廻し、意を決して佐吉さんに負さりました。
「ううむ、どっこいしょ。」なかなか重い様子でした。お母さんは七十近いけれど、目方は十五、六貫もそれ以上もあるような随分肥ったお方です。
「大丈夫だ、大丈夫。」と言いながら、そろそろ梯子を上り始めて、私はその親子の姿を見て、ああ、あれだから、お母さんも佐吉さんを可愛くてたまらないのだ。佐吉さんがどんな我儘なふしだらをしても、お母さんは兄さんと喧嘩してまでも、末弟の佐吉さんを庇かばうわけだ。私は花火の二尺玉よりもいいものを見たような気がして、満足して眠ってしまいました。三島には、その他にも数々の忘れ難い思い出があるのですけれども、それは又、あらためて申しましょう。そのとき三島で書いた「ロマネスク」という小説が、二三の人にほめられて、私は自信の無いままに今まで何やら下手へたな小説を書き続けなければならない運命に立ち至りました。三島は、私にとって忘れてならない土地でした。私のそれから八年間の創作は全部、三島の思想から教えられたものであると言っても過言でない程、三島は私に重大でありました。
八年後、いまは姉にお金をねだることも出来ず、故郷との音信も不通となり、貧しい痩せた一人の作家でしかない私は、先日、やっと少しまとまった金が出来て、家内と、家内の母と、妹を連れて伊豆の方へ一泊旅行に出かけました。清水で降りて、三保へ行き、それから修善寺へまわり、そこで一泊して、それから帰りみち、とうとう三島に降りてしまいました。いい所なんだ、とてもいい所だよ。そう言って皆を三島に下車させて、私は無理にはしゃいで三島の町をあちこち案内して歩き、昔の三島の思い出を面白おかしく、努めて語って聞かせたのですが、私自身だんだん、しょげて、しまいには、ものも言いたくなくなる程けわしい憂鬱に落ち込んでしまいました。今見る三島は荒涼として、全く他人の町でした。此こ処こにはもう、佐吉さんも居ない。妹さんも居ない。江島さんも居ないだろう。佐吉さんの店に毎日集って居た若者達も、今は分別くさい顔になり、女房を怒鳴ったりなどして居るのだろう。どこを歩いても昔の香が無い。三島が色褪いろあせたのではなくして、私の胸が老い干乾ひからびてしまったせいかもしれない。八年間、その間には、往年の呑気な帝国大学生の身の上にも、困苦窮乏の月日ばかりが続きました。八年間、その間に私は、二十も年をとりました。やがて雨さえ降って来て、家内も、母も、妹も、いい町です、落ち附いたいい町です、と口ではほめていながら、やはり当惑そうな顔色は蔽おおうべくもなく、私は、たまりかねて昔馴染みの飲み屋に皆を案内しました。あまり汚い家なので、門口で女達はためらって居ましたが、私は思わず大声になり、
「店は汚くても、酒はいいのだ。五十年間、お酒の燗ばかりしているじいさんが居るのだ。三島で由緒のある店ですよ。」と言い、むりやり入らせて、見るともう、あの赤シャツを着たおじいさんは居ないのです。つまらない女中さんが出て来て注文を聞きました。店の食卓も、腰掛も、昔のままだったけれど、店の隅に電気蓄音機があったり、壁には映画女優の、下品な大きい似顔絵が貼はられてあったり、下等に荒すさんだ感じが濃いのであります。せめて様々の料理を取寄せ、食卓を賑かにして、このどうにもならぬ陰鬱の気配を取払い度く思い、
「うなぎと、それから海老えびのおにがら焼と茶碗蒸し、四つずつ、此所で出来なければ、外へ電話を掛けてとって下さい。それから、お酒。」
母はわきで聞いてはらはらして、「いらないよ、そんなに沢山。無駄なことは、およしなさい。」と私のやり切れなかった心も知らず、まじめに言うので、私はいよいよやりきれなく、この世で一ばんしょげてしまいました。
底本:「太宰治全集3」ちくま文庫、筑摩書房
1988(昭和63)年10月25日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月刊行
入力:柴田卓治
校正:小林繁雄
1999年12月20日公開
2005年10月23日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
『老ハイデルベルヒ』序
太宰治
所收──「兄たち」「愛と美について」「新樹の言葉」「老ハイデルベルヒ」「おしやれ童子」「八十八夜」「秋風記」「短篇集─ア、秋・女人訓戒・座興に非ず・デカダン抗議」「俗天使」「花燭」
昭和十四年五月に「愛と美について」さうして、昭和十五年四月には「皮膚と心」が共に竹村書房より出版せられ、おのおの初版二千部くらゐを市場に送り、間もなく品切れとなつた樣子であるが、用紙不足の爲、竹村書房に於いても再版かなはず、この二つの創作集はしばらく、絶版同樣になつてゐたのである。しかるにその後、竹村書房に對して、讀者からの直接の註文が、かなりあるので、竹村書房主はその註文を受ける度毎に憂鬱、なんとかして讀者の求めに應じたいと煩悶、あげくの果は一日、著者の陋屋をおとづれ、名案なきかと相談に及ぶ始末であつた。
もとより迂愚の著者である。名案などのある筈はない。けれども、さらに多くの讀者に自分の作品を讀んでもらひたいのは、著者たるものの、ひそかな願望にちがひない。また、なんとかして、わづかな部數でも刷つて讀者の求めに應じたいといふのも、書房主たるものの眞情であらう。竹村書房主は沈思のあげく、かうしたらどうでせう、この紙不足の折に兩書とも再版などは、とても出來るものではありませんし、この二つの著書から特に著者の氣にいりの同じ匂ひの作品ばかりを寄せ集めて一本にまとめたら、といふ意見を提出した。戰時下の、自肅再版形式とでも稱すべきか。著者もよろこんで贊意を表した。いまだ兩書を讀まぬ人だけが、買ふとよい。兩書を讀んだ人も、この新しい編輯に依つて讀み直したいと思つたら、買ふがよい。羊頭狗肉ではないつもりだ。
作品の取捨に當り、懷郷の匂ひの強い作品のみを集めるといふ事を、根本方針とした。題も「老アルトハイデルベルヒ」として置いた。「老アルトハイデルベルヒ」とは、編中の一作品の題名であるが、この書に收録されて在る一系列の作品全體に冠しても、決して不自然ではないと思つたからである。人間は誰しも、思ひ出のハイデルベルヒを持つてゐる。著者のハイデルベルヒは、この一卷の中にある。
底本:「太宰治全集11」筑摩書房
1999(平成11)年3月25日初版第1刷発行
初出:「老ハイデルベルヒ」竹村書房
1942(昭和17)年5月20日発行
入力:小林繁雄
校正:阿部哲也
2012年1月7日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
或る忠告
太宰治
「その作家の日常の生活が、そのまま作品にもあらわれて居ります。ごまかそうたって、それは出来ません。生活以上の作品は書けません。ふやけた生活をしていて、いい作品を書こうたって、それは無理です。
どうやら『文人』の仲間入り出来るようになったのが、そんなに嬉しいのかね。宗匠頭巾をかぶって、『どうも此頃の青年はテニヲハの使用が滅茶で恐れ入りやす。』などは、げろが出そうだ。どうやら『先生』と言われるようになったのが、そんなに嬉しいのかね。八卦見はっけみだって、先生と言われています。どうやら、世の中から名士の扱いを受けて、映画の試写やら相撲の招待をもらうのが、そんなに嬉しいのかね。此頃すこしはお金がはいるようになったそうだが、それが、そんなに嬉しいのかね。小説を書かなくたって名士の扱いを受ける道があったでしょう。殊にお金は、他にもうける手段は、いくらでもあったでしょうに。
立身出世かね。小説を書きはじめた時の、あの悲壮ぶった覚悟のほどは、どうなりました。
けちくさいよ。ばかに気取ってるじゃないか。それでも何か、書いたつもりでいるのかね。時評に依ると、お前の心境いよいよ澄み渡ったそうだね、あはは。家庭の幸福か。妻子のあるのは、お前ばかりじゃありませんよ。
図々しいねえ。此頃めっきり色が白くなったじゃないか。万葉を読んでいるんだってね。読者を、あんまり、だまさないで下さい。図に乗って、あんまり人をなめていると、みんなばらしてやりますよ。僕が知らないと思っているのですか。
責任が重いんだぜ。わからないかね。一日一日、責任が重くなっているんだぜ。もっと、まともに苦しもうよ。まともに生き切る努力をしようぜ。明日の生活の計画よりは、きょうの没我のパッションが大事です。戦地に行った人たちの事を考えろ。正直はいつの時代でも、美徳だと思います。ごまかそうたって、だめですよ。明日の立派な覚悟より、きょうの、つたない献身が、いま必要であります。お前たちの責任は重いぜ。」
と或る詩人が、私の家へ来て私に向って言いました。その人は、酒に酔ってはいませんでした。
底本:「もの思う葦」新潮文庫、新潮社
1980(昭和55)年9月25日発行
1998(平成10)年10月15日39刷
入力:蒋龍
校正:今井忠夫
2004年6月16日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
朝
太宰治
私は遊ぶ事が何よりも好きなので、家で仕事をしていながらも、友あり遠方より来るのをいつもひそかに心待ちにしている状態で、玄関が、がらっとあくと眉まゆをひそめ、口をゆがめて、けれども実は胸をおどらせ、書きかけの原稿用紙をさっそく取りかたづけて、その客を迎える。
「あ、これは、お仕事中ですね。」
「いや、なに。」
そうしてその客と一緒に遊びに出る。
けれども、それではいつまでも何も仕事が出来ないので、某所に秘密の仕事部屋を設ける事にしたのである。それはどこにあるのか、家の者にも知らせていない。毎朝、九時頃ごろ、私は家の者に弁当を作らせ、それを持ってその仕事部屋に出勤する。さすがにその秘密の仕事部屋には訪れて来るひとも無いので、私の仕事もたいてい予定どおりに進行する。しかし、午後の三時頃になると、疲れても来るし、ひとが恋しくもなるし、遊びたくなって、頃合いのところで仕事を切り上げ、家へ帰る。帰る途中で、おでんやなどに引かかって、深夜の帰宅になる事もある。
仕事部屋。
しかし、その部屋は、女のひとの部屋なのである。その若い女のひとが、朝早く日本橋の或ある銀行に出勤する。そのあとに私が行って、そうして四、五時間そこで仕事をして、女のひとが銀行から帰って来る前に退出する。
愛人とか何とか、そんなものでは無い。私がそのひとのお母さんを知っていて、そうしてそのお母さんは、或る事情で、その娘さんとわかれわかれになって、いまは東北のほうで暮しているのである。そうして時たま私に手紙を寄こして、その娘の縁談に就いて、私の意見を求めたりなどして、私もその候補者の青年と逢あい、あれならいいお婿むこさんでしょう、賛成です、なんてひとかどの苦労人の言いそうな事を書いて送ってやった事もあった。
しかし、いまではそのお母さんよりも、娘さんのほうが、よけいに私を信頼しているように、どうも、そうらしく私には思われて来た。
「キクちゃん。こないだ、あなたの未来の旦那だんなさんに逢ったよ。」
「そう? どうでした? すこうし、キザね。そうでしょう?」
「まあ、でも、あんなところさ。そりゃもう、僕ぼくにくらべたら、どんな男でも、あほらしく見えるんだからね。我慢しな。」
「そりゃ、そうね。」
娘さんは、その青年とあっさり結婚する気でいるようであった。
先夜、私は大酒を飲んだ。いや、大酒を飲むのは、毎夜の事であって、なにも珍らしい事ではないけれども、その日、仕事場からの帰りに、駅のところで久し振りの友人と逢い、さっそく私のなじみのおでんやに案内して大いに飲み、そろそろ酒が苦痛になりかけて来た時に、雑誌社の編輯者へんしゅうしゃが、たぶんここだろうと思った、と言ってウイスキー持参であらわれ、その編輯者の相手をしてまたそのウイスキーを一本飲みつくして、こりゃもう吐くのではなかろうか、どうなるのだろう、と自分ながら、そらおそろしくなって来て、さすがにもう、このへんでよそうと思っても、こんどは友人が、席をあらためて僕にこれからおごらせてくれ、と言い出し、電車に乗って、その友人のなじみの小料理屋にひっぱって行かれ、そこでまた日本酒を飲み、やっとその友人、編輯者の両人とわかれた時には、私はもう、歩けないくらいに酔っていた。
「とめてくれ。うちまで歩いて行けそうもないんだ。このままで、寝ちまうからね。たのむよ。」
私は、こたつに足をつっこみ、二重廻にじゅうまわしを着たままで寝た。
夜中に、ふと眼がさめた。まっくらである。数秒間、私は自分のうちで寝ているような気がしていた。足を少しうごかして、自分が足袋をはいているままで寝ているのに気附きづいてはっとした。しまった! いけねえ!
ああ、このような経験を、私はこれまで、何百回、何千回、くりかえした事か。
私は、唸うなった。
「お寒くありません?」
と、キクちゃんが、くらやみの中で言った。
私と直角に、こたつに足を突込んで寝ているようである。
「いや、寒くない。」
私は上半身を起して、
「窓から小便してもいいかね。」
と言った。
「かまいませんわ。そのほうが簡単でいいわ。」
「キクちゃんも、時々やるんじゃねえか。」
私は立上って、電燈でんとうのスイッチをひねった。つかない。
「停電ですの。」
とキクちゃんが小声で言った。
私は手さぐりで、そろそろ窓のほうに行き、キクちゃんのからだに躓つまずいた。キクちゃんは、じっとしていた。
「こりゃ、いけねえ。」
と私はひとりごとのように呟つぶやき、やっと窓のカアテンに触って、それを排して窓を少しあけ、流水の音をたてた。
「キクちゃんの机の上に、クレーヴの奥方という本があったね。」
私はまた以前のとおりに、からだを横たえながら言う。
「あの頃の貴婦人はね、宮殿のお庭や、また廊下の階段の下の暗いところなどで、平気で小便をしたものなんだ。窓から小便をするという事も、だから、本来は貴族的な事なんだ。」
「お酒お飲みになるんだったら、ありますわ。貴族は、寝ながら飲むんでしょう?」
飲みたかった。しかし、飲んだら、あぶないと思った。
「いや、貴族は暗黒をいとうものだ、元来が臆病おくびょうなんだからね。暗いと、こわくて駄目だめなんだ。蝋燭ろうそくが無いかね。蝋燭をつけてくれたら、飲んでもいい。」
キクちゃんは黙って起きた。
そうして、蝋燭に火が点ぜられた。私は、ほっとした。もうこれで今夜は、何事も仕出かさずにすむと思った。
「どこへ置きましょう。」
「燭台しょくだいは高きに置け、とバイブルに在るから、高いところがいい。その本箱の上へどうだろう。」
「お酒は? コップで?」
「深夜の酒は、コップに注つげ、とバイブルに在る。」
私は嘘うそを言った。
キクちゃんは、にやにや笑いながら、大きいコップにお酒をなみなみと注いで持って来た。
「まだ、もう一ぱいぶんくらい、ございますわ。」
「いや、これだけでいい。」
私はコップを受け取って、ぐいぐい飲んで、飲みほし、仰向に寝た。
「さあ、もう一眠りだ。キクちゃんも、おやすみ。」
キクちゃんも仰向けに、私と直角に寝て、そうしてまつげの長い大きい眼を、しきりにパチパチさせて眠りそうもない。
私は黙って本箱の上の、蝋燭の焔ほのおを見た。焔は生き物のように、伸びたりちぢんだりして、うごいている。見ているうちに、私は、ふと或る事に思い到いたり、恐怖した。
「この蝋燭は短いね。もうすぐ、なくなるよ。もっと長い蝋燭が無いのかね。」
「それだけですの。」
私は黙した。天に祈りたい気持であった。あの蝋燭が尽きないうちに私が眠るか、またはコップ一ぱいの酔いが覚めてしまうか、どちらかでないと、キクちゃんが、あぶない。
焔はちろちろ燃えて、少しずつ少しずつ短かくなって行くけれども、私はちっとも眠くならず、またコップ酒の酔いもさめるどころか、五体を熱くして、ずんずん私を大胆にするばかりなのである。
思わず、私は溜息ためいきをもらした。
「足袋をおぬぎになったら?」
「なぜ?」
「そのほうが、あたたかいわよ。」
私は言われるままに足袋を脱いだ。
これはもういけない。蝋燭が消えたら、それまでだ。
私は覚悟しかけた。
焔は暗くなり、それから身悶みもだえするように左右にうごいて、一瞬大きく、あかるくなり、それから、じじと音を立てて、みるみる小さくいじけて行って、消えた。
しらじらと夜が明けていたのである。
部屋は薄明るく、もはや、くらやみではなかったのである。
私は起きて、帰る身支度をした。
底本:「グッド・バイ」新潮文庫、新潮社
1972(昭和47)年7月30日発行
1989(平成1)年3月20日37刷改版
1999(平成11)年6月10日56刷
入力:蒋龍
校正:鈴木厚司
2004年2月19日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
あさましきもの
太宰治
賭弓のりゆみに、わななく〳〵久しうありて、はづしたる矢の、もて離れてことかたへ行きたる。
こんな話を聞いた。
たばこ屋の娘で、小さく、愛くるしいのがいた。男は、この娘のために、飲酒をやめようと決心した。娘は、男のその決意を聞き、「うれしい。」と呟つぶやいて、うつむいた。うれしそうであった。「僕の意志の強さを信じて呉れるね?」男の声も真剣であった。娘はだまって、こっくり首肯うなずいた。信じた様子であった。
男の意志は強くなかった。その翌々日、すでに飲酒を為した。日暮れて、男は蹌踉そうろう、たばこ屋の店さきに立った。
「すみません」と小声で言って、ぴょこんと頭をさげた。真実わるい、と思っていた。娘は、笑っていた。
「こんどこそ、飲まないからね」
「なにさ」娘は、無心に笑っていた。
「かんにんして、ね」
「だめよ、お酒飲みの真似なんかして」
男の酔いは一時にさめた。「ありがとう。もう飲まない」
「たんと、たんと、からかいなさい」
「おや、僕は、僕は、ほんとうに飲んでいるのだよ」
あらためて娘の瞳ひとみを凝視した。
「だって」娘は、濁りなき笑顔で応じた。「誓ったのだもの。飲むわけないわ。ここではお芝居およしなさいね」
てんから疑って呉くれなかった。
男は、キネマ俳優であった。岡田時彦さんである。先年なくなったが、じみな人であった。あんな、せつなかったこと、ございませんでした、としんみり述懐して、行儀よく紅茶を一口すすった。
また、こんな話も聞いた。
どんなに永いこと散歩しても、それでも物たりなかったという。ひとけなき夜の道。女は、息もたえだえの思いで、幾度となく胴をくねらせた。けれども、大学生は、レインコオトのポケットに両手をつっこんだまま、さっさと歩いた。女は、その大学生の怒った肩に、おのれの丸いやわらかな肩をこすりつけるようにしながら男の後を追った。
大学生は、頭がよかった。女の発情を察知していた。歩きながら囁ささやいた。
「ね、この道をまっすぐに歩いていって、三つ目のポストのところでキスしよう」
女は、からだを固くした。
一つ。女は、死にそうになった。
二つ。息ができなくなった。
三つ。大学生は、やはりどんどん歩いて行った。女は、そのあとを追って、死ぬよりほかはないわ、と呟いて、わが身が雑巾ぞうきんのように思われたそうである。
女は、私の友人の画家が使っていたモデル女である。花の衣服をするっと脱いだら、おまもり袋が首にぷらんとさがっていたっけ、とその友人の画家が苦笑していた。
また、こんな話も聞いた。
その男は、甚はなはだ身だしなみがよかった。鼻をかむのにさえ、両手の小指をつんとそらして行った。洗練されている、と人もおのれも許していた。その男が、或る微妙な罪名のもとに、牢へいれられた。牢へはいっても、身だしなみがよかった。男は、左肺を少し悪くしていた。
検事は、男を、病気も重いことだし、不起訴にしてやってもいいと思っていたらしい。男は、それを見抜いていた。一日、男を呼び出して、訊問じんもんした。検事は、机の上の医師の診断書に眼を落しながら、
「君は、肺がわるいのだね?」
男は、突然、咳せきにむせかえった。こんこんこん、と三つはげしく咳をしたが、これは、ほんとうの咳であった。けれども、それから更に、こん、こん、と二つ弱い咳をしたが、それは、あきらかに嘘の咳であった。身だしなみのよい男は、その咳をしすましてから、なよなよと首こうべをあげた。
「ほんとうかね」能面に似た秀麗な検事の顔は、薄笑いしていた。
男は、五年の懲役ちょうえきを求刑されたよりも、みじめな思いをした。男の罪名は、結婚詐欺であった。不起訴ということになって、やがて出牢できたけれども、男は、そのときの検事の笑いを思うと、五年のちの今日こんにちでさえ、いても立っても居られません、と、やはり典雅に、なげいて見せた。男の名は、いまになっては、少し有名になってしまって、ここには、わざと明記しない。
弱く、あさましき人の世の姿を、冷く三つ列記したが、さて、そういう乃公だいこう自身は、どんなものであるか。これは、かの新人競作、幻燈のまちの、なでしこ、はまゆう、椿、などの、ちょいと、ちょいとの手招きと変らぬ早春コント集の一篇たるべき運命の不文、知りつつも濁酒三合を得たくて、ペン百貫の杖よりも重き思い、しのびつつ、ようやく六枚、あきらかにこれ、破廉恥はれんちの市井しせい売文の徒ともがら、あさましとも、はずかしとも、ひとりでは大家のような気で居れど、誰も大家と見ぬぞ悲しき。一笑。
底本:「太宰治全集2」ちくま文庫、筑摩書房
1988(昭和63)年9月27日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月
入力:柴田卓治
校正:小林繁雄
1999年8月20日公開
2004年3月4日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
新しい形の個人主義
太宰治
所謂社会主義の世の中になるのは、それは当り前の事と思わなければならぬ。民主々義とは云っても、それは社会民主々義の事であって、昔の思想と違っている事を知らなければならぬ。倫理に於いても、新しい形の個人主義の擡頭たいとうしているこの現実を直視し、肯定するところにわれらの生き方があるかも知れぬと思案することも必要かと思われる。
底本:「もの思う葦」新潮文庫、新潮社
1980(昭和55)年9月25日発行
1998(平成10)年10月15日39刷
入力:蒋龍
校正:土屋隆
2009年4月7日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
ア、秋
太宰治
本職の詩人ともなれば、いつどんな注文があるか、わからないから、常に詩材の準備をして置くのである。
「秋について」という注文が来れば、よし来た、と「ア」の部の引き出しを開いて、愛、青、赤、アキ、いろいろのノオトがあって、そのうちの、あきの部のノオトを選び出し、落ちついてそのノオトを調べるのである。
トンボ。スキトオル。と書いてある。
秋になると、蜻蛉とんぼも、ひ弱く、肉体は死んで、精神だけがふらふら飛んでいる様子を指して言っている言葉らしい。蜻蛉のからだが、秋の日ざしに、透きとおって見える。
秋ハ夏ノ焼ケ残リサ。と書いてある。焦土である。
夏ハ、シャンデリヤ。秋ハ、燈籠。とも書いてある。
コスモス、無残。と書いてある。
いつか郊外のおそばやで、ざるそば待っている間に、食卓の上の古いグラフを開いて見て、そのなかに大震災の写真があった。一面の焼野原、市松の浴衣ゆかた着た女が、たったひとり、疲れてしゃがんでいた。私は、胸が焼き焦げるほどにそのみじめな女を恋した。おそろしい情慾をさえ感じました。悲惨と情慾とはうらはらのものらしい。息がとまるほどに、苦しかった。枯野のコスモスに行き逢うと、私は、それと同じ痛苦を感じます。秋の朝顔も、コスモスと同じくらいに私を瞬時窒息させます。
秋ハ夏ト同時ニヤッテ来ル。と書いてある。
夏の中に、秋がこっそり隠れて、もはや来ているのであるが、人は、炎熱にだまされて、それを見破ることが出来ぬ。耳を澄まして注意をしていると、夏になると同時に、虫が鳴いているのだし、庭に気をくばって見ていると、桔梗ききょうの花も、夏になるとすぐ咲いているのを発見するし、蜻蛉だって、もともと夏の虫なんだし、柿も夏のうちにちゃんと実を結んでいるのだ。
秋は、ずるい悪魔だ。夏のうちに全部、身支度をととのえて、せせら笑ってしゃがんでいる。僕くらいの炯眼けいがんの詩人になると、それを見破ることができる。家の者が、夏をよろこび海へ行こうか、山へ行こうかなど、はしゃいで言っているのを見ると、ふびんに思う。もう秋が夏と一緒に忍び込んで来ているのに。秋は、根強い曲者くせものである。
怪談ヨロシ。アンマ。モシ、モシ。
マネク、ススキ。アノ裏ニハキット墓地ガアリマス。
路問エバ、オンナ唖ナリ、枯野原。
よく意味のわからぬことが、いろいろ書いてある。何かのメモのつもりであろうが、僕自身にも書いた動機が、よくわからぬ。
窓外、庭ノ黒土ヲバサバサ這はイズリマワッテイル醜キ秋ノ蝶ヲ見ル。並ハズレテ、タクマシキガ故ニ、死ナズ在リヌル。決シテ、ハカナキ態ていニハ非ズ。と書かれてある。
これを書きこんだときは、私は大へん苦しかった。いつ書きこんだか、私は決して忘れない。けれども、今は言わない。
捨テラレタ海。と書かれてある。
秋の海水浴場に行ってみたことがありますか。なぎさに破れた絵日傘が打ち寄せられ、歓楽の跡、日の丸の提灯ちょうちんも捨てられ、かんざし、紙屑、レコオドの破片、牛乳の空瓶、海は薄赤く濁って、どたりどたりと浪打っていた。
緒方サンニハ、子供サンガアッタネ。
秋ニナルト、肌ガカワイテ、ナツカシイワネ。
飛行機ハ、秋ガ一バンイイノデスヨ。
これもなんだか意味がよくわからぬが、秋の会話を盗み聞きして、そのまま書きとめて置いたものらしい。
また、こんなのも、ある。
芸術家ハ、イツモ、弱者ノ友デアッタ筈はずナノニ。
ちっとも秋に関係ない、そんな言葉まで、書かれてあるが、或いはこれも、「季節の思想」といったようなわけのものかも知れない。
その他、
農家。絵本。秋ト兵隊。秋ノ蚕カイコ。火事。ケムリ。オ寺。
ごたごた一ぱい書かれてある。
底本:「太宰治全集3」ちくま文庫、筑摩書房
1988(昭和63)年10月25日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月刊行
入力:柴田卓治
校正:小林繁雄
1999年10月20日公開
2005年10月22日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
「晩年」に就いて
太宰治
「晩年」は、私の最初の小説集なのです。もう、これが、私の唯一の遺著になるだろうと思いましたから、題も、「晩年」として置いたのです。
読んで面白い小説も、二、三ありますから、おひまの折に読んでみて下さい。
私の小説を、読んだところで、あなたの生活が、ちっとも楽になりません。ちっとも偉くなりません。なんにもなりません。だから、私は、あまり、おすすめできません。
「思い出」など、読んで面白いのではないでしょうか。きっと、あなたは、大笑いしますよ。それでいいのです。「ロマネスク」なども、滑稽な出鱈目でたらめに満ち満ちていますが、これは、すこし、すさんでいますから、あまり、おすすめできません。
こんど、ひとつ、ただ、わけもなく面白い長篇小説を書いてあげましょうね。いまの小説、みな、面白くないでしょう?
やさしくて、かなしくて、おかしくて、気高くて、他に何が要るのでしょう。
あのね、読んで面白くない小説はね、それは、下手な小説なのです。こわいことなんかない。面白くない小説は、きっぱり拒否したほうがいいのです。
みんな、面白くないからねえ。面白がらせようと努めて、いっこう面白くもなんともない小説は、あれは、あなた、なんだか死にたくなりますね。
こんな、ものの言いかたが、どんなにいやらしく響くか、私、知っています。それこそ人をばかにしたような言いかたかもわからぬ。
けれども私は、自身の感覚をいつわることができません。くだらないのです。いまさら、あなたに、なんにも言いたくないのです。
激情の極には、人は、どんな表情をするでしょう。無表情。私は微笑の能面になりました。いいえ、残忍のみみずくになりました。こわいことなんかない。私も、やっと世の中を知った、というだけのことなのです。
「晩年」お読みになりますか? 美しさは、人から指定されて感じいるものではなくて、自分で、自分ひとりで、ふっと発見するものです。「晩年」の中から、あなたは、美しさを発見できるかどうか、それは、あなたの自由です。読者の黄金権です。だから、あまりおすすめしたくないのです。わからん奴には、ぶん殴ったって、こんりんざい判りっこないんだから。
もう、これで、しつれいいたします。私はいま、とっても面白い小説を書きかけているので、なかば上うわの空で、対談していました。おゆるし下さい。
底本:「もの思う葦」新潮文庫、新潮社
1980(昭和55)年9月25日発行
1998(平成10)年10月15日39刷
入力:蒋龍
校正:今井忠夫
2004年6月16日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
「晩年」と「女生徒」
太宰治
「晩年」も品切になったようだし「女生徒」も同様、売り切れたようである。「晩年」は初版が五百部くらいで、それからまた千部くらい刷った筈はずである。「女生徒」は初版が二千で、それが二箇年経って、やっと売切れて、ことしの初夏には更に千部、増刷される事になった。「晩年」は、昭和十一年の六月に出たのであるから、それから五箇年間に、千五百冊売れたわけである。一年に、三百冊ずつ売れた事になるようだが、すると、まず一日に一冊ずつ売れたといってもいいわけになる。五箇年間に千五百部といえば、一箇月間に十万部も売れる評判小説にくらべて、いかにも見すぼらしく貧寒の感じがするけれど、一日に一冊ずつ売れたというと、まんざらでもない。「晩年」は、こんど砂子屋書房で四六判に改版して出すそうだが、早く出してもらいたいと思っている。売切れのままで、二年三年経過すると、一日に一冊ずつ売れたという私の自慢も崩壊する事になる。たとえば、売切れのままで、もう十年経過すると、「晩年」は、昭和十一年から十五箇年のあいだに、たった千五百部しか売れなかったという事になる。すると、一箇年に百冊ずつ売れたという事になって、私の本は、三日に一冊か四日に一冊しか売れなかったというわけになる。多く売れるという事は、必ずしも最高の名誉でもないが、しかし、なんにも売れないよりは、少しでも売れたほうが張り合いがあってよいと思う。けれども、文学書は、一万部以上売れると、あぶない気がする。作家にとって、危険である。先輩の山岸外史氏の説に依よると、貨幣のどっさりはいっている財布を、懐ふところにいれて歩いていると、胃腸が冷えて病気になるそうである。それは銅銭ばかりいれて歩くからではないかと反問したら、いや紙幣でも同じ事だ、あの紙は、たいへん冷く、あれを懐にいれて歩くと必ず胃腸をこわすから、用心し給え、とまじめに忠告してくれた。富をむさぼらぬように気をつけなければならぬ。
底本:「太宰治全集10」ちくま文庫、筑摩書房
1989(平成元)年6月27日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集第十巻」筑摩書房
1977(昭和52)年2月25日初版第1刷発行
初出:「文筆 夏季版」
1941(昭和16)年6月20日発行
入力:杜十朗
校正:土屋隆
2003年9月4日作成
2016年7月12日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
美男子と煙草
太宰治
私は、独ひとりで、きょうまでたたかって来たつもりですが、何だかどうにも負けそうで、心細くてたまらなくなりました。けれども、まさか、いままで軽蔑けいべつしつづけて来た者たちに、どうか仲間にいれて下さい、私が悪うございました、と今さら頼む事も出来ません。私は、やっぱり独りで、下等な酒など飲みながら、私のたたかいを、たたかい続けるよりほか無いんです。
私のたたかい。それは、一言で言えば、古いものとのたたかいでした。ありきたりの気取りに対するたたかいです。見えすいたお体裁ていさいに対するたたかいです。ケチくさい事、ケチくさい者へのたたかいです。
私は、エホバにだって誓って言えます。私は、そのたたかいの為に、自分の持ち物全部を失いました。そうして、やはり私は独りで、いつも酒を飲まずには居られない気持で、そうして、どうやら、負けそうになって来ました。
古い者は、意地が悪い。何のかのと、陳腐ちんぷきわまる文学論だか、芸術論だか、恥かしげも無く並べやがって、以もって新しい必死の発芽を踏みにじり、しかも、その自分の罪悪に一向お気づきになっておらない様子なんだから、恐れいります。押せども、ひけども、動きやしません。ただもう、命が惜しくて、金が惜しくて、そうして、出世して妻子をよろこばせたくて、そのために徒党を組んで、やたらと仲間ぼめして、所謂いわゆる一致団結して孤影の者をいじめます。
私は、負けそうになりました。
先日、或るところで、下等な酒を飲んでいたら、そこへ年寄りの文学者が三人はいって来て、私がそのひとたちとは知合いでも何でも無いのに、いきなり私を取りかこみ、ひどくだらしない酔い方をして、私の小説に就ついて全く見当ちがいの悪口を言うのでした。私は、いくら酒を飲んでも、乱れるのは大きらいのたちですから、その悪口も笑って聞き流していましたが、家へ帰って、おそい夕ごはんを食べながら、あまり口惜くやしくて、ぐしゃと嗚咽おえつが出て、とまらなくなり、お茶碗ちゃわんも箸はしも、手放して、おいおい男泣きに泣いてしまって、お給仕していた女房に向い、
「ひとが、ひとが、こんな、いのちがけで必死で書いているのに、みんなが、軽いなぶりものにして、……あのひとたちは、先輩なんだ、僕より十も二十も上なんだ、それでいて、みんな力を合せて、僕を否定しようとしていて、……卑怯ひきょうだよ、ずるいよ、……もう、いい、僕だってもう遠慮しない、先輩の悪口を公然と言う、たたかう、……あんまり、ひどいよ。」
などと、とりとめの無い事をつぶやきながら、いよいよ烈はげしく泣いて、女房は呆あきれた顔をして、
「おやすみなさい、ね。」
と言い、私を寝床に連れて行きましたが、寝てからも、そのくやし泣きの嗚咽が、なかなか、とまりませんでした。
ああ、生きて行くという事は、いやな事だ。殊ことにも、男は、つらくて、哀かなしいものだ。とにかく、何でもたたかって、そうして、勝たなければならぬのですから。
その、くやし泣きに泣いた日から、数日後、或る雑誌社の、若い記者が来て、私に向い、妙な事を言いました。
「上野の浮浪者を見に行きませんか?」
「浮浪者?」
「ええ、一緒の写真をとりたいのです。」
「僕が、浮浪者と一緒の?」
「そうです。」
と答えて、落ちついています。
なぜ、特に私を選んだのでしょう。太宰といえば、浮浪者。浮浪者といえば、太宰。何かそのような因果関係でもあるのでしょうか。
「参ります。」
私は、泣きべその気持の時に、かえって反射的に相手に立向う性癖を持っているようです。
私はすぐ立って背広に着換え、私の方から、その若い記者をせき立てるようにして家を出ました。
冬の寒い朝でした。私はハンカチで水洟みずばなを押えながら、無言で歩いて、さすがに浮かぬ心地ここちでした。
三鷹みたか駅から省線で東京駅迄まで行き、それから市電に乗換え、その若い記者に案内されて、先まず本社に立寄り、応接間に通されて、そうして早速ウイスキイの饗応にあずかりました。
思うに、太宰はあれは小心者だから、ウイスキイでも飲ませて少し元気をつけさせなければ、浮浪者とろくに対談も出来ないに違いないという本社編輯部へんしゅうぶの好意ある取計らいであったのかも知れませんが、率直に言いますと、そのウイスキイは甚はなはだ奇怪なしろものでありました。私も、これまでさまざまの怪しい酒を飲んで来た男で、何も決して上品ぶるわけではありませんが、しかし、ウイスキイの独り酒というのは初めてでした。ハイカラなレッテルなど貼はられ、ちゃんとした瓶びんでしたが、内容が濁っているのです。ウイスキイのドブロクとでも言いましょうか。
けれども私はそれを飲みました。グイグイ飲みました。そうして、応接間に集って来ていた記者たちにも、飲みませんか、と言ってすすめました。しかし、皆うす笑いして飲まないのです。そこに集って来ていた記者たちは、たいていひどいお酒飲みなのを私は噂うわさで聞いて知っているのでした。けれども、飲まないのです。さすがの酒豪たちも、ウイスキイのドブロクは敬遠の様子でした。
私だけが酔っぱらい、
「なんだい、君たちは失敬じゃあないか。てめえたちが飲めない程の珍妙なウイスキイを、客にすすめるとは、ひどいじゃないか。」
と笑いながら言って、記者たちは、もうそろそろ太宰も酔って来た、この勢いの消えないうちに、浮浪者と対面させなければならぬと、いわばチャンスを逃さず、私を自動車に乗せ、上野駅に連れて行き、浮浪者の巣と言われる地下道へ導くのでした。
けれども、記者たちのこの用意周到の計画も、あまり成功とは言えないようでした。私は、地下道へ降りて何も見ずに、ただ真直まっすぐに歩いて、そうして地下道の出口近くなって、焼鳥屋の前で、四人の少年が煙草を吸っているのを見掛け、ひどく嫌いやな気がして近寄り、
「煙草は、よし給たまえ。煙草を吸うとかえっておなかが空すくものだ。よし給え。焼鳥が喰いたいなら、買ってやる。」
少年たちは、吸い掛けの煙草を素直に捨てました。すべて拾歳前後の、ほんの子供なのです。私は焼鳥屋のおかみに向い、
「おい、この子たちに一本ずつ。」
と言い、実に、へんな情なさを感じました。
これでも、善行という事になるのだろうか、たまらねえ。私は唐突にヴァレリイの或ある言葉を思い出し、さらに、たまらなくなりました。
もし、私のその時の行いが俗物どもから、多少でも優しい仕草と見られたとしたら、私はヴァレリイにどんなに軽蔑されても致し方なかったんです。
ヴァレリイの言葉、──善をなす場合には、いつも詫わびながらしなければいけない。善ほど他人を傷きずつけるものはないのだから。
私は風邪かぜをひいたような気持になり、背中を丸め、大股で地下道の外に出てしまいました。
四五人の記者たちが、私の後を追いかけて来て、
「どうでした。まるで地獄でしょう。」
別の一人が、
「とにかく、別世界だからな。」
また別の一人が、
「驚いたでしょう? 御感想は?」
私は声を出して笑いました。
「地獄? まさか。僕は少しも驚きませんでした。」
そう言って上野公園の方に歩いて行き、私は少しずつおしゃべりになって行きました。
「実は、僕なんにも見て来なかったんです。自分自身の苦しさばかり考えて、ただ真直を見て、地下道を急いで通り抜けただけなんです。でも、君たちが特に僕を選んで地下道を見せた理由は、判わかった。それはね、僕が美男子であるという理由からに違いない。」
みんな大笑いしました。
「いや、冗談じゃない。君たちには気がつかなかったかね。僕は、真直を見て歩いていても、あの薄暗い隅すみに寝そべっている浮浪者の殆ほとんど全部が、端正な顔立をした美男子ばかりだということを発見したんだ。つまり、美男子は地下道生活におちる可能性を多分に持っているということになる。君なんか色が白くて美男子だから、危いぞ、気をつけ給え。僕も、気をつけるがね。」
また、みんながどっと笑いました。
自惚うぬぼれて、自惚れて、人がなんと言っても自惚れて、ふと気がついたらわが身は、地下道の隅に横たわり、もはや人間でなくなっているのです。私は、地下道を素通りしただけで、そのような戦慄せんりつを、本気に感じたのでした。
「美男子の件はとに角、そのほかに何か発見出来ましたか。」
と問われて私は、
「煙草です。あの美男子たちは、酒に酔っているようにも見えなかったが、煙草だけはたいてい吸っていましたね。煙草だって、安かないんだろう。煙草を買うお金があったら、莚むしろ一枚でも、下駄げた一足でも買えるんじゃないかしら。コンクリイトの上にじかに寝て、はだしで、そうして煙草をふかしている。人間は、いや、いまの人間は、どん底に落ちても、丸裸になっても、煙草を吸わなければならぬように出来ているのだろうね。ひとごとじゃない。どうも、僕にもそんな気持が思い当らぬこともない。いよいよこれは、僕の地下道行きは実現性の色を増して来たようだわい。」
上野公園前の広場に出ました。さっきの四名の少年が冬の真昼の陽射ひざしを浴びて、それこそ嬉々として遊びたわむれていました。私は自然に、その少年たちの方にふらふら近寄ってしまいました。
「そのまま、そのまま。」
ひとりの記者がカメラを私たちの方に向けて叫び、パチリと写真をうつしました。
「こんどは、笑って!」
その記者が、レンズを覗のぞきながら、またそう叫び、少年のひとりは、私の顔を見て、
「顔を見合せると、つい笑ってしまうものだなあ。」
と言って笑い、私もつられて笑いました。
天使が空を舞い、神の思召おぼしめしにより、翼が消え失せ、落下傘らっかさんのように世界中の処々方々に舞い降りるのです。私は北国の雪の上に舞い降り、君は南国の蜜柑畑みかんばたけに舞い降り、そうして、この少年たちは上野公園に舞い降りた、ただそれだけの違いなのだ、これからどんどん生長しても、少年たちよ、容貌ようぼうには必ず無関心に、煙草を吸わず、お酒もおまつり以外には飲まず、そうして、内気でちょっとおしゃれな娘さんに気永きながに惚ほれなさい。
附記
この時うつした写真を、あとで記者が持って来てくれた。笑い合っている写真と、それからもう一枚は、私が浮浪児たちの前にしゃがんで、ひとりの浮浪児の足をつかんでいる甚はなはだ妙なポーズの写真であった。もしこれが後日、何か雑誌にでも掲載された場合、太宰はキザな奴だ、キリスト気取りで、あのヨハネ伝の弟子でしの足を洗ってやる仕草を真似まねしていやがる、げえっ、というような誤解を招くおそれなしとしないので一言弁明するが、私はただはだしで歩いている子供の足の裏がどんなになっているのだろうという好奇心だけであんな恰好かっこうをしただけだ。
さらに一つ、笑い話を附け加えよう。その二枚の写真が届けられた時、私は女房を呼び、
「これが、上野の浮浪者だ。」
と教えてやったら、女房は真面目まじめに、
「はあ、これが浮浪者ですか。」
と言い、つくづく写真を見ていたが、ふと私はその女房の見詰めている個所を見て驚き、
「お前は、何を感違いして見ているのだ。それは、おれだよ。お前の亭主じゃないか。浮浪者は、そっちの方だ。」
女房は生真面目過ぎる程の性格の所有者で、冗談など言える女ではないのである。本気に私の姿を浮浪者のそれと見誤ったらしい。
底本:「太宰治全集9」ちくま文庫、筑摩書房
1989(平成元)年5月30日第1刷発行
1998(平成10)年6月15日第5刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月発行
入力:柴田卓治
校正:かとうかおり
2000年1月23日公開
2004年3月4日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
美少女
太宰治
ことしの正月から山梨県、甲府市のまちはずれに小さい家を借り、少しずつ貧しい仕事をすすめてもう、はや半年すぎてしまった。六月にはいると、盆地特有の猛烈の暑熱が、じりじりやって来て、北国育ちの私は、その仮借かしゃくなき、地の底から湧きかえるような熱気には、仰天した。机の前にだまって坐っていると、急に、しんと世界が暗くなって、たしかに眩暈めまいの徴候である。暑熱のために気が遠くなるなどは、私にとって生れてはじめての経験であった。家内は、からだじゅうのアセモに悩まされていた。甲府市のすぐ近くに、湯村という温泉部落があって、そこのお湯が皮膚病に特効を有する由を聞いたので、家内をして毎日、湯村へ通わせることにした。私たちの借りている家賃六円五拾銭の草庵は、甲府市の西北端、桑畑の中にあり、そこから湯村までは歩いて二十分くらい。(四十九聯隊の練兵場を横断して、まっすぐに行くと、もっと早い。十五分くらいのものかも知れない。)家内は、朝ごはんの後片附がすむと、湯道具持って、毎日そこへ通った。家内の話に依よれば、その湯村の大衆浴場は、たいへんのんびりして、浴客も農村のじいさんばあさんたちで、皮膚病に特効があるといっても、皮膚病らしい人は、ひとりも無く、家内のからだが一等きたないくらいで、浴室もタイル張で清潔であるし、お湯のぬるいのが欠点であるけれども、みんな三十分も一時間も、しゃがんでお湯にひたったまま、よもやまの世間話を交かわして、とにかく別天地であるから、あなたも、一度おいでなさい、ということであった。早朝、練兵場の草原を踏みわけて行くと、草の香も新鮮で、朝露が足をぬらして冷や冷やして、心が豁然かつぜんとひらけ、ひとりで笑い出したくなるくらいである、という家内の話であった。私は暑熱をいい申しわけにして、仕事を怠けていて、退屈していた時であったから、早速さっそく行ってみることにした。朝の八時頃、家内に案内させて、出掛けた。たいしたことも無かった。練兵場の草原を踏みわけて歩いてみても、ひとりで笑い出したくなるようなことは無かった。湯村のその大衆浴場の前庭には、かなり大きい石榴ざくろの木が在り、かっと赤い花が、満開であった。甲府には石榴の樹が非常に多い。
浴場は、つい最近新築されたものらしく、よごれが無く、純白のタイルが張られて明るく、日光が充満していて、清楚せいその感じである。湯槽ゆぶねは割に小さく、三坪くらいのものである。浴客が、五人いた。私は湯槽にからだを滑り込ませて、ぬるいのに驚いた。水とそんなにちがわない感じがした。しゃがんで、顎あごまでからだを沈めて、身動きもできない。寒いのである。ちょっと肩を出すと、ひやと寒い。だまって、死んだようにして、しゃがんでいなければならぬ。とんでもないことになったと私は心細かった。家内は、落ちついてじっとしゃがみ、悟ったような顔して眼をつぶっている。
「ひでえな。身動きもできやしない。」私は小声でぶつぶつ言った。
「でも、」家内は平気で、「三十分くらいこうしていると、汗がたらたら出てまいります。だんだん効いて来るのです。」
「そうかね。」私は、観念した。
けれども、まさか家内のように悟りすまして眼をつぶっていることもできず、膝小僧だいてしゃがんだまま、きょろきょろあたりを見廻した。二組の家族がいる。一組は、六十くらいの白髪の老爺ろうやと、どこか垢抜あかぬけした五十くらいの老婆である。品のいい老夫婦である。この在ざいの小金持であろう。白髪の老爺は鼻が高く、右手に金の指輪、むかし遊んだ男かも知れない。からだも薄赤く、ふっくりしている。老婆も、あるいは、煙草くらいは意気にふかす女かも知れないと思わせるふしが無いでもないが、問題は、この老夫婦に在るのではない。問題は、別に在るのだ。私と対角線を為す湯槽の隅に、三人ひしとかたまって、しゃがんでいる。七十くらいの老爺、からだが黒くかたまっていて、顔もくしゃくしゃ縮小して奇怪である。同じ年恰好としかっこうの老婆、小さく痩せていて胸が鎧扉よろいどのようにでこぼこしている。黄色い肌で、乳房がしぼんだ茶袋を思わせて、あわれである。老夫婦とも、人間の感じでない。きょろきょろして、穴にこもった狸たぬきのようである。あいだに、孫娘でもあろうか、じいさんばあさんに守護されているみたいに、ひっそりしゃがんでいる。そいつが、素晴らしいのである。きたない貝殻かいがらに附着し、そのどすぐろい貝殻に守られている一粒の真珠である。私は、ものを横眼で見ることのできぬたちなので、そのひとを、まっすぐに眺めた。十六、七であろうか。十八、になっているかも知れない。全身が少し青く、けれども決して弱ってはいない。大柄の、ぴっちり張ったからだは、青い桃実を思わせた。お嫁に行けるような、ひとりまえのからだになった時、女は一ばん美しいと志賀直哉の随筆に在ったが、それを読んだとき、志賀氏もずいぶん思い切ったことを言うと冷ひやりとした。けれども、いま眼のまえに少女の美しい裸体を、まじまじと見て、志賀氏のそんな言葉は、ちっともいやらしいものでは無く、純粋な観賞の対象としても、これは崇高なほど立派なものだと思った。少女は、きつい顔をしていた。一重瞼ひとえまぶたの三白眼で、眼尻がきりっと上っている。鼻は尋常で、唇は少し厚く、笑うと上唇がきゅっとまくれあがる。野性のものの感じである。髪は、うしろにたばねて、毛は少いほうの様である。ふたりの老人にさしはさまれて、無心らしく、しゃがんでいる。私が永いことそのからだを直視していても、平気である。老夫婦が、たからものにでも触るようにして、背中を撫なでたり、肩をとんとん叩いてやったりする。この少女は、どうやら病後のものらしい。けれども、決して痩せてはいない。清潔に皮膚が張り切っていて、女王のようである。老夫婦にからだをまかせて、ときどきひとりで薄く笑っている。白痴的なものをさえ私は感じた。すらと立ちあがったとき、私は思わず眼を見張った。息が、つまるような気がした。素晴らしく大きい少女である。五尺二寸もあるのではないかと思われた。見事なのである。コーヒー茶碗一ぱいになるくらいのゆたかな乳房、なめらかなおなか、ぴちっと固くしまった四肢、ちっとも恥じずに両手をぶらぶらさせて私の眼の前を通る。可愛いすきとおるほど白い小さい手であった。湯槽にはいったまま腕をのばし、水道のカランをひねって、備付けのアルミニウムのコップで水を幾杯も幾杯も飲んだ。
「おお、たくさん飲めや。」老婆は、皺しわの口をほころばせて笑い、うしろから少女を応援するようにして言うのである。「精出して飲まんと、元気にならんじゃ。」すると、もう一組の老夫婦も、そうだ、そうだ、という意味の合槌あいづちを打って、みんな笑い出し、だしぬけに指輪の老爺がくるりと私のほうを向いて、
「あんたも、飲まんといかんじゃ。衰弱には、いっとうええ。」と命令するように言ったので、私は瞬時へどもどした。私の胸は貧弱で、肋骨ろっこつが醜く浮いて見えているので、やはり病後のものと思われたにちがいない。老爺のその命令には、大いに面くらったが、けれども、知らぬふりをしているのも失礼のように思われたから、私は、とにかくあいそ笑いを浮べて、それから立ち上った。ひやと寒く、ぶるっと震えた。少女は、私にアルミニウムのコップを、だまって渡した。
「や、ありがとう。」小声で礼を言って、それを受け取り、少女の真似して湯槽にはいったまま腕をのばしカランをひねり、意味もわからずがぶがぶ飲んだ。塩からかった。鉱泉なのであろう。そんなに、たくさん飲むわけにも行かず、三杯やっとのことで飲んで、それから浮かぬ顔してコップをもとの場所にかえして、すぐにしゃがんで肩を沈めた。
「調子がええずら?」指輪は、得意そうに言うのである。私は閉口であった。やはり浮かぬ顔して、
「ええ。」と答えて、ちょっとお辞儀した。
家内は、顔を伏せてくすくす笑っている。私は、それどころでないのである。胸中、戦戦兢兢せんせんきょうきょうたるものがあった。私は不幸なことには、気楽に他人と世間話など、どうしてもできないたちなので、もし今から、この老爺に何かと話を仕掛けられたら、どうしようと恐ろしく、いよいよこれは、とんでもないことになったと、少しも早くここを逃げ出したくなって来た。ちらと少女のほうを見ると、少女は落ちついて、以前のとおりに、ふたりの老夫婦のあいだにひっそりしゃがんで、ひたと守られ、顔を仰向あおむけにして全然の無表情であった。ちっとも私を問題にしていない。私は、あきらめた。ふたたび指輪の老爺に話掛けられぬうちに、私は立ちあがって、
「出よう。いっこうあたたまらない。」と家内に囁ささやき、さっさと湯槽から出て、からだをふいた。
「あたし、もう少し。」家内は、ねばるつもりである。
「そうか。さきに帰るからね。」脱衣場で、そそくさ着物を着ていたら、湯槽のほうでは、なごやかな世間話がはじまった。やはり私が、気取って口を引きしめて、きょろきょろしていると異様のもので、老人たちにも、多少気づまりの思いを懐かせていたらしく、私がいなくなると、みんなその窮屈から解放されて、ほっとした様子で、会話がなだらかに進行している。家内まで、その仲間にはいってアセモの講釈などをはじめた。私は、どうも駄目である。仲間になれない。どうせおれは異様なんだ、とひとりでひがんで、帰りしなに、またちらと少女を見た。やっぱり、ふたりの黒い老人のからだに、守られて、たからもののように美事に光って、じっとしている。
あの少女は、よかった。いいものを見た、とこっそり胸の秘密の箱の中に隠して置いた。
七月、暑熱は極点に達した。畳が、かっかっと熱いので、寝ても坐っても居られない。よっぽど、山の温泉にでも避難しようかと思ったが、八月には私たち東京近郊に移転する筈はずになっているし、そのために少しお金を残して置かなければならないのだから、温泉などへ行く余分のお金が、どうしても都合つかないのである。私は気が狂いそうになった。髪を思い切って短く刈ったら、少しは頭も涼しくなり、はっきりして来るかも知れぬと思い、散髪屋に駈けつけた。行きあたりばったり、どこの散髪屋でも、空すいているようなところだったら少しは汚い店でもかまわないと、二、三軒覗のぞいて歩いたが、どこも満員の様子である。横丁の銭湯屋の向いに、小さな店が一軒あって、そこを覗いてみたら、やはり客がいるような様子だったので、引き返しかけたら、主人が窓から首を出して、
「すぐ出来ますよ。散髪でしょう?」と私の意向を、うまく言い当てた。
私は苦笑して、その散髪屋のドアを押して中へはいった。私自身では気がつかなかったけれど、よその人から見ると、ずいぶんぼうぼうと髪が伸びて、見苦しく、それだから散髪屋の主人も、私の意向をちゃんと見抜いてしまったのだ、それにちがいない、と私は流石さすがに恥ずかしく思ったのである。
主人は、四十くらいで丸坊主である。太いロイド眼鏡をかけて、唇がとがり、ひょうきんな顔をしていた。十七、八の弟子がひとりいて、これは蒼黒あおぐろく痩せこけていた。散髪所と、うすいカアテンをへだて、洋風の応接間があり、二三人の人の話声が聞えて、私はその人たちをお客と見誤ったのである。
椅子に腰をおろすと、裾すそから煽風機が涼しい風を送ってよこして、私はほっと救われた。植木鉢や、金魚鉢が、要所要所に置かれて、小ざっぱりした散髪屋である。暑いときには、散髪に限ると思った。
「うんと、うしろを短く刈り上げて下さい。」口の重い私には、それだけ言うのも精一ぱいであった。そう言って鏡を見ると、私の顔はものものしく、異様に緊張してぎゅっと口を引きしめて気取っていた。不幸な宿命にちがいない。散髪屋に来てまで、こんなに気取らなければいけないのかと、われながら情なく思った。なお鏡を見つめていると、ちらと鏡の奥に花が写った。青い簡単服かんたんふく着て、窓のすぐ傍の椅子に腰かけている少女の姿である。そこに少女の坐っているのを、そのときはじめて知ったわけである。私は、けれどもあまり問題にしなかった。女弟子かな? 娘かな? ちらとそう思っただけで、それ以上、注意して見なかった。しばらくして、少女が、私の背後から首筋のばして、私の鏡の顔をちょいちょい見ていることに気附いた。二度も、三度も鏡の中で視線が逢った。私は振り向きたいのを我慢しながら、見たような顔だと思っていた。私が、背後のその少女の顔に注意しはじめたら、少女のほうでは、それで満足したようなふうで、こんどは、ちっとも私のほうを見なかった。自信たっぷりで、窓縁まどべりに頬杖ついて、往来のほうを見ていた。猫と女は、だまって居れば名を呼ぶし、近寄って行けば逃げ去る、とか。この少女も、もはや無意識にその特性を体得していやがる、といまいましく思っているうちに、少女は傍のテエブルから、もの憂げに牛乳の瓶びんを取りあげ、瓶のままで静かに飲みほした。はっと気附いた。病身。あれだ、あの素晴らしいからだの病後の少女だ。ああ、わかりました。その牛乳で、やっとわかりました。顔より乳房のほうを知っているので、失礼しました、と私は少女に挨拶したく思った。いまは青い簡単服に包まれているが、私はこの少女の素晴らしい肉体、隅の隅まで知ってる。そう思うと、うれしかった。少女を、肉親のようにさえ思われた。
私は不覚にも、鏡の中で少女に笑いかけてしまった。少女は、少しも笑わず、それを見て、すらと立って、カアテンのかげの応接間のほうへゆっくり歩いて行った。なんの表情もなかった。私は再び白痴を感じた。けれども私は満足だった。ひとり可愛い知り合いが、できたと思った。おそらくは、あの少女のこれが父親であろう主人に、ざくざく髪を刈らせて、私は涼しく、大へん愉快であったという、それだけの悪徳物語である。
底本:「太宰治全集3」ちくま文庫、筑摩書房
1988(昭和63)年10月25日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月刊行
入力:柴田卓治
校正:小林繁雄
1999年10月20日公開
2005年10月27日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
眉山
太宰治
これは、れいの飲食店閉鎖の命令が、未いまだ発せられない前のお話である。
新宿辺も、こんどの戦火で、ずいぶん焼けたけれども、それこそ、ごたぶんにもれず最も早く復興したのは、飲み食いをする家であった。帝都座の裏の若松屋という、バラックではないが急ごしらえの二階建の家も、その一つであった。
「若松屋も、眉山びざんがいなけりゃいいんだけど。」
「イグザクトリイ。あいつは、うるさい。フウルというものだ。」
そう言いながらも僕たちは、三日に一度はその若松屋に行き、そこの二階の六畳で、ぶっ倒れるまで飲み、そうして遂ついに雑魚寝ざこねという事になる。僕たちはその家では、特別にわがままが利きいた。何もお金を持たずに行って、後払いという自由も出来た。その理由を簡単に言えば、三鷹みたかの僕の家のすぐ近くに、やはり若松屋というさかなやがあって、そこのおやじが昔から僕と飲み友達でもあり、また僕の家の者たちとも親しくしていて、そいつが、「行ってごらんなさい、私の姉が新宿に新しく店を出しました。以前は築地つきじでやっていたのですがね。あなたの事は、まえから姉に言っていたのです。泊って来たってかまやしません。」
僕はすぐに出かけ、酔っぱらって、そうして、泊った。姉というのはもう、初老のあっさりしたおかみさんだった。
何せ、借りが利くので重宝ちょうほうだった。僕は客をもてなすのに、たいていそこへ案内した。僕のところへ来る客は、自分もまあこれでも、小説家の端くれなので、小説家が多くならなければならぬ筈なのに、画家や音楽家の来訪はあっても、小説家は少かった。いや、ほとんど無いと言っても過言ではない状態であった。けれども、新宿の若松屋のおかみさんは、僕の連れて行く客は、全部みな小説家であると独ひとり合点がてんしている様子で、殊ことにも、その家の女中さんのトシちゃんは、幼少の頃より、小説というものがメシよりも好きだったのだそうで、僕がその家の二階に客を案内するともう、こちら、どなた? と好奇の眼をかがやかして僕に尋ねる。
「林芙美子さんだ。」
それは僕より五つも年上の頭の禿はげた洋画家であった。
「あら、だって、……」
小説というものがメシよりも好きと法螺ほらを吹いているトシちゃんは、ひどく狼狽ろうばいして、
「林先生って、男の方なの?」
「そうだ。高浜虚子きよこというおじいさんもいるし、川端龍子りゅうこという口髭くちひげをはやした立派な紳士もいる。」
「みんな小説家?」
「まあ、そうだ。」
それ以来、その洋画家は、新宿の若松屋に於おいては、林先生という事になった。本当は二科の橋田新一郎氏であった。
いちど僕は、ピアニストの川上六郎氏を、若松屋のその二階に案内した事があった。僕が下の御不浄に降りて行ったら、トシちゃんが、お銚子ちょうしを持って階段の上り口に立っていて、
「あのかた、どなた?」
「うるさいなあ。誰だっていいじゃないか。」
僕も、さすがに閉口していた。
「ね、どなた?」
「川上っていうんだよ。」
もはや向っ腹が立って来て、いつもの冗談も言いたく無く、つい本当の事を言った。
「ああ、わかった。川上眉山。」
滑稽こっけいというよりは、彼女のあまりの無智にうんざりして、ぶん殴りたいような気にさえなり、
「馬鹿野郎!」
と言ってやった。
それ以来、僕たちは、面と向えば彼女をトシちゃんと呼んでいたが、かげでは、眉山と呼ぶようになった。そうしてまた、若松屋の事を眉山軒などと呼ぶ人も出て来た。
眉山の年齢は、はたち前後とでもいうようなところで、その風采ふうさいは、背が低くて色が黒く、顔はひらべったく眼が細く、一つとしていいところが無かったけれども、眉まゆだけは、ほっそりした三ヶ月型で美しく、そのためにもまた、眉山という彼女のあだ名は、ぴったりしている感じであった。
けれども、その無智と図々ずうずうしさと騒がしさには、我慢できないものがあった。下にお客があっても、彼女は僕たちの二階のほうにばかり来ていて、そうして、何も知らんくせに自信たっぷりの顔つきで僕たちの話の中に割り込む。たとえば、こんな事もあった。
「でも、基本的人権というのは、……」
と、誰かが言いかけると、
「え?」
とすぐに出しゃばり、
「それは、どんなんです? やはり、アメリカのものなんですか? いつ、配給になるんです?」
人絹じんけんと間違っているらしいのだ。あまりひどすぎて一座みな興が覚さめ、誰も笑わず、しかめつらになった。
眉山ひとり、いかにも楽しげな笑顔で、
「だって、教えてくれないんですもの。」
「トシちゃん、下にお客さんが来ているらしいぜ。」
「かまいませんわ。」
「いや、君が、かまわなくたって、……」
だんだん不愉快になるばかりであった。
「白痴じゃないですか、あれは。」
僕たちは、眉山のいない時には、思い切り鬱憤うっぷんをはらした。
「いかに何でも、ひどすぎますよ。この家も、わるくはないが、どうもあの眉山がいるんじゃあ。」
「あれで案外、自惚うぬぼれているんだぜ。僕たちにこんなに、きらわれているとは露知らず、かえって皆の人気者、……」
「わあ! たまらねえ。」
「いや、おおきにそうかも知れん。なんでも、あれは、貴族、……」
「へえ? それは初耳。めずらしい話だな。眉山みずからの御託宣ですか?」
「そうですとも。その貴族の一件でね、あいつ大失敗をやらかしてね、誰かが、あいつをだまして、ほんものの貴婦人は、おしっこをする時、しゃがまないものだと教えたのですね、すると、あの馬鹿が、こっそり御不浄でためしてみて、いやもう、四方八方に飛散し、御不浄は海、しかもあとは、知らん顔、御承知でしょうが、ここの御不浄は、裏の菓物屋さんと共同のものなんですから、菓物屋さんは怒り、下のおかみさんに抗議して、犯人はてっきり僕たち、酔っぱらいには困る、という事になり、僕たちが無実の罪を着せられたというにがにがしい経験もあるんです、しかし、いくら僕たちが酔っぱらっていたって、あんな大洪水の失礼は致しませんからね、不審に思って、いろいろせんさくの結果、眉山でした、かれは僕たちにあっさり白状したんです、御不浄の構造が悪いんだそうです。」
「どうしてまた、貴族だなんて。」
「いまの、はやり言葉じゃないんですか? 何でも、眉山の家は、静岡市の名門で、……」
「名門? ピンからキリまであるものだな。」
「住んでいた家が、ばかに大きかったんだそうです。戦災で全焼していまは落ちぶれたんだそうですけどね、何せ帝都座と同じくらいの大きさだったというんだから、おどろきますよ。よく聞いてみると、何、小学校なんです。その小学校の小使さんの娘なんですよ、あの眉山は。」
「うん、それで一つ思い出した事がある。あいつの階段の昇り降りが、いやに乱暴でしょう。昇る時は、ドスンドスン、降りる時はころげ落ちるみたいに、ダダダダダ。いやになりますよ、ダダダダダと降りてそのまま御不浄に飛び込んで扉をピシャリッでしょう。おかげで僕たちが、ほら、いつか、冤罪えんざいをこうむった事があったじゃありませんか。あの階段の下には、もう一部屋あって、おかみさんの親戚しんせきのひとが、歯の手術に上京して来ていてそこに寝ていたのですね。歯痛には、あのドスンドスンもダダダダも、ひびきますよ。おかみさんに言ったってね、私はあの二階のお客さんたちに殺されますって。ところが僕たちの仲間には、そんな乱暴な昇り降りするひとは無い。でも、おかみさんに僕が代表で注意をされたんです。面白くないから、僕は、おかみさんに言いましたよ、あれは眉山、いや、トシちゃんにきまっていますって。すると、傍でそれを聞いていた眉山は、薄笑いして、私は小さい時から、しっかりした階段を昇り降りして育って来ましたから、とむしろ得意そうな顔で言うんですね。その時は、僕は、女って浅間あさましい虚栄の法螺ほらを吹くものだと、ただ呆あきれていたんですが、そうですか、学校育ちですか、それなら、法螺じゃありません、小学校のあの階段は頑丈ですからねえ。」
「聞けば聞くほど、いやになる。あすからもう、河岸かしをかえましょうよ。いい潮時ですよ。他にどこか、巣を捜しましょう。」
そのような決意をして、よその飲み屋をあちこち覗のぞいて歩いても、結局、また若松屋という事になるのである。何せ、借りが利くので、つい若松屋のほうに、足が向く。
はじめは僕の案内でこの家へ来たれいの頭の禿はげた林先生すなわち洋画家の橋田氏なども、その後は、ひとりでやって来てこの家の常連の一人になったし、その他にも、二、三そんな人物が出来た。
あたたかくなって、そろそろ桜の花がひらきはじめ、僕はその日、前進座の若手俳優の中村国男君と、眉山軒で逢って或る用談をすることになっていた。用談というのは、実は彼の縁談なのであるが、少しややこしく、僕の家では、ちょっと声をひそめて相談しなければならぬ事情もあったので、眉山軒で逢って互いに大声で論じ合うべく約束をしていたのである。中村国男君も、その頃はもう、眉山軒の半常連くらいのところになっていて、そうして眉山は、彼を中村武羅夫むらお氏だとばかり思い込んでいた。
行ってみると、中村武羅夫先生はまだ来ていなくて、林先生の橋田新一郎氏が土間のテーブルで、ひとりでコップ酒を飲みニヤニヤしていた。
「壮観でしたよ。眉山がミソを踏んづけちゃってね。」
「ミソ?」
僕は、カウンターに片肘かたひじをのせて立っているおかみさんの顔を見た。
おかみさんは、いかにも不機嫌そうに眉をひそめ、それから仕方無さそうに笑い出し、
「話にも何もなりやしないんですよ、あの子のそそっかしさったら。外からバタバタ眼つきをかえて駈かけ込んで来て、いきなり、ずぶりですからね。」
「踏んだのか。」
「ええ、きょう配給になったばかりのおミソをお重箱に山もりにして、私も置きどころが悪かったのでしょうけれど、わざわざそれに片足をつっ込まなくてもいいじゃありませんか。しかも、それをぐいと引き抜いて、爪先立つまさきだちになってそのまま便所ですからね。どんなに、こらえ切れなくなっていたって、何もそれほどあわて無くてもよろしいじゃございませんか。お便所にミソの足跡なんか、ついていたひには、お客さまが何と、……」
と言いかけて、さらに大声で笑った。
「お便所にミソは、まずいね。」
と僕は笑いをこらえながら、
「しかし、御不浄へ行く前でよかった。御不浄から出て来た足では、たまらない。何せ眉山の大海たいかいといってね、有名なものなんだからね、その足でやられたんじゃ、ミソも変じてクソになるのは確かだ。」
「何だか、知りませんがね、とにかくあのおミソは使い物になりやしませんから、いまトシちゃんに捨てさせました。」
「全部か? そこが大事なところだ。時々、朝ここで、おみおつけのごちそうになる事があるからな。後学のために、おたずねする。」
「全部ですよ。そんなにお疑いなら、もう、うちではお客さまに、おみおつけは、お出し致しません。」
「そう願いたいね。トシちゃんは?」
「井戸端いどばたで足を洗っています。」
と橋田氏は引き取り、
「とにかく壮烈なものでしたよ。私は見ていたんです。ミソ踏み眉山。吉右衛門きちえもんの当り芸になりそうです。」
「いや、芝居にはなりますまい。おミソの小道具がめんどうです。」
橋田氏は、その日、用事があるとかで、すぐに帰り、僕は二階にあがって、中村先生を待っていた。
ミソ踏み眉山は、お銚子を持ってドスンドスンとやって来た。
「君は、どこか、からだが悪いんじゃないか? 傍に寄るなよ、けがれるわい。御不浄にばかり行ってるじゃないか。」
「まさか。」
と、たのしそうに笑い、
「私ね、小さい時、トシちゃんはお便所へいちども行った事が無いような顔をしているって、言われたものだわ。」
「貴族なんだそうだからね。……しかし、僕のいつわらざる実感を言えば、君はいつでもたったいま御不浄から出て来ましたって顔をしているが、……」
「まあ、ひどい。」
でも、やはり笑っている。
「いつか、羽織の裾すそを背中に背負ったままの姿で、ここへお銚子を持って来た事があったけれども、あんなのは、一目瞭然いちもくりょうぜん、というのだ、文学のほうではね。どだい、あんな姿で、お酌しゃくするなんて、失敬だよ。」
「あんな事ばかり。」
平然たるものである。
「おい、君、汚いじゃないか。客の前で、爪の垢あかをほじくり出すなんて。こっちは、これでもお客だぜ。」
「あら、だって、あなたたちも、皆こうしていらっしゃるんでしょう? 皆さん、爪がきれいだわ。」
「ものが違うんだよ。いったい、君は、風呂へはいるのかね。正直に言ってごらん。」
「それあ、はいりますわよ。」
と、あいまいな返事をして、
「私ね、さっき本屋へ行ったのよ。そうしてこれを買って来たの。あなたのお名前も出ていてよ。」
ふところから、新刊の文芸雑誌を出して、パラパラ頁を繰って、その、僕の名前の出ているところを捜している様子である。
「やめろ!」
こらえ切れず、僕は怒声を発した。打ち据えてやりたいくらいの憎悪ぞうおを感じた。
「そんなものを、読むもんじゃない。わかりやしないよ、お前には。何だってまた、そんなものを買って来るんだい。無駄だよ。」
「あら、だって、あなたのお名前が。」
「それじゃ、お前は、僕の名前の出ている本を、全部片っ端から買い集めることが出来るかい。出来やしないだろう。」
へんな論理であったが、僕はムカついて、たまらなかった。その雑誌は、僕のところにも恵送せられて来ていたのであるが、それには僕の小説を、それこそ、クソミソに非難している論文が載っているのを僕は知っているのだ。それを、眉山がれいの、けろりとした顔をして読む。いや、そんな理由ばかりではなく、眉山ごときに、僕の名前や、作品を、少しでもいじられるのが、いやでいやで、堪え切れなかった。いや、案外、小説がメシより好き、なんて言っている連中には、こんな眉山級が多いのかも知れない。それに気附かず、作者は、汗水流し、妻子を犠牲にしてまで、そのような読者たちに奉仕しているのではあるまいか、と思えば、泣くにも泣けないほどの残念無念の情が胸にこみ上げて来るのだ。
「とにかく、その雑誌は、ひっこめてくれ。ひっこめないと、ぶん殴るぜ。」
「わるかったわね。」
と、やっぱりニヤニヤ笑いながら、
「読まなけれあいいんでしょう?」
「どだい、買うのが馬鹿の証拠だ。」
「あら、私、馬鹿じゃないわよ。子供なのよ。」
「子供? お前が? へえ?」
僕は二の句がつげず、しんから、にがり切った。
それから数日後、僕はお酒の飲みすぎで、突然、からだの調子を悪くして、十日ほど寝込み、どうやら恢復かいふくしたので、また酒を飲みに新宿に出かけた。
黄昏たそがれの頃だった。僕は新宿の駅前で、肩をたたかれ、振り向くと、れいの林先生の橋田氏が微醺びくんを帯びて笑って立っている。
「眉山軒ですか?」
「ええ、どうです、一緒に。」
と、僕は橋田氏を誘った。
「いや、私はもう行って来たんです。」
「いいじゃありませんか、もう一回。」
「おからだを、悪くしたとか、……」
「もう大丈夫なんです。まいりましょう。」
「ええ。」
橋田氏は、そのひとらしくも無く、なぜだか、ひどく渋々しぶしぶ応じた。
裏通りを選んで歩きながら、僕は、ふいと思い出したみたいな口調でたずねた。
「ミソ踏み眉山は、相変らずですか?」
「いないんです。」
「え?」
「きょう行ってみたら、いないんです。あれは、死にますよ。」
ぎょっとした。
「おかみから、いま聞いて来たんですけどね、」
と橋田氏も、まじめな顔をして、
「あの子は、腎臓結核じんぞうけっかくだったんだそうです。もちろん、おかみにも、また、トシちゃんにも、そんな事とは気づかなかったが、妙にお小用が近いので、おかみがトシちゃんを病院に連れて行って、しらべてもらったらその始末で、しかも、もう両方の腎臓が犯されていて、手術も何もすべて手おくれで、あんまり永い事は無いらしいのですね。それで、おかみは、トシちゃんには何も知らせず、静岡の父親のもとにかえしてやったんだそうです。」
「そうですか。……いい子でしたがね。」
思わず、溜息と共にその言葉が出て、僕は狼狽ろうばいし、自分で自分の口を覆おおいたいような心地がした。
「いい子でした。」
と、橋田氏は、落ちついてしみじみ言い、
「いまどき、あんないい気性の子は、めったにありませんですよ。私たちのためにも、一生懸命つとめてくれましたからね。私たちが二階に泊って、午前二時でも三時でも眼がさめるとすぐ、下へ行って、トシちゃん、お酒、と言えば、その一ことで、ハイッと返事して、寒いのに、ちっともたいぎがらずにすぐ起きてお酒を持って来てくれましたね、あんな子は、めったにありません。」
涙が出そうになったので、僕は、それをごまかそうとして、
「でも、ミソ踏み眉山なんて、あれは、あなたの命名でしたよ。」
「悪かったと思っているんです。腎臓結核は、おしっこが、ひどく近いものらしいですからね、ミソを踏んだり、階段をころげ落ちるようにして降りてお便所にはいるのも、無理がないんですよ。」
「眉山の大海たいかいも?」
「きまっていますよ、」
と橋田氏は、僕の茶化すような質問に立腹したような口調で、
「貴族の立小便なんかじゃありませんよ。少しでも、ほんのちょっとでも永く、私たちの傍にいたくて、我慢に我慢をしていたせいですよ。階段をのぼる時の、ドスンドスンも、病気でからだが大儀で、それでも、無理して、私たちにつとめてくれていたんです。私たちみんな、ずいぶん世話を焼かせましたからね。」
僕は立ちどまり、地団駄じだんだ踏みたい思いで、
「ほかへ行きましょう。あそこでは、飲めない。」
「同感です。」
僕たちは、その日から、ふっと河岸かしをかえた。
底本:「太宰治全集9」ちくま文庫、筑摩書房
1989(平成元)年5月30日第1刷発行
1998(平成10)年6月15日第5刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月発行
入力:柴田卓治
校正:かとうかおり
2000年1月23日公開
2005年11月7日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
チャンス
太宰治
人生はチャンスだ。結婚もチャンスだ。恋愛もチャンスだ。と、したり顔して教える苦労人が多いけれども、私は、そうでないと思う。私は別段、れいの唯物論的弁証法に媚こびるわけではないが、少くとも恋愛は、チャンスでないと思う。私はそれを、意志だと思う。
しからば、恋愛とは何か。私は言う。それは非常に恥かしいものである。親子の間の愛情とか何とか、そんなものとはまるで違うものである。いま私の机の傍の辞苑をひらいて見たら、「恋愛」を次の如ごとく定義していた。
「性的衝動に基づく男女間の愛情。すなわち、愛する異性と一体になろうとする特殊な性的愛。」
しかし、この定義はあいまいである。「愛する異性」とは、どんなものか。「愛する」という感情は、異性間に於いて、「恋愛」以前にまた別個に存在しているものなのであろうか。異性間に於いて恋愛でもなく「愛する」というのは、どんな感情だろう。すき。いとし。ほれる。おもう。したう。こがれる。まよう。へんになる。之等これらは皆、恋愛の感情ではないか。これらの感情と全く違って、異性間に於いて「愛する」というまた特別の感情があるのであろうか。よくキザな女が「恋愛抜きの愛情で行きましょうよ。あなたは、あたしのお兄さまになってね」などと言う事があるけれど、あれがつまり、それであろうか。しかし、私の経験に依よれば、女があんな事を言う時には、たいてい男がふられているのだと解して間違い無いようである。「愛する」もクソもありやしない。お兄さまだなんてばからしい。誰がお前のお兄さまなんかになってやるものか。話がちがうよ。
キリストの愛、などと言い出すのは大袈裟おおげさだが、あのひとの教える「隣人愛」ならばわかるのだが、恋愛でなく「異性を愛する」というのは、私にはどうも偽善のような気がしてならない。
つぎにまた、あいまいな点は、「一体になろうとする特殊な性的愛」のその「性的愛」という言葉である。
性が主なのか、愛が主なのか、卵が親か、鶏が親か、いつまでも循環するあいまい極きわまる概念である。性的愛、なんて言葉はこれは日本語ではないのではなかろうか。何か上品めかして言いつくろっている感じがする。
いったい日本に於いて、この「愛」という字をやたらに何にでもくっつけて、そうしてそれをどこやら文化的な高尚こうしょうなものみたいな概念にでっち上げる傾きがあるようで、(そもそも私は「文化」という言葉がきらいである。文のお化けという意味であろうか。昔の日本の本には、文華または文花と書いてある)恋と言ってもよさそうなのに、恋愛、という新語を発明し、恋愛至上主義なんてのを大学の講壇で叫んで、時の文化的なる若い男女の共鳴を得たりしたようであったが、恋愛至上というから何となく高尚みたいに聞えるので、これを在来の日本語で、色慾至上主義と言ったら、どうであろうか。交合至上主義と言っても、意味は同じである。そんなに何も私を、にらむ事は無いじゃないか。恋愛女史よ。
つまり私は恋愛の「愛」の字、「性的愛」の「愛」の字が、気がかりでならぬのである。「愛」の美名に依って、卑猥感ひわいかんを隠蔽いんぺいせんとたくらんでいるのではなかろうかとさえ思われるのである。
「愛」は困難な事業である。それは、「神」にのみ特有の感情かも知れない。人間が人間を「愛する」というのは、なみなみならぬ事である。容易なわざではないのである。神の子は弟子たちに「七度の七十倍ゆるせ」と教えた。しかし、私たちには、七度でさえ、どうであろうか。「愛する」という言葉を、気軽に使うのは、イヤミでしかない。キザである。
「きれいなお月さまだわねえ。」なんて言って手を握り合い、夜の公園などを散歩している若い男女は、何もあれは「愛し」合っているのではない。胸中にあるものは、ただ「一体になろうとする特殊な性的煩悶はんもん」だけである。
それで、私がもし辞苑の編纂者へんさんしゃだったならば、次のように定義するであろう。
「恋愛。好色の念を文化的に新しく言いつくろいしもの。すなわち、性慾衝動に基づく男女間の激情。具体的には、一個または数個の異性と一体になろうとあがく特殊なる性的煩悶。色慾の Warming-up とでも称すべきか。」
ここに一個または数個と記したのは、同時に二人あるいは三人の異性を恋い慕い得るという剛の者の存在をも私は聞き及んでいるからである。俗に、三角だの四角だのいう馬鹿らしい形容の恋の状態をも考慮にいれて、そのように記したのである。江戸の小咄こばなしにある、あの、「誰でもよい」と乳母うばに打ち明ける恋いわずらいの令嬢も、この数個のほうの部類にいれて差さし支つかえなかろう。
太宰もイヤにげびて来たな、と高尚な読者は怒ったかも知れないが、私だってこんな事を平気で書いているのではない。甚はなはだ不愉快な気持で、それでも我慢してこうして書いているのである。
だから私は、はじめから言ってある。
恋愛とは何か。
曰いわく、「それは非常に恥かしいものである」と。
その実態が、かくの如きものである以上、とてもそれは恥かしくて、口に出しては言えない言葉であるべき筈なのに、「恋愛」と臆おくするところ無くはっきりと発音して、きょとんとしている文化女史がその辺にもいたようであった。ましてや「恋愛至上主義」など、まあなんという破天荒はてんこう、なんというグロテスク。「恋愛は神聖なり」なんて飛んでも無い事を言い出して居直ろうとして、まあ、なんという図々ずうずうしさ。「神聖」だなんて、もったいない。口が腐りますよ。まあ、どこを押せばそんな音ねが出るのでしょう。色気違いじゃないかしら。とても、とても、あんな事が、神聖なものですか。
さて、それでは、その恋愛、すなわち色慾の Warming-up は、単にチャンスに依よってのみ開始せられるものであろうか。チャンスという異国語はこの場合、日本に於いて俗に言われる「ひょんな事」「ふとした事」「妙な縁」「きっかけ」「もののはずみ」などという意味に解してもよろしいかと思われるが、私の今日までの三十余年間の好色生活を回顧しても、そのような事から所謂いわゆる「恋愛」が開始せられた事は一度も無かった。「もののはずみ」で、つい、女性の繊手せんしゅを握ってしまった事も無かったし、いわんや、「ふとした事」から異性と一体になろうとあがく特殊なる性的煩悶、などという壮烈な経験は、私には未いまだかつて無いのである。
私は決して嘘うそをついているのではない。まあ、おしまいまで読み給え。
「もののはずみ」とか「ひょんな事」とかいうのは、非常にいやらしいものである。それは皆、拙劣きわまる演技でしかない。稲妻いなずま。あー こわー なんて男にしがみつく、そのわざとらしさ、いやらしさ。よせやい、と言いたい。こわかったら、ひとりで俯伏うつぶしたらいいじゃないか。しがみつかれた男もまた、へたくそな手つきで相手の肩を必要以上に強く抱いてしまって、こわいことない、だいじょぶ、など外人の日本語みたいなものを呟つぶやく。舌がもつれ、声がかすれているという情無い有様である。演技拙劣もきわまれりと言うべきである。「甘美なる恋愛」の序曲と称する「もののはずみ」とかいうものの実況は、たいていかくの如く、わざとらしく、いやらしく、あさましく、みっともないものである。
だいたいひとを馬鹿にしている。そんな下手へたくそな見えすいた演技を行っていながら、何かそれが天から与えられた妙な縁の如く、互いに首肯しゅこうし合おうというのだから、厚かましいにも程があるというものだ。自分たちの助平の責任を、何もご存じない天の神さまに転嫁しようとたくらむのだから、神さまだって唖然あぜんとせざるを得まい。まことにふとい了見りょうけんである。いくら神さまが寛大だからといって、これだけは御許容なさるまい。
寝てもさめても、れいの「性的煩悶」ばかりしている故に、そんな「もののはずみ」だの「きっかけ」だのでわけもなく「恋愛関係」に突入する事が出来るのかも知れないが、しかし心がそのところに無い時には、「きっかけ」も「妙な縁」もあったものでない。
いつか電車で、急停車のために私は隣りに立っている若い女性のほうによろめいた事があった。するとその女性は、けがらわしいとでもいうようなひどい嫌悪けんおと侮蔑ぶべつの眼つきで、いつまでも私を睨にらんでいた。たまりかねて私は、その女性の方に向き直り、まじめに、低い声で言ってやった。
「僕が何かあなたに猥褻わいせつな事でもしたのですか? 自惚うぬぼれてはいけません。誰があなたみたいな女に、わざとしなだれかかるものですか。あなたご自身、性慾が強いから、そんなへんな気のまわし方をするのだと思います。」
その女性は、私の話がはじまるやいなや、ぐいとそっぽを向いてしまって、全然聞えない振りをした。馬鹿野郎! と叫んで、ぴしゃんと頬を一つぶん殴ってやりたい気がした。かくの如く、心に色慾の無い時には、「きっかけ」も「もののはずみ」も甚はなはだ白々しい結果に終るものなのである。よく列車などで、向い合せに坐った女性と「ひょんな事」から恋愛関係におちいったなど、ばからしい話を聞くが、「ひょんな事」も「ふとした事」もありやしない。はじめから、そのつもりで両方が虎視眈々こしたんたん、何か「きっかけ」を作ろうとしてあがきもがいた揚句あげくの果の、ぎごちないぶざまな小細工こざいくに違いないのだ。心がそのところにあらざれば、脚がさわったって頬がふれたって、それが「恋愛」の「きっかけ」などになる筈は無いのだ。かつて私は新宿から甲府まで四時間汽車に乗り、甲府で下車しようとして立ち上り、私と向い合せに凄すごい美人が坐っていたのにはじめて気がつき、驚いた事がある。心に色慾の無い時は、凄いほどの美人と膝頭ひざがしらを接し合って四時間も坐っていながら、それに気がつかない事もあるのだ。いや、本当にこれは、事実談なのである。図に乗ってまくし立てるようだが、登楼とうろうして、おいらんと二人でぐっすり眠って、そうして朝まで、「ひょんな事」も「妙な縁」も何も無く、もちろんそれゆえ「恋愛」も何も起らず、「おや、お帰り?」「そう。ありがとう。」と一夜の宿のお礼を言ってそのまま引き上げた経験さえ私にはあった。
こんな事を言っていると、いかにも私は我慢してキザに木石を装っている男か、或あるいは、イムポテンツか、或いは、実は意馬心猿いばしんえんなりと雖いえども如何いかんせんもてず、振られどおしの男のように思うひともあるかも知れぬが、私は決してイムポテンツでもないし、また、そんな、振られどおしの哀あわれな男でも無いつもりでいる。要するに私の恋の成立不成立は、チャンスに依らず、徹頭徹尾、私自身の意志に依るのである。私には、一つのチャンスさえ無かったのに、十年間の恋をし続け得た経験もあるし、また、所謂絶好のチャンスが一夜のうちに三つも四つも重っても、何の恋愛も起らなかった事もある。恋愛チャンス説は、私に於いては、全く取るにも足らぬあさはかな愚説のようにしか思われない。それを立派に証明せんとする目的を以て、私は次に私の学生時代の或るささやかな出来事を記して置こうと思う。恋はチャンスに依らぬものだ。一夜に三つも四つも「妙な縁」やら「ふとした事」やら「思わぬきっかけ」やらが重って起っても、一向に恋愛が成立しなかった好例として、次のような私の体験を告白しようと思うのである。
あれは私が弘前ひろさきの高等学校にはいって、その翌年の二月のはじめ頃だったのではなかったかしら、とにかく冬の、しかも大寒だいかんの頃の筈である。どうしても大寒の頃でなければならぬわけがあるのだが、しかし、そのわけは、あとで言う事にして、何の宴会であったか、四五十人の宴会が弘前の或る料亭でひらかれ、私が文字どおりその末席に寒さにふるえながら坐っていた事から、この話をはじめたほうがよさそうである。
あれは何の宴会であったろう。何か文芸に関係のある宴会だったような気もする。弘前の新聞記者たち、それから町の演劇研究会みたいなもののメンバー、それから高等学校の先生、生徒など、いろいろな人たちで、かなり多人数の宴会であった。高等学校の生徒でそこに出席していたのは、ほとんど上級生ばかりで、一年生は、私ひとりであったような気がする。とにかく、私は末席であった。絣かすりの着物に袴はかまをはいて、小さくなって坐っていた。芸者が私の前に来て坐って、
「お酒は? 飲めないの?」
「だめなんだ。」
当時、私はまだ日本酒が飲めなかった。あのにおいが厭いやでたまらなかった。ビイルも飲めなかった。にがくて、とても、いけなかった。ポートワインとか、白酒とか、甘味のある酒でなければ飲めなかった。
「あなたは、義太夫ぎだゆうをおすきなの?」
「どうして?」
「去年の暮に、あなたは小土佐ことさを聞きにいらしてたわね。」
「そう。」
「あの時、あたしはあなたの傍にいたのよ。あなたは稽古本けいこぼんなんか出して、何だか印をつけたりして、きざだったわね。お稽古も、やってるの?」
「やっている。」
「感心ね。お師匠さんは誰?」
「咲栄太夫さきえだゆうさん。」
「そう。いいお師匠さんについたわね。あのかたは、この弘前では一ばん上手じょうずよ。それにおとなしくて、いいひとだわ。」
「そう。いいひとだ。」
「あんなひと、すき?」
「師匠だもの。」
「師匠だからどうなの?」
「そんな、すきだのきらいだのって、あのひとに失敬だ。あのひとは本当にまじめなひとなんだ。すきだのきらいだの。そんな、馬鹿な。」
「おや、そうですか。いやに固苦しいのね。あなたはこれまで芸者遊びをした事なんかあるの?」
「これからやろうと思っている。」
「そんなら、あたしを呼んでね、あたしの名はね、おしのというのよ。忘れないようにね。」
昔のくだらない花柳かりゅう小説なんていうものに、よくこんな場面があって、そうして、それが「妙な縁」という事になり、そこから恋愛がはじまるという陳腐ちんぷな趣向が少くなかったようであるが、しかし、私のこの体験談に於いては、何の恋愛もはじまらなかった。したがってこれはちっとも私のおのろけというわけのものではないから、読者も警戒御無用にしていただきたい。
宴会が終って私は料亭から出た。粉雪が降っている。ひどく寒い。
「待ってよ。」
芸者は酔っている。お高祖頭巾こそずきんをかぶっている。私は立ちどまって待った。
そうして私は、或る小さい料亭に案内せられた。女は、そこの抱かかえ芸者とでもいうようなものであったらしい。奥の部屋に通されて、私は炬燵こたつにあたった。
女はお酒や料理を自分で部屋に運んで来て、それからその家の朋輩ほうばいらしい芸者を二人呼んだ。みな紋附を着ていた。なぜ紋附を着ていたのか私にはわからなかったが、とにかく、その酔っているお篠しのという芸者も、その朋輩の芸者も、みな紋の附いた裾すその長い着物を着ていた。
お篠は、二人の朋輩を前にして、宣言した。
「あたしは、こんどは、このひとを好きになる事にしましたから、そのつもりでいて下さい。」
二人の朋輩は、イヤな顔をした。そうして、二人で顔を見合せ、何か眼で語り、それから二人のうちの若いほうの芸者が膝を少しすすめて、
「ねえさん、それは本気?」と怒っているような口調で問うた。
「ああ、本気だとも、本気だとも。」
「だめですよ。間違っています。」と若い子は眉まゆをひそめてまじめに言い、それから私にはよくわからない「花柳隠語」とでもいうような妙な言葉をつかって、三人の紋附の芸者が大いに言い争いをはじめた。
しかし、私の思いは、ただ一点に向って凝結されていたのである。炬燵の上にはお料理のお膳ぜんが載せられてある。そのお膳の一隅ぐうに、雀焼すずめやきの皿がある。私はその雀焼きが食いたくてならぬのだ。頃しも季節は大寒だいかんである。大寒の雀の肉には、こってりと油が乗っていて最もおいしいのである。寒雀かんすずめと言って、この大寒の雀は、津軽の童児の人気者で、罠わなやら何やらさまざまの仕掛けをしてこの人気者をひっとらえては、塩焼きにして骨ごとたべるのである。ラムネの玉くらいの小さい頭も全部ばりばり噛かみくだいてたべるのである。頭の中の味噌みそはまた素敵においしいという事になっていた。甚だ野蛮な事には違いないが、その独特の味覚の魅力に打ち勝つ事が出来ず、私なども子供の頃には、やはりこの寒雀を追いまわしたものだ。
お篠さんが紋附の長い裾をひきずって、そのお料理のお膳を捧げて部屋へはいって来て、(すらりとしたからだつきで、細面ほそおもての古風な美人型のひとであった。としは、二十二、三くらいであったろうか。あとで聞いた事だが、その弘前の或る有力者のお妾めかけで、まあ、当時は一流のねえさんであったようである)そうして、私のあたっている炬燵の上に置いた瞬間、既に私はそのお膳の一隅に雀焼きを発見し、や、寒雀! と内心ひそかに狂喜したのである。たべたかった。しかし、私はかなりの見栄坊であった。紋附を着た美しい芸者三人に取りまかれて、ばりばりと寒雀を骨ごと噛みくだいて見せる勇気は無かった。ああ、あの頭の中の味噌はどんなにかおいしいだろう。思えば、寒雀もずいぶんしばらく食べなかったな、と悶もだえても、猛然とそれを頬張る蛮勇は無いのである。私は仕方なく銀杏ぎんなんの実を爪楊枝つまようじでつついて食べたりしていた。しかし、どうしても、あきらめ切れない。
一方、女どもの言い争いは、いつまでもごたごた続いている。
私は立上って、帰ると言った。
お篠は、送ると言った、私たちは、どやどやと玄関に出た。あ、ちょっと、と言って、私は飛鳥の如く奥の部屋に引返し、ぎょろりと凄くあたりを見廻し、矢庭やにわにお膳の寒雀二羽を掴つかんでふところにねじ込み、それからゆっくり玄関へ出て行って、
「わすれもの。」と嗄しゃがれた声で嘘を言った。
お篠はお高祖頭巾をかぶって、おとなしく私の後について来た。私は早く下宿へ行って、ゆっくり二羽の寒雀を食べたいとそればかり思っていた。二人は雪路を歩きながら、格別なんの会話も無い。
下宿の門はしまっていた。
「ああ、いけない。しめだしを食っちゃった。」
その家の御主人は厳格なひとで、私の帰宅のおそすぎる時には、こらしめの意味で門をしめてしまうのである。
「いいわよ。」とお篠は落ちついて、「知ってる旅館がありますから。」
引返して、そのお篠の知っている旅館に案内してもらった。かなり上等の宿屋である。お篠は戸を叩いて番頭を起し、私の事をたのんだ。
「さようなら。どうも、ありがとう。」と私は言った。
「さようなら。」とお篠も言った。
これでよし、あとはひとりで雀焼きという事になる。私は部屋に通され、番頭の敷いてくれた蒲団ふとんにさっさともぐり込んで、さて、これからゆっくり寒雀をと思ったとたんに玄関で、
「番頭さん!」と呼ぶお篠の声。私は、ぎょっとして耳をすました。
「あのね、下駄げたの鼻緒はなおを切らしちゃったの。お願いだから、すげてね。あたしその間、お客さんの部屋で待ってるわ。」
これはいけない、と私は枕元まくらもとの雀焼きを掛蒲団の下にかくした。
お篠は部屋へはいって来て、私の枕元にきちんと坐り、何だか、いろいろ話しかける。私は眠そうな声で、いい加減の返辞をしている。掛蒲団の下には雀焼きがある。とうとうお篠とは、これほどたくさんのチャンスがあったのに、恋愛のレの字も起らなかった。お篠はいつまでも私の枕元に坐っていて、そうしてこう言った。
「あたしを、いやなの。」
私はそれに対してこう答えた。
「いやじゃないけど、ねむくって。」
「そう。それじゃまたね。」
「ああ、おやすみ。」と私のほうから言った。
「おやすみなさい。」
とお篠も言って、やっと立ち上った。
そうして、それだけであった。その後、私は芸者遊びなど大いにするようになったが、なぜだか弘前で遊ぶのは気がひけて、おもに青森の芸者と遊んだ。問題の雀焼きは、お篠の退去後に食べたか、または興覚めて棄てちゃったか、思い出せない。さすがに、食べるのがいやになって、棄てちゃったような気もする。
これが即ち、恋はチャンスに依らぬものだ、一夜のうちに「妙な縁」やら「ふとした事」やら「もののはずみ」やらが三つも四つも重って起っても、或る強固な意志のために、一向に恋愛が成立しないという事の例証である。ただもう「ふとした事」で恋愛が成立するものとしたら、それは実に卑猥ひわいな世相になってしまうであろう。恋愛は意志に依るべきである。恋愛チャンス説は、淫乱いんらんに近い。それではもう一つの、何のチャンスも無かったのに、十年間の恋をし続け得た経験とはどんなものであるかと読者にたずねられたならば、私は次のように答えるであろう。それは、片恋というものであって、そうして、片恋というものこそ常に恋の最高の姿である。
庭訓ていきん。恋愛に限らず、人生すべてチャンスに乗ずるのは、げびた事である。
底本:「太宰治全集8」ちくま文庫、筑摩書房
1989(平成元)年4月25日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月
入力:柴田卓治
校正:miyako
2000年4月7日公開
2005年11月4日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
父
太宰治
イサク、父ちちアブラハムに語かたりて、
父ちちよ、と曰いふ。
彼かれ、答こたへて、
子こよ、われ此ここにあり、
といひければ、
──創世記二十二ノ七
義のために、わが子を犠牲にするという事は、人類がはじまって、すぐその直後に起った。信仰の祖といわれているアブラハムが、その信仰の義のために、わが子を殺そうとした事は、旧約の創世記に録されていて有名である。
ヱホバ、アブラハムを試みんとて、
アブラハムよ、
と呼びたまふ。
アブラハム答へていふ、
われここにあり。
ヱホバ言ひたまひけるは、
汝なんじの愛する独子ひとりご、すなはちイサクを携たずさへ行き、かしこの山の頂きに於おいて、イサクを燔祭はんさいとして献ささぐべし。
アブラハム、朝つとに起きて、その驢馬ろばに鞍くらを置き、愛するひとりごイサクを乗せ、神のおのれに示したまへる山の麓ふもとにいたり、イサクを驢馬よりおろし、すなはち燔祭の柴薪たきぎをイサクに背負はせ、われはその手に火と刀を執とりて、二人ともに山をのぼれり。
イサク、父アブラハムに語りて、
父よ、
と言ふ。
彼、こたへて、
子よ、われここにあり、
といひければ、
イサクすなはち父に言ふ、
火と柴薪たきぎは有り、されど、いけにへの小羊は何処いずこにあるや。
アブラハム、言ひけるは、
子よ、神みづから、いけにへの小羊を備へたまはん。
斯かくして二人ともに進みゆきて、遂ついに山のいただきに到れり。
アブラハム、壇を築き、柴薪をならべ、その子イサクを縛りて、之これを壇の柴薪の上に置のせたり。
すなはち、アブラハム、手を伸べ、刀を執りて、その子を殺さんとす。
時に、ヱホバの使者、天より彼を呼びて、
アブラハムよ、
アブラハムよ、
と言へり。
彼言ふ、
われ、ここにあり。
使者の言ひけるは、
汝の手を童子わらべより放て、
何をも彼に為すべからず、
汝はそのひとりごをも、わがために惜まざれば、われいま汝が神を畏おそるるを知る。
云々うんぬんというような事で、イサクはどうやら父に殺されずにすんだのであるが、しかし、アブラハムは、信仰の義者ただしきものたる事を示さんとして躊躇ちゅうちょせず、愛する一人息子を殺そうとしたのである。
洋の東西を問わず、また信仰の対象の何たるかを問わず、義の世界は、哀かなしいものである。
佐倉宗吾郎一代記という活動写真を見たのは、私の七つか八つの頃の事であったが、私はその活動写真のうちの、宗吾郎の幽霊が悪代官をくるしめる場面と、それからもう一つ、雪の日の子わかれの場を、いまでも忘れずにいる。
宗吾郎が、いよいよ直訴じきそを決意して、雪の日に旅立つ。わが家の格子窓こうしまどから、子供らが顔を出して、別れを惜しむ。ととさまえのう、と口々に泣いて父を呼ぶ。宗吾郎は、笠かさで自分の顔を覆うて、渡し舟に乗る。降りしきる雪は、吹雪ふぶきのようである。
七つ八つの私は、それを見て涙を流したのであるが、しかし、それは泣き叫ぶ子供に同情したからではなかった。義のために子供を捨てる宗吾郎のつらさを思って、たまらなくなったからであった。
そうして、それ以来、私には、宗吾郎が忘れられなくなったのである。自分がこれから生き伸びて行くうちに、必ずあの宗吾郎の子別れの場のような、つらくてかなわない思いをする事が、二度か三度あるに違いないという予感がした。
私のこれまでの四十年ちかい生涯に於いて、幸福の予感は、たいていはずれるのが仕来しきたりになっているけれども、不吉の予感はことごとく当った。子わかれの場も、二度か三度、どころではなく、この数年間に、ほとんど一日置きくらいに、実にひんぱんに演ぜられて来ているのである。
私さえいなかったら、すくなくとも私の周囲の者たちが、平安に、落ちつくようになるのではあるまいか。私はことし既に三十九歳になるのであるが、私のこれまでの文筆に依よって得た収入の全部は、私ひとりの遊びのために浪費して来たと言っても、敢あえて過言ではないのである。しかも、その遊びというのは、自分にとって、地獄の痛苦のヤケ酒と、いやなおそろしい鬼女とのつかみ合いの形に似たる浮気であって、私自身、何のたのしいところも無いのである。また、そのような私の遊びの相手になって、私の饗応きょうおうを受ける知人たちも、ただはらはらするばかりで、少しも楽しくない様子である。結局、私は私の全収入を浪費して、ひとりの人間をも楽しませる事が出来ず、しかも女房が七輪しちりん一つ買っても、これはいくらだ、ぜいたくだ、とこごとを言う自分勝手の亭主なのである。よろしくないのは、百も承知である。しかし私は、その癖を直す事が出来なかった。戦争前もそうであった。戦争中もそうであった。戦争の後も、そうである。私は生れた時から今まで、実にやっかいな大病にかかっているのかも知れない。生れてすぐにサナトリアムみたいなところに入院して、そうして今日まで充分の療養の生活をして来たとしても、その費用は、私のこれまでの酒煙草の費用の十分の一くらいのものかも知れない。実に、べらぼうにお金のかかる大病人である。一族から、このような大病人がひとり出たばかりに、私の身内の者たちは、皆痩やせて、一様に少しずつ寿命をちぢめたようだ。死にやいいんだ。つまらんものを書いて、佳作だの何だのと、軽薄におだてられたいばかりに、身内の者の寿命をちぢめるとは、憎みても余りある極悪人ではないか。死ね!
親が無くても子は育つ、という。私の場合、親が有るから子は育たぬのだ。親が、子供の貯金をさえ使い果している始末なのだ。
炉辺の幸福。どうして私には、それが出来ないのだろう。とても、いたたまらない気がするのである。炉辺が、こわくてならぬのである。
午後三時か四時頃、私は仕事に一区切りをつけて立ち上る。机の引出しから財布さいふを取り出し、内容をちらと調べて懐ふところにいれ、黙って二重廻しを羽織って、外に出る。外では、子供たちが遊んでいる。その子供たちの中に、私の子もいる。私の子は遊びをやめて、私のほうに真正面向いて、私の顔を仰ぎ見る。私も、子の顔を見下す。共に無言である。たまに私は、袂たもとからハンケチを出して、きゅっと子の洟はなを拭いてやる事もある。そうして、さっさと私は歩く。子供のおやつ、子供のおもちゃ、子供の着物、子供の靴、いろいろ買わなければならぬお金を、一夜のうちに紙屑かみくずの如く浪費すべき場所に向って、さっさと歩く。これがすなわち、私の子わかれの場なのである。出掛けたらさいご、二日も三日も帰らない事がある。父はどこかで、義のために遊んでいる。地獄の思いで遊んでいる。いのちを賭かけて遊んでいる。母は観念して、下の子を背負い、上の子の手を引き、古本屋に本を売りに出掛ける。父は母にお金を置いて行かないから。
そうして、ことしの四月には、また子供が生れるという。それでなくても乏しかった衣類の、大半を、戦火で焼いてしまったので、こんど生れる子供の産衣うぶぎやら蒲団ふとんやら、おしめやら、全くやりくりの方法がつかず、母は呆然ぼうぜんとして溜息ためいきばかりついている様子であるが、父はそれに気附かぬ振りしてそそくさと外出する。
ついさっき私は、「義のために」遊ぶ、と書いた。義? たわけた事を言ってはいけない。お前は、生きている資格も無い放埒病ほうらつびょうの重患者に過ぎないではないか。それをまあ、義、だなんて。ぬすびとたけだけしいとは、この事だ。
それは、たしかに、盗人の三分さんぶの理にも似ているが、しかし、私の胸の奥の白絹に、何やらこまかい文字が一ぱいに書かれている。その文字は、何であるか、私にもはっきり読めない。たとえば、十匹の蟻ありが、墨汁の海から這はい上って、そうして白絹の上をかさかさと小さい音をたてて歩き廻り、何やらこまかく、ほそく、墨の足跡をえがき印し散らしたみたいな、そんな工合いの、幽かすかな、くすぐったい文字。その文字が、全部判読できたならば、私の立場の「義」の意味も、明白に皆に説明できるような気がするのだけれども、それがなかなか、ややこしく、むずかしいのである。
こんな譬喩ひゆを用いて、私はごまかそうとしているのでは決してない。その文字を具体的に説明して聞かせるのは、むずかしいのみならず、危険なのだ。まかり間違うと、鼻持ちならぬキザな虚栄の詠歎に似るおそれもあり、または、呆あきれるばかりに図々ずうずうしい面つらの皮千枚張りの詭弁きべん、または、淫祠いんし邪教のお筆先、または、ほら吹き山師の救国政治談にさえ堕する危険無しとしない。
それらの不潔な虱しらみと、私の胸の奥の白絹に書かれてある蟻の足跡のような文字とは、本質に於いて全く異るものであるという事には、私も確信を持っているつもりであるが、しかし、その説明は出来ない。また、げんざい、しようとも思わぬ。キザな言い方であるが、花ひらく時節が来なければ、それは、はっきり解明できないもののようにも思われる。
ことしの正月、十日頃、寒い風の吹いていた日に、
「きょうだけは、家にいて下さらない?」
と家の者が私に言った。
「なぜだ。」
「お米の配給があるかも知れませんから。」
「僕が取りに行くのか?」
「いいえ。」
家の者が二、三日前から風邪かぜをひいて、ひどいせきをしているのを、私は知っていた。その半病人に、配給のお米を背負わせるのは、むごいとも思ったが、しかし、私自身であの配給の列の中にはいるのも、頗すこぶるたいぎなのである。
「大丈夫か?」
と私は言った。
「私がまいりますけど、子供を連れて行くのは、たいへんですから、あなたが家にいらして、子供たちを見ていて下さい。お米だけでも、なかなか重いんです。」
家の者の眼には、涙が光っていた。
おなかにも子供がいるし、背中にひとりおんぶして、もうひとりの子の手をひいて、そうして自身もかぜ気味で、一斗ちかいお米を運ぶ苦難は、その涙を見るまでもなく、私にもわかっている。
「いるさ。いるよ。家にいるよ。」
それから、三十分くらい経って、
「ごめん下さい。」
と玄関で女のひとの声がして、私が出て見ると、それは三鷹みたかの或るおでんやの女中であった。
「前田さんが、お見えになっていますけど。」
「あ、そう。」
部屋の出口の壁に吊り下げられている二重廻しに、私はもう手をかけていた。
とっさに、うまい嘘うそも思いつかず、私は隣室の家の者には一言も、何も言わず、二重廻しを羽織って、それから机の引出しを掻かきまわし、お金はあまり無かったので、けさ雑誌社から送られて来たばかりの小為替こがわせを三枚、その封筒のまま二重廻しのポケットにねじ込み、外に出た。
外には、上の女の子が立っていた。子供のほうで、間まの悪そうな顔をしていた。
「前田さんが? ひとりで?」
私はわざと子供を無視して、おでんやの女中にたずねた。
「ええ。ちょっとでいいから、おめにかかりたいって。」
「そう。」
私たちは子供を残して、いそぎ足で歩いた。
前田さんとは、四十を越えた女性であった。永い事、有楽町の新聞社に勤めていたという。しかし、いまは何をしているのか、私にもわからない。そのひとは、二週間ほど前、年の暮に、そのおでんやに食事をしに来て、その時、私は、年少の友人ふたりを相手に泥酔でいすいしていて、ふとその女のひとに話しかけ、私たちの席に参加してもらって、私はそのひとと握手をした、それだけの附合いしか無かったのであるが、
「遊ぼう。これから、遊ぼう。大いに、遊ぼう。」
と私がそのひとに言った時に、
「あまり遊べない人に限って、そんなに意気込むものですよ。ふだんケチケチ働いてばかりいるんでしょう?」
とそのひとが普通の音声で、落ちついて言った。
私は、どきりとして、
「よし、そんならこんど逢った時、僕の徹底的な遊び振りを見せてあげる。」
と言ったが、内心は、いやなおばさんだと思った。私の口から言うのもおかしいだろうが、こんなひとこそ、ほんものの不健康というものではなかろうかと思った。私は苦悶くもんの無い遊びを憎悪する。よく学び、よく遊ぶ、その遊びを肯定する事が出来ても、ただ遊ぶひと、それほど私をいらいらさせる人種はいない。
ばかな奴だと思った。しかし、私も、ばかであった。負けたくなかった。偉そうな事を言ったって、こいつは、どうせ俗物に違いないんだ。この次には、うんと引っぱり歩いて、こづきまわして、面皮をひんむいてやろうと思った。
いつでもお相手をするから、気のむいたときに、このおでんやに来て、そうして女中を使って僕を呼び出しなさい、と言って、握手をしてわかれたのを、私は泥酔していても、忘れてはいなかった。
と書けば、いかにも私ひとり高潔の、いい子のようになってしまうが、しかし、やっぱり、泥酔の果の下等な薄汚いお色気だけのせいであったのかも知れない。謂いわば、同臭相寄るという醜怪な図に過ぎなかったのかも知れない。
私は、その不健康な、悪魔の許もとにいそいで出掛けた。
「おめでとう。新年おめでとう。」
私はそんな事を前田さんに、てれ隠しに言った。
前田さんは、前は洋装であったが、こんどは和服であった。おでんやの土間の椅子に腰かけて、煙草を吸っていた。痩やせて、背の高いひとであった。顔は細長くて蒼白く、おしろいも口紅もつけていないようで、薄い唇は白く乾いている感じであった。かなり度の強い近眼鏡をかけ、そうして眉間みけんには深い縦皺たてじわがきざまれていた。要するに、私の最も好かない種属の容色であった。先夜の酔眼には、も少しましなひとに見えたのだが、いま、しらふでまともに見て、さすがにうんざりしたのである。
私はただやたらにコップ酒をあおり、そうして、おもに、おでんやのおかみや女中を相手におしゃべりした。前田さんは、ほとんど何も口をきかず、お酒もあまり飲まなかった。
「きょうは、ばかに神妙じゃありませんか。」
と私は実に面白くない気持で、そう言ってみた。
しかし、前田さんは、顔を伏せたまま、ふんと笑っただけだった。
「思い切り遊ぶという約束でしたね。」と私はさらに言った。「少し飲みなさいよ。こないだの晩は、かなり飲みましたね。」
「昼は、だめなんですの。」
「昼だって、夜だって同じ事ですよ。あなたは、遊びのチャンピオンなんでしょう?」
「お酒は、プレイのうちにはいりませんわ。」
と小生意気な事を言った。
私はいよいよ興覚めて、
「それじゃ何がいいんですか? 接吻せっぷんですか?」
色婆め! こっちは、子わかれの場まで演じて、遊びの附合いをしてやっているんだ。
「わたくし、帰りますわ。」女はテーブルの上のハンドバッグを引き寄せ、「失礼しました。そんなつもりで、お呼びしたのでは、……」と言いかけて、泣き面つらになった。
それは、実にまずい顔つきであった。あまりにまずくて、あわれであった。
「あ、ごめんなさい。一緒に出ましょう。」
女は幽かすかに首肯うなずき、立って、それから、はなをかんだ。
一緒に外へ出て、
「僕は野蛮人でね、プレイも何も知らんのですよ。お酒がだめなら、困ったな。」
なぜこのまますぐに、おわかれが出来ないのだろう。
女は、外へ出ると急に元気になって、
「恥をかきましたわ。あそこのおでんやは、わたくし、せんから知っているんですけど、きょう、あなたをお呼びしてって、おかみさんにたのんだら、とてもいやな、へんな顔をするんですもの。わたくしなんかもう、女でも何でも無いのに、いやあねえ。あなたは、どうなの? 男ですか?」
いよいよキザな事を言う。しかし、それでも私は、まださよならが言えなかった。
「遊びましょう。何かプレイの名案が無いですか?」
と、気持とまるで反対の事を、足もとの石ころを蹴けって言った。
「わたくしのアパートにいらっしゃいません? きょうは、はじめから、そのつもりでいたのよ。アパートには、面白いお友達がたくさんいますわ。」
私は憂鬱ゆううつであった。気がすすまないのだ。
「アパートに行けば、すばらしいプレイがあるのですか?」
くすと笑って、
「何もありやしませんわ。作家って、案外、現実家なのねえ。」
「そりゃ、……」
と私は、言いかけて口を噤つぐんだ。
いた! いたのだ。半病人の家の者が、白いガーゼのマスクを掛けて、下の男の子を背負い、寒風に吹きさらされて、お米の配給の列の中に立っていたのだ。家の者は、私に気づかぬ振りをしていたが、その傍に立っている上の女の子は、私を見つけた。女の子は、母の真似まねをして、小さい白いガーゼのマスクをして、そうして白昼、酔ってへんなおばさんと歩いている父のほうへ走って来そうな気配を示し、父は息いきの根のとまる思いをしたが、母は何気無さそうに、女の子の顔を母のねんねこの袖そでで覆おおいかくした。
「お嬢さんじゃありません?」
「冗談じゃない。」
笑おうとしたが、口がゆがんだだけだった。
「でも、感じがどこやら、……」
「からかっちゃいけない。」
私たちは、配給所の前を通り過ぎた。
「アパートは? 遠いんですか?」
「いいえ、すぐそこよ。いらして下さる? お友達がよろこぶわ。」
家の者にお金を置いて来なかったが、大丈夫なのかしら。私は脂汗あぶらあせを流していた。
「行きましょう。どこか途中に、ウイスキイでも、ゆずってくれる店が無いかな?」
「お酒なら、わたくし、用意してありますわ。」
「どれくらい?」
「現実家ねえ。」
アパートの、前田さんの部屋には、三十歳をとうに越えて、やはりどうにも、まともでない感じの女が二人、あそびに来ていた。そうして色気も何もなく、いや、色気におびえて発狂気味、とでも言おうか、男よりも乱暴なくらいの態度で私に向って話しかけ、また女同士で、哲学だか文学だか美学だか、なんの事やら、まるでちっともなっていない、阿呆あほくさい限りの議論をたたかわすのである。地獄だ、地獄だ、と思いながら、私はいい加減のうけ応えをして酒を飲み、牛鍋ぎゅうなべをつつき散らし、お雑煮ぞうにを食べ、こたつにもぐり込んで、寝て、帰ろうとはしないのである。
義。
義とは?
その解明は出来ないけれども、しかし、アブラハムは、ひとりごを殺さんとし、宗吾郎は子わかれの場を演じ、私は意地になって地獄にはまり込まなければならぬ、その義とは、義とは、ああやりきれない男性の、哀しい弱点に似ている。
底本:「太宰治全集9」ちくま文庫、筑摩書房
1989(平成元)年5月30日第1刷発行
1998(平成10)年6月15日第5刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月発行
入力:柴田卓治
校正:かとうかおり
2000年1月23日公開
2005年11月6日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
小さいアルバム
太宰治
せっかくおいで下さいましたのに、何もおかまい出来ず、お気の毒に存じます。文学論も、もう、あきました。なんの事はない、他人の悪口を言うだけの事じゃありませんか。文学も、いやになりました。こんな言いかたは、どうでしょう。「かれは、文学がきらいな余りに文士になった。」
本当ですよ。もともと戦いを好まぬ国民が、いまは忍ぶべからずと立ち上った時、こいつは強い。向うところ敵なしじゃないか。君たちも、も少し、文学ぎらいになったらどうだね。真に新しいものは、そんなところから生れて来るのですよ。
まあ私の文学論は、それだけで、あとは、鳴かぬ蛍ほたる、沈黙の海軍というところです。
どうも、せっかく遊びにおいで下さったのに、こんなに何も、あいそが無くては、私のほうでしょげてしまいます。お酒でもあるといいんだけど、二、三日前に配給されたお酒は、もう、その日のうちに飲んでしまって、まことに生憎あいにくでした。どこかへ飲みに出たいものですね。ところが、これも生憎で、あははは、──無いんだ。今月はお金を使いすぎて、蟄居ちっきょの形なのです。本を売ってまで飲みたくはないし、まあ、がまんして、お茶でも飲んで、今夜これからどうして遊ぶか、ゆっくり考えてみましょうか。
君は遊びに来たのでしょう? どこへ行っても軽蔑けいべつされるし、懐中も心細いし、Dのところへでも行ったら、あるいは気が晴れるかも知れん、と思ってやって来たのでしょう? 光栄な事だ。そんなに、たよりにされて、何一つ期待に添わぬというのも、むごい話だ。
よろしい。今夜は一つ、私のアルバムをお見せしましょう。面白い写真も、あるかも知れない。お客の接待にアルバムを出すというのは、こいつあ、よっぽど情熱の無い証拠なのだ。いい加減にあしらって、ていよく追い帰そうとしている時に、この、アルバムというやつが出るものだ。注意し給え。怒っちゃいけない。私の場合は、そうじゃないんだ。今夜は、生憎お酒も無ければ、お金も無い。文学論も、いやだ。けれども君を、このままむなしく帰らせるのも心苦しくて、謂いわば、窮余の一策として、こんな貧弱なアルバムを持ち出したというわけだ。元来、私は、自分の写真などを、人に見せるのは、実に、いや味な事だと思っている。失敬な事だ。よほど親しい間柄の人にでもなければ、見せるものではない。男が、いいとしをして、みっともない。私は、どうも、写真そのものに、どだい興味がないのです。撮影する事にも、撮影される事にも、ちっとも興味がない。写真というものを、まるで信用していないのです。だから、自分の写真でも、ひとの写真でも、大事に保存しているというようなことは無い。たいてい、こんな、机の引出しなんかへ容いれっ放ぱなしにして置くので、大掃除や転居の度毎に少しずつ散逸さんいつして、残っているのは、ごくわずかになってしまいました。先日、家内が、その残っているわずかな写真を整理して、こんなアルバムを作って、はじめは私も、大袈裟おおげさな事をする、と言って不賛成だったのですが、でも、こうして出来上ったのを、ゆっくり見ているうちに、ちょっとした感慨も湧わいて来ました。けれどもそれは、私ひとりに限られたひそかな感慨で、よその人が見たって、こんなもの、ちっとも面白くもなんとも無いかも知れません。今夜は、どうも、他に話題も無いし、せっかくおいで下さったのになんのおかまいも出来ず、これでは余り殺風景ですから、窮した揚句の果に、こんなものを持ち出したのですから、そこのところは貧者一燈の心意気にめんじて、面白くもないだろうけれど見てやって下さい。
一つ、説明してあげましょうか。下手な紙芝居みたいになるかも知れませんが、笑わずに、まあ聞き給え。
あまり古い写真は無い。前にも言ったように、移転やら大掃除やらで、いつのまにか無くなってしまいました。アルバムの最初のペエジには、たいてい、その人の父母の写真が貼はられているものですが、私のアルバムにはそれも無い。父母の写真どころか、肉親の写真が一枚も無い。いや去年の秋、すぐ上の姉がその幼い長女と共に写した手札型の写真を一枚送ってよこしたが、本当に、その写真一枚きりで、他の肉親の写真は何も無いのだ。私がわざと肉親の写真を排除したわけではない。十数年前から、故郷の肉親たちと文通していないので、自然と、そんな結果になってしまったのだ。また、たいていのアルバムには、その持主の赤児の時の写真、あるいは小学生時代の写真などもあって興を添えているものだが、私のアルバムには、それも無い。故郷の家には、保存されているかも知れぬが、私の手許てもとには無い。だから、このアルバムを見ただけでは、人は私を、どこの馬の骨だか見当も何もつかぬ筈はずです。考えてみると、うすら寒いアルバムですね。開巻、第一ペエジ、もう主人公はこのとおり高等学校の生徒だ。実に、唐突とうとつな第一ペエジです。
これはH高等学校の講堂だ。生徒が四十人ばかり、行儀よくならんでいるが、これは皆、私の同級生です。主任の教授が、前列の中央に腰かけていますね。これは英語の先生で、私は時々、この先生にほめられた。笑っちゃいけない。本当ですよ。私だって、このころは、大いに勉強したものだ。この先生にばかりでなく、他の二、三の先生にもほめられた。本当ですよ。首席になってやろうと思って努力したが、到底だめだった。この、三列目の端に立っている小柄な生徒、この生徒だけには、どうしてもかなわなかった。こいつは、出来た。こんな、ぼんやりした顔をしていながら、実に、よく出来た。意気込んだところが一つも無くて、そうして堅実だった。あんなのを、ほんものというのかも知れない。いまは朝鮮の銀行に勤めているとかいう話だが、このひとに較べたら私なんかは、まず、おっちょこちょいの軽薄才士とでもいったところかね。見給え、私がこの写真のどこにいるか、わかるかね? そうだ、その主任の教授にぴったり寄り添って腰かけて、いかにも、どうも、軽薄に、ニヤリと笑っている生徒が私だ。十九歳にして、既にこのように技巧的である。まったく、いやになるね。なぜ、笑ったりなんかしているのだろう。見給え、この約四十人の生徒の中で、笑っているのは、私ひとりじゃないか。とても厳粛な筈の記念撮影に、ニヤリと笑うなどとは、ふざけた話だ。不謹慎だよ。どうして、こうなんだろうね。撮影の前のドサクサにまぎれて、いつのまにやら、ちゃんと最前列の先生の隣席に坐ってニヤリと笑っている。呆あきれた奴だ。こんなのが大きくなって、掏摸すりの名人なんかになるものだ。けれども、案外にも、どこか一つ大きく抜けているところがあると見えて、掏摸の親方になれなかったばかりか、いやもう、みっともない失敗の連続で、以後十数年間、泣いたりわめいたり、きざに唸うなるやら呻うめくやら大変な騒ぎでありました。
それ、ごらん。その次の写真に於いて、既に間抜けの本性を暴露している。これもやはり高等学校時代の写真だが、下宿の私の部屋で、机に頬杖ほおづえをつき、くつろいでいらっしゃるお姿だ。なんという気障きざな形だろう。くにゃりと上体をねじ曲げて、歌舞伎のうたた寝の形の如く右の掌を軽く頬にあて、口を小さくすぼめて、眼は上目使うわめづかいに遠いところを眺めているという馬鹿さ加減だ。紺絣こんがすりに角帯というのもまた珍妙な風俗ですね。これあいかん。襦袢じゅばんの襟えりを、あくまでも固くきっちり合せて、それこそ、われとわが襟でもって首をくくって死ぬつもり、とでもいったようなところだ。ひどいねえ。矢庭やにわにこの写真を、破って棄てたい発作にとらわれるのだが、でも、それは卑怯ひきょうだ。私の過去には、こんな姿も、たしかにあったのだ。鏡花きょうかの悪影響かも知れない。笑って下さい。逃げもかくれもせずに、罰を受けます。いさぎよく御高覧に供する次第だ。それにしても、どうも、こいつは、ひどいねえ。そのころ高等学校では、硬派と軟派と対立していて、軟派の生徒が、時々、硬派の生徒に殴なぐられたものですが、私が、このような大軟派の恰好で街を歩いても、ついに一度も殴られた事がない。忠告された事も無い。さすがの硬派たちも、私のこんな姿に接しては、あまりの事に、呆れて、敬遠したのかも知れませんね。私は今だってなかなかの馬鹿ですが、そのころは馬鹿より悪い。妖怪でした。贅沢三昧ぜいたくざんまいの生活をしていながら、生きているのがいやになって、自殺を計った事もありました。何が何やら、わからぬ時代でありました。大軟派といっても、それは形ばかりで、女性には臆病でした。ただ、むやみに、気取ってばかりいるのです。女の事で、実際に問題を起したのは、大学へはいってからです。
これは大学時代の写真ですが、この頃になると、多少、生活苦に似たものを嘗なめているので、顔の表情も、そんなに突飛では無いようですし、服装も、普通の制服制帽で、どこやら既に老い疲れている影さえ見えます。もう、この頃、私は或る女のひとと同棲どうせいをはじめていたのです。でも、こんな工合いに大袈裟に腕組みをしているところなど、やっぱり少し気取っていますね。もっとも、この写真を写す時には、私もちょっと気取らざるを得なかったのです。私の両側に立っている二人の美男子に、見覚えがあるでしょう? そうです、映画俳優です。Yと、Tです。それから、前にしゃがんでいる二人の婦人にも、見覚えがあるでしょう? そうです、女優のKとSです。おどろいたでしょう。これはね、私が大学へはいったとしの秋に、或るひとに連れられて松竹の蒲田かまた撮影所へ遊びに行って、その時の記念写真なのです。その頃、松竹の撮影所は、蒲田にありました。その時、私を連れて行ってくれた人というのは、映画界の余程の顔役らしく、私たちはその日たいへん歓迎されました。うしろに二人、でっぷり太った男が立っているでしょう? 眼鏡をかけているのが、その顔役の人で、もうひとりの、色の白いのが撮影所の所長です。この所長は、とても腰の低いひとで、一介の書生に過ぎぬ私を、それこそ下にも置かず、もてなしてくれました。商売人のようないや味もなく、まじめな、礼儀正しい人でした。本当に、感心な人でした。撮影所の中庭で、幹部の俳優たちと記念撮影をしたのですが、世の中から美男子と言われ騒がれているYもTも、私には、さほどの美男子とも思われず、三人ならぶと、私が一ばんいいのではなかろうかというような気がして、そこでこの大袈裟な腕組という事になったのですが、あとで、この写真がとどけられたのを見たら、やっぱり、だめでした。どうして私はこんなに、あか抜けないのだろう。YもTも、こうしてみると、さすがにスッキリしていますね。二匹の競馬の馬の間に、駱駝らくだがのっそり立っているみたいですね。私は、どうしてこんなに、田舎いなかくさいのだろう。これでも、たいへんいいつもりで腕組みしたのですがね。自惚うぬぼれの強い男です。自分の鈍重な田舎っぺいを、明確に、思い知ったのは、つい最近の事なのですからね。もっとも今では、自分のこの野暮ったさを、そんなに恥じてもいませんけれど。
学生時代の写真は、この三枚だけです。この後の三、四年間の生活は滅茶苦茶で、写真をとってもらうような心の余裕も無かったし、また誰か物好きの人があって、当時の私の姿を撮影しようと企てたとしても、私は絶えずキョトキョト動き廻って一瞬もじっとしていないので、撮影の計画を放棄するより他は無かったでしょう。それでも、菜っ葉服を着て銀座裏のバアの前に立っている写真など、二、三枚あった筈ですが、いつのまにやら、無くなりました。ちっとも惜しい写真ではありません。
すったもんだの揚句は大病になって、やっと病院から出て千葉県の船橋の町はずれに小さい家を一軒借りて半病人の生活をはじめた時の姿は、これです。ひどく痩やせているでしょう? それこそ、骨と皮です。私の顔のようでないでしょう? 自分ながら少し、気味が悪い。爬虫類はちゅうるいの感じですね。自分でも、もう命が永くないと思っていました。このころ第一創作集の「晩年」というのが出版せられて、その創作集の初版本に、この写真をいれました。それこそ「晩年の肖像」のつもりでしたが、未だに私は死にもせず、たとえば、昼の蛍みたいに、ぶざまにのそのそ歩きまわっているのです。めっきり、太った。この写真をごらんなさい。二年ほど船橋にいましたが、また東京へ出て来て、それまで六年間一緒に暮していた女のひとともわかれて、独りで郊外の下宿でごろごろしているうちに、こんなに太ってしまいました。最近はまた少し痩せましたけど、この下宿の時代は、私は、もぐらもちのように太っていました。この写真は、すなわち太りすぎて、てれて笑っているところです。「虚構の彷徨ほうこう」という私の第二創作集に、この写真を挿入しました。カモノハシという動物に酷似していると言った友人がありました。また、ある友人はなぐさめて、ダグラスという喜劇俳優に似ている、おごれ、と言いました。とにかく、ひどく太ったものです。こんなに太っていると、淋さびしい顔をしていても、ちっとも、引立たないものですね。そのころ私は、太っていながら、たいへん淋しかったのですけれど、淋しさが少しも顔にあらわれず、こんな、てれた笑いのような表情になってしまうので、誰にもあまり同情されませんでした。見給え、この湖水の岸にしゃがんで、うつむいて何か考えている写真、これはその頃、先輩たちに連れられて、三宅島へ遊びに行った時の写真ですが、私はたいへん淋しい気持で、こうしてひとりしゃがんでいたのですが、冷静に批判するならば、これはだらしなく居眠りをしているような姿です。少しも憂愁の影が無い。これは、島の王様のA氏が、私の知らぬまに、こっそり写して、そうしてこんなに大きく引伸しをして私に送って下さったものです。A氏は、島一ばんの長者で、そうして詩など作って、謂わば島の王様のようにゆったりと暮している人で、この旅行も、そのA氏の招待だったのです。私たち一行は、この時はずいぶんお世話になりました。筆不精の私は、未だにお礼状も何も差し上げていない仕末ですが、こないだの三宅島爆発では、さぞ難儀をなさったろうと思いながら、これまたれいの筆不精でお見舞い状も差し上げず、東京の作家というものは、ずいぶん義理知らずだと王様も呆れていらっしゃるだろうと思います。
次は甲府にいた頃の写真です。少しずつ、また痩せて来ました。東京の郊外の下宿から、鞄かばん一つ持って旅に出て、そのまま甲府に住みついてしまったのです。二箇年ほど甲府にいて、甲府で結婚して、それからいまの此この三鷹みたかに移って来たのです。この写真は、甲府の武田神社で家内の弟が写してくれたものですが、さすがにもう、老けた顔になっていますね。ちょうど三十歳だったと思います。けれども、この写真でみると、四十歳以上のおやじみたいですね。人並に苦労したのでしょう。ポーズも何も無く、ただ、ぼんやり立っていますね。いや、足もとの熊笹くまざさを珍らしそうに眺めていますね。まるで、ぼけて居ります。それから、この縁側に腰を掛けて、眼をショボショボさせている写真、これも甲府に住んでいた頃の写真ですが、颯爽さっそうとしたところも無ければ、癇癖かんぺきらしい様子もなく、かぼちゃのように無神経ですね。三日も洗面しないような顔ですね。醜悪な感じさえあります。でも、作家の日常の顔は、これくらいでたくさんです。だんだん、ほんものになって来たのかも知れない。つまり、ほんものの俗人ですね。
あとは皆、三鷹へ来てからの写真です。写真をとってくれる人も多くなって、右むけ、はい、左むけ、はい、ちょっと笑って、はい、という工合いにその人たちの命令のままにポーズを作ったのです。つまらない写真ばかりです。二つ三つ、面白い写真もあります。いや、滑稽こっけいな写真と言ったほうが当っている。裸体写真が一枚あります。これは四万しま温泉にI君と一緒に行った時、I君は、私のお湯にはいっているところを、こっそりパチリと写してしまったのです。横向きの姿だから、たすかりました。正面だったらたまりません。あぶないところでした。でもこれはI君にたのんで、原板のフィルムも頂戴してしまいました。焼増しなどされては、たまりませんからね。I君には、ずいぶん写してもらいました。これはことしのお正月にK君と二人で、共に紋服を着て、井伏さんのお留守宅(作家井伏鱒二氏は、軍報道班員としてその前年の晩秋、南方に派遣せられたり)へ御年始にあがって、ちょうどI君も国民服を着て御年始に来ていましたが、その時、I君が私たち二人を庭先に立たせて撮影した物です。似合いませんね。へんですね。K君はともかく、私の紋服姿は、まるで、異様ですね。K君の批評に依ると、モーゼが紋服を着たみたいだそうですが、当っていますかね。どうせ、まともではありません。ひどく顔が骨ばって、そうして大きくなったようですね。ごらんなさい。これは或る友人の出版記念会の時の写真ですが、こんなにたくさんの顔が並んでいる中で、ずば抜けて一つ大きい顔があります。私の顔です。羽子板がずらりと並んでいて、その中で際立って大きいのを、三つになるお嬢さんが、あれほしい、あれ買って、とだだをこねて、店のあるじの答えて言うには、お嬢さん、あれはいけません、あれは看板です、という笑い話。こんなに顔が大きくなると、恋愛など、とても出来るものではありません。高麗屋こうらいやに似ているそうですね。笑ってはいけません。「汚きたな作り」の高麗屋です。もっとも、これは、床屋へはいって、すっぱり綺麗になるというあの「実は」という場面は無くて、おしまいまで、「きたな作り」だそうです。「作り」でもなんでもない、ほんものの「きたな」だった。芝居にも何もなりません。でも、どこか似ているそうですよ。つまり、立派なのですね。物好きな婦人の出現を待つより他は無い。
調子づいて、馬鹿な事ばかり言いました。あなたともあろうものが、あんな馬鹿話をなさるのはおよしなさい、お客様に軽蔑されるばかりです、もっと真面目なお話が出来ないのですか、まるで三流の戯作者げさくしゃみたいです、と家内から忠告を受けた事もあるのですが、くるしい時に、素直にくるしい表情の浮ぶ人は、さいわいです。緊張している時に、そのまま緊張の姿勢をとれる人は、さいわいです。私は、くるしい時に、ははんと馬鹿笑いしたくなるので困ります。内心大いに緊張している時でも、突然、馬鹿話などはじめたくなるので困ります。「笑いながら、厳粛な事を語れ!」ニイチェもいい事を言います。もっとも、私は、怒る時には、本気に怒ってしまいます。私の表情には、怒りと笑いと、二つしか無いようです。意外にも、表情の乏とぼしい男ですね。このごろは、でも、怒るのも年に一回くらいにしようと思っています。たいてい忍んで、笑っているように心掛けて居ります。そのかわり怒った時には、いや、脅迫がましいような言いかたは、やめましょう。私自身でも不愉快です。怒った時には、怒った時です。この写真をごらんなさい。これは最近の写真です。ジャンパーに、半ズボンという軽装です。乳母車を押していますね。これは、私の小さい女の子を乳母車に乗せて、ちかくの井いの頭かしら、自然文化園の孔雀くじゃくを見せに連れて行くところです。幸福そうな風景ですね。いつまで続く事か。つぎのペエジには、どんな写真が貼はられるのでしょう。意外の写真が。
底本:「太宰治全集5」ちくま文庫、筑摩書房
1989(平成元)年1月31日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月
入力:柴田卓治
校正:夏海
2000年4月13日公開
2005年10月28日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
畜犬談
─伊馬鵜平君に与える─
太宰治
私は、犬については自信がある。いつの日か、かならず喰くいつかれるであろうという自信である。私は、きっと噛かまれるにちがいない。自信があるのである。よくぞ、きょうまで喰いつかれもせず無事に過してきたものだと不思議な気さえしているのである。諸君、犬は猛獣である。馬を斃たおし、たまさかには獅し子しと戦ってさえこれを征服するとかいうではないか。さもありなんと私はひとり淋しく首肯しゅこうしているのだ。あの犬の、鋭い牙きばを見るがよい。ただものではない。いまは、あのように街路で無心のふうを装い、とるに足らぬもののごとくみずから卑下して、芥箱ごみばこを覗のぞきまわったりなどしてみせているが、もともと馬を斃すほどの猛獣である。いつなんどき、怒り狂い、その本性を暴露するか、わかったものではない。犬はかならず鎖に固くしばりつけておくべきである。少しの油断もあってはならぬ。世の多くの飼い主は、みずから恐ろしき猛獣を養い、これに日々わずかの残飯ざんぱんを与えているという理由だけにて、まったくこの猛獣に心をゆるし、エスやエスやなど、気楽に呼んで、さながら家族の一員のごとく身辺に近づかしめ、三歳のわが愛子をして、その猛獣の耳をぐいと引っぱらせて大笑いしている図にいたっては、戦慄せんりつ、眼を蓋おおわざるを得ないのである。不意に、わんといって喰いついたら、どうする気だろう。気をつけなければならぬ。飼い主でさえ、噛みつかれぬとは保証できがたい猛獣を、(飼い主だから、絶対に喰いつかれぬということは愚かな気のいい迷信にすぎない。あの恐ろしい牙のある以上、かならず噛む。けっして噛まないということは、科学的に証明できるはずはないのである)その猛獣を、放し飼いにして、往来をうろうろ徘徊はいかいさせておくとは、どんなものであろうか。昨年の晩秋、私の友人が、ついにこれの被害を受けた。いたましい犠牲者である。友人の話によると、友人は何もせず横丁を懐手ふところでしてぶらぶら歩いていると、犬が道路上にちゃんと坐っていた。友人は、やはり何もせず、その犬の傍を通った。犬はその時、いやな横目を使ったという。何事もなく通りすぎた、とたん、わんといって右の脚あしに喰いついたという。災難である。一瞬のことである。友人は、呆然自失ぼうぜんじしつしたという。ややあって、くやし涙が沸いて出た。さもありなん、と私は、やはり淋しく首肯している。そうなってしまったら、ほんとうに、どうしようも、ないではないか。友人は、痛む脚をひきずって病院へ行き手当を受けた。それから二十一日間、病院へ通ったのである。三週間である。脚の傷がなおっても、体内に恐水病といういまわしい病気の毒が、あるいは注入されてあるかもしれぬという懸念けねんから、その防毒の注射をしてもらわなければならぬのである。飼い主に談判するなど、その友人の弱気をもってしては、とてもできぬことである。じっと堪こらえて、おのれの不運に溜息ためいきついているだけなのである。しかも、注射代などけっして安いものではなく、そのような余分の貯たくわえは失礼ながら友人にあるはずもなく、いずれは苦しい算段をしたにちがいないので、とにかくこれは、ひどい災難である。大災難である。また、うっかり注射でも怠おこたろうものなら、恐水病といって、発熱悩乱の苦しみあって、果ては貌かおが犬に似てきて、四つ這ばいになり、ただわんわんと吠ゆるばかりだという、そんな凄惨せいさんな病気になるかもしれないということなのである。注射を受けながらの、友人の憂慮、不安は、どんなだったろう。友人は苦労人で、ちゃんとできた人であるから、醜くとり乱すこともなく、三七、二十一日病院に通い、注射を受けて、いまは元気に立ち働いているが、もしこれが私だったら、その犬、生かしておかないだろう。私は、人の三倍も四倍も復讐心ふくしゅうしんの強い男なのであるから、また、そうなると人の五倍も六倍も残忍性を発揮してしまう男なのであるから、たちどころにその犬の頭蓋骨ずがいこつを、めちゃめちゃに粉砕ふんさいし、眼玉をくり抜き、ぐしゃぐしゃに噛んで、べっと吐き捨て、それでも足りずに近所近辺の飼い犬ことごとく毒殺してしまうであろう。こちらが何もせぬのに、突然わんといって噛みつくとはなんという無礼、狂暴の仕草しぐさであろう。いかに畜生といえども許しがたい。畜生ふびんのゆえをもって、人はこれを甘やかしているからいけないのだ。容赦ようしゃなく酷刑こっけいに処すべきである。昨秋、友人の遭難を聞いて、私の畜犬に対する日ごろの憎悪は、その極点に達した。青い焔ほのおが燃え上るほどの、思いつめたる憎悪である。
ことしの正月、山梨県、甲府こうふのまちはずれに八畳、三畳、一畳という草庵そうあんを借り、こっそり隠れるように住みこみ、下手な小説あくせく書きすすめていたのであるが、この甲府のまち、どこへ行っても犬がいる。おびただしいのである。往来に、あるいは佇たたずみ、あるいはながながと寝そべり、あるいは疾駆しっくし、あるいは牙を光らせて吠えたて、ちょっとした空地でもあるとかならずそこは野犬の巣のごとく、組んずほぐれつ格闘の稽古にふけり、夜など無人の街路を風のごとく、野盗のごとくぞろぞろ大群をなして縦横に駈け廻っている。甲府の家ごと、家ごと、少くとも二匹くらいずつ養っているのではないかと思われるほどに、おびただしい数である。山梨県は、もともと甲斐かい犬の産地として知られているようであるが、街頭で見かける犬の姿は、けっしてそんな純血種のものではない。赤いムク犬が最も多い。採るところなきあさはかな駄犬ばかりである。もとより私は畜犬に対しては含むところがあり、また友人の遭難以来いっそう嫌悪けんおの念を増し、警戒おさおさ怠るものではなかったのであるが、こんなに犬がうようよいて、どこの横丁にでも跳梁ちょうりょうし、あるいはとぐろを巻いて悠然と寝ているのでは、とても用心しきれるものでなかった。私はじつに苦心をした。できることなら、すね当あて、こて当、かぶとをかぶって街を歩きたく思ったのである。けれども、そのような姿は、いかにも異様であり、風紀上からいっても、けっして許されるものではないのだから、私は別の手段をとらなければならぬ。私は、まじめに、真剣に、対策を考えた。私はまず犬の心理を研究した。人間については、私もいささか心得があり、たまには的確に、あやまたず指定できたことなどもあったのであるが、犬の心理は、なかなかむずかしい。人の言葉が、犬と人との感情交流にどれだけ役立つものか、それが第一の難問である。言葉が役に立たぬとすれば、お互いの素振り、表情を読み取るよりほかにない。しっぽの動きなどは、重大である。けれども、この、しっぽの動きも、注意して見ているとなかなかに複雑で、容易に読みきれるものではない。私は、ほとんど絶望した。そうして、はなはだ拙劣せつれつな、無能きわまる一法を案出した。あわれな窮余の一策である。私は、とにかく、犬に出逢うと、満面に微笑を湛たたえて、いささかも害心のないことを示すことにした。夜は、その微笑が見えないかもしれないから、無邪気に童謡を口ずさみ、やさしい人間であることを知らせようと努めた。これらは、多少、効果があったような気がする。犬は私には、いまだ飛びかかってこない。けれどもあくまで油断は禁物である。犬の傍を通る時は、どんなに恐ろしくても、絶対に走ってはならぬ。にこにこ卑しい追従笑ついしょうわらいを浮べて、無心そうに首を振り、ゆっくり、ゆっくり、内心、背中に毛虫が十匹這はっているような窒息ちっそくせんばかりの悪寒おかんにやられながらも、ゆっくりゆっくり通るのである。つくづく自身の卑屈がいやになる。泣きたいほどの自己嫌悪を覚えるのであるが、これを行わないと、たちまち噛みつかれるような気がして、私は、あらゆる犬にあわれな挨拶を試みる。髪をあまりに長く伸ばしていると、あるいはウロンの者として吠えられるかもしれないから、あれほどいやだった床屋へも精出してゆくことにした。ステッキなど持って歩くと、犬のほうで威嚇いかくの武器と勘かんちがいして、反抗心を起すようなことがあってはならぬから、ステッキは永遠に廃棄はいきすることにした。犬の心理を計りかねて、ただ行き当りばったり、むやみやたらに御機嫌とっているうちに、ここに意外の現象が現われた。私は、犬に好かれてしまったのである。尾を振って、ぞろぞろ後についてくる。私は、じだんだ踏んだ。じつに皮肉である。かねがね私の、こころよからず思い、また最近にいたっては憎悪の極点にまで達している、その当の畜犬に好かれるくらいならば、いっそ私は駱駝らくだに慕われたいほどである。どんな悪女にでも、好かれて気持の悪いはずはない、というのはそれは浅薄せんぱくの想定である。プライドが、虫が、どうしてもそれを許容できない場合がある。堪忍かんにんならぬのである。私は、犬をきらいなのである。早くからその狂暴の猛獣性を看破し、こころよからず思っているのである。たかだか日に一度や二度の残飯の投与にあずからんがために、友を売り、妻を離別し、おのれの身ひとつ、家の軒下に横たえ、忠義顔して、かつての友に吠え、兄弟、父母をも、けろりと忘却し、ただひたすらに飼主の顔色を伺い、阿諛あゆ追従ついしょうてんとして恥じず、ぶたれても、きゃんといい尻尾しっぽまいて閉口してみせて、家人を笑わせ、その精神の卑劣、醜怪、犬畜生とはよくもいった。日に十里を楽々と走破しうる健脚を有し、獅子をも斃たおす白光鋭利の牙きばを持ちながら、懶惰らんだ無頼ぶらいの腐りはてたいやしい根性をはばからず発揮し、一片の矜持きょうじなく、てもなく人間界に屈服し、隷属れいぞくし、同族互いに敵視して、顔つきあわせると吠えあい、噛みあい、もって人間の御機嫌をとり結ぼうと努めている。雀を見よ。何ひとつ武器を持たぬ繊弱の小禽しょうきんながら、自由を確保し、人間界とはまったく別個の小社会を営み、同類相親しみ、欣然きんぜん日々の貧しい生活を歌い楽しんでいるではないか。思えば、思うほど、犬は不潔だ。犬はいやだ。なんだか自分に似ているところさえあるような気がして、いよいよ、いやだ。たまらないのである。その犬が、私を特に好んで、尾を振って親愛の情を表明してくるに及んでは、狼狽ろうばいとも、無念とも、なんとも、いいようがない。あまりに犬の猛獣性を畏敬し、買いかぶり節度もなく媚笑びしょうを撒まきちらして歩いたゆえ、犬は、かえって知己を得たものと誤解し、私を組みしやすしとみてとって、このような情ない結果に立ちいたったのであろうが、何事によらず、ものには節度が大切である。私は、いまだに、どうも、節度を知らぬ。
早春のこと。夕食の少しまえに、私はすぐ近くの四十九聯隊の練兵場へ散歩に出て、二、三の犬が私のあとについてきて、いまにも踵かかとをがぶりとやられはせぬかと生きた気もせず、けれども毎度のことであり、観念して無心平生を装い、ぱっと脱兎だっとのごとく逃げたい衝動を懸命に抑え、抑え、ぶらりぶらり歩いた。犬は私についてきながら、みちみちお互いに喧嘩などはじめて、私は、わざと振りかえって見もせず、知らぬふりして歩いているのだが、内心、じつに閉口であった。ピストルでもあったなら、躊躇ちゅうちょせずドカンドカンと射殺してしまいたい気持であった。犬は、私にそのような、外面如菩薩げめんにょぼさつ、内心如夜叉ないしんにょやしゃ的の奸佞かんねいの害心があるとも知らず、どこまでもついてくる。練兵場をぐるりと一廻りして、私はやはり犬に慕われながら帰途についた。家へ帰りつくまでには、背後の犬もどこかへ雲散霧消うんさんむしょうしているのが、これまでの、しきたりであったのだが、その日に限って、ひどく執拗しつようで馴なれ馴れしいのが一匹いた。真黒の、見るかげもない小犬である。ずいぶん小さい。胴の長さ五寸の感じである。けれども、小さいからといって油断はできない。歯は、すでにちゃんと生えそろっているはずである。噛まれたら病院に三、七、二十一日間通わなければならぬ。それにこのような幼少なものには常識がないから、したがって気まぐれである。いっそう用心をしなければならぬ。小犬は後になり、さきになり、私の顔を振り仰ぎ、よたよた走って、とうとう私の家の玄関まで、ついてきた。
「おい。へんなものが、ついてきたよ」
「おや、可愛い」
「可愛いもんか。追っ払ってくれ、手荒くすると喰いつくぜ、お菓子でもやって」
れいの軟弱外交である。小犬は、たちまち私の内心畏怖の情を見抜き、それにつけこみ、ずうずうしくもそれから、ずるずる私の家に住みこんでしまった。そうしてこの犬は、三月、四月、五月、六、七、八、そろそろ秋風吹きはじめてきた現在にいたるまで、私の家にいるのである。私は、この犬には、幾度泣かされたかわからない。どうにも始末ができないのである。私はしかたなく、この犬を、ポチなどと呼んでいるのであるが、半年もともに住んでいながら、いまだに私は、このポチを、一家のものとは思えない。他人の気がするのである。しっくりゆかない。不和である。お互い心理の読みあいに火花を散らして戦っている。そうしてお互い、どうしても釈然しゃくぜんと笑いあうことができないのである。
はじめこの家にやってきたころは、まだ子供で、地べたの蟻ありを不審そうに観察したり、蝦蟇がまを恐れて悲鳴を挙げたり、その様には私も思わず失笑することがあって、憎いやつであるが、これも神様の御心によってこの家へ迷いこんでくることになったのかもしれぬと、縁の下に寝床を作ってやったし、食い物も乳幼児むきに軟らかく煮て与えてやったし、蚤取粉のみとりこなどからだに振りかけてやったものだ。けれども、ひとつき経つと、もういけない。そろそろ駄犬の本領を発揮してきた。いやしい。もともと、この犬は練兵場の隅に捨てられてあったものにちがいない。私のあの散歩の帰途、私にまつわりつくようにしてついてきて、その時は、見るかげもなく痩やせこけて、毛も抜けていてお尻の部分は、ほとんど全部禿はげていた。私だからこそ、これに菓子を与え、おかゆを作り、荒い言葉一つかけるではなし、腫はれものにさわるように鄭重ていちょうにもてなしてあげたのだ。ほかの人だったら、足蹴あしげにして追い散らしてしまったにちがいない。私のそんな親切なもてなしも、内実は、犬に対する愛情からではなく、犬に対する先天的な憎悪と恐怖から発した老獪ろうかいな駈け引きにすぎないのであるが、けれども私のおかげで、このポチは、毛並もととのい、どうやら一人まえの男の犬に成長することを得たのではないか。私は恩を売る気はもうとうないけれども、少しは私たちにも何か楽しみを与えてくれてもよさそうに思われるのであるが、やはり捨犬はだめなものである。大めし食って、食後の運動のつもりであろうか、下駄をおもちゃにして無残に噛み破り、庭に干してある洗濯物を要いらぬ世話して引きずりおろし、泥まみれにする。
「こういう冗談はしないでおくれ。じつに、困るのだ。誰が君に、こんなことをしてくれとたのみましたか?」
と、私は、内に針を含んだ言葉を、精いっぱい優しく、いや味をきかせて言ってやることもあるのだが、犬は、きょろりと眼を動かし、いや味を言い聞かせている当の私にじゃれかかる。なんという甘ったれた精神であろう。私はこの犬の鉄面皮てつめんぴには、ひそかに呆あきれ、これを軽蔑さえしたのである。長ずるに及んで、いよいよこの犬の無能が暴露された。だいいち、形がよくない。幼少のころには、も少し形の均斉もとれていて、あるいは優れた血が雑まじっているのかもしれぬと思わせるところあったのであるが、それは真赤ないつわりであった。胴だけが、にょきにょき長く伸びて、手足がいちじるしく短い。亀のようである。見られたものでなかった。そのような醜い形をして、私が外出すればかならず影のごとくちゃんと私につき従い、少年少女までが、やあ、へんてこな犬じゃと指さして笑うこともあり、多少見栄坊みえぼうの私は、いくらすまして歩いても、なんにもならなくなるのである。いっそ他人のふりをしようと早足に歩いてみても、ポチは私の傍を離れず、私の顔を振り仰ぎ振り仰ぎ、あとになり、さきになり、からみつくようにしてついてくるのだから、どうしたって二人は他人のようには見えまい。気心の合った主従としか見えまい。おかげで私は外出のたびごとに、ずいぶん暗い憂欝な気持にさせられた。いい修行になったのである。ただ、そうして、ついて歩いていたころは、まだよかった。そのうちにいよいよ隠してあった猛獣の本性を暴露してきた。喧嘩格闘を好むようになったのである。私のお伴をして、まちを歩いて行きあう犬、行きあう犬、すべてに挨拶して通るのである。つまりかたっぱしから喧嘩して通るのである。ポチは足も短く、若年でありながら、喧嘩は相当強いようである。空地の犬の巣に踏みこんで、一時に五匹の犬を相手に戦ったときはさすがに危く見えたが、それでも巧みに身をかわして難を避けた。非常な自信をもって、どんな犬にでも飛びかかってゆく。たまには勢負いきおいまけして、吠えながらじりじり退却することもある。声が悲鳴に近くなり、真黒い顔が蒼あお黒くなってくる。いちど小牛のようなシェパアドに飛びかかっていって、あのときは、私が蒼くなった。はたして、ひとたまりもなかった。前足でころころポチをおもちゃにして、本気につきあってくれなかったのでポチも命が助かった。犬は、いちどあんなひどいめに逢うと、大へん意気地がなくなるものらしい。ポチは、それからは眼に見えて、喧嘩を避けるようになった。それに私は、喧嘩を好まず、否、好まぬどころではない、往来で野獣の組打ちを放置し許容しているなどは、文明国の恥辱と信じているので、かの耳を聾ろうせんばかりのけんけんごうごう、きゃんきゃんの犬の野蛮やばんのわめき声には、殺してもなおあき足らない憤怒と憎悪を感じているのである。私はポチを愛してはいない。恐れ、憎んでこそいるが、みじんも愛しては、いない。死んでくれたらいいと思っている。私にのこのこついてきて、何かそれが飼われているものの義務とでも思っているのか、途で逢う犬、逢う犬、かならず凄惨せいさんに吠えあって、主人としての私は、そのときどんなに恐怖にわななき震えていることか。自動車呼びとめて、それに乗ってドアをばたんと閉じ、一目散に逃げ去りたい気持なのである。犬同士の組打ちで終るべきものなら、まだしも、もし敵の犬が血迷って、ポチの主人の私に飛びかかってくるようなことがあったら、どうする。ないとは言わせぬ。血に飢えたる猛獣である。何をするか、わかったものでない。私はむごたらしく噛み裂かれ、三、七、二十一日間病院に通わなければならぬ。犬の喧嘩は、地獄である。私は、機会あるごとにポチに言い聞かせた。
「喧嘩しては、いけないよ。喧嘩するなら、僕からはるか離れたところで、してもらいたい。僕は、おまえを好いてはいないんだ」
少し、ポチにもわかるらしいのである。そう言われると多少しょげる。いよいよ私は犬を、薄気味わるいものに思った。その私の繰り返し繰り返し言った忠告が効を奏したのか、あるいは、かのシェパアドとの一戦にぶざまな惨敗ざんぱいを喫きっしたせいか、ポチは、卑屈なほど柔弱にゅうじゃくな態度をとりはじめた。私といっしょに路を歩いて、他の犬がポチに吠えかけると、ポチは、
「ああ、いやだ、いやだ。野蛮ですねえ」
と言わんばかり、ひたすら私の気に入られようと上品ぶって、ぶるっと胴震いさせたり、相手の犬を、しかたのないやつだね、とさもさも憐れむように流し目で見て、そうして、私の顔色を伺い、へっへっへっと卑しい追従ついしょう笑いするかのごとく、その様子のいやらしいったらなかった。
「一つも、いいところないじゃないか、こいつは。ひとの顔色ばかり伺っていやがる」
「あなたが、あまり、へんにかまうからですよ」家内は、はじめからポチに無関心であった。洗濯物など汚されたときはぶつぶつ言うが、あとはけろりとして、ポチポチと呼んで、めしを食わせたりなどしている。「性格が破産しちゃったんじゃないかしら」と笑っている。
「飼い主に、似てきたというわけかね」私は、いよいよ、にがにがしく思った。
七月にはいって、異変が起った。私たちは、やっと、東京の三鷹村みたかむらに、建築最中の小さい家を見つけることができて、それの完成ししだい、一か月二十四円で貸してもらえるように、家主と契約の証書交して、そろそろ移転の仕度をはじめた。家ができ上ると、家主から速達で通知が来ることになっていたのである。ポチは、もちろん、捨ててゆかれることになっていたのである。
「連れていったって、いいのに」家内は、やはりポチをあまり問題にしていない。どちらでもいいのである。
「だめだ。僕は、可愛いから養っているんじゃないんだよ。犬に復讐されるのが、こわいから、しかたなくそっとしておいてやっているのだ。わからんかね」
「でも、ちょっとポチが見えなくなると、ポチはどこへ行ったろう、どこへ行ったろう、と大騒ぎじゃないの」
「いなくなると、いっそう薄気味が悪いからさ、僕に隠れて、ひそかに同志を糾合きゅうごうしているのかもわからない。あいつは、僕に軽蔑されていることを知っているんだ。復讐心が強いそうだからなあ、犬は」
いまこそ絶好の機会であると思っていた。この犬をこのまま忘れたふりして、ここへ置いて、さっさと汽車に乗って東京へ行ってしまえば、まさか犬も、笹子峠ささごとうげを越えて三鷹村まで追いかけてくることはなかろう。私たちは、ポチを捨てたのではない。まったくうっかりして連れてゆくことを忘れたのである。罪にはならない。またポチに恨まれる筋合もない。復讐されるわけはない。
「だいじょうぶだろうね。置いていっても、飢え死するようなことはないだろうね。死霊の祟たたりということもあるからね」
「もともと、捨犬だったんですもの」家内も、少し不安になった様子である。
「そうだね。飢え死することはないだろう。なんとか、うまくやってゆくだろう。あんな犬、東京へ連れていったんじゃ、僕は友人に対して恥ずかしいんだ。胴が長すぎる。みっともないねえ」
ポチは、やはり置いてゆかれることに、確定した。すると、ここに異変が起った。ポチが、皮膚病にやられちゃった。これが、またひどいのである。さすがに形容をはばかるが、惨状さんじょう、眼をそむけしむるものがあったのである。おりからの炎熱とともに、ただならぬ悪臭を放つようになった。こんどは家内が、まいってしまった。
「ご近所にわるいわ。殺してください」女は、こうなると男よりも冷酷で、度胸がいい。
「殺すのか」私は、ぎょっとした。「もう少しの我慢じゃないか」
私たちは、三鷹の家主からの速達を一心に待っていた。七月末には、できるでしょうという家主の言葉であったのだが、七月もそろそろおしまいになりかけて、きょうか明日かと、引越しの荷物もまとめてしまって待機していたのであったが、なかなか、通知が来ないのである。問いあわせの手紙を出したりなどしている時に、ポチの皮膚病がはじまったのである。見れば、見るほど、酸鼻さんびの極である。ポチも、いまはさすがに、おのれの醜い姿を恥じている様子で、とかく暗闇の場所を好むようになり、たまに玄関の日当りのいい敷石の上で、ぐったり寝そべっていることがあっても、私が、それを見つけて、
「わあ、ひでえなあ」と罵倒ばとうすると、いそいで立ち上って首を垂れ、閉口したようにこそこそ縁の下にもぐりこんでしまうのである。
それでも私が外出するときには、どこからともなく足音忍ばせて出てきて、私についてこようとする。こんな化け物みたいなものに、ついてこられて、たまるものか、とその都度、私は、だまってポチを見つめてやる。あざけりの笑いを口角にまざまざと浮べて、なんぼでも、ポチを見つめてやる。これは大へんききめがあった。ポチは、おのれの醜い姿にハッと思い当る様子で、首を垂れ、しおしおどこかへ姿を隠す。
「とっても、我慢ができないの。私まで、むず痒がゆくなって」家内は、ときどき私に相談する。「なるべく見ないように努めているんだけれど、いちど見ちゃったら、もうだめね。夢の中にまで出てくるんだもの」
「まあ、もうすこしの我慢だ」がまんするよりほかはないと思った。たとえ病んでいるとはいっても、相手は一種の猛獣である。下手に触ったら噛みつかれる。「明日にでも、三鷹から、返事が来るだろう、引越してしまったら、それっきりじゃないか」
三鷹の家主から返事が来た。読んで、がっかりした。雨が降りつづいて壁が乾かず、また人手も不足で完成までには、もう十日くらいかかる見こみ、というのであった。うんざりした。ポチから逃のがれるためだけでも、早く、引越してしまいたかったのだ。私は、へんな焦躁感で、仕事も手につかず、雑誌を読んだり、酒を呑んだりした。ポチの皮膚病は一日一日ひどくなっていって、私の皮膚も、なんだか、しきりに痒くなってきた。深夜、戸外でポチが、ばたばたばた痒さに身悶えしている物音に、幾度ぞっとさせられたかわからない。たまらない気がした。いっそひと思いにと、狂暴な発作に駆かられることも、しばしばあった。家主からは、さらに二十日待て、と手紙が来て、私のごちゃごちゃの忿懣ふんまんが、たちまち手近のポチに結びついて、こいつあるがために、このように諸事円滑えんかつにすすまないのだ、と何もかも悪いことは皆、ポチのせいみたいに考えられ、奇妙にポチを呪咀じゅそし、ある夜、私の寝巻に犬の蚤のみが伝播でんぱされてあることを発見するに及んで、ついにそれまで堪えに堪えてきた怒りが爆発し、私はひそかに重大の決意をした。
殺そうと思ったのである。相手は恐るべき猛獣である。常の私だったら、こんな乱暴な決意は、逆立ちしたってなしえなかったところのものなのであったが、盆地特有の酷暑こくしょで、少しへんになっていた矢先であったし、また、毎日、何もせず、ただぽかんと家主からの速達を待っていて、死ぬほど退屈な日々を送って、むしゃくしゃいらいら、おまけに不眠も手伝って発狂状態であったのだから、たまらない。その犬の蚤を発見した夜、ただちに家内をして牛肉の大片を買いに走らせ、私は、薬屋に行きある種の薬品を少量、買い求めた。これで用意はできた。家内は少なからず興奮していた。私たち鬼夫婦は、その夜、鳩首きゅうしゅして小声で相談した。
翌あくる朝、四時に私は起きた。目覚時計を掛けておいたのであるが、それの鳴りださぬうちに、眼が覚めてしまった。しらじらと明けていた。肌寒いほどであった。私は竹の皮包をさげて外へ出た。
「おしまいまで見ていないですぐお帰りになるといいわ」家内は玄関の式台に立って見送り、落ち着いていた。
「心得ている。ポチ、来い!」
ポチは尾を振って縁の下から出てきた。
「来い、来い!」私は、さっさと歩きだした。きょうは、あんな、意地悪くポチの姿を見つめるようなことはしないので、ポチも自身の醜さを忘れて、いそいそ私についてきた。霧が深い。まちはひっそり眠っている。私は、練兵場へいそいだ。途中、おそろしく大きい赤毛の犬が、ポチに向って猛烈に吠えたてた。ポチは、れいによって上品ぶった態度を示し、何を騒いでいるのかね、とでも言いたげな蔑視べっしをちらとその赤毛の犬にくれただけで、さっさとその面前を通過した。赤毛は、卑劣ひれつである。無法にもポチの背後から、風のごとく襲いかかり、ポチの寒しげな睾丸こうがんをねらった。ポチは、咄嗟とっさにくるりと向きなおったが、ちょっと躊躇ちゅうちょし、私の顔色をそっと伺った。
「やれ!」私は大声で命令した。「赤毛は卑怯だ! 思う存分やれ!」
ゆるしが出たのでポチは、ぶるんと一つ大きく胴震いして、弾丸のごとく赤犬のふところに飛びこんだ。たちまち、けんけんごうごう、二匹は一つの手毬てまりみたいになって、格闘した。赤毛は、ポチの倍ほども大きい図体ずうたいをしていたが、だめであった。ほどなく、きゃんきゃん悲鳴を挙げて敗退した。おまけにポチの皮膚病までうつされたかもわからない。ばかなやつだ。
喧嘩が終って、私は、ほっとした。文字どおり手に汗して眺めていたのである。一時は二匹の犬の格闘に巻きこまれて、私もともに死ぬるような気さえしていた。おれは噛み殺されたっていいんだ。ポチよ、思う存分、喧嘩をしろ! と異様に力んでいたのであった。ポチは、逃げてゆく赤毛を少し追いかけ、立ちどまって、私の顔色をちらと伺い、きゅうにしょげて、首を垂れすごすご私のほうへ引返してきた。
「よし! 強いぞ」ほめてやって私は歩きだし、橋をかたかた渡って、ここはもう練兵場である。
むかしポチは、この練兵場に捨てられた。だからいま、また、この練兵場へ帰ってきたのだ。おまえのふるさとで死ぬがよい。
私は立ちどまり、ぼとりと牛肉の大片を私の足もとへ落として、
「ポチ、食え」私はポチを見たくなかった。ぼんやりそこに立ったまま、「ポチ、食え」足もとで、ぺちゃぺちゃ食べている音がする。一分たたぬうちに死ぬはずだ。
私は猫背ねこぜになって、のろのろ歩いた。霧が深い。ほんのちかくの山が、ぼんやり黒く見えるだけだ。南アルプス連峰も、富士山も、何も見えない。朝露で、下駄がびしょぬれである。私はいっそうひどい猫背になって、のろのろ帰途についた。橋を渡り、中学校のまえまで来て、振り向くとポチが、ちゃんといた。面目なげに、首を垂れ、私の視線をそっとそらした。
私も、もう大人である。いたずらな感傷はなかった。すぐ事態を察知した。薬品が効かなかったのだ。うなずいて、もうすでに私は、白紙還元である。家へ帰って、
「だめだよ。薬が効かないのだ。ゆるしてやろうよ。あいつには、罪がなかったんだぜ。芸術家は、もともと弱い者の味方だったはずなんだ」私は、途中で考えてきたことをそのまま言ってみた。「弱者の友なんだ。芸術家にとって、これが出発で、また最高の目的なんだ。こんな単純なこと、僕は忘れていた。僕だけじゃない。みんなが、忘れているんだ。僕は、ポチを東京へ連れてゆこうと思うよ。友がもしポチの恰好かっこうを笑ったら、ぶん殴なぐってやる。卵あるかい?」
「ええ」家内は、浮かぬ顔をしていた。
「ポチにやれ、二つあるなら、二つやれ。おまえも我慢しろ。皮膚病なんてのは、すぐなおるよ」
「ええ」家内は、やはり浮かぬ顔をしていた。
底本:「日本文学全集70 太宰治集」集英社
1972(昭和47)年3月初版
初出:「文学者」
1939(昭和14)年8月
入力:網迫
校正:田尻幹二
1999年4月12日公開
2009年3月6日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
竹青
──新曲聊斎志異──
太宰治
むかし湖南こなんの何とやら郡邑ぐんゆうに、魚容という名の貧書生がいた。どういうわけか、昔から書生は貧という事にきまっているようである。この魚容君など、氏うじ育ち共に賤いやしくなく、眉目びもく清秀、容姿また閑雅かんがの趣おもむきがあって、書を好むこと色を好むが如ごとしとは言えないまでも、とにかく幼少の頃より神妙に学に志して、これぞという道にはずれた振舞いも無かった人であるが、どういうわけか、福運には恵まれなかった。早く父母に死別し、親戚しんせきの家を転々して育って、自分の財産というものも、その間に綺麗きれいさっぱり無くなっていて、いまは親戚一同から厄介者やっかいものの扱いを受け、ひとりの酒くらいの伯父おじが、酔余すいよの興にその家の色黒く痩やせこけた無学の下婢かひをこの魚容に押しつけ、結婚せよ、よい縁だ、と傍若無人に勝手にきめて、魚容は大いに迷惑ではあったが、この伯父もまた育ての親のひとりであって、謂いわば海山の大恩人に違いないのであるから、その酔漢の無礼な思いつきに対して怒る事も出来ず、涙を怺こらえ、うつろな気持で自分より二つ年上のその痩せてひからびた醜い女をめとったのである。女は酒くらいの伯父の妾めかけであったという噂うわさもあり、顔も醜いが、心もあまり結構でなかった。魚容の学問を頭から軽蔑して、魚容が「大学の道は至善に止とどまるに在あり」などと口ずさむのを聞いて、ふんと鼻で笑い、「そんな至善なんてものに止るよりは、お金に止って、おいしい御馳走ごちそうに止る工夫でもする事だ」とにくにくしげに言って、「あなた、すみませんが、これをみな洗濯して下さいな。少しは家事の手助けもするものです」と魚容の顔をめがけて女のよごれ物を投げつける。魚容はそのよごれ物をかかえて裏の河原におもむき、「馬嘶いななきて白日暮れ、剣鳴て秋気来る」と小声で吟じ、さて、何の面白い事もなく、わが故土にいながらも天涯の孤客こかくの如く、心は渺びょうとして空むなしく河上を徘徊はいかいするという間の抜けた有様であった。
「いつまでもこのような惨みじめな暮しを続けていては、わが立派な祖先に対しても申しわけが無い。乃公おれもそろそろ三十、而立じりつの秋だ。よし、ここは、一奮発して、大いなる声名を得なければならぬ」と決意して、まず女房を一つ殴なぐって家を飛び出し、満々たる自信を以もって郷試きょうしに応じたが、如何いかにせん永い貧乏暮しのために腹中に力無く、しどろもどろの答案しか書けなかったので、見事に落第。とぼとぼと、また故郷のあばら屋に帰る途中の、悲しさは比類が無い。おまけに腹がへって、どうにも足がすすまなくなって、洞庭湖畔どうていこはんの呉王廟ごおうびょうの廊下に這はい上って、ごろりと仰向あおむけに寝ころび、「あああ、この世とは、ただ人を無意味に苦しめるだけのところだ。乃公の如きは幼少の頃より、もっぱら其その独ひとりを慎んで古聖賢の道を究きわめ、学んで而しこうして時に之これを習っても、遠方から福音の訪れ来る気配はさらに無く、毎日毎日、忍び難い侮辱ばかり受けて、大勇猛心を起して郷試に応じても無慙むざんの失敗をするし、この世には鉄面皮の悪人ばかり栄えて、乃公の如き気の弱い貧書生は永遠の敗者として嘲笑せられるだけのものか。女房をぶん殴って颯爽さっそうと家を出たところまではよかったが、試験に落第して帰ったのでは、どんなに強く女房に罵倒ばとうせられるかわからない。ああ、いっそ死にたい」と極度の疲労のため精神朦朧もうろうとなり、君子の道を学んだ者にも似合わず、しきりに世を呪のろい、わが身の不幸を嘆いて、薄目をあいて空飛ぶ烏からすの大群を見上げ、「からすには、貧富が無くて、仕合せだなあ。」と小声で言って、眼を閉じた。
この湖畔の呉王廟は、三国時代の呉の将軍甘寧かんねいを呉王と尊称し、之を水路の守護神としてあがめ祀まつっているもので、霊顕すこぶるあらたかの由、湖上往来の舟がこの廟前を過ぐる時には、舟子かこども必ず礼拝し、廟の傍の林には数百の烏が棲息せいそくしていて、舟を見つけると一斉に飛び立ち、唖あ々あとやかましく噪さわいで舟の帆柱に戯れ舞い、舟子どもは之を王の使いの烏として敬愛し、羊の肉片など投げてやるとさっと飛んで来て口に咥くわえ、千に一つも受け損ずる事は無い。落第書生の魚容は、この使い烏の群が、嬉き々きとして大空を飛び廻っている様をうらやましがり、烏は仕合せだなあ、と哀れな細い声で呟つぶやいて眠るともなく、うとうとしたが、その時、「もし、もし。」と黒衣の男にゆり起されたのである。
魚容は未だ夢心地で、
「ああ、すみません。叱しからないで下さい。あやしい者ではありません。もう少しここに寝かせて置いて下さい。どうか、叱らないで下さい。」と小さい時からただ人に叱られて育って来たので、人を見ると自分を叱るのではないかと怯おびえる卑屈な癖が身についていて、この時も、譫言うわごとのように「すみません」を連発しながら寝返りを打って、また眼をつぶる。
「叱るのではない。」とその黒衣の男は、不思議な嗄しわがれたる声で言って、「呉王さまのお言いつけだ。そんなに人の世がいやになって、からすの生涯がうらやましかったら、ちょうどよい。いま黒衣隊が一卒欠けているから、それの補充にお前を採用してあげるというお言葉だ。早くこの黒衣を着なさい。」ふわりと薄い黒衣を、寝ている魚容にかぶせた。
たちまち、魚容は雄おすの烏。眼をぱちぱちさせて起き上り、ちょんと廊下の欄干らんかんにとまって、嘴くちばしで羽をかいつくろい、翼をひろげて危げに飛び立ち、いましも斜陽を一ぱい帆に浴びて湖畔を通る舟の上に、むらがり噪いで肉片の饗応きょうおうにあずかっている数百の神烏しんうにまじって、右往左往し、舟子の投げ上げる肉片を上手じょうずに嘴に受けて、すぐにもう、生れてはじめてと思われるほどの満腹感を覚え、岸の林に引上げて来て、梢こずえにとまり、林に嘴をこすって、水満々の洞庭の湖面の夕日に映えて黄金色に輝いている様を見渡し、「秋風飜ひるがえす黄金浪花千片か」などと所謂いわゆる君子蕩々然とうとうぜんとうそぶいていると、
「あなた、」と艶えんなる女性の声がして、「お気に召しまして?」
見ると、自分と同じ枝に雌めすの烏が一羽とまっている。
「おそれいります。」魚容は一揖いちゆうして、「何せどうも、身は軽くして泥滓でいしを離れたのですからなあ。叱らないで下さいよ。」とつい口癖になっているので、余計な一言を附加えた。
「存じて居ります。」と雌の烏は落ちついて、「ずいぶんいままで、御苦労をなさいましたそうですからね。お察し申しますわ。でも、もう、これからは大丈夫。あたしがついていますわ。」
「失礼ですが、あなたは、どなたです。」
「あら、あたしは、ただ、あなたのお傍に。どんな用でも言いつけて下さいまし。あたしは、何でも致します。そう思っていらして下さい。おいや?」
「いやじゃないが、」魚容は狼狽ろうばいして、「乃公おれにはちゃんと女房があります。浮気は君子の慎しむところです。あなたは、乃公を邪道に誘惑しようとしている。」と無理に分別顔を装うて言った。
「ひどいわ。あたしが軽はずみの好色の念からあなたに言い寄ったとでもお思いなの? ひどいわ。これはみな呉王さまの情深いお取りはからいですわ。あなたをお慰め申すように、あたしは呉王さまから言いつかったのよ。あなたはもう、人間でないのですから、人間界の奥さんの事なんか忘れてしまってもいいのよ。あなたの奥さんはずいぶんお優しいお方かも知れないけれど、あたしだってそれに負けずに、一生懸命あなたのお世話をしますわ。烏の操みさおは、人間の操よりも、もっと正しいという事をお見せしてあげますから、おいやでしょうけれど、これから、あたしをお傍に置いて下さいな。あたしの名前は、竹青というの。」
魚容は情に感じて、
「ありがとう。乃公も実は人間界でさんざんの目に遭あって来ているので、どうも疑い深くなって、あなたの御親切も素直に受取る事が出来なかったのです。ごめんなさい。」
「あら、そんなに改まった言い方をしては、おかしいわ。きょうから、あたしはあなたの召使いじゃないの。それでは旦那だんな様、ちょっと食後の御散歩は、いかがでしょう。」
「うむ、」と魚容もいまは鷹揚おうようにうなずき、「案内たのむ。」
「それでは、ついていらっしゃい。」とぱっと飛び立つ。
秋風嫋々じょうじょうと翼を撫なで、洞庭の烟波えんぱ眼下にあり、はるかに望めば岳陽の甍いらか、灼爛しゃくらんと落日に燃え、さらに眼を転ずれば、君山、玉鏡に可憐かれん一点の翠黛すいたいを描いて湘君しょうくんの俤おもかげをしのばしめ、黒衣の新夫婦は唖あ々あと鳴きかわして先になり後になり憂うれえず惑わず懼おそれず心のままに飛翔ひしょうして、疲れると帰帆の檣上しょうじょうにならんで止って翼を休め、顔を見合わせて微笑ほほえみ、やがて日が暮れると洞庭秋月皎々こうこうたるを賞しながら飄然ひょうぜんと塒ねぐらに帰り、互に羽をすり寄せて眠り、朝になると二羽そろって洞庭の湖水でぱちゃぱちゃとからだを洗い口を嗽すすぎ、岸に近づく舟をめがけて飛び立てば、舟子どもから朝食の奉納があり、新婦の竹青は初うい初ういしく恥じらいながら影の形に添う如くいつも傍にあって何かと優しく世話を焼き、落第書生の魚容も、その半生の不幸をここで一ぺんに吹き飛ばしたような思いであった。
その日の午後、いまは全く呉王廟の神烏の一羽になりすまして、往来の舟の帆檣にたわむれ、折から兵士を満載した大舟が通り、仲間の烏どもは、あれは危いと逃げて、竹青もけたたましく鳴いて警告したのだけれども、魚容の神烏は何せ自由に飛翔できるのがうれしくてたまらず、得意げにその兵士の舟の上を旋回せんかいしていたら、ひとりのいたずらっ児この兵士が、ひょうと矢を射てあやまたず魚容の胸をつらぬき、石のように落下する間一髪、竹青、稲妻いなずまの如く迅速に飛んで来て魚容の翼を咥くわえ、颯さっと引上げて、呉王廟の廊下に、瀕死ひんしの魚容を寝かせ、涙を流しながら甲斐甲斐かいがいしく介抱かいほうした。けれども、かなりの重傷で、とても助からぬと見て竹青は、一声悲しく高く鳴いて数百羽の仲間の烏を集め、羽ばたきの音も物凄ものすごく一斉に飛び立ってかの舟を襲い、羽で湖面を煽あおって大浪を起し忽たちまち舟を顛覆てんぷくさせて見事に報讐ほうしゅうし、大烏群は全湖面を震撼しんかんさせるほどの騒然たる凱歌がいかを挙げた。竹青はいそいで魚容の許もとに引返し、その嘴を魚容の頬にすり寄せて、
「聞えますか。あの、仲間の凱歌が聞えますか。」と哀慟あいどうして言う。
魚容は傷の苦しさに、もはや息も絶える思いで、見えぬ眼をわずかに開いて、
「竹青。」と小声で呼んだ、と思ったら、ふと眼が醒さめて、気がつくと自分は人間の、しかも昔のままの貧書生の姿で呉王廟の廊下に寝ている。斜陽あかあかと目前の楓かえでの林を照らして、そこには数百の烏が無心に唖々と鳴いて遊んでいる。
「気がつきましたか。」と農夫の身なりをした爺じじいが傍に立っていて笑いながら尋ねる。
「あなたは、どなたです。」
「わしはこの辺の百姓だが、きのうの夕方ここを通ったら、お前さんが死んだように深く眠っていて、眠りながら時々微笑んだりして、わしは、ずいぶん大声を挙げてお前さんを呼んでも一向に眼を醒まさない。肩をつかんでゆすぶっても、ぐたりとしている。家へ帰ってからも気になるので、たびたびお前さんの様子を見に来て、眼の醒めるのを待っていたのだ。見れば、顔色もよくないが、どこか病気か。」
「いいえ、病気ではございません。」不思議におなかも今はちっとも空すいていない。「すみませんでした。」とれいのあやまり癖が出て、坐り直して農夫に叮嚀ていねいにお辞儀をして、「お恥かしい話ですが、」と前置きをしてこの廟の廊下に行倒れるにいたった事情を正直に打明け、重ねて、「すみませんでした。」とお詫びを言った。
農夫は憐あわれに思った様子で、懐ふところから財布さいふを取出しいくらかの金を与え、
「人間万事塞翁さいおうの馬。元気を出して、再挙を図はかるさ。人生七十年、いろいろさまざまの事がある。人情は飜覆ほんぷくして洞庭湖の波瀾はらんに似たり。」と洒落しゃれた事を言って立ち去る。
魚容はまだ夢の続きを見ているような気持で、呆然ぼうぜんと立って農夫を見送り、それから振りかえって楓の梢にむらがる烏を見上げ、
「竹青!」と叫んだ。一群の烏が驚いて飛び立ち、ひとしきりやかましく騒いで魚容の頭の上を飛びまわり、それからまっすぐに湖の方へいそいで行って、それっきり、何の変った事も無い。
やっぱり、夢だったかなあ、と魚容は悲しげな顔をして首を振り、一つ大きい溜息ためいきをついて、力無く故土に向けて発足する。
故郷の人たちは、魚容が帰って来ても、格別うれしそうな顔もせず、冷酷の女房は、さっそく伯父の家の庭石の運搬を魚容に命じ、魚容は汗だくになって河原から大いなる岩石をいくつも伯父の庭先まで押したり曳ひいたり担かついだりして運び、「貧して怨えん無きは難し」とつくづく嘆じ、「朝あしたに竹青の声を聞かば夕ゆうべに死するも可なり矣」と何につけても洞庭一日の幸福な生活が燃えるほど劇はげしく懐慕せられるのである。
伯夷叔斉はくいしゅくせいは旧悪を念おもわず、怨うらみ是これを用いて希まれなり。わが魚容君もまた、君子の道に志している高邁こうまいの書生であるから、不人情の親戚をも努めて憎まず、無学の老妻にも逆わず、ひたすら古書に親しみ、閑雅の清趣を養っていたが、それでも、さすがに身辺の者から受ける蔑視べっしには堪えかねる事があって、それから三年目の春、またもや女房をぶん殴って、いまに見ろ、と青雲の志を抱いだいて家出して試験に応じ、やっぱり見事に落第した。よっぽど出来ない人だったと見える。帰途、また思い出の洞庭湖畔、呉王廟に立ち寄って、見るものみな懐しく、悲しみもまた千倍して、おいおい声を放って廟前で泣き、それから懐中のわずかな金を全部はたいて羊肉を買い、それを廟前にばら撒まいて神烏に供して樹上から降りて肉を啄ついばむ群烏を眺めて、この中に竹青もいるのだろうなあ、と思っても、皆一様に真黒で、それこそ雌雄をさえ見わける事が出来ず、
「竹青はどれですか。」と尋ねても振りかえる烏は一羽も無く、みんなただ無心に肉を拾ってたべている。魚容はそれでも諦められず、
「この中に、竹青がいたら一番あとまで残っておいで。」と、千万の思慕の情をこめて言ってみた。そろそろ肉が無くなって、群烏は二羽立ち、五羽立ち、むらむらぱっと大部分飛び立ち、あとには三羽、まだ肉を捜して居残り、魚容はそれを見て胸をとどろかせ手に汗を握ったが、肉がもう全く無いと見てぱっと未練みれんげも無く、その三羽も飛び立つ。魚容は気抜けの余りくらくら眩暈めまいして、それでも尚なお、この場所から立ち去る事が出来ず、廟の廊下に腰をおろして、春霞はるがすみに煙る湖面を眺めてただやたらに溜息をつき、「ええ、二度も続けて落第して、何の面目があっておめおめ故郷に帰られよう。生きて甲斐かいない身の上だ、むかし春秋戦国の世にかの屈原くつげんも衆人皆酔い、我独ひとり醒さめたり、と叫んでこの湖に身を投げて死んだとかいう話を聞いている、乃公おれもこの思い出なつかしい洞庭に身を投げて死ねば、或あるいは竹青がどこかで見ていて涙を流してくれるかも知れない、乃公を本当に愛してくれたのは、あの竹青だけだ、あとは皆、おそろしい我慾の鬼ばかりだった、人間万事塞翁の馬だと三年前にあのお爺じいさんが言ってはげましてくれたけれども、あれは嘘だ、不仕合せに生れついた者は、いつまで経たっても不仕合せのどん底であがいているばかりだ、これすなわち天命を知るという事か、あはは、死のう、竹青が泣いてくれたら、それでよい、他には何も望みは無い」と、古聖賢の道を究きわめた筈の魚容も失意の憂愁に堪えかね、今夜はこの湖で死ぬる覚悟。やがて夜になると、輪郭りんかくの滲にじんだ満月が中空に浮び、洞庭湖はただ白く茫ぼうとして空と水の境が無く、岸の平沙へいさは昼のように明るく柳の枝は湖水の靄もやを含んで重く垂れ、遠くに見える桃畑の万朶ばんだの花は霰あられに似て、微風が時折、天地の溜息の如く通過し、いかにも静かな春の良夜、これがこの世の見おさめと思えば涙も袖そでにあまり、どこからともなく夜猿やえんの悲しそうな鳴声が聞えて来て、愁思まさに絶頂に達した時、背後にはたはたと翼の音がして、
「別来、恙つつが無きや。」
振り向いて見ると、月光を浴びて明眸皓歯めいぼうこうし、二十はたちばかりの麗人がにっこり笑っている。
「どなたです、すみません。」とにかく、あやまった。
「いやよ、」と軽く魚容の肩を打ち、「竹青をお忘れになったの?」
「竹青!」
魚容は仰天して立ち上り、それから少し躊躇ちゅうちょしたが、ええ、ままよ、といきなり美女の細い肩を掻き抱いた。
「離して。いきが、とまるわよ。」と竹青は笑いながら言って巧みに魚容の腕からのがれ、「あたしは、どこへも行かないわよ。もう、一生あなたのお傍に。」
「たのむ! そうしておくれ。お前がいないので、乃公は今夜この湖に身を投げて死んでしまうつもりだった。お前は、いったい、どこにいたのだ。」
「あたしは遠い漢陽に。あなたと別れてからここを立ち退き、いまは漢水の神烏になっているのです。さっき、この呉王廟にいる昔のお友達があなたのお見えになっている事を知らせにいらして下さったので、あたしは、漢陽からいそいで飛んで来たのです。あなたの好きな竹青が、ちゃんとこうして来たのですから、もう、死ぬなんておそろしい事をお考えになっては、いやよ。ちょっと、あなたも痩せたわねえ。」
「痩せる筈さ。二度も続けて落第しちゃったんだ。故郷に帰れば、またどんな目に遭うかわからない。つくづくこの世が、いやになった。」
「あなたは、ご自分の故郷にだけ人生があると思い込んでいらっしゃるから、そんなに苦しくおなりになるのよ。人間到いたるところに青山せいざんがあるとか書生さんたちがよく歌っているじゃありませんか。いちど、あたしと一緒に漢陽の家へいらっしゃい。生きているのも、いい事だと、きっとお思いになりますから。」
「漢陽は、遠いなあ。」いずれが誘うともなく二人ならんで廟びょうの廊下から出て月下の湖畔を逍遥しょうようしながら、「父母在いませば遠く遊ばず、遊ぶに必ず方有り、というからねえ。」魚容は、もっともらしい顔をして、れいの如くその学徳の片鱗へんりんを示した。
「何をおっしゃるの。あなたには、お父さんもお母さんも無いくせに。」
「なんだ、知っているのか。しかし、故郷には父母同様の親戚の者たちが多勢いる。乃公は何とかして、あの人たちに、乃公の立派に出世した姿をいちど見せてやりたい。あの人たちは昔から乃公をまるで阿呆か何かみたいに思っているのだ。そうだ、漢陽へ行くよりは、これからお前と一緒に故郷に帰り、お前のその綺麗きれいな顔をみんなに見せて、おどろかしてやりたい。ね、そうしようよ。乃公は、故郷の親戚の者たちの前で、いちど、思いきり、大いに威張ってみたいのだ。故郷の者たちに尊敬されるという事は、人間の最高の幸福で、また終極の勝利だ。」
「どうしてそんなに故郷の人たちの思惑ばかり気にするのでしょう。むやみに故郷の人たちの尊敬を得たくて努めている人を、郷原きょうげんというんじゃなかったかしら。郷原は徳の賊なりと論語に書いてあったわね。」
魚容は、ぎゃふんとまいって、やぶれかぶれになり、
「よし、行こう。漢陽に行こう。連れて行ってくれ。逝者ゆくものは斯かくの如き夫かな、昼夜を舎すてず。」てれ隠しに、甚はなはだ唐突な詩句を誦しょうして、あははは、と自らを嘲あざけった。
「まいりますか。」竹青はいそいそして、「ああ、うれしい。漢陽の家では、あなたをお迎えしようとして、ちゃんと仕度がしてあります。ちょっと、眼をつぶって。」
魚容は言われるままに眼を軽くつぶると、はたはたと翼の音がして、それから何か自分の肩に薄い衣のようなものがかかったと思うと、すっとからだが軽くなり、眼をひらいたら、すでに二人は雌雄の烏、月光を受けて漆黒しっこくの翼は美しく輝き、ちょんちょん平沙を歩いて、唖々と二羽、声をそろえて叫んで、ぱっと飛び立つ。
月下白光三千里の長江ちょうこう、洋々と東北方に流れて、魚容は酔えるが如く、流れにしたがっておよそ二ときばかり飛翔して、ようよう夜も明けはなれて遥はるか前方に水の都、漢陽の家々の甍いらかが朝靄あさもやの底に静かに沈んで眠っているのが見えて来た。近づくにつれて、晴川せいせん歴々たり漢陽の樹、芳草萋々せいせいたり鸚鵡おうむの洲、対岸には黄鶴楼の聳そびえるあり、長江をへだてて晴川閣と何事か昔を語り合い、帆影点々といそがしげに江上を往来し、更にすすめば大別山だいべつざんの高峰眼下にあり、麓ふもとには水漫々の月湖ひろがり、更に北方には漢水蜿蜒えんえんと天際に流れ、東洋のヴェニス一眸ぼうの中に収り、「わが郷関きょうかん何いずれの処ぞ是これなる、煙波江上、人をして愁えしむ」と魚容は、うっとり呟いた時、竹青は振りかえって、
「さあ、もう家へまいりました。」と漢水の小さな孤洲の上で悠然と輪を描きながら言った。魚容も真似して大きく輪を描いて飛びながら、脚下の孤洲を見ると、緑楊りょくよう水にひたり若草烟けむるが如き一隅にお人形の住家みたいな可憐な美しい楼舎があって、いましもその家の中から召使いらしき者五、六人、走り出て空を仰ぎ、手を振って魚容たちを歓迎している様が豆人形のように小さく見えた。竹青は眼で魚容に合図して、翼をすぼめ、一直線にその家めがけて降りて行き、魚容もおくれじと後を追い、二羽、その洲の青草原に降り立ったとたんに、二人は貴公子と麗人、にっこり笑い合って寄り添い、迎えの者に囲まれながらその美しい楼舎にはいった。
竹青に手をひかれて奥の部屋へ行くと、その部屋は暗く、卓上の銀燭ぎんしょくは青烟せいえんを吐はき、垂幕すいばくの金糸銀糸は鈍く光って、寝台には赤い小さな机が置かれ、その上に美酒佳肴かこうがならべられて、数刻前から客を待ち顔である。
「まだ、夜が明けぬのか。」魚容は間まの抜けた質問を発した。
「あら、いやだわ。」と竹青は少し顔をあからめて、「暗いほうが、恥かしくなくていいと思って。」と小声で言った。
「君子の道は闇然あんぜんたり、か。」魚容は苦笑して、つまらぬ洒落しゃれを言い、「しかし、隠いんに素むかいて怪を行う、という言葉も古書にある。よろしく窓を開くべしだ。漢陽の春の景色を満喫しよう。」
魚容は、垂幕を排して部屋の窓を押しひらいた。朝の黄金の光が颯さっと射し込み、庭園の桃花は、繚乱りょうらんたり、鶯うぐいすの百囀ひゃくてんが耳朶じだをくすぐり、かなたには漢水の小波さざなみが朝日を受けて躍っている。
「ああ、いい景色だ。くにの女房にも、いちど見せたいなあ。」魚容は思わずそう言ってしまって、愕然がくぜんとした。乃公は未だあの醜い女房を愛しているのか、とわが胸に尋ねた。そうして、急になぜだか、泣きたくなった。
「やっぱり、奥さんの事は、お忘れでないと見える。」竹青は傍で、しみじみ言い、幽かすかな溜息をもらした。
「いや、そんな事は無い。あれは乃公の学問を一向に敬重せず、よごれ物を洗濯させたり、庭石を運ばせたりしやがって、その上あれは、伯父の妾であったという評判だ。一つとして、いいところが無いのだ。」
「その、一つとしていいところの無いのが、あなたにとって尊くなつかしく思われているのじゃないの? あなたの御心底は、きっと、そうなのよ。惻隠そくいんの心は、どんな人にもあるというじゃありませんか。奥さんを憎まず怨うらまず呪わず、一生涯、労苦をわかち合って共に暮して行くのが、やっぱり、あなたの本心の理想ではなかったのかしら。あなたは、すぐにお帰りなさい。」竹青は、一変して厳粛な顔つきになり、きっぱりと言い放つ。
魚容は大いに狼狽ろうばいして、
「それは、ひどい。あんなに乃公を誘惑して、いまさら帰れとはひどい。郷原だの何だのと言って乃公を攻撃して故郷を捨てさせたのは、お前じゃないか。まるでお前は乃公を、なぶりものにしているようなものだ。」と抗弁した。
「あたしは神女です。」と竹青は、きらきら光る漢水の流れをまっすぐに見つめたまま、更にきびしい口調で言った。「あなたは、郷試には落第いたしましたが、神の試験には及第しました。あなたが本当に烏の身の上を羨望せんぼうしているのかどうか、よく調べてみるように、あたしは呉王廟の神様から内々に言いつけられていたのです。禽獣きんじゅうに化して真の幸福を感ずるような人間は、神に最も倦厭けんえんせられます。いちどは、こらしめのため、あなたを弓矢で傷つけて、人間界にかえしてあげましたが、あなたは再び烏の世界に帰る事を乞いました。神は、こんどはあなたに遠い旅をさせて、さまざまの楽しみを与え、あなたがその快楽に酔い痴しれて全く人間の世界を忘却するかどうか、試みたのです。忘却したら、あなたに与えられる刑罰は、恐しすぎて口に出して言う事さえ出来ないほどのものです。お帰りなさい。あなたは、神の試験には見事に及第なさいました。人間は一生、人間の愛憎の中で苦しまなければならぬものです。のがれ出る事は出来ません。忍んで、努力を積むだけです。学問も結構ですが、やたらに脱俗を衒てらうのは卑怯です。もっと、むきになって、この俗世間を愛惜し、愁殺し、一生そこに没頭してみて下さい。神は、そのような人間の姿を一ばん愛しています。ただいま召使いの者たちに、舟の仕度をさせて居ります。あれに乗って、故郷へまっすぐにお帰りなさい。さようなら。」と言い終ると、竹青の姿はもとより、楼舎も庭園も忽然こつぜんと消えて、魚容は川の中の孤洲に呆然と独り立っている。
帆も楫かじも無い丸木舟が一艘そうするすると岸に近寄り、魚容は吸われるようにそれに乗ると、その舟は、飄然ひょうぜんと自行じこうして漢水を下り、長江を溯さかのぼり、洞庭を横切り、魚容の故郷ちかくの漁村の岸畔に突き当り、魚容が上陸すると無人の小舟は、またするすると自おのずから引返して行って洞庭の烟波えんぱの間に没し去った。
頗すこぶるしょげて、おっかなびっくり、わが家の裏口から薄暗い内部を覗くと、
「あら、おかえり。」と艶然えんぜんと笑って出迎えたのは、ああ、驚くべし、竹青ではないか。
「やあ! 竹青!」
「何をおっしゃるの。あなたは、まあ、どこへいらしていたの? あたしはあなたの留守に大病して、ひどい熱を出して、誰もあたしを看病してくれる人がなくて、しみじみあなたが恋いしくなって、あたしが今まであなたを馬鹿にしていたのは本当に間違った事だったと後悔して、あなたのお帰りを、どんなにお待ちしていたかわかりません。熱がなかなかさがらなくて、そのうちに全身が紫色に腫はれて来て、これもあなたのようないいお方を粗末そまつにした罰で、当然の報いだとあきらめて、もう死ぬのを静かに待っていたら、腫れた皮膚が破れて青い水がどっさり出て、すっとからだが軽くなり、けさ鏡を覗いてみたら、あたしの顔は、すっかり変って、こんな綺麗な顔になっているので嬉しくて、病気も何も忘れてしまい、寝床から飛び出て、さっそく家の中のお掃除などはじめていたら、あなたのお帰りでしょう? あたしは、うれしいわ。ゆるしてね。あたしは顔ばかりでなく、からだ全体変ったのよ。それから、心も変ったのよ。あたしは悪かったわ。でも、過去のあたしの悪事は、あの青い水と一緒にみんな流れ出てしまったのですから、あなたも昔の事は忘れて、あたしをゆるして、あなたのお傍に一生置いて下さいな。」
一年後に、玉のような美しい男子が生れた。魚容はその子に「漢産」という名をつけた。その名の由来は最愛の女房にも明さなかった。神烏の思い出と共に、それは魚容の胸中の尊い秘密として一生、誰にも語らず、また、れいの御自慢の「君子の道」も以後はいっさい口にせず、ただ黙々と相変らずの貧しいその日暮しを続け、親戚の者たちにはやはり一向に敬せられなかったが、格別それを気にするふうも無く、極めて平凡な一田夫として俗塵ぞくじんに埋もれた。
自註。これは、創作である。支那のひとたちに読んでもらいたくて書いた。漢訳せられる筈である。
底本:「太宰治全集6」ちくま文庫、筑摩書房
1989(平成元)年2月28日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月
入力:柴田卓治
校正:山本奈津恵
2000年9月19日公開
2005年10月31日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
地球図
太宰治
ヨワン榎えのきは伴天連バテレンヨワン・バッティスタ・シロオテの墓標である。切支丹キリシタン屋敷の裏門をくぐってすぐ右手にそれがあった。いまから二百年ほどむかしに、シロオテはこの切支丹屋敷の牢のなかで死んだ。彼のしかばねは、屋敷の庭の片隅にうずめられ、ひとりの風流な奉行がそこに一本の榎を植えた。榎は根を張り枝をひろげた。としを経て大木になり、ヨワン榎とうたわれた。
ヨワン・バッティスタ・シロオテは、ロオマンの人であって、もともと名門の出であった。幼いときからして天主の法をうけ、学に従うこと二十二年、そのあいだ十六人もの先生についた。三十六歳のとき、本師キレイメンス十二世からヤアパンニアに伝道するよう言いつけられた。西暦一千七百年のことである。
シロオテは、まず日本の風俗と言葉とを勉強した。この勉強に三年かかったのである。ヒイタサントオルムという日本の風俗を記した小冊子と、デキショナアリヨムという日本の単語をいちいちロオマンの単語でもって飜訳してある書物と、この二冊で勉強したのであった。ヒイタサントオルムのところどころには、絵をえがきいれた頁がさしはさまれていた。
三年研究して自信のついたころ、やはりおなじ師命をうけてペッケンにおもむくトオマス・テトルノンという人と、めいめいカレイ一隻ずつに乗りつれ、東へ進んだ。ヤネワを経て、カナアリヤに至り、ここでまたフランスヤの海舶一隻ずつに乗りかえ、とうとうロクソンに着いた。ロクソンの海岸に船をつなぎ、ふたりは上陸した。トオマス・テトルノンは、すぐシロオテと別れてペッケンへむかったが、シロオテはひとりいのこって、くさぐさの準備をととのえた。ヤアパンニアは近いのである。
ロクソンには日本人の子孫が三千人もいたので、シロオテにとって何かと便利であった。シロオテは所持の貨幣を黄金に換えた。ヤアパンニアでは黄金を重宝ちょうほうにするという噂話うわさばなしを聞いたからであった。日本の衣服をこしらえた。碁盤のすじのような模様がついた浅黄いろの木綿着物であった。刀も買った。刃わたり二尺四寸余の長さであった。
やがてシロオテはロクソンより日本へ向った。海上たちまちに風逆し、浪あらく、航海は困難であった。船が三たびも覆くつがえりかけたのである。ロオマンをあとにして三年目のことであった。
宝永五年の夏のおわりごろ、大隅おおすみの国の屋久島やくしまから三里ばかり距へだてた海の上に、目なれぬ船の大きいのが一隻うかんでいるのを、漁夫たちが見つけた。また、その日の黄昏時たそがれどき、おなじ島の南にあたる尾野間おのまという村の沖に、たくさんの帆をつけた船が、小舟を一隻引きながら、東さしてはしって行くのを、村の人たちが発見し、海岸へ集って罵ののしりさわいだが、漸ようやく沖合いのうすぐらくなるにつれ、帆影は闇の中へ消えた。そのあくる朝、尾野間から二里ほど西の湯泊ゆどまりという村の沖のかなたに、きのうの船らしいものが見えたが、強い北風をいっぱい帆にはらみつつ、南をさしてみるみる疾航し去った。
その日のことである。屋久島の恋泊こいどまり村の藤兵衛という人が、松下というところで炭を焼くための木を伐っていると、うしろの方で人の声がした。ふりむくと、刀をさしたさむらいが、夏木立の青い日影を浴びて立っていた。シロオテである。髪を剃そってさかやきをこしらえていた。あの浅黄色の着物を着て、刀を帯び、かなしい眼をして立っていた。
シロオテは片手あげておいでおいでをしつつ、デキショナアリヨムで覚えた日本の言葉を二つ三つ歌った。しかし、それは不思議な言葉であった。デキショナアリヨムが不完全だったのである。藤兵衛は幾度となく首を振って考えた。言葉より動作が役に立った。シロオテは両手で水を掬すくって呑む真似を、烈しく繰り返した。藤兵衛は持ち合せの器に水を汲んで、草原の上にさし置き、いそいで後ずさりした。シロオテはその水を一息に呑んでしまって、またおいでおいでをした。藤兵衛はシロオテの刀をおそれて近よらなかった。シロオテは藤兵衛の心をさとったと見えて、やがて刀を鞘さやながら抜いて差し出し、また、あやしい言葉を叫ぶのであった。藤兵衛は身をひるがえして逃げた。きのうの大船のものにちがいない、と気附いたのである。磯辺に出て、かなたこなたを見廻したが、あの帆掛船の影も見えず、また、他に人のいるけはいもなかった。引返して村へ駈けこんで、安兵衛という人にたのみ、奇態なものを見つけたゆえ、参り呉れるよう、村中へ触れさせた。
こうしてシロオテは、ヤアパンニアの土を踏むか踏まぬかのうちに、その変装を見破られ、島の役人に捕えられた。ロオマンで三年のとしつき日本の風俗と言葉とを勉強したことが、なんのたしにもならなかったのである。
シロオテは、長崎へ護送された。伴天連らしきものとして長崎の獄舎に置かれたのである。しかし、長崎の奉行たちは、シロオテを持てあましてしまった。阿蘭陀オランダの通事たちに、シロオテの日本へ渡って来たわけを調べさせたけれど、シロオテの言葉が日本語のようではありながら発音やアクセントの違うせいか、エド、ナンガサキ、キリシタン、などの言葉しか聞きわけることができなかったのである。阿蘭陀人を背教者の故をもってか、ずいぶん憎がっているような素振りも見えるので、阿蘭陀人をして直接シロオテと対談させることもならず、奉行たちはたいへん困った。ひとりの奉行は、一策として、法廷のうしろの障子しょうじの蔭にふとった阿蘭陀人をひそませて置いて、シロオテを訊問してみた。ほかの奉行たちも、これをいい思いつきであるとして期待した。さて、奉行とシロオテとは、わけの判らぬ問答をはじめた。シロオテは、いかにもしてその思うところを言いあらわし自分の使命を了解させたいとむなしい苦悶くもんをしているようであった。よい加減のところで訊問を切りあげてから、奉行たちは障子のかげの阿蘭陀人に、どうだ、と尋ねた。阿蘭陀人は、とんとわからぬ、と答えた。だいいち阿蘭陀人には、ロオマンの言葉がわからぬうえに、まして、その言うところは半ば日本の言葉もまじっているのであるから、猶々なおなお、聞きわけることがむずかしかったのであろう。
長崎では、とうとう訊問に絶望して、このことを江戸へ上訴した。江戸でこの取調べに当ったのは、新井白石あらいはくせきである。
長崎の奉行たちがシロオテを糺問きゅうもんして失敗したのは宝永五年の冬のことであるが、そのうちに年も暮れて、あくる宝永六年の正月に将軍が死に、あたらしい将軍が代ってなった。そういう大きなさわぎのためにシロオテは忘れられていた。ようようその年の十一月のはじめになって、シロオテは江戸へ召喚された。シロオテは長崎から江戸までの長途を駕籠かごにゆられながらやって来た。旅のあいだは、来る日も来る日も、焼栗四つ、蜜柑みかん二つ、干柿五つ、丸柿二つ、パン一つを役人から与えられて、わびしげに食べていた。
新井白石は、シロオテとの会見を心待ちにしていた。白石は言葉について心配をした。とりわけ、地名や人名または切支丹の教法上の術語などには、きっとなやまされるであろうと考えた。白石は、江戸小日向こひなたにある切支丹屋敷から蛮語ばんごに関する文献を取り寄せて、下調べをした。
シロオテは、程なく江戸に到着して切支丹屋敷にはいった。十一月二十二日をもって訊問を開始するようにきめた。ときの切支丹奉行は横田備中守びっちゅうのかみと柳沢八郎右衛門のふたりであった。白石は、まえもってこの人たちと打ち合せをして置いて、当日は朝はやくから切支丹屋敷に出掛けて行き、奉行たちと共に、シロオテの携えて来た法衣や貨幣や刀やその他の品物を検査し、また、長崎からシロオテに附き添うて来た通事たちを招き寄せて、たとえばいま、長崎のひとをして陸奥むつの方言を聞かせたとしても、十に七八は通じるであろう、ましてイタリヤと阿蘭陀とは、私が万国の図を見てしらべたところに依ると、長崎陸奥のあいだよりは相さること近いのであるから、阿蘭陀の言葉でもってイタリヤの言葉を押しはかることもさほどむずかしいとは思われぬ、私もその心して聞こう故、かたがたもめいめいの心に推しはかり、思うところを私に申して呉れ、たとえかたがたの推量にひがごとがあっても、それは咎とがむべきでない、奉行の人たちも通事の誤訳を罪せぬよう、と諭さとした。人々は、承知した、と答えて審問の席に臨んだ。そのときの大通事は今村源右衛門。稽古通事は品川兵次郎、嘉福喜蔵。
その日のひるすぎ、白石はシロオテと会見した。場所は切支丹屋敷内であって、その法庭の南面に板縁があり、その縁ちかくに奉行の人たちが着席し、それより少し奥の方に白石が坐った。大通事は板縁の上、西に跪ひざまずき、稽古通事ふたりは板縁の上、東に跪いた。縁から三尺ばかり離れた土間に榻こしかけを置いてシロオテの席となした。やがて、シロオテは獄中から輿こしではこばれて来た。長い道中のために両脚が萎なえてかたわになっていたのである。歩卒ふたり左右からさしはさみ助けて、榻につかせた。
シロオテのさかやきは伸びていた。薩州さっしゅうの国守からもらった茶色の綿入れ着物を着ていたけれど、寒そうであった。座につくと、静かに右手で十字を切った。
白石は通事に言いつけて、シロオテの故郷のことなど問わせ、自分はシロオテの答える言葉に耳傾けていた。その語る言葉は、日本語にちがいなく、畿内、山陰、西南海道の方言がまじっていて聞きとりがたいところもあったけれど、かねて思いはかっていたよりは了解がやさしいのであった。ヤアパンニアの牢のなかで一年をすごしたシロオテは、日本の言葉がすこし上手になっていたのである。通事との問答を一時間ほど聞いてから、白石みずから問いもし答えもしてみて、その会話にやや自信を得た。白石は、万国の図を取り出して、シロオテのふるさとをたずね問うた。シロオテは板縁にひろげられたその地図を首筋のばして覗いていたがやがて、これは明人みんじんのつくったもので意味のないものである、と言って声たてて笑った。地図の中央に薔薇の花のかたちをした大きい国があって、それには「大明」と記入されているのであった。
この日は、それだけの訊問で打ち切った。シロオテは、わずかの機会をもとらえて切支丹の教法を説こうと思ってか、ひどくあせっているふうであったが、白石はなぜか聞えぬふりをするのである。
あくる日の夜、白石は通事たちを自分のうちに招いて、シロオテの言うたことに就つき、みんなに復習させた。白石は万国の図がはずかしめられたのを気にかけていた。切支丹屋敷にオオランド鏤版ろうはんの古い図があるということを奉行たちから聞き、このつぎの訊問のときにはひとつそれをシロオテに見せてやるよう、言いつけて散会した。
一日おいて二十五日に、白石は早朝から吟味所へつめかけた。午前十時ごろ、奉行の人たちもみんな出そろって着席した。やがてシロオテも輿ではこばれてやって来た。
きょうは、だいいちばんに、あのオオランド鏤版の地図を板縁いっぱいにひろげて、かの地方のことを問いただしたのである。地図のここかしこは破れて、虫に食われた孔あながそちこちにちらばっていた。シロオテはその図を暫しばらく眺めてから、これは七十余年まえに作られたものであって、いまでは、むこうの国でも得がたい好地図である、とほめた。ロオマンはどこであるか、と白石も膝をすすめて尋ねた。シロオテは、チルチヌスがあるか、と言った。通事たちは、ない、と答えた。なにごとか、と白石は通事たちに聞いた。阿蘭陀語ではパッスルと申し、イタリヤ語ではコンパスと申すもののことである、と通事のひとりが教えた。白石は、コンパスというものかどうか知らぬが、地図に用ありげな機械であるから、私がこの屋敷で見つけていま持って来てある、と言いつつ懐中から古びたコンパスを出して見せた。シロオテはそれを受けとり鳥渡ちょっとの間いじくりまわしていたが、これはコンパスにちがいないが、ねじがゆるんで用に立たぬ、しかし、ないよりはましかも知れぬ、という意味のことを述べ、その地図のうちに計るべきところをこまかく図してあるところを見て、筆を求め、その字を写しとってから、コンパスを持ち直してその分数をはかりとり、榻こしかけに坐ったまま板縁の地図へずっと手をさしのばして、そのこまかく図してあるところより蜘蛛くもの網いのように画かれた線路をたずねながら、かなたこなたへコンパスを歩かせているうちに、手のやっと届くようなところへいって、ここであろう、見給え、と言いコンパスをさし立てた。みんな頭を寄せて見ると、針の孔のような小さいまるにコンパスのさきが止っていた。通事のひとりは、そのまるのかたわらの蕃字ばんじをロオマンと読んだ。それから、阿蘭陀や日本の国々のあるところを問うに、また、まえの法のようにして、ひとところもさし損ねることがなかった。日本は思いのほかにせまくるしく、エドは虫に食われて、その所在をたしかめることさえできなかった。
シロオテは、コンパスをあちらこちらと歩かせつつ、万国のめずらしい話を語って聞かせた。黄金の産する国。たんばこの実る国。海鯨の住む大洋。木に棲すみ穴にいて生れながらに色の黒いくろんぼうの国。長人国。小人国。昼のない国。夜のない国。さては、百万の大軍がいま戦争さいちゅうの曠野。戦船百八十隻がたがいに砲火をまじえている海峡。シロオテは、日の没するまで語りつづけたのである。
日が暮れて、訊問もおわってから、白石はシロオテをその獄舎に訪れた。ひろい獄舎を厚い板で三つに区切ってあって、その西の一間にシロオテがいた。赤い紙を剪きって十字を作り、それを西の壁に貼りつけてあるのが、くらがりを通して、おぼろげに見えた。シロオテはそれにむかって、なにやら経文きょうもんを、ひくく読みあげていた。
白石は家へ帰って、忘れぬうちにもと、きょうシロオテから教わった知識を手帖に書いた。
──大地、海水と相合うて、その形まどかなること手毬てまりの如くにして、天、円のうちに居る。たとえば、鶏子の黄なる、青きうちにあるが如し。その地球の周囲、九万里にして、上下四旁ほう、皆、人ありて居れり。凡およそ、その地をわかちて、五大州となす。云々。
それから十日ほど経って十二月の四日に、白石はまたシロオテを召し出し、日本に渡って来たことの由をも問い、いかなる法を日本にひろめようと思うのか、とたずねたのである。その日は朝から雪が降っていた。シロオテは降りしきる雪の中で、悦びに堪えぬ貌かおをして、私が六年さきにヤアパンニアに使するよう本師より言いつけられ、承って万里の風浪をしのぎ来て、ついに国都へついた、しかるに、きょうしも本国にあっては新年の初めの日として、人、皆、相賀するのである、このよき日にわが法をかたがたに説くとは、なんという仕合せなことであろう、と身をふるわせてそのよろこびを述べ、めんめんと宗門の大意を説きつくしたのであった。
デウスがハライソを作って無量無数のアンゼルスを置いたことから、アダン、エワの出生と堕落について。ノエの箱船のことや、モイセスの十誡じっかいのこと。そうしてエイズス・キリストスの降誕、受難、復活のてんまつ。シロオテの物語は、尽きるところなかった。
白石は、ときどき傍見わきみをしていた。はじめから興味がなかったのである。すべて仏教の焼き直しであると独断していた。
白石のシロオテ訊問は、その日を以ておしまいにした。白石はシロオテの裁断について将軍へ意見を言上した。このたびの異人は万里のそとから来た外国人であるし、また、この者と同時に唐へ赴おもむいたものもある由なれば、唐でも裁断をすることであろうし、わが国の裁断をも慎重にしなければならぬ、と言って三つの策を建言した。
第一にかれを本国へ返さるる事は上策也(此事難きに似て易き歟か)
第二にかれを囚となしてたすけ置るる事は中策也(此事易きに似て尤もっとも難し)
第三にかれを誅ちゅうせらるる事は下策也(此事易くして易かるべし)
将軍は中策を採って、シロオテをそののち永く切支丹屋敷の獄舎につないで置いた。しかし、やがてシロオテは屋敷の奴婢ぬひ、長助はる夫婦に法を授けたというわけで、たいへんいじめられた。シロオテは折檻せっかんされながらも、日夜、長助はるの名を呼び、その信を固くして死ぬるとも志を変えるでない、と大きな声で叫んでいた。
それから間もなく牢死した。下策をもちいたもおなじことであった。
底本:「太宰治全集1」ちくま文庫、筑摩書房
1988(昭和63)年8月30日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集第一卷」筑摩書房
1975(昭和50)年6月20日初版第1刷発行
初出:「新潮 第三十二年第十二号」
1935(昭和10)年12月1日発行
入力:柴田卓治
校正:すずきともひろ
1999年6月23日公開
2014年6月27日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
「地球圖」序
太宰治
「新潮」編輯者楢崎勤氏、私に命ずるに、「ちかごろ何か感想云々」を以てす。案ずるに、「ダス・ゲマイネ」の註釋などせよとの親切心より發せしお言葉ならむ。拙作「ダス・ゲマイネ」は、此の國のジヤアナリズムより、かつてなきほどの不當の冷遇を受け、私をして、言葉通ぜぬ國に在るが如き痛苦を嘗めしむ。舌を燒き、胸を焦がし、生命の限り、こんのかぎりの絶叫も、馬耳東風の有樣なれば、私に於いて、いまさらなんの感想ぞや。すなはち、左に「地球圖」と題する一篇の小品を默示するのみ。もとより、これは諷刺に非ず、格言に非ず、一篇のかなしき物語にすぎず、されど、わが若き二十代の讀者よ、諸君はこの物語讀了ののち、この國いまだ頑迷にして、よき通事ひとり、好學の白石ひとりなきことを覺悟せざるべからず。「われら血まなこの態になれば、彼等いよいよ笑ひさざめき、才子よ、化け物よ、もしくはピエロよ、と呼稱す。人は、けつして人を嘲ふべきものではないのだけれど。」
底本:「太宰治全集11」筑摩書房
1999(平成11)年3月25日初版第1刷発行
初出:「新潮 第三十二年第十二号」
1935(昭和10)年12月1日発行
入力:小林繁雄
校正:阿部哲也
2012年1月7日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
千代女
太宰治
女は、やっぱり、駄目なものなのね。女のうちでも、私という女ひとりが、だめなのかも知れませんけれども、つくづく私は、自分を駄目だと思います。そう言いながらも、また、心の隅すみで、それでもどこか一ついいところがあるのだと、自分をたのみにしている頑固がんこなものが、根づよく黒く、わだかまって居るような気がして、いよいよ自分が、わからなくなります。私は、いま、自分の頭に錆さびた鍋なべでも被かぶっているような、とっても重くるしい、やり切れないものを感じて居ります。私は、きっと、頭が悪いのです。本当に、頭が悪いのです。もう、来年は、十九です。私は、子供ではありません。
十二の時に、柏木かしわぎの叔父おじさんが、私の綴方つづりかたを「青い鳥」に投書して下さって、それが一等に当選し、選者の偉い先生が、恐ろしいくらいに褒ほめて下さって、それから私は、駄目になりました。あの時の綴方は、恥ずかしい。あんなのが、本当に、いいのでしょうか。どこが、いったい、よかったのでしょう。「お使い」という題の綴方でしたけれど、私がお父さんのお使いで、バットを買いに行った時の、ほんのちょっとした事を書いたのでした。煙草屋のおばさんから、バットを五つ受取って、緑のいろばかりで淋さびしいから、一つお返しして、朱色の箱の煙草と換えてもらったら、お金が足りなくなって困った。おばさんが笑って、あとでまた、と言って下さったので嬉しかった。緑の箱の上に、朱色の箱を一つ重ねて、手のひらに載せると、桜草さくらそうのように綺麗きれいなので、私は胸がどきどきして、とても歩きにくかった、というような事を書いたのでしたが、何だか、あまり子供っぽく、甘えすぎていますから、私は、いま考えると、いらいらします。また、そのすぐ次に、やっぱり柏木の叔父さんにすすめられて、「春日町かすがちょう」という綴方を投書したところが、こんどは投書欄では無しに、雑誌の一ばんはじめのペエジに、大きな活字で掲載せられて居りました。その、「春日町」という綴方は、池袋の叔母おばさんが、こんど練馬の春日町へお引越しになって、庭も広いし、是非いちど遊びにいらっしゃいと言われて私は、六月の第一日曜に、駒込駅から省線に乗って、池袋駅で東上線に乗り換え、練馬駅で下車しましたが、見渡す限り畑ばかりで、春日町は、どの辺か見当が附かず、野良のらの人に聞いてもそんなところは知らん、というので私は泣きたくなりました。暑い日でした。リヤカアに、サイダアの空瓶を一ぱい積んで曳ひいて歩いている四十くらいの男のひとに、最後に、おたずねしたら、そのひとは淋しそうに笑って、立ちどまり、だくだく流れる顔の汗を鼠ねずみいろに汚れているタオルで拭きながら、春日町、春日町、と何度も呟つぶやいて考えて下さいました。それから、こう言いました。春日町は、たいへん遠いです。そこの練馬駅から東上線で池袋へ行き、そこで省線に乗り換え、新宿駅へ着いたら、東京行の省線に乗り換え、水道橋というところで降りて、とたいへん遠い路みちのりを、不自由な日本語で一生懸命に説明して下さいましたが、どうやらそれは、本郷の春日町に行く順路なのでありました。お話を聞いて、そのおかたが朝鮮のおかたであるということも、私にはすぐにわかりましたが、それゆえいっそう私には有がたくて、胸が一ぱいになったのでした。日本のひとは、知っていても、面倒なので、知らんと言っているのに、朝鮮の此このおかたは、知らなくても、なんとかして私に教えて下さろうとして汗をだらだら流して一生懸命におっしゃるのです。私は、おじさん、ありがとうと言いました。そうして、おじさんの教えて下さったとおりに、練馬駅に行き、また東上線に乗って、うちへ帰ってしまいました。よっぽど、本郷の春日町まで行こうかしらと思いました。うちへ帰ってから、なんだか悲しく具合いのわるい感じでした。私はその事を正直に書いたのです。すると、それが雑誌の一ばんはじめのペエジに大きい活字で印刷されて、たいへんな事になりました。私の家は、滝野川の中里町にあります。父は東京の人ですが、母は伊勢の生れであります。父は、私立大学の英語の教師をしています。私には、兄も姉もありません。からだの弱い弟がひとりあるきりです。弟は、ことし市立の中学へはいりました。私は、私の家庭を決してきらいでは無いのですが、それでも淋しくてなりません。以前はよかった。本当に、よかった。父にも母にも、思うぞんぶんに甘えて、おどけたことばかり言い、家中を笑わせて居りました。弟にも優しくしてあげて、私はよい姉さんでありました。それが、あの、「青い鳥」に綴方を掲載せられてからは、急に臆病な、いやな子になりました。母と、口喧嘩くちげんかをするようにさえなりました。「春日町」が、雑誌に載った時には、その同じ雑誌には、選者の岩見先生が、私の綴方の二倍も三倍も長い感想文を書いて下さって、私はそれを読んで淋しい気持になりました。先生が、私にだまされているのだ、と思いました。岩見先生のほうが、私よりも、ずっと心の美しい、単純なおかただと思いました。それから、また学校では、受持の沢田先生が、綴方のお時間にあの雑誌を教室に持って来て、私の「春日町」の全文を、黒板に書き写し、ひどく興奮なされて、一時間、叱り飛ばすような声で私を、ほめて下さいました。私は息がくるしくなって、眼のさきがもやもや暗く、自分のからだが石になって行くような、おそろしい気持が致しました。こんなに、ほめられても、私にはその値打が無いのがわかっていましたから、この後、下手へたな綴方を書いて、みんなに笑われたら、どんなに恥ずかしく、つらい事だろうと、その事ばかりが心配で、生きている気もしませんでした。また沢田先生だって、本当に私の綴方に感心なさっているのではなく、私の綴方が雑誌に大きい活字で印刷され、有名な岩見先生に褒められているので、それで、あんなに興奮していらっしゃるのだろうという事は、子供心にも、たいてい察しが附いて居りましたから、なおのこと淋しく、たまらない気持でした。私の心配は、その後、はたして全部、事実となってあらわれました。くるしい、恥ずかしい事ばかり起りました。学校のお友達は、急に私によそよそしくなって、それまで一ばん仲の良かった安藤さんさえ、私を一葉さんだの、紫式部さまだのと意地のわるい、あざけるような口調で呼んで、ついと私から逃げて行き、それまであんなにきらっていた奈良さんや今井さんのグルウプに飛び込んで、遠くから私のほうをちらちら見ては何やら囁ささやき合い、そのうちに、わあいと、みんな一緒に声を合せて、げびた囃はやしかたを致します。私は、もう一生、綴方を書くまいと思いました。柏木の叔父さんにおだてられて、うっかり投書したのが、いけなかったのでした。柏木の叔父さんは、母の弟です。淀橋の区役所に勤めていて、ことしは三十四だか五だかになって、赤ちゃんも去年生れたのに、まだ若い者のつもりで、時々お酒を飲みすぎて、しくじりをする事もあるようです。来る度毎に、母から少しずつお金をもらって帰るようです。大学へはいった頃には、小説家になるつもりで勉強して、先輩のひとたちにも期待されていたのに、わるい友達がいた為に、いけなくなって大学も中途でよしてしまったのだ、と母から聞かされた事があります。日本の小説でも、外国の小説でも、ずいぶんたくさん読んでいるようであります。七年前に、私の下手な綴方を無理矢理、「青い鳥」に投書させたのも、此の叔父さんですし、それから七年間、何かにつけて私をいじめているのも、此の叔父さんであります。私は小説を、きらいだったのです。いまはまた違うようになりましたが、その頃は、私のたわいも無い綴方が、雑誌に二度も続けて掲載せられて、お友達には意地悪くされるし、受持の先生には特殊な扱いをされて重苦しく、本当に綴方がいやになって、それからは柏木の叔父さんから、どんなに巧うまくおだてられても、決して投書しようとはしませんでした。あまり、しつこくすすめられると、私は大声で泣いてやりました。学校の綴方のお時間にも、私は、一字も一行いちぎょうも書かず綴方のお帳面に、まるだの三角だの、あねさまの顔だのを書いていました。沢田先生は、私を教員室にお呼びになって、慢心してはいけない、自重せよ、と言ってお叱りになりました。私は、くやしく思いました。けれども、まもなく小学校を卒業してしまいましたので、そのような苦しさからは、どうやら、のがれる事が出来たのでした。お茶の水の女学校に通うようになってからは、クラスの中で、私のつまらない綴方の、当選などを知っていたかたは、ひとりも居りませんでしたので、私は、ほっとしたのです。作文のお時間にも、私は気楽に書いて、普通のお点をもらっていました。けれども、柏木の叔父さんだけは、いつまでも、うるさく私を、からかうのです。うちへいらっしゃる度毎に、三四冊の小説の御本を持って来て下さって、読め、読めと言うのです。読んでみても、私には、むずかしくて、よくわかりませんでしたので、たいてい、読んだ振りして叔父さんに返してしまいました。私が女学校の三年生になった時、突然、「青い鳥」の選者の岩見先生から、私の父に長いお手紙がまいりました。惜しい才能と思われるから、とか何とか、恥ずかしくて、とても私には言えませんけれども、なんだか、ひどく私を褒めて、このまま埋うもらせてしまうのは残念だ、もう少し書かせてみないか、発表の雑誌の世話をしてあげる、というような事を、もったいない叮嚀ていねいなお言葉で、まじめにおっしゃっているのでした。父が、私にそのお手紙を、だまって渡して下さったのです。私はそのお手紙を読ませていただき、岩見先生というお方は本当に、厳粛な、よい先生だとは思いましたが、その裏には叔父さんのおせっかいがあったのだという事も、そのお手紙の文面で、はっきりわかるのでした。叔父さんは、きっと何か小細工をして岩見先生に近づき、こんなお手紙を私の父にお書き下さるようにさまざま計略したのです。それに違いないのです。「叔父さんが、おたのみになったのよ。それにきまっているわ。叔父さんは、どうしてこんな、こわい事をなさるのでしょう。」と泣きたい気持で、父の顔を見上げたら、父も、それはちゃんと見抜いていらっしゃった様子で、小さく首肯うなずき、「柏木の弟も、わるい気でやっているのではないだろうが、こちらでは岩見さんへ、なんと挨拶したものか困ってしまう。」と不機嫌そうにおっしゃいました。父は前から、柏木の叔父さんを、あんまり好いてはいなかったようでした。私が綴方に当選した時なども、母や叔父さんは大へんな喜びかたでありましたけれども、父だけは、こんな刺激の強い事をさせてはいけないとか言って、叔父さんをお叱りになったそうで、あとで母が私に不満そうに言い聞かせてくれました。母は、叔父さんの事をいつも悪く言っていますが、その癖、父が叔父さんの事を一言でも悪く言うと、たいへん怒るのです。母は優しく、にぎやかな、いい人ですが、叔父さんの事になると、時々、父と言い争いを致します。叔父さんは、私の家の悪魔です。岩見先生から、叮嚀なお手紙をもらってから、二三日後に父と母は、とうとう、ひどい言い争いを致しました。夕ごはんの時、父は、「岩見さんが、あんなに誠意を以もって言って下さっているのだし、こちらでも失礼にならないように、私が和子を連れて行って、よく和子の気持も説明して、おわびして来なければならないと思う。手紙だけでは、誤解も生じて、お気をわるくなさる事があったりすると困るから。」とおっしゃったところが、母は伏目になって、ちょっと考えて、「弟が、わるいのです。本当に皆さんに御手数をおかけします。」と言って、顔を挙げ、ひょいと右手の小指でおくれ毛を掻かき上げてから、「私たちは馬鹿のせいか、和子がそんなに有名な先生から褒められると、なんだか此の後もよろしくとお願いしたい気が起って来るのです。伸びるものなら、伸ばしてやりたい気がします。いつも、あなたに叱られるのですけど、あなたも少し、頑固すぎやしませんか。」と早口で言って、薄く笑いました。父は、お箸はしを休めて、「伸ばしてみたって、どうにもなりません。女の子の文才なんて、たかの知れたものです。一時の、もの珍らしさから騒がれ、そうして一生を台無しにされるだけの事です。和子だって、こわがっているのです。女の子は、平凡に嫁いで、いいお母さんになるのが一ばん立派な生きかたです。お前たちは、和子を利用して、てんでの虚栄心や功名心を満足させようとしているのです。」と教えるような口調で言いました。母は、父のおっしゃる言葉をちっとも聞こうとなさらず、腕を伸ばして私の傍の七輪しちりんのお鍋を、どさんと下におろして、あちちと言って右手の親指と人さし指を唇に押し当て、「おう熱い、やけどしちゃった。でも、ねえ、弟だって、わるい気でしているのではないのですからねえ。」とそっぽを向いておっしゃいました。父は、こんどは、お茶碗とお箸を下に置いて、「なんど言ったらわかるのだ。お前たちは、和子を、食いものにしようとしているのだ。」と大きい声でおっしゃって、左手で眼鏡を軽く抑え、それから続けて何か言いかけた時、母は、突然ひいと泣き出しました。前掛まえかけで涙を拭きながら、父の給料の事やら、私たちの洋服代の事やら、いろいろとお金の事を、とても露骨に言い出しました。父は、顎あごをしゃくって私と弟に、あっちへ行けというような合図をなさいましたので、私は弟をうながして、勉強室へ引き上げましたが、茶の間のほうからは、それから一時間も、言い争いの声が聞えました。母は、普段は、とても気軽な、さっぱりしたひとなのですが、かっと興奮すると、聞いて居られないような極端な荒い事ばかりおっしゃるので、私は悲しくなります。翌あくる日、父は学校のおつとめの帰りに、岩見先生のお家へ、お礼とお詫びにあがったようでした。その朝、父は私にも一緒に行くようにすすめて下さったのですが、私は何だか、こわくて、下唇がぷるぷる震えて、とてもお伺いする元気が出なかったのです。父は、その晩、七時頃にお帰りになって、岩見さんは、まだお年もお若いのに、なかなか立派なお人だ、こちらの気持も充分にわかって下さって、かえって向うのほうから父にお詫びを言って、自分も本当は女のお子さんには、あまり文学をすすめたくないのだ、とおっしゃって、はっきり名前は言わなかったが、やはり柏木の叔父さんから再三たのまれて、やむなく父に手紙を書いた御様子であった、と父は、母と私に語って下さいました。私は、父の手を、つねりましたら、父は、眼鏡の奥で、そっと眼をつぶって笑って見せました。母は、何事も忘れたような、落ちついた態度で、父の言葉にいちいち首肯いて、別に、なんにも言いませんでした。
それから暫しばらくの間は、叔父さんもあまり姿を見せませんでしたし、おいでになっても、私にはへんによそよそしくなさって、すぐにお帰りになりました。私は、綴方の事は、きれいに忘れて、学校から帰ると、花壇の手入れ、お使い、台所のお手伝い、弟の家庭教師、お針、学課の勉強、お母さんに按摩あんまをしてあげたり、なかなかいそがしく、みんなの役にたって、張り合いのある日々を送りました。
あらしが、やって来ました。私が女学校四年生の時の事でしたが、お正月にひょっくり、小学校の沢田先生が、家へ年賀においでになって、父も母も、めずらしがるやら、なつかしがるやら、とても喜んでおもてなし致しましたが、沢田先生は、もうとっくに、小学校のほうはお止よしになって、いまは、あちこちの、家庭教師をしながら、のんきに暮していらっしゃるというお話でありました。けれども、私の感じたところでは、失礼ながら、のんきそうには見えず、柏木の叔父さんと同じくらいのお年としの筈はずなのに、どうしても四十過ぎの、いや、五十ちかくのお人の感じで、以前も、老けたお顔のおかたでありましたが、でも、この四、五年お逢いせずにいる間に、二十もお年をとられて疲れ切っているように見受けられました。笑うのにも力が無く、むりに笑おうとなさるので、頬に苦しい固い皺しわが畳たたまれて、お気の毒というよりは、何だかいやしい感じさえ致しました。おつむは相変らず短く丸刈にして居られましたが、白髪しらががめっきりふえていました。以前と違って、矢鱈やたらに私にお追従ついしょうばかりおっしゃるので、私は、まごついて、それから苦しくなりました。きりょうが良いの、しとやかだのと、聞いて居られないくらいに見え透いたお世辞をおっしゃって、まるで私が、先生の目上めうえの者か何かみたいに馬鹿叮嚀な扱いをなさるのでした。父や母に向って、私の小学校時代の事を、それはいやらしいくらいに、くどくどと語り、私が折角せっかくいい案配に忘れていたあの綴方の事まで持ち出して、全く惜しい才能でした、あの頃は僕も、児童の綴方に就いては、あまり関心を持っていなかったし、綴方に依よって童心を伸ばすという教育法も存じませんでしたが、いまは違います。児童の綴方に就いて、充分に研究も致しましたし、その教育法に於いても自信があります。どうです、和子さん、僕の新しい指導のもとに、もう一度、文章の勉強をなさいませぬか、僕は、必ずや、などとずいぶんお酒に酔ってもいましたが、大袈裟おおげさな事を片肘かたひじ張って言い出す仕末で、果ては、さあ僕と握手をしましょうと、しつこくおっしゃるので、父も母も、笑っていながら内心は、閉口していた様子でありました。けれども、その時、沢田先生が酔っておっしゃった事は、口から出まかせの冗談では無かったのです。それから十日ほど経ったら、また仔細しさいらしい顔つきをして、家へおいでになって、さて、それでは少しずつ、綴方の基本練習をはじめましょうね、とおっしゃったので、私は、まごついてしまいました。後でわかった事ですが、沢田先生は、小学校で生徒の受験勉強の事から、問題を起し、やめさせられ、それから、くらしが思うように行かず、昔の教え子の家を歴訪しては無理矢理、家庭教師みたいな形になりすまし、生活の方便にしていらっしゃったというような具合いなのでした。お正月においでになって、その後すぐに私の母へ、こっそりお手紙を寄こした様子で、私の文才とやらいうものを褒めちぎり、また、そのころ起った綴方の流行、天才少女とかの出現などを例に挙げて、母をそそのかし、母もまた以前から、私の綴方には未練があったものですから、それでは一週にいちどくらい家庭教師としておいで下さるようにと御返事して、父には、沢田先生のおくらしを、少しでもお助けするためです、と言い張って、父も、沢田先生は昔の和子の先生ですから、それはいけないとも言えなかった様子で、しぶしぶ沢田先生をお迎えするというような事情だったらしいのでございます。沢田先生は、土曜日毎にお見えになり、私の勉強室でひそひそ、なんとも馬鹿らしい事ばかりおっしゃるので、私は、いやでなりませんでした。文章というものは、第一に、てにをはの使用を確実にしなければならぬ、等と当り前の事を、一大事のように繰り返し繰り返しおっしゃって、太郎は庭を遊ぶというのは、あやまり。太郎は庭へ遊ぶというのも、やっぱり、あやまり。太郎は庭にて遊ぶといわなければいけないのだそうで、私が、くすくす笑うと、とても、うらめしそうな目つきで、私の顔を穴のあくほど見つめて、ほうと溜息をつき、あなたには誠実が不足している、いかに才能が豊富でも、人間には誠実がなければ、何事に於いても成功しない、あなたは寺田まさ子という天才少女を知っていますか、あの人は、貧しい生れで、勉強したくても本一冊買えなかったほど、不自由な気の毒な身の上であった、けれども誠実だけはあった、先生の教えをよく守った、それゆえ、あれほどの名作を完成できたのです、教える先生にしても、どんなに張り合いのあった事でしょう、あなたに、もうすこし誠実というものがあったならば、僕だって、あなたを寺田まさ子さんくらいには仕上げて見せます、いや、あなたは環境にめぐまれてもいるし、もっと大きな文章家に仕上げる事が出来るのです、僕は、寺田まさ子さんの先生よりも或ある点で進歩しているつもりです、それは徳育という点であります、あなたは、ルソオという人を知っていますか、ジャン・ジャック・ルソオ、西暦千六百、いや、西暦千七百、千九百、笑いなさい、うんと笑いなさい、あなたは自分の才能にたよりすぎて、師を軽蔑しているのです、むかし支那に顔回がんかいという人物がありました、等といろんな事を言い出して一時間くらい経つと、けろりとして、また此の次の事にしましょうと言って私の勉強室から出て行かれ、茶の間で母と世間話をなさって帰ります。小学校の時に、多少でもお世話になった先生の事を、とやかく申し上げるのは悪い事でございますが、本当に、沢田先生は、ぼけていらっしゃるとしか私には思えませんでした。文章には描写が大切だ、描写が出来ていないと何を書いているのかわからない、等と、もっとも過ぎるような事を、小さい手帖を見ながら、おっしゃって、たとえば此の雪の降るさまを形容する場合、と言って手帖を胸のポケットにおさめ、窓の外で、こまかい雪が芝居のようにたくさん降っているさまを屹きっと見て、雪がざあざあ降るといっては、いけない。雪の感じが出ない。どしどし降る、これも、いけない。それでは、ひらひら降る、これはどうか。まだ足りない。さらさら、これは近い。だんだん、雪の感じに近くなって来た。これは、面白い、とひとりで首を振りながら感服なさって腕組みをし、しとしとは、どうか、それじゃ春雨の形容になってしまうか、やはり、さらさらに、とどめを刺すかな? そうだ、さらさらひらひら、と続けるのも一興だ。さらさらひらひら、と低く呟いてその形容を味わい楽しむみたいに眼を細めていらっしゃる、かと思うと急に、いや、まだ足りない、ああ、雪は鵝毛がもうに似て飛んで散乱す、か。古い文章は、やっぱり確実だなあ、鵝毛とは、うまく言ったものですねえ、和子さん、おわかりになったでしょう? と、はじめて私のほうへ向き直っておっしゃるのです。私は、なんだか先生が気の毒なやら、憎らしいやらで、泣きそうになりました。それでも三箇月間ほど我慢して、そんな侘わびしい、出鱈目でたらめの教育をつづけて受けて居りましたが、もう、なんとしても、沢田先生のお顔を見るのさえ、いやになって、とうとう父に洗いざらい申し上げ、沢田先生のおいでになるのをお断りして下さるようにお願い致しました。父は私の話を聞いて、それは意外だ、とおっしゃいました。父は、もともと、家庭教師を呼ぶ事には反対だったのですが、沢田先生のおくらしの一助という名目めいもくに負けて、おいでを願う事にしていたのであって、まさか、そんな無責任な綴方教育を授けているとは思いも寄らず、毎週いちど、少しは和子の学課の勉強の手伝いをして下さっているものとばかり思っていた様子でした。さっそく母と、ひどい言い争いになりました。茶の間の言い争いを、私は勉強室で聞きながら、思うぞんぶんに泣きました。私の事で、こんな騒ぎになって、私ほど悪い不孝な娘は無いという気がしました。こんな事なら、いっそ、綴方でも小説でも、一心に勉強して、母を喜ばせてあげたいとさえ思いましたが、私は、だめなのです。もう、ちっとも何も書けないのです。文才とやらいうものは、はじめから無かったのです。雪の降る形容だって、沢田先生のほうが、きっと私より上手なのでしょう。私は、自分では何も出来やしない癖くせに、沢田先生を笑ったりして、なんという馬鹿な娘でしょう。さらさらひらひらという形容さえ、とても私には、考えつかぬ事だった。私は、茶の間の言い争いを聞きながら、つくづく自分をいけない娘だと思いました。
その時は、母も父に言い負けて、沢田先生も姿を見せなくなりましたが、悪い事が、つづいて起りました。東京の深川で、金沢ふみ子という十八の娘さんが、たいへん立派な文章を書いて、それが世間の大評判になったのでした。そのひとの本が、どんな偉い小説家の本よりも、はるかに多く売れて、一躍、大金持になったという噂うわさを、柏木の叔父さんが、まるで御自分が大金持にでもなったみたいに得意顔で家へやって来られて、母に話して聞かせたので、母は、また興奮して、和子だって書けば書ける文才があるのに、どうしてこうかねえ、いまは昔とちがって、女だからとて家にひっこんでばかりいてはいけない、ひとつ柏木の叔父さんから教わって、書いてみたらいい、柏木の叔父さんは、沢田先生なんかと違って、大学まですすんだ人だから、それは、何と言ったって、たのもしいところがあります、そんなにお金になるんだったら、お父さんだって大目おおめに見てくれますよ、とお台所のあとかたづけをしながら、たいへん意気込んでおっしゃるのです。柏木の叔父さんは、その頃からまた、私の家へ、ほとんど毎日のようにお見えになり、私を勉強室へひっぱって行って、まず日記を書け、見たところ感じたところを、そのまま書いたら、それでもう立派な文学だ、等とおっしゃって、それから何やらむずかしい理窟りくつをいろいろと言い聞かせるのですが、私には、てんで書く気が無かったので、いつも、いい加減に聞き流していました。母は興奮しては、すぐ醒めるたちなので、その時の興奮も、ひとつきくらいつづいて、あとは、けろりとしていましたが、柏木の叔父さんだけは、醒めるどころか、こんどは、いよいよ本気に和子を小説家にしようと決心した、とか真顔でおっしゃって、和子は結局は、小説家になるより他に仕様のない女なのだ、こんなに、へんに頭のいい子は、とても、ふつうのお嫁さんにはなれない、すべてをあきらめて、芸術の道に精進しょうじんするより他は無いんだ等と、父の留守の時には、大声で私と母に言って聞かせるのでした。母も、さすがに、そんなにまで、ひどく言われると、いい気持がしないらしく、そうかねえ、それじゃ和子が可哀想じゃないか、と淋しそうに笑いながら言いました。
叔父さんの言葉が、あたっていたのかも知れません。私はその翌年に女学校を卒業して、つまり、今は、その叔父さんの悪魔のような予言を、死ぬほど強く憎んでいながら、或あるいはそうかも知れぬと心の隅で、こっそり肯定しているところもあるのです。私は、だめな女です。きっと、頭が悪いのです。自分で自分が、わからなくなって来ました。女学校を出たら、急に私は、人が変ってしまいました。私は、毎日毎日、退屈です。家事の手伝いも、花壇の手入れも、お琴の稽古けいこも、弟の世話も、なんでも、みんな馬鹿らしく、父や母にかくれて、こっそり蓮葉な小説ばかり読みふけるようになりました。小説というものは、どうしてこんなに、人の秘密の悪事ばかりを書いているのでしょう。私は、みだらな空想をする、不潔な女になりました。いまこそ私は、いつか叔父さんに教えられたように、私の見た事、感じた事をありのままに書いて神様にお詫びしたいとも思うのですが、私には、その勇気がありません。いいえ、才能が無いのです。それこそ頭に錆さびた鍋なべでも被かぶっているような、とってもやり切れない気持だけです。私には、何も書けません。このごろは、書いてみたいとも思うのです。先日も私は、こっそり筆ならしに、眠り箱という題で、たわいもない或る夜の出来事を手帖に書いて、叔父さんに読んでもらったのでした。すると叔父さんは、それを半分も読まずに手帖を投げ出し、和子、もういい加減に、女流作家はあきらめるのだね、と興醒めた、まじめな顔をして言いました。それからは、叔父さんが、私に、文学というものは特種の才能が無ければ駄目なものだと、苦笑しながら忠告めいた事をおっしゃるようになりました。かえって、いまは父のほうが、好きならやってみてもいいさ、等と気軽に笑って言っているのです。母は時々、金沢ふみ子さんや、それから、他の娘さんでやっぱり一躍有名になったひとの噂を、よそで聞いて来ては興奮して、和子だって、書けば書けるのにねえ、根気こんきが無いからいけません、むかし加賀の千代女が、はじめてお師匠さんのところへ俳句を教わりに行った時、まず、ほととぎすという題で作って見よと言われ、早速さまざま作ってお師匠さんにお見せしたのだが、お師匠さんは、これでよろしいとはおっしゃらなかった、それでね、千代女は一晩ねむらずに考えて、ふと気が附いたら夜が明けていたので、何心なく、ほととぎす、ほととぎすとて明けにけり、と書いてお師匠さんにお見せしたら、千代女でかした! とはじめて褒められたそうじゃないか、何事にも根気が必要です、と言ってお茶を一と口のんで、こんどは低い声で、ほととぎす、ほととぎすとて明けにけり、と呟つぶやき、なるほどねえ、うまく作ったものだ、と自分でひとりで感心して居られます。お母さん、私は千代女ではありません。なんにも書けない低能の文学少女、炬燵こたつにはいって雑誌を読んでいたら眠くなって来たので、炬燵は人間の眠り箱だと思った、という小説を一つ書いてお見せしたら、叔父さんは中途で投げ出してしまいました。私が、あとで読んでみても、なるほど面白くありませんでした。どうしたら、小説が上手になれるだろうか。きのう私は、岩見先生に、こっそり手紙を出しました。七年前の天才少女をお見捨てなく、と書きました。私は、いまに気が狂うのかも知れません。
底本:「太宰治全集4」ちくま文庫、筑摩書房
1988(昭和63)年12月1日第1刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房
1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月
入力:柴田卓治
校正:青木直子
2000年1月28日公開
2005年10月27日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
地図
太宰治
琉球、首里の城の大広間は朱の唐様の燭台にとりつけてある無数の五十匁掛の蝋燭がまばゆい程明るく燃えて昼の様にあかるかつた。
まだ敷いてから間もないと思はれる銀べりの青畳がその光に反射して、しき通るやうな、スガ〳〵しい色合を見せて居た。慶長十九年。内地では豊臣の世が徳川の世と変つて行かうとして居る時であつた。首里の名主といはれて居る謝源は大広間の上座にうちくつろいで座つて居た。謝源のすぐ傍に丞相の郭光はもう大分酩酊したやうにして膝をくづして、ひかへて居た。やゝ下つて多くの家来達がグデングデンに酔つぱらつてガヤ〳〵騒ぎたてて居た。広間の四方の障子はスツカリ取り払はれ、大洋を拭ふて来る海風は無数の蝋燭の焔をユラユラさせながら気持ちよく皆の肌に入つて行くのであつた。十月といつても南国の秋は暑かつた。
謝源は派手な琉球絣の薄ものをたつた一枚身にまとひ、郭光の酌で泡盛の大杯をチビリ、チビリと飲んで居た。謝源は今宵程自分といふものが大きく思はれた時はなかつた。その為か彼は今迄の苦い戦の味もはや忘れてしまつたやうになつて居た。五年の長い歳月を費し、しかも大敗の憂目を見ること三度、やうやうにして首里よりはるか遠くの石垣島を占領したあの苦しみも忘れてしまふ程であつた。
石垣島は可成大きい国であつた。そして兵も十分に強かつた。チヨツとした動機から彼は石垣島征服を思ひ立ち、直ちに大兵を率ゐて石垣島を攻めたのであつた。石垣島の兵はよく戦つた。そして外敵を三度も退りぞけることが出来た。謝源は文字通りの悪戦苦闘を続けた。併し彼は忍耐強かつた。ジリジリ石垣島を攻めたてた。五年の年月を過し、遂に石垣島を陥し入れたのは、つい旬日前のことであつた。首里に凱旋して来た謝源は今夜の宴を開いたのであつた。彼は満足げに大杯を傾けて居た。彼は下座で騒いで居る家来達をズツと見廻した。その時の彼の眼には、もう家来なんぞは虫けらのやうに見えて、しやうがなかつた。フイと首を傾けて外を眺めた。暗い晩であつた。まだ月が出るには間があるのか、たゞまつくらで空と大地との区別すらつかない程であつた。彼はその空を見て居るうちにもう、その空までも自分が征服してしまつたやうな気がした。勝つた者の喜び‼ 彼はそれを十二分に味つて居た。
ジーと暗い空の方を眺めて居た。彼はフト空のスグ低い所に気味の悪い程大きな星がまばたきもせず黙つて輝いて居るのを見た。
「大きい星だナ」彼は何気なくつぶやいた。郭光はその王の独りごとを耳に聞きはさんだ。「どれ、どれ、どこにその星が……」郭光はおかしみたつぷりにそう言つた。謝源はそれを聞いて微笑みながら、だまつてその星のある方を指さした。郭光は「ウム、ななーる程これア大きい星ぢや。何といふ星ぢやらう。うらめしそうに、わしの方を見て居りますナ。王、あれア石垣の、やつらがくやしがつてあの様ににらめて居るので御座らう」ヒヨウキン者の郭光は妙な口調でこういつた。そしてその星に向つて、「ヤイ〳〵いくさに負けて、くやしいだらう」とやゝ高声に変なフシをつけて叫んだ。謝源も、これを聞いた家来の一部のものも、あまりのオカシさに笑ひこけてしまつた。その瞬間その大きな気味の悪い星が不吉を予言するかのやうにスーツと音もなく青白い長い尾を引きながら暗の中に消えてしまつたのは誰も知らなかつたことである。謝源と郭光はそれから一しきり、いくさの手柄話に花を咲かせて居た。
その時一人の家来があはたゞしく王の前に参り「たゞ今二人の蘭人がこれに見えて、王に戦勝の祝の品を持つて来たと申して居ます。いかゞとりはからひませうか」と言つた。謝源はフト郭光との話を止めて上機嫌で「アヽそうか、すぐこれへ」と口ばやに言つた。家来は「承知致しました」と急いで、そこを去つた。
謝源には二人の蘭人とは誰と誰であるかゞわかつて居た。八年前に謝源がこの沖合で難破した蘭人の二人を家来の救ふて来たのを、世話してやつたことがあつた。キツトその蘭人があれから先づ己の国に帰つて又日本に来る途中で自分の戦勝を聞き、取り敢へず祝の品を持つて来たのだらうと思つた。
彼はその蘭人の恩を忘れぬ美しい心が又となく嬉しく思はれた。果してあの蘭人であつた。二人はあれからは大分老いて見えた。丈の高い方はもう頭に白髪が十分まじつて居た。
肥えて居た方はことに衰へて、あのはち切れさうだつた血色のいゝ皮膚が、今はもうタブタブして居て、ガサガサした感じさへ与へて居た。
二人はめいめい先年の絶大な恩を受けたこと、及びこの度の戦勝の祝をくどくどしく申し述べた。謝源は絶えずニコ〳〵してそれを聞いて居た。殊に両人ともまだ琉球のことばを忘れて居ないで、たやすく思ふまゝに言ふことが出来て居たといふことは謝源をムシヤウに嬉しがらせた。謝源は二人の言葉の終るのを待ち遠しそうにして「アヽよし〳〵両人とも大儀であつたナ」と言つた。彼の得意はもうその絶頂に達して居た。異人種から戦勝の祝のことばを述べられる。恐らくそれは日本の内地にでさへもなかつたことだつたらう。
もう五十の齢にも及ばうとして居る謝源も前後を忘れて「アヽ愉快だ‼」と叫びたくなつた程であつた。蘭人はやがて紫の布に包んだ祝の品を恭しく差し出した。郭光はこれを介して謝源に渡した。偉いと言はれてもいくらか原始的な人種である琉球人たる謝源はその品を受け取つてしまつてからは、それを見たくてたまらなかつた。それは長い軸物であつた。一体なんであらうと彼は考へた。南蛮の……兵法……そうでなければ何か新らしい武器の製法……剣術の法……を書いたもの……それとも舶来の絵……いろ〳〵と考へて見た。
もう彼はこらへ切れなくなつて、両人に「オイここで開いて見てもいゝだらうナ」と言つた。勿論両人はそれに対して異存がある筈はなかつた。謝源はその時は全く子供のやうにハシヤギながら、急いでそれを開いて見たのであつた。地図であつた。勿論それは両人に聞いて始めて世界の地図だといふことを知つたのだ。
謝源は全くそれを珍らしがつた。彼はこの地図の中に自分の国も亦今自分の占領した石垣島もあるのだといふことを思ひついた。
そう思ひついた以上は彼はそれがどんな風にこの地図に記入されてあるかを知りたくてしやうがなかつた。謝源はその地図を蘭人に示して「もそつと、前に進んでこれを説明して呉れぬか」と言つた。両人は静かに前に進んで行つた。謝源は地図を下に置いて蘭人の説明を待つた。丈の高い方の蘭人はスラスラ説明をして行つた。「この青い所は海で……このとび色をして居る所が山で御座います。この地図は上の方は北で、下の方は南……」謝源はそんなことはどうでもよかつた。早く自分の領土がどこにあるかを知りたくてたまらなかつた。丈の高い蘭人は尚説明をし続けて行つた。「この北方の大きな国は夜国と申します。夜ばかり続くそうです。そのチヨツと下の大きな所はガルシヤと申します。ズーツとこつちに来ましてこの広い島はメリカンと申します……」謝源は可成失望をしてしまつた。目ぼしい大きい国は皆名さへ聞いたことのないものばかりであつたからだ。それでも彼は細いながらも望みをもつて居た。とうとう「ヨシヨシ。して、わしの領土は一体どこぢや」と聞いてしまつた。謝源はやがて蘭人が指さして呉れる大きな国を想像して居た。蘭人は少しためらつて居た。謝源はせきこんで「ウン一体どこぢや」と言つた。二人の蘭人は互に顔を見合せて何事かうなづき合つて居たが、やがて太つた方の蘭人がさも当惑したやうにして「サア、チヨツト見つかりませんやうです、この地図は大きい国ばかりを書いたものですから、あまり名の知れてない、こまかい国は記入してないかも知れません、現にこれには日本さへあるかなしのやうに、小さく書かれて居ますから……」とモヂモヂしながら言つた。
謝源は「何ツ‼」とたつた一こと低いが併し鋭く叫んだ。それきり呼吸が止つてしまつたやうな気がした。全身の血が一度に血管を破つて体外にほとばしり出たやうな感じがした。眼玉の上がズキンとなにかで、こ突かれたやうな気がした。全身がブルブル震つたことも意識した。彼はその蘭人の為に土足のまゝで鼻柱を挫かれたやうな思ひがした。今の蘭人の言葉は彼にとつては致命的な侮辱であつた。真赤な眼をして凍つたやうになつて、地図を穴のあく程みつめて居た。「名高くない小さい所は記入してないといふのか」彼はヤツとこれだけ言ふことが出来た。そしてキツト二人の蘭人を見つめた。蘭人達はあまりに変つた王の様子にタヾ恐ろしさの為に震つてばかり居た。そして「ハイ日本さへもこのやうに小さく出てるんですから」とやつと青くなりながら言つた。
謝源はもうだまつて居ることが出来なくなつた。そして妙にフラフラになつて「郭光‼ 酒だ‼」といつた。郭光はあまりのことにボンヤリして「ハツ」と答へたが別に酒をついでやらうともしなかつた。「酒だといふに‼」郭光はこの二度目の呼び声にハツと気がつき謝源のグツと差し出した大杯に少しく酒を注いだ。
謝源はガブと一口飲んだ。濁酒の面には蝋燭の焔がチラホラとうつつて居た。実際それは彼にとつては火を飲むやうに苦しかつた。
謝源は「ウーム」とうなつた。ホントに彼は今の所では唸るよりほかに、すべがなかつたのであらう。血ばしつたまなこで蘭人をヂツとにらめつけて居た。大広間の酔ぱらつて居る家来も流石に王のこの様子に気づいたのか急にヒツソリとなつた。殺気に満ちた静けさが長くつゞいた。やゝあつて謝源は何と思つたか丈の高い方の蘭人に彼の大杯をグイツと差しのべて「飲んで見ろ」と言つた。そして郭光に眼でついでやれと言ひつけた。その蘭人はさすがに狼狽した。そして「失礼でございませうが、私は日本の酒は飲めないんで……」と言つて、「イヒヽヽヽ」と追従笑ひをした。実際蘭人達は日本酒、殊にアルコール分の強い泡盛は飲めなかつたのである。
謝源はカツとなつた。さつきのことばと言へ、今の笑ひ声と言ひ明らかに自分を侮辱してると彼は一途に思ひつめた。「わしのやうな小国の王の杯は受けぬと言ふのか、恩知らず奴ツ」彼はこう叫ぶやいなや、その大杯を丈の高い蘭人の額にハツシとぶつけた。彼は何もかもわからなくなつた。傍にあつた刀をとり上げて鞘を払つた。立ち上つた。刀をめちやくちやに振り廻した。蘭人二人の首は飛んだ。これらのことは皆同時になつて表はれたと、いつてもいゝ程であつた。やゝあつて謝源はニヨツキリとつつ立つたまゝ「恩知らずツ馬鹿ツたわけめツ」とあらゆる罵声を首のない二人の死骸にあびせかけて居た。もう酒宴どころの騒ぎではなかつた。家来はたゞあはて、ふためいて居るばかりであつた。やゝあつて謝源の心は少しく落ちついて来た。彼は力なげに外をながめた。
月が出たのかそれらは一面に白くあかるかつた。夜露にしめつた秋草の葉は月の光で青白くキラキラ光つて居た。
虫の声さへ聞えて居た。
謝源はもうシツカリ自暴自棄に陥つて居た。
地図にさへ出てない小さな島を五年もかゝつて、やつと占領した自分の力のふがひなさにはもう呆れ返つて居た。謝源は人が自分の力に全く愛想をつかした時程淋しいことはあるものでないと考へた。彼は男泣きに大声をあげて泣いてしまひたかつた。波の音がかすかにザザザと聞えて居た。裏の甘蔗畑が月に照らされて一枚一枚の甘蔗の葉影も鮮やかに数へることが出来た。そして謝源にはその青白い色をして居る畑が自分を冷笑して居るやうにも見えた。若しこの時謝源が空を見上げたならば、もう一つの気味の悪い大きな星が彼の丁度頭の上で、さつきと同じやうに長い尾を引いて流れたのを見たことであつたらう。
彼は長い間ボンヤリ立つて居た……
謝源の乱行は日増に甚だしくなつて行つた。
飲酒、邪淫、殺生その他犯さぬ悪さとてなかつた。この時に於ける郭光の切腹して果てたことも謝源の心に何の反省も与へては呉れなかつた。
中にも土民狩と言つて人民を小鳥か何かのやうに取扱ひ弓等で射殺し、今日は獲物が不足だつたとか、多かつたとかで喜んで居たりしたことは鬼と言つてもまだ言ひ足りない気がする位である。人民の呪詛もひどかつた。
一人として王を恐れ且つ憎まぬ者はないやうになつた。そして人民は皆「王が石垣島を占領した功に誇り、慢心を起し遂にこんなになつてしまつたのだ」と口々に言つて居た。
若し謝源がこれを聞いたならキツと心からの苦笑を洩らしてしまふにちがひない。
こんなフウだつたからそれから一年もたゝぬ中に石垣島のもとの兵に首里が襲はれて易々と復讐されたのは言ふまでもないことである。併し謝源は少しも残念がる様子もなく或夜コツソリと一そうの小舟で首里からのがれて行つた。どこに行つたか一人も知つて居るものがなかつた。
たゞ数ヶ月の後、石垣島の王のやしきの隅にその頃日本では、なかなか得ることの出来なかつた世界の地図が落ちてあるのを家来の一人が発見した。誰がどんな理由で持つて来てここのやしきの中に投げこんで行つたのか無論わからなかつた。そしてその地図の所々に薄い血痕のやうなものが付いて居た。石垣島の王はそれを、たいへん珍らしがつて保存して置いたことであらう。
底本:「日本の名随筆 別巻46 地図」堀淳一編、作品社
1994(平成6)年12月25日第1刷発行
底本の親本:「太宰治全集 第一二巻」筑摩書房
1977(昭和52)年11月
※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5-86)を、大振りにつくっています。
入力:ブラン
校正:土屋隆
2003年12月14日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
大恩は語らず
太宰治