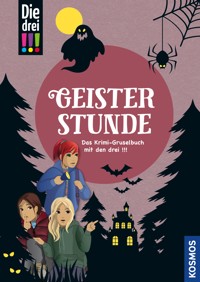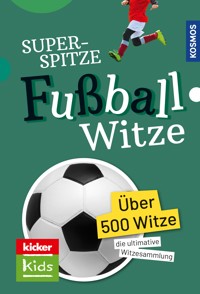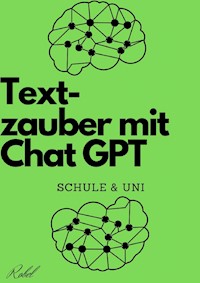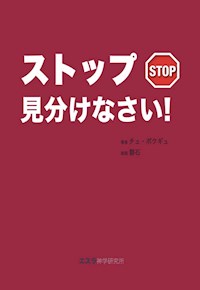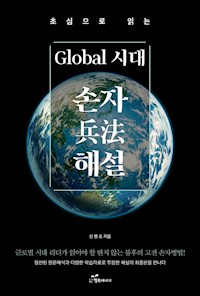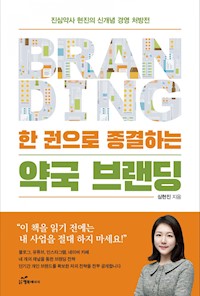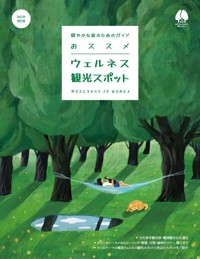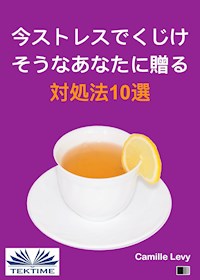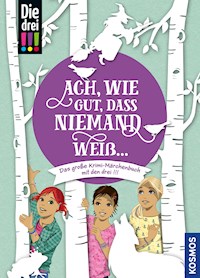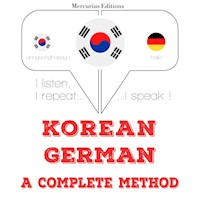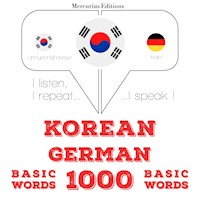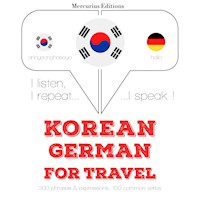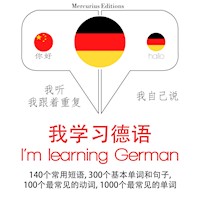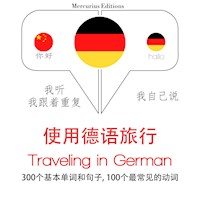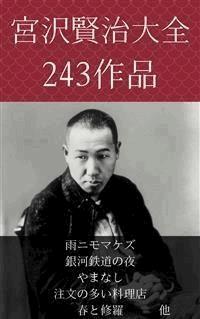
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: micpub.com
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: ja
最新の宮沢賢治の作品を集めた大全です。 宮沢賢治の代表作である雨ニモマケズ、銀河鉄道の夜、やまなし、注文の多い料理店、春と修羅を始めとして、彼の小説、詩集、論文などを全て掲載しています。 宮沢賢治の世界をご堪能ください。 「宮沢賢治は、日本の詩人、童話作家。 仏教信仰と農民生活に根ざした創作を行った。作品中に登場する架空の理想郷に、郷里の岩手県をモチーフとしてイーハトーブと名付けたことで知られる。彼の作品は生前ほとんど一般には知られず無名に近く、没後、草野心平らの尽力により作品群が広く知られ、世評が急速に高まり国民的作家となっていった。そうした経緯もあって日本には広く愛好者がおり、出身地である岩手県花巻市は彼の故郷として有名である。」 (Wikipediaより抜粋) <掲載作品一覧> あけがた 秋田街道 〔あくたうかべる朝の水〕 〔雨ニモマケズ〕 〔青びかる天弧のはてに〕 青柳教諭を送る ありときのこ 或る農学生の日誌 朝に就ての童話的構図 化物丁場 バキチの仕事 茨海小学校 葡萄水 文語詩稿 一百篇 文語詩稿 五十篇 病中幻想 『注文の多い料理店』広告文 注文の多い料理店 『注文の多い料理店』序 『注文の多い料理店』新刊案内 中尊寺〔二〕 台川 田園迷信 電車 毒蛾 毒もみのすきな署長さん どんぐりと山猫 駅長 不軽菩薩 〔二川こゝにて会したり〕 双子の星 二人の役人 ガドルフの百合 学者アラムハラドの見た着物 月天讃歌(擬古調) 〔月光の鉛のなかに〕 幻想 疑獄元兇 銀河鐵道の夜 〔郡属伊原忠右エ門〕 グスコーブドリの伝記 八戸 凾館港春夜光景 雹雲砲手 花巻農学校精神歌 花椰菜 『春と修羅』 春と修羅 第二集 春と修羅 第三集 『春と修羅』補遺 畑のへり 〔廿日月かざす刃は音無しの〕 林の底 隼人 ひかりの素足 〔卑屈の友らをいきどほろしく〕 秘境 ひのきとひなげし 火の島 〔ひとひははかなくことばをくだし〕 火渡り 北守将軍と三人兄弟の医者 洞熊学校を卒業した三人 星めぐりの歌 フランドン農学校の豚 氷河鼠の毛皮 いちょうの実 イギリス海岸 イーハトーボ農学校の春 インドラの網 〔いざ渡せかし おいぼれめ〕 泉ある家 樹園 十月の末 十六日 十月の末 家長制度 花壇工作 蛙のゴム靴 会計課 開墾 開墾地 貝の火 カイロ団長 〔かくまでに〕 釜石よりの帰り 看痾 〔甘藍の球は弾けて〕 烏の北斗七星 烏百態 雁の童子 かしわばやしの夜 革トランク 風の又三郎 県道 虔十公園林 饑餓陣営 黄いろのトマト 機会 気のいい火山弾 講後 恋 こゝろ 〔こゝろの影を恐るなと〕 国柱会 〔こんにやくの〕 〔このみちの醸すがごとく〕 氷と後光 〔洪積の台のはてなる〕 校庭 耕耘部の時計 〔こはドロミット洞窟の〕 〔雲ふかく 山裳を曳けば〕 〔くもにつらなるでこぼこがらす〕 〔雲を濾し〕 蜘蛛となめくじと狸 訓導 クねずみ 黒ぶだう 車 饗宴 マグノリアの木 〔まひるつとめにまぎらひて〕 マリヴロンと少女 まなづるとダァリヤ 〔ま青きそらの風をふるはし〕 祭の晩 めくらぶどうと虹 みじかい木ぺん 〔最も親しき友らにさへこれを秘して〕 〔モザイク成り〕 〔なべてはしけく よそほひて〕 〔ながれたり〕 〔鉛のいろの冬海の〕 なめとこ山の熊 楢ノ木大学士の野宿 猫 猫の事務所 虹の絵具皿 二十六夜 農学校歌 農民芸術の興隆 農民芸術概論 農民芸術概論綱要 沼森 狼森と笊森、盗森 丘 おきなぐさ 女 オツベルと象 ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記 ペンネンノルデはいまはいないよ 太陽にできた黒い棘をとりに行ったよ ポラーノの広場 ラジュウムの雁 〔昤々としてひかれるは〕 〔りんごのみきのはひのひかり〕 龍と詩人 サガレンと八月 〔鷺はひかりのそらに餓ゑ〕 祭日〔二〕 さいかち淵 山地の稜 さるのこしかけ 〔聖なる窓〕 製炭小屋 雪峡 〔せなうち痛み息熱く〕 セレナーデ 恋歌 セロ弾きのゴーシュ 疾中 四八 黄泉路 紫紺染について 〔島わにあらき潮騒を〕 〔霧降る萱の細みちに〕 〔霜枯れのトマトの気根〕 鹿踊りのはじまり 詩ノート 植物医師 職員室 小祠 春章作中判 〔棕梠の葉やゝに痙攣し〕 シグナルとシグナレス 僧園 〔そのかたち収得に似て〕 〔蒼冷と純黒〕 宗谷〔一〕 宗谷〔二〕 スタンレー探検隊に対する二人のコンゴー土人の演説 水部の線 水仙月の四日 隅田川 〔たゞかたくなのみをわぶる〕 大礼服の例外的効果 対酌 宅地 丹藤川〔「家長制度」先駆形〕 タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった 種山ヶ原 谷 手紙 一 手紙 二 手紙 三 手紙 四 とっこべとら子 床屋 鳥箱先生とフウねずみ 鳥をとるやなぎ 圖書館幻想 土神ときつね 〔土をも掘らん汗もせん〕 ツェねずみ 月夜のでんしんばしらの軍歌 月夜のけだもの 〔つめたき朝の真鍮に〕 チュウリップの幻術 〔馬行き人行き自転車行きて〕 うろこ雲 ビジテリアン大祭 若い木霊 〔われ聴衆に会釈して〕 〔われらが書に順ひて〕 〔われらひとしく丘に立ち〕 〔われはダルケを名乗れるものと〕 〔われかのひとをこととふに〕 敗れし少年の歌へる 〔館は台地のはななれば〕 やまなし 山男の四月 柳沢 よだかの星 よく利く薬とえらい薬 四又の百合 楊林 遊園地工作 〔ゆがみつゝ月は出で〕 〔夕陽は青めりかの山裾に〕 〔雪とひのきの坂上に〕 雪渡り 〔弓のごとく〕 百合を掘る ざしき童子のはなし 税務署長の冒険
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Guide
表紙
目次
扉
本文
目 次
あけがた
秋田街道
〔あくたうかべる朝の水〕
〔雨ニモマケズ〕
〔青びかる天弧のはてに〕
青柳教諭を送る
ありときのこ
或る農学生の日誌
朝に就ての童話的構図
化物丁場
バキチの仕事
茨海小学校
葡萄水
文語詩稿 一百篇
文語詩稿 五十篇
病中幻想
『注文の多い料理店』広告文
注文の多い料理店
『注文の多い料理店』序
『注文の多い料理店』新刊案内
中尊寺〔二〕
台川
田園迷信
電車
毒蛾
毒もみのすきな署長さん
どんぐりと山猫
駅長
不軽菩薩
〔二川こゝにて会したり〕
双子の星
二人の役人
ガドルフの百合
学者アラムハラドの見た着物
月天讃歌(擬古調)
〔月光の鉛のなかに〕
幻想
疑獄元兇
銀河鐵道の夜
〔郡属伊原忠右エ門〕
グスコーブドリの伝記
八戸
凾館港春夜光景
雹雲砲手
花巻農学校精神歌
花椰菜
『春と修羅』
春と修羅 第二集
春と修羅 第三集
『春と修羅』補遺
畑のへり
〔廿日月かざす刃は音無しの〕
林の底
隼人
ひかりの素足
〔卑屈の友らをいきどほろしく〕
秘境
ひのきとひなげし
火の島
〔ひとひははかなくことばをくだし〕
火渡り
北守将軍と三人兄弟の医者
洞熊学校を卒業した三人
星めぐりの歌
フランドン農学校の豚
氷河鼠の毛皮
いちょうの実
イギリス海岸
イーハトーボ農学校の春
インドラの網
〔いざ渡せかし おいぼれめ〕
泉ある家
樹園
十月の末
十六日
十月の末
家長制度
花壇工作
蛙のゴム靴
会計課
開墾
開墾地
貝の火
カイロ団長
〔かくまでに〕
釜石よりの帰り
看痾
〔甘藍の球は弾けて〕
烏の北斗七星
烏百態
雁の童子
かしわばやしの夜
革トランク
風の又三郎
県道
虔十公園林
饑餓陣営
黄いろのトマト
機会
気のいい火山弾
講後
恋
こゝろ
〔こゝろの影を恐るなと〕
国柱会
〔こんにやくの〕
〔このみちの醸すがごとく〕
氷と後光
〔洪積の台のはてなる〕
校庭
耕耘部の時計
〔こはドロミット洞窟の〕
〔雲ふかく 山裳を曳けば〕
〔くもにつらなるでこぼこがらす〕
〔雲を濾し〕
蜘蛛となめくじと狸
訓導
クねずみ
黒ぶだう
車
饗宴
マグノリアの木
〔まひるつとめにまぎらひて〕
マリヴロンと少女
まなづるとダァリヤ
〔ま青きそらの風をふるはし〕
祭の晩
めくらぶどうと虹
みじかい木ぺん
〔最も親しき友らにさへこれを秘して〕
〔モザイク成り〕
〔なべてはしけく よそほひて〕
〔ながれたり〕
〔鉛のいろの冬海の〕
なめとこ山の熊
楢ノ木大学士の野宿
猫
猫の事務所
虹の絵具皿
二十六夜
農学校歌
農民芸術の興隆
農民芸術概論
農民芸術概論綱要
沼森
狼森と笊森、盗森
丘
おきなぐさ
女
オツベルと象
ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記
ペンネンノルデはいまはいないよ 太陽にできた黒い棘をとりに行ったよ
ポラーノの広場
ラジュウムの雁
〔昤々としてひかれるは〕
〔りんごのみきのはひのひかり〕
龍と詩人
サガレンと八月
〔鷺はひかりのそらに餓ゑ〕
祭日〔二〕
さいかち淵
山地の稜
さるのこしかけ
〔聖なる窓〕
製炭小屋
雪峡
〔せなうち痛み息熱く〕
セレナーデ 恋歌
セロ弾きのゴーシュ
疾中
四八 黄泉路
紫紺染について
〔島わにあらき潮騒を〕
〔霧降る萱の細みちに〕
〔霜枯れのトマトの気根〕
鹿踊りのはじまり
詩ノート
植物医師
職員室
小祠
春章作中判
〔棕梠の葉やゝに痙攣し〕
シグナルとシグナレス
僧園
〔そのかたち収得に似て〕
〔蒼冷と純黒〕
宗谷〔一〕
宗谷〔二〕
スタンレー探検隊に対する二人のコンゴー土人の演説
水部の線
水仙月の四日
隅田川
〔たゞかたくなのみをわぶる〕
大礼服の例外的効果
対酌
宅地
丹藤川〔「家長制度」先駆形〕
タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった
種山ヶ原
谷
手紙 一
手紙 二
手紙 三
手紙 四
とっこべとら子
床屋
鳥箱先生とフウねずみ
鳥をとるやなぎ
圖書館幻想
土神ときつね
〔土をも掘らん汗もせん〕
ツェねずみ
月夜のでんしんばしらの軍歌
月夜のけだもの
〔つめたき朝の真鍮に〕
チュウリップの幻術
〔馬行き人行き自転車行きて〕
うろこ雲
ビジテリアン大祭
若い木霊
〔われ聴衆に会釈して〕
〔われらが書に順ひて〕
〔われらひとしく丘に立ち〕
〔われはダルケを名乗れるものと〕
〔われかのひとをこととふに〕
敗れし少年の歌へる
〔館は台地のはななれば〕
やまなし
山男の四月
柳沢
よだかの星
よく利く薬とえらい薬
四又の百合
楊林
遊園地工作
〔ゆがみつゝ月は出で〕
〔夕陽は青めりかの山裾に〕
〔雪とひのきの坂上に〕
雪渡り
〔弓のごとく〕
百合を掘る
ざしき童子のはなし
税務署長の冒険
あけがた
宮沢賢治
おれはその時その青黒く淀んだ室の中の堅い灰色の自分の席にそわそわ立ったり座ったりしてゐた。
二人の男がその室の中に居た。一人はたしかに獣医の有本でも一人はさまざまのやつらのもやもやした区分キメラであった。
おれはどこかへ出て行かうと考へてゐるらしかった。飛ぶんだぞ霧の中をきいっとふっとんでやるんだなどと頭の奥で叫んでゐた。ところがその二人がしきりに着物のはなしをした。
おれはひどくむしゃくしゃした。そして卓をガタガタゆすってゐた。
いきなり霧積が入って来た。霧積は変に白くぴかぴかする金襴の羽織を着てゐた。そしてひどく嬉しさうに見えた。今朝は支那版画展覧会があって自分はその幹事になってゐるからそっちへ行くんだと云ってかなり大声で笑った。おれはそれがしゃくにさわった。第一霧積は今日はおれと北の方の野原へ出かける約束だったのだ、それを白っぽい金襴の羽織などを着込んでわけもわからない処へ行ってけらけら笑ったりしやうといふのはあんまり失敬だと おれは考へた。
ところが霧積はどう云ふわけか急におれの着物を笑ひ出した。有本も笑った。区分キメラもつめたくあざ笑った。なんだ着物のことなどか きさまらは男だらう それに本気で着もののことを云ふのか、などとおれはそっと考へて見たがどうも気持が悪かった。それから今度は有本が何かもにやもにや云っておれを慰めるやうにした。
おれにはどういふわけで自分に着物が斯う足りないのかどう考へても判らなくてひどく悲しかった。そこでおれは立ちあがって云〔っ〕た。
「あたりまへさ。おれなんぞまだ着物など三つも四つもためられる訳はないんだ。おれはこれで沢山だ。」有本や霧積は何か眩しく光る絵巻か角帯らしいものをひろげて引っぱってしゃべってゐた。おれはぷいと外へ出た。そしていきなり川ばたの白い四角な家に入った。知らない赤い女が髪もよく削らずに立ってゐた。そしていきなり
「お履物はこちらへまはしましたから。」と云っておれの革スリッパを変な裏口のやうな土間に投げ出した。おれは「ふん」と云ひながらそっちへ行った。それでも気分はよかった。
片っ方のスリッパが裏返しになってゐた。その女が手を延ばして直す風をした。おれはこんな赤いすれっからしが本統にそれを直すかどうかと考へながら黙ってそれを見てゐた。
女は本統にスリッパを直した。おれは外へ出た。
川が烈しく鳴ってゐる。一月十五日の村の踊りの太鼓が向岸から強くひゞいて来る。強い透明な太鼓の音だ。
川はあんまり冷たく物凄かった。おれは少し上流にのぼって行った。そこの所で川はまるで白と水色とぼろぼろになって崩れ落ちてゐた。そして殊更空の光が白く冷たかった。
(おれは全体川をきらひだ。)おれはかなり高い声で云った。
ひどい洪水の後らしかった。もう水は澄んでゐた。それでも非常な水勢なのだ。波と波とが激しく拍って青くぎらぎらした。
支流が北から落ちてゐた。おれはだまってその岸について溯った。
空がツンツンと光ってゐる。水はごうごうと鳴ってゐた。おれはかなしかった。それから口笛を吹いた。口笛は向ふの方に行ってだんだん広く大きくなってしまひには手もつけられないやうにひろがった。
そして向ふに大きな島が見えた。それはいつかの洪水でできてからもう余程の年を経たらしく高さも百尺はあった。栗や雑木が一杯にしげってゐた。
おれはそっちへ行かうと思った。
そしていつかもう島の上に立ってゐた。どうして川を渡ったらう、私は考へながらさびしくふり返った。
たしかにそれは水が切れて小さなぴちゃぴちゃの瀬になってゐたのだ。
おれは青白く光る空を見た。洪水がいつまた黒い壁のやうになって襲って来るかわからないと考へた。小さな子供のいきなりながされる模様を想像した。それから西の山脈を見た。それは碧くなめらかに光ってゐた。あんな明るいところで今雨の降ってゐるわけはない、おれは考へた。
そらにひろがる高い雑木の梢を見た、あすこまで昇ればまづ大低の洪水なら大丈夫だ、そのうちにきっと弟が助けに来る、けれどもどうして助けるのかなとおれは考へた。
いつか島が又もとの岸とくっついてゐた。その手前はうららかな孔雀石の馬蹄形の淵になってゐた。おれは立ちどまった。そして又口笛を吹いた。そして雑木の幹に白いきのこを見た。まっしろなさるのこしかけを見た。
それから志木、大高と彫られた白い二列の文字を見た。
瘠せてオーバアコートを着てわらじを穿いた男が青光りのさるとりいばらの中にまっすぐに立ってゐた。
「私は志木です。こゝの測量に着手したのは私であります。」帽子をとっていやに堅苦しくその男が云った。志木、志木とはてな、どこかで聞いたぞとおれは思った。
底本:「【新】校本宮澤賢治全集 第十二巻 童話5・劇・その他 本文篇」筑摩書房
1995(平成7)年11月25日初版第1刷発行
※底本の本文は、草稿による。
※本文中〔〕で括られた部分は、底本の編者により校訂された箇所である。
(例)云〔っ〕た。
入力:砂場清隆
校正:noriko saito
2008年8月25日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
秋田街道
宮沢賢治
どれもみんな肥料や薪炭をやりとりするさびしい家だ。街道のところどころにちらばって黒い小さいさびしい家だ。それももうみな戸を閉めた。
おれはかなしく来た方をふりかへる。盛岡もりをかの電燈は微かすかにゆらいでねむさうにならび只ただ公園のアーク燈だけ高い処ところでそらぞらしい気焔きえんの波を上げてゐる。どうせ今頃いまごろは無鉄砲な羽虫が沢山集ってぶっつかったりよろけたりしてゐるのだ。
私はふと空いっぱいの灰色はがねに大きな床屋のだんだら棒、あのオランダ伝来の葱ねぎの蕾つぼみの形をした店飾りを見る。これも随分たよりないことだ。
道が小さな橋にかゝる。螢ほたるがプイと飛んで行く。誰たれかがうしろで手をあげて大きくためいきをついた。それも間違ひかわからない。とにかくそらが少し明るくなった。夜明けにはまだ途方もないしきっと雲が薄くなって月の光が透とほって来るのだ。
向ふの方は小岩井農場だ。
四っ角山にみんなぺたぺた一緒に座る。
月見草が幻よりは少し明るくその辺一面浮んで咲いてゐる。マッチがパッとすられ莨たばこの青いけむりがほのかにながれる。
右手に山がまっくろにうかび出した。その山に何の鳥だか沢山とまって睡ねむってゐるらしい。
並木は松になりみんなは何かを云いひ争ふ。そんならお前さんはこゝらでいきなり頭を撲なぐりつけられて殺されてもいゝな。誰かが云ふ。それはいゝ。いゝと思ふ。睡さうに誰かが答へる。
道が悪いので野原を歩く。野原の中の黒い水潦みづたまりに何べんもみんな踏み込んだ。けれどもやがて月が頭の上に出て月見草の花がほのかな夢をたゞよはしフィーマスの土の水たまりにも象牙ざうげ細工の紫がかった月がうつりどこかで小さな羽虫がふるふ。
けれども今は崇高な月光のなかに何かよそよそしいものが漂ひはじめた。その成分こそはたしかによあけの白光らしい。
東がまばゆく白くなった。月は少しく興さめて緑の松の梢こずゑに高くかかる。
みんなは七つ森の機嫌きげんの悪い暁の脚まで来た。道が俄にはかに青々と曲る。その曲り角におれはまた空にうかぶ巨おほきな草穂くさぼを見るのだ。カアキイ色の一人の兵隊がいきなり向ふにあらはれて青い茂みの中にこゞむ。さうだ。あそこに湧水わきみづがあるのだ。
雲が光って山山に垂れ冷たい奇麗な朝になった。長い長い雫石しづくいしの宿に来た。犬が沢山吠ほえ出した。けれどもみんなお互に争ってゐるのらしい。
葛根田かっこんだ川の河原におりて行く。すぎなに露が一ぱいに置き美しくひらめいてゐる。新鮮な朝のすぎなに。
いつかみんな睡ねむってゐたのだ。河本さんだけ起きてゐる。冷たい水を渉わたってゐる。変に青く堅さうなからだをはだかになって体操をやってゐる。
睡ってゐる人の枕まくらもとに大きな石をどしりどしりと投げつける。安山岩の柱状節理、安山岩の板状節理。水に落ちてはつめたい波を立てうつろな音をあげ、目を覚ました、目を覚ました。低い銀の雲の下で愕おどろいてよろよろしてゐる。それから怒ってゐる。今度はにがわらひをしてゐる。銀色の雲の下。
帰りみち、ひでり雨が降りまたかゞやかに霽はれる。そのかゞやく雲の原
今日こそ飛んであの雲を踏め。
けれどもいつか私は道に置きすてられた荷馬車の上に洋傘かうもりがさを開いて立ってゐるのだ。
ひどい怒鳴り声がする。たしかに荷馬車の持ち主だ。怒りたけって走って来る。そのほっペたが腐って黒いすもものやう、いまにも穴が明きさうだ。癩病らいびゃうにちがひない。さびしいことだ。
虹にじがたってゐる。虹の脚にも月見草が咲き又こゝらにもそのバタの花。一つぶ二つぶひでりあめがきらめき、去年の堅い褐色かっしょくのすがれに落ちる。
すっかり晴れて暑くなった。雫石しづくいし川の石垣いしがきは烈はげしい草のいきれの中にぐらりぐらりとゆらいでゐる。その中でうとうとする。
遠くの楊やなぎの中の白雲でくわくこうが啼ないた。
「あの鳥はゆふべ一晩なき通しだな。」
「うんうん鳴いてゐた。」誰たれかが云ってゐる。
底本:「新修宮沢賢治全集 第十四巻」筑摩書房
1980(昭和55)年5月15日初版第1刷発行
1983(昭和58)年1月20日初版第4刷発行
※本作品中には、身体的・精神的資質、職業、地域、階層、民族などに関する不適切な表現が見られます。しかし、作品の時代背景と価値、加えて、作者の抱えた限界を読者自身が認識することの意義を考慮し、底本のままとしました。(青空文庫)
入力:林 幸雄
校正:mayu
2003年1月10日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
〔あくたうかべる朝の水〕
宮沢賢治
あくたうかべる朝の水
ひらととびかふつばくらめ
苗のはこびの遅ければ
熊ははぎしり雲を見る
苗つけ馬を引ききたり
露のすぎなの畔に立ち
権は朱塗の盃を
ましろきそらにあふぐなり
底本:「新修宮沢賢治全集 第六巻」筑摩書房
1980(昭和55)年2月15日初版第1刷発行
※〔〕付きの表題は、底本編集時におぎなわれたものです。
入力:junk
校正:土屋隆
2011年5月14日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
〔雨ニモマケズ〕
宮澤賢治
雨ニモマケズ
風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク
決シテ瞋ラズ
イツモシヅカニワラッテヰル
一日ニ玄米四合ト
味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ
ソシテワスレズ
野原ノ松ノ林ノ䕃ノ
小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ
東ニ病気ノコドモアレバ
行ッテ看病シテヤリ
西ニツカレタ母アレバ
行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ
南ニ死ニサウナ人アレバ
行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ
北ニケンクヮヤソショウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイヒ
ヒドリノトキハナミダヲナガシ
サムサノナツハオロオロアルキ
ミンナニデクノボートヨバレ
ホメラレモセズ
クニモサレズ
サウイフモノニ
ワタシハナリタイ
南無無辺行菩薩
南無上行菩薩
南無多宝如来
南無妙法蓮華経
南無釈迦牟尼仏
南無浄行菩薩
南無安立行菩薩
底本:「【新】校本宮澤賢治全集 第十三巻(上)覚書・手帳 本文篇」筑摩書房
1997(平成9)年7月30日初版第1刷発行
※本文については写真版を含む本書によった。また、改行等の全体の体裁については、「【新】校本宮澤賢治全集 第六巻」筑摩書房1996(平成8)年5月30日初版第1刷発行を参照した。
入力:田中敬三
校正:土屋隆
2006年7月26日作成
2011年4月27日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
〔青びかる天弧のはてに〕
宮沢賢治
青びかる天弧のはてに
きらゝかに町はうかびて
六月のたつきのみちは
いまやはた尽きはてにけり
いさゝかの書籍とセロを
思ふまゝ〔以下空白〕
底本:「新修宮沢賢治全集 第六巻」筑摩書房
1980(昭和55)年2月15日初版第1刷発行
※〔〕付きの表題は、底本編集時におぎなわれたものです。
※「〔以下空白〕」は、底本編集時の注記です。
入力:junk
校正:土屋隆
2011年5月14日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
青柳教諭を送る
宮沢賢治
瘠せて青めるなが頬は
九月の雨に聖くして
一すぢ遠きこのみちを
草穂のけぶりはてもなし
底本:「新修宮沢賢治全集 第六巻」筑摩書房
1980(昭和55)年2月15日初版第1刷発行
入力:junk
校正:土屋隆
2011年5月14日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
ありときのこ
宮沢賢治
苔こけいちめんに、霧きりがぽしゃぽしゃ降ふって、蟻ありの歩哨ほしょうは鉄てつの帽子ぼうしのひさしの下から、するどいひとみであたりをにらみ、青く大きな羊歯しだの森の前をあちこち行ったり来たりしています。
向むこうからぷるぷるぷるぷる一ぴきの蟻ありの兵隊へいたいが走って来ます。
「停とまれ、誰だれかッ」
「第だい百二十八聯隊れんたいの伝令でんれい!」
「どこへ行くか」
「第五十聯隊 聯隊本部ほんぶ」
歩哨はスナイドル式しきの銃剣じゅうけんを、向むこうの胸むねに斜ななめにつきつけたまま、その眼めの光りようや顎あごのかたち、それから上着うわぎの袖そでの模様もようや靴くつのぐあい、いちいち詳くわしく調しらべます。
「よし、通れ」
伝令はいそがしく羊歯しだの森のなかへはいって行きました。
霧きりの粒つぶはだんだん小さく小さくなって、いまはもう、うすい乳ちちいろのけむりに変かわり、草や木の水を吸すいあげる音は、あっちにもこっちにも忙いそがしく聞こえだしました。さすがの歩哨もとうとうねむさにふらっとします。
二疋ひきの蟻ありの子供こどもらが、手をひいて、何かひどく笑わらいながらやって来ました。そしてにわかに向むこうの楢ならの木の下を見てびっくりして立ちどまります。
「あっ、あれなんだろう。あんなところにまっ白な家ができた」
「家じゃない山だ」
「昨日はなかったぞ」
「兵隊へいたいさんにきいてみよう」
「よし」
二疋の蟻は走ります。
「兵隊さん、あすこにあるのなに?」
「なんだうるさい、帰れ」
「兵隊さん、いねむりしてんだい。あすこにあるのなに?」
「うるさいなあ、どれだい、おや!」
「昨日はあんなものなかったよ」
「おい、大変たいへんだ。おい。おまえたちはこどもだけれども、こういうときには立派りっぱにみんなのお役やくにたつだろうなあ。いいか。おまえはね、この森をはいって行ってアルキル中佐ちゅうさどのにお目にかかる。それからおまえはうんと走って陸地測量部りくちそくりょうぶまで行くんだ。そして二人ともこう言いうんだ。北緯ほくい二十五度ど東経とうけい六厘りんの処ところに、目的もくてきのわからない大きな工事こうじができましたとな。二人とも言ってごらん」
「北緯ほくい二十五度ど東経とうけい六厘りんの処ところに目的もくてきのわからない大きな工事こうじができました」
「そうだ。では早く。そのうち私は決けっしてここを離はなれないから」
蟻ありの子供こどもらはいちもくさんにかけて行きます。
歩哨ほしょうは剣をかまえて、じっとそのまっしろな太い柱はしらの、大きな屋根やねのある工事をにらみつけています。
それはだんだん大きくなるようです。だいいち輪廓りんかくのぼんやり白く光ってぶるぶるぶるぶるふるえていることでもわかります。
にわかにぱっと暗くらくなり、そこらの苔こけはぐらぐらゆれ、蟻ありの歩哨ほしょうは夢中むちゅうで頭をかかえました。眼めをひらいてまた見ますと、あのまっ白な建物たてものは、柱が折おれてすっかり引っくり返かえっています。
蟻の子供らが両方りょうほうから帰ってきました。
「兵隊へいたいさん。かまわないそうだよ。あれはきのこというものだって。なんでもないって。アルキル中佐ちゅうさはうんと笑わらったよ。それからぼくをほめたよ」
「あのね、すぐなくなるって。地図に入れなくてもいいって。あんなもの地図に入れたり消けしたりしていたら、陸地測量部りくちそくりょうぶなど百あっても足りないって。おや! 引っくりかえってらあ」
「たったいま倒たおれたんだ」歩哨は少しきまり悪わるそうに言いいました。
「なあんだ。あっ。あんなやつも出て来たぞ」
向むこうに魚の骨ほねの形をした灰はいいろのおかしなきのこが、とぼけたように光りながら、枝えだがついたり手が出たりだんだん地面じめんからのびあがってきます。二疋ひきの蟻ありの子供らは、それを指ゆびさして、笑わらって笑って笑います。
そのとき霧きりの向むこうから、大きな赤い日がのぼり、羊歯しだもすぎごけもにわかにぱっと青くなり、蟻の歩哨ほしょうは、またいかめしくスナイドル式銃剣しきじゅうけんを南の方へ構かまえました。
底本:「セロ弾きのゴーシュ」角川文庫、角川書店
1957(昭和32)年11月15日初版発行
1967(昭和42)年4月5日10版発行
1993(平成5)年5月20日改版50版発行
初出:「天才人」
1933(昭和8)年3月号
※初出時の表題は「朝に就ての童話的構図」。
入力:土屋隆
校正:砂場清隆
2007年1月6日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
或る農学生の日誌
宮沢賢治
序
ぼくは農のう学校の三年生になったときから今日まで三年の間のぼくの日誌にっしを公開こうかいする。どうせぼくは字も文章ぶんしょうも下手へただ。ぼくと同じように本気に仕事しごとにかかった人でなかったらこんなもの実じつに厭いやな面白おもしろくもないものにちがいない。いまぼくが読み返かえしてみてさえ実に意気地いくじなく野蛮やばんなような気のするところがたくさんあるのだ。ちょうど小学校の読本の村のことを書いたところのようにじつにうそらしくてわざとらしくていやなところがあるのだ。けれどもぼくのはほんとうだから仕方しかたない。ぼくらは空想くうそうでならどんなことでもすることができる。けれどもほんとうの仕事はみんなこんなにじみなのだ。そしてその仕事をまじめにしているともう考えることも考えることもみんなじみな、そうだ、じみというよりはやぼな所謂いわゆる田舎臭いなかくさいものに変かわってしまう。
ぼくはひがんで云いうのでない。けれどもぼくが父とふたりでいろいろな仕事のことを云いながらはたらいているところを読んだら、ぼくを軽けいべつする人がきっと沢山たくさんあるだろう。そんなやつをぼくは叩たたきつけてやりたい。ぼくは人を軽べつするかそうでなければ妬ねたむことしかできないやつらはいちばん卑怯ひきょうなものだと思う。ぼくのように働はたらいている仲間なかまよ、仲間よ、ぼくたちはこんな卑怯さを世界せかいから無なくしてしまおうでないか。
一九二五、四月一日 火曜日 晴
今日から新らしい一学期がっきだ。けれども学校へ行っても何だか張合はりあいがなかった。一年生はまだはいらないし三年生は居いない。居ないのでないもうこっちが三年生なのだが、あの挨拶あいさつを待まってそっと横眼よこめで威張いばっている卑怯ひきょうな上級生じょうきゅうせいが居ないのだ。そこで何だか今まで頭をぶっつけた低ひくい天井裏てんじょううらが無なくなったような気もするけれどもまた支柱しちゅうをみんな取とってしまった桜さくらの木のような気もする。今日の実習じっしゅうにはそれをやった。去年きょねんの九月古い競馬場けいばじょうのまわりから掘って来て植うえておいたのだ。今ごろ支柱を取るのはまだ早いだろうとみんな思った。なぜならこれからちょうど小さな根ねがでるころなのに西風はまだまだ吹ふくから幹みきがてこになってそれを切るのだ。けれども菊池きくち先生はみんな除とらせた。花が咲さくのに支柱があっては見っともないと云いうのだけれども桜が咲くにはまだ一月もその余よもある。菊池先生は春になったのでただ面白おもしろくてあれを取ったのだとおもう。
その古い縄なわだの冬の間のごみだの運動場うんどうじょうの隅すみへ集あつめて燃もやした。そこでほかの実習の組の人たちは羨うらやましがった。午前中その実習をして放課ほうかになった。教科書がまだ来ないので明日もやっぱり実習だという。午ご后ごはみんなでテニスコートを直なおしたりした。
四月二日 水曜日 晴
今日は三年生は地質ちしつと土性どせいの実習だった。斉藤さいとう先生が先に立って女学校の裏うらで洪積層こうせきそうと第だい三紀きの泥岩でいがんの露出ろしゅつを見てそれからだんだん土性を調しらべながら小船渡こぶなとの北上きたかみの岸きしへ行った。河かわへ出ている広い泥岩の露出で奇体きたいなギザギザのあるくるみの化石かせきだの赤い高師小僧たかしこぞうだのたくさん拾ひろった。それから川岸を下って朝日橋あさひばしを渡わたって砂利じゃりになった広い河原かわらへ出てみんなで鉄鎚かなづちでいろいろな岩石の標本ひょうほんを集あつめた。河原からはもうかげろうがゆらゆら立って向むこうの水などは何だか風のように見えた。河原で分れて二時頃ごろうちへ帰った。
そして晩ばんまで垣根かきねを結ゆって手伝てつだった。あしたはやすみだ。
四月三日 今日はいい付つけられて一日古い桑くわの根掘ねほりをしたので大へんつかれた。
四月四日、上田君うえだくんと高橋君たかはしくんは今日も学校へ来なかった。上田君は師範しはん学校の試験しけんを受うけたそうだけれどもまだ入ったかどうかはわからない。なぜ農のう学校を二年もやってから師範学校なんかへ行くのだろう。高橋君は家で稼かせいでいてあとは学校へは行かないと云ったそうだ。高橋君のところは去年きょねんの旱魃かんばつがいちばんひどかったそうだから今年はずいぶん難儀なんぎするだろう。それへ較くらべたらうちなんかは半分でもいくらでも穫とれたのだからいい方だ。今年は肥料ひりょうだのすっかり僕ぼくが考えてきっと去年の埋うめ合せを付つける。実習じっしゅうは苗代掘なわしろほりだった。去年の秋小さな盛もりにしていた土を崩くずすだけだったから何でもなかった。教科書がたいてい来たそうだ。ただ測量そくりょうと園芸えんげいが来ないとか云っていた。あしたは日曜だけれども無なくならないうちに買いに行こう。僕は国語と修身しゅうしんは農事試験場へ行った工藤くどうさんから譲ゆずられてあるから残のこりは九冊さつだけだ。
四月五日 日
南万丁目みなみまんちょうめへ屋根換やねがえの手伝てつだえにやられた。なかなかひどかった。屋根の上にのぼっていたら南の方に学校が長々と横よこたわっているように見えた。ぼくは何だか今日は一日あの学校の生徒せいとでないような気がした。教科書は明日買う。
四月六日 月
今日は入学式しきだった。ぼんやりとしてそれでいて何だか堅苦かたくるしそうにしている新入生はおかしなものだ。ところがいまにみんな暴あばれ出す。来年になるとあれがみんな二年生になっていい気になる。さ来年はみんな僕ぼくらのようになってまた新入生をわらう。そう考かんがえると何だか変へんな気がする。伊藤君いとうくんと行って本屋ほんやへ教科書を九冊さつだけとっておいてもらうように頼たのんでおいた。
四月七日 火、朝父から金を貰もらって教科書を買った。
そして今日から授業じゅぎょうだ。測量そくりょうはたしかに面白おもしろい。地図を見るのも面白い。ぜんたいここらの田や畑はたけでほんとうの反別たんべつになっている処ところがないと武田たけだ先生が云いった。それだから仕事しごとの予定よていも肥料ひりょうの入れようも見当がつかないのだ。僕ぼくはもう少し習ならったらうちの田をみんな一枚まいずつ測はかって帳面ちょうめんに綴とじておく。そして肥料だのすっかり考えてやる。きっと今年は去年きょねんの旱魃かんばつの埋うめ合せと、それから僕の授業料じゅぎょうりょうぐらいを穫とってみせる。実習は今日も苗代掘なわしろほりだった。
四月八日 水、今日は実習じっしゅうはなくて学校の行進歌こうしんかの練習れんしゅうをした。僕らが歌って一年生がまねをするのだ。けれどもぼくは何だか圧おしつけられるようであの行進歌こうしんかはきらいだ。何だかあの歌を歌うと頭が痛いたくなるような気がする。実習じっしゅうのほうが却かえっていいくらいだ。学校から纏まとめて注文ちゅうもんするというので僕ぼくは苹果りんごを二本と葡萄ぶどうを一本頼たのんでおいた。
四月九日〔以下空白〕
一千九百廿にじゅう五年五月五日 晴
まだ朝の風は冷つめたいけれども学校へ上り口の公園の桜さくらは咲さいた。けれどもぼくは桜の花はあんまり好すきでない。朝日にすかされたのを木の下から見ると何だか蛙かえるの卵たまごのような気がする。それにすぐ古くさい歌やなんか思い出すしまた歌など詠よむのろのろしたような昔むかしの人を考えるからどうもいやだ。そんなことがなかったら僕ぼくはもっと好きだったかも知れない。誰だれも桜が立派りっぱだなんて云いわなかったら僕はきっと大声でそのきれいさを叫さけんだかも知れない。僕は却かえってたんぽぽの毛のほうを好きだ。夕陽ゆうひになんか照てらされたらいくら立派だか知れない。
今日の実習は陸稲播おかぼまきで面白おもしろかった。みんなで二うねずつやるのだ。ぼくは杭くいを借かりて来て定規じょうぎをあてて播いた。種子しゅしが間隔かんかくを正しくまっすぐになった時はうれしかった。いまに芽めを出せばその通り青く見えるんだ。学校の田のなかにはきっとひばりの巣すが三つ四つある。実習している間になんべんも降おりたのだ。けれども飛とびあがるところはつい見なかった。ひばりは降りるときはわざと巣からはなれて降りるから飛びあがるとこを見なければ巣のありかはわからない。
一千九百二十五年五月六日
今日学校で武田たけだ先生から三年生の修学旅行しゅうがくりょこうのはなしがあった。今月の十八日の夜十時で発たって二十三日まで札幌さっぽろから室蘭むろらんをまわって来るのだそうだ。先生は手に取とるように向むこうの景色けしきだの見て来ることだの話した。
津軽海峡つがるかいきょう、トラピスト、函館はこだて、五稜郭ごりょうかく、えぞ富士ふじ、白樺しらかば、小樽おたる、札幌の大学、麦酒ビール会社、博物館はくぶつかん、デンマーク人の農場のうじょう、苫小牧とまこまい、白老しらおいのアイヌ部落ぶらく、室蘭むろらん、ああ僕ぼくは数かぞえただけで胸むねが踊おどる。五時間目には菊池きくち先生がうちへ宛あてた手紙を渡わたして、またいろいろ話された。武田先生と菊池先生がついて行かれるのだそうだ。
行く人が二十八人にならなければやめるそうだ。それは県けんの規則きそくが全級ぜんきゅうの三分の一以上いじょう参加さんかするようになってるからだそうだ。けれども学校へ十九円納おさめるのだしあと五円もかかるそうだから。きっと行けると思う人はと云ったら内藤ないとう君や四人だけ手をあげた。みんな町の人たちだ。うちではやってくれるだろうか。父が居いないので母へだけ話したけれども母は心配しんぱいそうに眼めをあげただけで何とも云わなかった。けれどもきっと父はやってくれるだろう。そしたら僕は大きな手帳てちょうへ二冊さつも書いて来て見せよう。
五月七日
今朝父へ学校からの手紙を渡してそれからいろいろ先生の云ったことを話そうとした。すると父は手紙を読んでしまってあとはなぜか大へんあたりに気兼きがねしたようすで僕が半分しか云わないうちに止めてしまった。そしてよく相談そうだんするからと云った。祖母そぼや母に気兼ねをしているのかもしれない。
五月八日 行く人が大ぶあるようだ。けれどもうちでは誰だれも何とも云わない。だから僕ぼくはずいぶんつらい。
五月九日、
三時間目に菊池きくち先生がまたいろいろ話された。行くときまった人はみんな面白おもしろそうにして聞いていた。僕は頭が熱あつくて痛いたくなった。ああ北海道、雑嚢ざつのうを下げてマントをぐるぐる捲まいて肩かたにかけて津軽海峡つがるかいきょうをみんなと船で渡わたったらどんなに嬉うれしいだろう。
五月十日 今日もだめだ。
五月十一日 日曜 曇くもり 午前は母や祖母そぼといっしょに田打たうちをした。午ご后ごはうちのひば垣がきをはさんだ。何だか修学旅行しゅうがくりょこうの話が出てから家中へんになってしまった。僕はもう行かなくてもいい。行かなくてもいいから学校ではあと授業じゅぎょうの時間に行く人を調しらべたり旅行の話をしたりしなければいいのだ。
北海道なんか何だ。ぼくは今に働はたらいて自分で金をもうけてどこへでも行くんだ。ブラジルへでも行ってみせる。
五月十二日、今日また人数を調べた。二十八人に四人足りなかった。みんなは僕ぼくだの斉藤君さいとうくんだの行かないので旅行が不成立ふせいりつになると云いってしきりに責せめた。武田たけだ先生まで何だか変へんな顔をして僕に行けと云う。僕はほんとうにつらい。明后日みょうごにちまでにすっかり決きまるのだ。夕方父が帰って炉ろばたに居いたからぼくは思い切って父にもう一度ど学校の事情じじょうを云った。
すると父が母もまだ伊勢詣いせまいりさえしないのだし祖母そぼだって伊勢詣り一ぺんとここらの観音巡かんのんめぐり一ぺんしただけこの十何年死しぬまでに善光寺ぜんこうじへお詣りしたいとそればかり云っているのだ、ことに去年きょねんからのここら全体ぜんたいの旱魃かんばつでいま外へ遊あそんで歩くなんてことはとなりやみんなへ悪わるくてどうもいけないということを云った。
僕はいくら下を向いていても炉のなかへ涙なみだがこぼれて仕方しかたなかった。それでもしばらくたってからそんなら僕はもう行かなくてもいいからと云いった。ぼくはみんなが修学旅行しゅうがくりょこうへ発たつ間休みだといって学校は欠席けっせきしようと思ったのだ。すると父がまたしばらくだまっていたがとにかくもいちど相談そうだんするからと云ってあとはいろいろ稲いねの種類しゅるいのことだのふだんきかないようなことまでぼくにきいた。ぼくはけれども気持きもちがさっぱりした。
五月十三日 今日学校から帰って田に行ってみたら母だけ一人居いて何だか嬉うれしそうにして田の畦あぜを切っていた。
何かあったのかと思ってきいたら、今にお父さんから聞けといった。ぼくはきっと修学旅行のことだと思った。
僕ぼくもそこで母が家へ帰るまで田打たうちをして助たすけた。
けれども父はまだ帰って来ない。
五月十四日、昨夜さくや父が晩おそく帰って来て、僕を修学旅行にやると云った。母も嬉しそうだったし祖母もいろいろ向むこうのことを聞いたことを云った。祖母の云うのはみんな北海道開拓当時かいたくとうじのことらしくて熊くまだのアイヌだの南瓜かぼちゃの飯めしや玉蜀黍とうもろこしの団子だんごやいまとはよほどちがうだろうと思われた。今日学校へ行って武田たけだ先生へ行くと云いって届とどけたら先生も大へんよろこんだ。もうあと二人足りないけれども定員ていいんを超こえたことにして県けんへは申請書しんせいしょを出したそうだ。ぼくはもう行ってきっとすっかり見て来る、そしてみんなへ詳くわしく話すのだ。
一九二五、五、一八、
汽車は闇やみのなかをどんどん北へ走って行く。盛岡もりおかの上のそらがまだぼうっと明るく濁にごって見える。黒い藪やぶだの松林まつばやしだのぐんぐん窓まどを通って行く。北上きたかみ山地の上のへりが時々かすかに見える。
さあいよいよぼくらも岩手県いわてけんをはなれるのだ。
うちではみんなもう寝ねただろう。祖母さんはぼくにお守まもりを借かしてくれた。さよなら、北上山地、北上川、岩手県の夜の風、今武田先生が廻まわってみんなの席せきの工合ぐあいや何かを見て行った。
一九二六、五、一九、〔以下空白〕
五月十九日
*
いま汽車は青森県の海岸かいがんを走っている。海は針はりをたくさん並ならべたように光っているし木のいっぱい生はえた三角な島もある。いま見ているこの白い海が太平洋たいへいようなのだ。その向むこうにアメリカがほんとうにあるのだ。ぼくは何だか変へんな気がする。
海が岬みさきで見えなくなった。松林まつばやしだ。また見える。次つぎは浅虫あさむしだ。石を載のせた屋根やねも見える。何て愉快ゆかいだろう。
*
青森の町は盛岡もりおかぐらいだった。停車場ていしゃじょうの前にはバナナだの苹果りんごだの売る人がたくさんいた。待合室まちあいしつは大きくてたくさんの人が顔を洗あらったり物ものを食べたりしている。待合室で白い服ふくを着きた車掌しゃしょうみたいな人が蕎麦そばも売っているのはおかしい。
*
船はいま黒い煙けむりを青森の方へ長くひいて下北半島しもきたはんとうと津軽つがる半島の間を通って海峡かいきょうへ出るところだ。みんなは校歌をうたっている。けむりの影かげは波なみにうつって黒い鏡かがみのようだ。津軽半島の方はまるで学校にある広重ひろしげの絵のようだ。山の谷がみんな海まで来ているのだ。そして海岸かいがんにわずかの砂浜すなはまがあってそこには巨おおきな黒松くろまつの並木なみきのある街道かいどうが通っている。少し大きな谷には小さな家が二、三十も建たっていてそこの浜には五、六そうの舟ふねもある。
さっきから見えていた白い燈台とうだいはすぐそこだ。ぼくは船が横よこを通る間にだまってすっかり見てやろう。絵が上手じょうずだといいんだけれども僕ぼくは絵は描かけないから覚おぼえて行ってみんな話すのだ。風は寒さむいけれどもいい天気だ。僕は少しも船に酔よわない。ほかにも誰だれも酔ったものはない。
*
いるかの群むれが船の横を通っている。いちばんはじめに見附みつけたのは僕だ。ちょっと向うを見たら何か黒いものが波なみから抜ぬけ出て小さな弧こを描えがいてまた波へはいったのでどうしたのかと思ってみていたらまたすぐ近くにも出た。それからあっちにもこっちにも出た。そこでぼくはみんなに知らせた。何だか手を気を付つけの姿勢しせいで水を出たり入ったりしているようで滑稽こっけいだ。
先生も何だかわからなかったようだが漁師りょうしの頭かしららしい洋服ようふくを着きた肥ふとった人がああいるかですと云いった。あんまりみんな甲板かんぱんのこっち側がわへばかり来たものだから少し船が傾かたむいた。
風が出てきた。
何だか波が高くなってきた。
東も西も海だ。向うにもう北海道が見える。何だか工合ぐあいがわるくなってきた。
*
いま汽車は函館はこだてを発たって小樽おたるへ向むかって走っている。窓まどの外はまっくらだ。もう十一時だ。函館の公園はたったいま見て来たばかりだけれどもまるで夢ゆめのようだ。
巨おおきな桜さくらへみんな百ぐらいずつの電燈でんとうがついていた。それに赤や青の灯ひや池にはかきつばたの形した電燈でんとうの仕掛しかけものそれに港みなとの船の灯や電車の火花じつにうつくしかった。けれどもぼくは昨夜さくやからよく寝ねないのでつかれた。書かないでおいたってあんなうつくしい景色けしきは忘わすれない。それからひるは過燐酸かりんさんの工場と五稜郭ごりょうかく。過燐酸石灰せっかい、硫酸りゅうさんもつくる。
五月廿日
*
いま窓まどの右手にえぞ富士ふじが見える。火山だ。頭が平ひらたい。焼やいた枕木まくらぎでこさえた小さな家がある。熊笹くまざさが茂しげっている。植民地しょくみんちだ。
*
いま小樽おたるの公園に居いる。高等商業こうとうしょうぎょうの標本室ひょうほんしつも見てきた。馬鈴薯ばれいしょからできるもの百五、六十種しゅの標本が面白おもしろかった。
この公園も丘おかになっている。白樺しらかばがたくさんある。まっ青さおな小樽湾わんが一目だ。軍艦ぐんかんが入っているので海軍には旗はたも立っている。時間があれば見せるのだがと武田たけだ先生が云った。ベンチへ座すわってやすんでいると赤い蟹かにをゆでたのを売りに来る。何だか怖こわいようだ。よくあんなの食べるものだ。
*
一千九百廿五年十月十六日
一時間目の修身しゅうしんの講義こうぎが済すんでもまだ時間が余あまっていたら校長が何でも質問しつもんしていいと云った。けれども誰だれも黙だまっていて下を向むいているばかりだった。ききたいことは僕ぼくだってみんなだって沢山たくさんあるのだ。けれどもぼくらがほんとうにききたいことをきくと先生はきっと顔をおかしくするからだめなのだ。
なぜ修身がほんとうにわれわれのしなければならないと信しんずることを教えるものなら、どんな質問でも出さしてはっきりそれをほんとうかうそか示しめさないのだろう。
一千九百廿五年十月廿五日
今日は土性調査どせいちょうさの実習じっしゅうだった。僕ぼくは第だい二班はんの班長で図板ずばんをもった。あとは五人でハムマアだの検土杖けんどじょうだの試験紙しけんしだの塩化加里えんかカリの瓶びんだの持もって学校を出るときの愉快ゆかいさは何とも云いわれなかった。谷たに先生もほんとうに愉快そうだった。六班がみんな思い思いの計画で別々べつべつのコースをとって調査にかかった。僕は郡ぐんで調しらべたのをちゃんと写うつして予察図よさつずにして持っていたからほかの班のようにまごつかなかった。けれどもなかなかわからない。郡のも十万分一だしほんの大体しか調ばっていない。猿ヶ石さるがいし川の南の平地ひらちに十時半ころまでにできた。それからは洪積層こうせきそうが旧天王キーデンノーの安山集塊岩あんざんしゅうかいがんの丘おかつづきのにも被かぶさっているかがいちばんの疑問ぎもんだったけれどもぼくたちは集塊岩のいくつもの露頭ろとうを丘の頂部ちょうぶ近くで見附みつけた。結局けっきょく洪積紀きは地形図の百四十米メートルの線以下いかという大体の見当も附けてあとは先生が云ったように木の育そだち工合ぐあいや何かを参照さんしょうして決きめた。ぼくは土性の調査よりも地質ちしつの方が面白おもしろい。土性の方ならただ土をしらべてその場所を地図の上にその色で取とっていくだけなのだが地質の方は考えなければいけないしその考えがなかなかうまくあたるのだから。
ぼくらは松林まつばやしの中だの萱かやの中で何べんもほかの班に出会った。みんなぼくらの地図をのぞきたがった。
萱の中からは何べんも雉子きじも飛とんだ。
耕地整理こうちせいりになっているところがやっぱり旱害かんがいで稲いねは殆ほとんど仕付しつからなかったらしく赤いみじかい雑草ざっそうが生はえておまけに一ぱいにひびわれていた。
やっと仕付かった所ところも少しも分蘖ぶんけつせず赤くなって実みのはいらない稲がそのまま刈かりとられずに立っていた。耕地整理の先に立った人はみんなの為ためにしたのだそうだけれどもほんとうにひどいだろう。ぼくらはそこの土性どせいもすっかりしらべた。水さえ来るならきっと将来しょうらいは反当たんあたり三石ごくまではとれるようにできると思う。
午ご后ご一時に約束やくそくの通り各班かくはんが猿ヶ石さるがいし川の岸きしにあるきれいな安山集塊岩あんざんしゅうかいがんの露出ろしゅつのところに集あつまった。どこからか小梨こなしを貰もらったと云いって先生はみんなに分けた。ぼくたちはそこで地図を塗ぬりなおしたりした。先生はその場所ばしょでは誰だれのもいいとも悪わるいとも云わなかった。しばらくやすんでから、こんどはみんなで先生について川の北の花崗岩かこうがんだの三紀きの泥岩でいがんだのまではいった込こんだ地質ちしつや土性のところを教わってあるいた。図は次つぎの月曜までに清書せいしょして出すことにした。
ぼくはあの図を出して先生に直なおしてもらったら次の日曜に高橋君たかはしくんを頼たのんで僕のうちの近所きんじょのをすっかりこしらえてしまうんだ。僕のうちの近くなら洪積こうせきと沖積ちゅうせきがあるきりだしずっと簡単かんたんだ。それでも肥料ひりょうの入れようやなんかまるでちがうんだから。いまならみんなはまるで反対はんたいにやってるんでないかと思う。
一九二五、十一月十日。
今日実習じっしゅうが済すんでから農舎のうしゃの前に立ってグラジオラスの球根きゅうこんの旱ほしてあるのを見ていたら武田たけだ先生も鶏小屋にわとりごやの消毒しょうどくだか済んで硫黄華いおうかをずぼんへいっぱいつけて来られた。そしてやっぱり球根を見ていられたがそこから大きなのを三つばかり取とって僕に呉くれた。僕がもじもじしているとこれは新らしい高価たかい種類しゅるいだよ。君きみにだけやるから来春植うえてみたまえと云った。すると農場の方から花の係かかりの内藤ないとう先生が来たら武田先生は大へんあわててポケットへしまっておきたまえ、と云った。ぼくは変へんな気がしたけれども仕方しかたなくポケットへ入れた。すると武田先生は急いそいで農舎の中へはいって農具のうぐだか何だか整理せいりし出した。ぼくはいやで仕方なかったので内藤先生が行ってからそっと球根をむしろの中へ返かえして、急いで校舎へ入って実習服ふくを着換きがえてうちに帰った。
一千九百二十六年三月廿〔一字分空白〕日、
塩水撰えんすいせんをやった。うちのが済すんでから楢戸ならどのもやった。
本にある通りの比重ひじゅうでやったら亀かめの尾おは半分も残のこらなかった。去年きょねんの旱害かんがいはいちばんよかった所ところでもこんな工合ぐあいだったのだ。けれども陸羽りくう一三二号ごうのほうは三割わりぐらいしか浮く分がなかった。それでも塩水選せんをかけたので恰度ちょうど六斗とあったから本田の一町一反たん分には充分じゅうぶんだろう。とにかく僕ぼくは今日半日で大丈夫だいじょうぶ五十円の仕事しごとはした訳わけだ。
なぜならいままでは塩水選をしないでやっと反当たんあたり二石こくそこそこしかとっていなかったのを今度こんどはあちこちの農事試験場のうじしけんじょうの発表はっぴょうのように一割の二斗ずつの増収ぞうしゅうとしても一町一反では二石二斗になるのだ。みんなにもほんとうにいいということが判わかるようになったら、ぼくは同じ塩水で長根ちょうこんぜんたいのをやるようにしよう。一軒けんのうちで三十円ずつ得とくしてもこの部落全体ぶらくぜんたいでは四百五十円になる。それが五、六人ただ半日の仕事しごとなのだ。塩水選をする間は父はそこらの冬の間のごみを集あつめて焼やいた。籾もみができると父は細長ほそながくきれいに藁わらを通して編あんだ俵たわらにつめて中へつめた。あれは合理的ごうりてきだと思う。湧水わきみずがないので、あのつつみへ漬つけた。氷こおりがまだどての陰かげには浮いているからちょうど摂氏零度せっしれいどぐらいだろう。十二月にどてのひびを埋うめてから水は六分目までたまっていた。今年こそきっといいのだ。あんなひどい旱魃かんばつが二年続つづいたことさえいままでの気象きしょうの統計とうけいにはなかったというくらいだもの、どんな偶然ぐうぜんが集あつまったって今年まで続くなんてことはないはずだ。気候きこうさえあたり前だったら今年は僕はきっといままでの旱魃の損害そんがいを恢復かいふくしてみせる。そして来年らいねんからはもううちの経済けいざいも楽にするし長根ぜんたいまできっと生々いきいきした愉快ゆかいなものにしてみせる。
一千九百二十六年六月十四日 今日はやっと正午しょうごから七時まで番水ばんすいがあたったので樋番といばんをした。何せ去年きょねんからの巨おおきなひびもあるとみえて水はなかなかたまらなかった。くろへ腰掛こしかけてこぼこぼはっていく温あたたかい水へ足を入れていてついとろっとしたらなんだかぼくが稲いねになったような気がした。そしてぼくが桃ももいろをした熱病ねつびょうにかかっていてそこへいま水が来たのでぼくは足から水を吸すいあげているのだった。どきっとして眼めをさました。水がこぼこぼ裂目さけめのところで泡あわを吹ふきながらインクのようにゆっくりゆっくりひろがっていったのだ。
水が来なくなって下田の代掻しろかきができなくなってから今日で恰度ちょうど十二日雨が降ふらない。いったいそらがどう変かわったのだろう。あんな旱魃かんばつの二年続つづいた記録きろくが無ないと測候所そっこうじょが云いったのにこれで三年続くわけでないか。大堰おおぜきの水もまるで四寸すんぐらいしかない。夕方になってやっといままでの分へ一わたり水がかかった。
三時ごろ水がさっぱり来なくなったからどうしたのかと思って大堰の下の岐わかれまで行ってみたら権十ごんじゅうがこっちをとめてじぶんの方へ向むけていた。ぼくはまるで権十が甘藍かんらんの夜盗虫よとうむしみたいな気がした。顔がむくむく膨ふくれていて、おまけにあんな冠かぶらなくてもいいような穴あなのあいたつばの下った土方どかたしゃっぽをかぶってその上からまた頬ほおかぶりをしているのだ。
手も足も膨れているからぼくはまるで権十が夜盗虫みたいな気がした。何をするんだと云ったら、なんだ、農のう学校終おわったって自分だけいいことをするなと云うのだ。ぼくもむっとした。何だ、農学校なぞ終っても終らなくてもいまはぼくのとこの番にあたって水を引いているのだ。それを盗ぬすんで行くとは何だ。と云ったら、学校へ入ったんでしゃべれるようになったもんな、と云う。ぼくはもう大きな石をたたきつけてやろうとさえ思った。
けれども権十はそのまま行ってしまったから、ぼくは水をうちの方へ向け直なおした。やっぱり権十はぼくを子供こどもだと思ってぼくだけ居いたものだからあんなことをしたのだ。いまにみろ、ぼくは卑怯ひきょうなやつらはみんな片かたっぱしから叩たたきつけてやるから。
一千九百二十七年八月廿一日
稲いねがとうとう倒たおれてしまった。ぼくはもうどうしていいかわからない。あれぐらい昨日きのうまでしっかりしていたのに、明方あけがたの烈はげしい雷雨らいうからさっきまでにほとんど半分倒れてしまった。喜作きさくのもこっそり行ってみたけれどもやっぱり倒れた。いまもまだ降ふっている。父はわらって大丈夫だいじょうぶ大丈夫だと云うけれどもそれはぼくをなだめるためでじつは大へんひどいのだ。母はまるでぼくのことばかり心配しんぱいしている。ぼくはうちの稲が倒れただけなら何でもないのだ。ぼくが肥料ひりょうを教えた喜作のだってそれだけなら何でもない。それだけならぼくは冬に鉄道てつどうへ出ても行商ぎょうしょうしてもきっと取とり返かえしをつける。けれども、あれぐらい手入をしてあれぐらい肥料を考えてやってそれでこんなになるのならもう村はどこももっとよくなる見込みこみはないのだ。ぼくはどこへも相談そうだんに行くとこがない。学校へ行ったってだめだ。……先生はああ倒れたのか、苗なえが弱くはなかったかな、あんまり力を落おとしてはいけないよ、ぐらいのことを云って笑わらうだけのもんだ。日誌にっし、日誌、ぼくはこの書きつける日誌がなかったら今夜どうしているだろう。せきはとめたし落し口は切ったし田のなかへはまだ入られないしどうすることもできずだまってあのぼしょぼしょしたりまたおどすように強くなったりする雨の音を聞いていなければならないのだ。いったいこの雨があしたのうちに晴れるだなんてことがあるだろうか。
ああどうでもいい、なるようになるんだ。あした雨が晴れるか晴れないかよりも、今夜ぼくが…………を一足つくれることのほうがよっぽどたしかなんだから。
底本:「イーハトーボ農学校の春」角川文庫、角川書店
1996(平成8)年3月25日初版発行
底本の親本:「新校本 宮澤賢治全集」筑摩書房
1995(平成7)年5月
※底本は、一つ目の「猿ヶ石」の「ヶ」(区点番号5-86)は大振りに、二つ目の「猿ヶ石」のそれは、小振りにつくっています。
入力:ゆうき
校正:noriko saito
2009年8月23日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
朝に就ての童話的構図
宮沢賢治
苔こけいちめんに、霧がぽしやぽしや降つて、蟻ありの歩哨ほせうは、鉄の帽子のひさしの下から、するどいひとみであたりをにらみ、青く大きな羊歯しだの森の前をあちこち行つたり来たりしてゐます。
向ふからぷるぷるぷるぷる一ぴきの蟻の兵隊が走つて来ます。
「停とまれ、誰たれかツ」
「第百二十八聯隊れんたいの伝令!」
「どこへ行くか」
「第五十聯隊 聯隊本部」
歩哨はスナイドル式の銃剣を、向ふの胸に斜めにつきつけたまま、その眼の光りやうや顎あごのかたち、それから上着の袖そでの模様や靴の工合ぐあひ、いちいち詳しく調べます。
「よし、通れ」
伝令はいそがしく羊歯の森のなかへ入つて行きました。
霧の粒はだんだん小さく小さくなつて、いまはもううすい乳いろのけむりに変り、草や木の水を吸ひあげる音は、あつちにもこつちにも忙しく聞え出しました。さすがの歩哨もたうとう睡ねむさにふらつとします。
二疋ひきの蟻の子供らが、手をひいて、何かひどく笑ひながらやつて来ました。そして俄にはかに向ふの楢ならの木の下を見てびつくりして立ちどまります。
「あつあれなんだらう。あんなとこにまつ白な家ができた」
「家ぢやない山だ」
「昨日はなかつたぞ」
「兵隊さんにきいて見よう」
「よし」
二疋の蟻は走ります。
「兵隊さん、あすこにあるのなに?」
「何だうるさい、帰れ」
「兵隊さん、ゐねむりしてんだい。あすこにあるのなに?」
「うるさいなあ、どれだい、おや!」
「昨日はあんなものなかつたよ」
「おい、大変だ。おい。おまへたちはこどもだけれども、かういふときには立派にみんなのお役に立つだらうなあ。いゝか。おまへはね、この森を入つて行つてアルキル中佐どのにお目にかゝる。それからおまへはうんと走つて陸地測量部まで行くんだ。そして二人ともかう云ふんだ。北緯二十五度東経六厘の処ところに、目的のわからない大きな工事ができましたとな。二人とも云つてごらん」
「北緯二十五度東経六厘の処に目的のわからない大きな工事ができました」
「さうだ。では早く。そのうち私は決してこゝを離れないから」
蟻ありの子供らは一目散にかけて行きます。
歩哨ほせうは剣をかまへて、じつとそのまつしろな太い柱の、大きな屋根のある工事をにらみつけてゐます。
それはだんだん大きくなるやうです。だいいち輪廓りんくわくのぼんやり白く光つてぷるぷるぷるぷる顫ふるへてゐることでもわかります。
俄にはかにぱつと暗くなり、そこらの苔こけはぐらぐらゆれ、蟻の歩哨は夢中で頭をかかへました。眼をひらいてまた見ますと、あのまつ白な建物は、柱が折れてすつかり引つくり返つてゐます。
蟻の子供らが両方から帰つてきました。
「兵隊さん。構はないさうだよ。あれはきのこといふものだつて。何でもないつて。アルキル中佐はうんと笑つたよ。それからぼくをほめたよ」
「あのね、すぐなくなるつて。地図に入れなくてもいいつて。あんなもの地図に入れたり消したりしてゐたら、陸地測量部など百あつても足りないつて。おや! 引つくりかへつてらあ」
「たつたいま倒れたんだ」歩哨は少しきまり悪さうに云ひました。
「なあんだ。あつ。あんなやつも出て来たぞ」
向ふに魚の骨の形をした灰いろのをかしなきのこが、とぼけたやうに光りながら、枝がついたり手が出たりだんだん地面からのびあがつてきます。二疋の蟻の子供らは、それを指さして、笑つて笑つて笑ひます。
そのとき霧の向ふから、大きな赤い日がのぼり、羊歯しだもすぎごけもにはかにぱつと青くなり、蟻の歩哨は、また厳いかめしくスナイドル式銃剣を南の方へ構へました。
底本:「宮沢賢治全集8」ちくま文庫、筑摩書房
1986(昭和61)年1月28日第1刷発行
2004(平成16)年4月25日第20刷発行
初出:「天才人 第六輯」
1933(昭和8)年3月25日発行
入力:土屋隆
校正:noriko saito
2009年5月4日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
化物丁場
宮沢賢治
五六日続いた雨の、やっとあがった朝でした。黄金きんの日光が、青い木や稲を、照してはゐましたが、空には、方角の決まらない雲がふらふら飛び、山脈も非常に近く見えて、なんだかまだほんたうに霽はれたといふやうな気がしませんでした。
私は、西の仙人せんにん鉱山に、小さな用事がありましたので、黒沢尻くろさはじりで、軽便鉄道に乗りかへました。
車室の中は、割合空すいて居をりました。それでもやっぱり二十人ぐらゐはあったでせう。がやがや話して居りました。私のあとから入って来た人もありました。
話はここでも、本線の方と同じやうに、昨日までの雨と洪水の噂うはさでした。大抵南の方のことでした。狐禅寺こぜんじでは、北上きたかみ川が一丈六尺増したと誰たれかが云ひました。宮城の品井沼の岸では、稲がもう四日も泥水を被かぶってゐる、どうしても今年はあの辺は半作だらうと又誰か言ってゐました。
ところが私のうしろの席で、突然太い強い声がしました。
「雫石しづくいし、橋場間、まるで滅茶苦茶だ。レールが四間も突き出されてゐる。枕木まくらぎも何もでこぼこだ。十日や十五日でぁ、一寸ちょっと六むつヶ敷しぃな。」
ははあ、あの化物丁場だな、私は思ひながら、急いでそっちを振り向きました。その人は線路工夫の半纒はんてんを着て、鍔つばの広い麦藁むぎわら帽を、上の棚たなに載せながら、誰に云いふとなく大きな声でさう言ってゐたのです。
「あゝ、あの化物丁場ですか、壊れたのは。」私は頭を半分そっちへ向けて、笑ひながら尋ねました。鉄道工夫の人はちらっと私を見てすぐ笑ひました。
「さうです。どうして知ってゐますか。」少し改った兵隊口調で尋ねました。
「はあ、なあに、あの頃ころ一寸あすこらを歩いたもんですから。今度は大分ひどくやられましたか。」
「やられました。」その人はやっと席へ腰をおろしながら答へました。
「やっぱり今でも化物だって云ひますか。」
「うんは。」その人は大へん曖昧あいまいな調子で答へました。これが、私を、どうしても、もっと詳しく化物丁場の噂を聴きたくしたのです。そこで私は、向ふに話をやめてしまはれない為ために、又少し遠まはりのことから話し掛けました。
「鉄道院へ渡してから、壊れたのは今度始めてですか。」
「はあ、鉄道院でも大損す。」
「渡す前にも三四度壊れたんですね。」
「はあ、大きなのは三度です。」
「請負の方でも余程の損だったでせう。」
「はあ、やっぱり損だってました。あゝ云ふ難渋な処ところにぶっつかっては全く損するより仕方ありません。」
「どうしてさう度々壊れたでせう。」
「なあに、私ぁ行ってから二度崩れましたが雨降るど崩れるんだ。さうだがらって水の為でもないんだ、全くをかしいです。」
「あなたも行って働いてゐたのですか。」
「私の行ったのは十一月でしたが、丁度砂利を盛って、そいつが崩れたばかりの処でした。全体、あれは請負の岩間組の技師が少し急いだんです。ああ云ふ場所だがら思ひ切って下の岩からコンクリー使へば善かったんです。それでもやっぱり崩れたかも知れませんが。」
「大した谷川も無かったやうでしたがね。」
「いゝえ、水は、いくらか、下の岩からも、横の山の崖がけからも、湧わくんです。土も黒くてしめってゐたのです。その土の上に、すぐ砂利を盛りましたから、一層いけなかったのです。」
その時汽笛が鳴って汽車は発たちました。私は行手の青く光ってゐる仙人せんにんの峡を眺ながめ、それからふと空を見て、思はず、こいつはひどい、と、つぶやきました。雲が下の方と上の方と、すっかり反対に矢のやうに馳はせちがってゐたのです。
「また嵐あらしになりますよ。風がまったく変です。」私は工夫に云ひました。
その人も一寸ちょっと立って窓から顔を出してそれから、
「まだまだ降ります、今日は一寸あらしの日曜といふ訳だ。」と、つぶやくやうに云ひながら、又席に戻りました。電信柱の瀬戸の碍子がいしが、きらっと光ったり、青く葉をゆすりながら楊やなぎがだんだんめぐったり、汽車は丁度黒沢尻くろさはじりの町をはなれて、まっすぐに西の方へ走りました。
「でその崩れた砂利を、あなたも積み直したのですか。」
「さうです。」その人は笑ひました。たしかにこの人は化物丁場の話をするのが厭いやぢゃないのだと私は思ひました。
「それが、又、崩れたのですか。」私は尋ねました。
「崩れたのです。それも百人からの人夫で、八日かゝってやったやつです。積み直しといっても大部分は雫石しづくいしの河原から、トロで運んだんです。前に崩れた分もそっくり使って。だからずうっと脚がひろがっていかにも丈夫さうになったんです。」
「中々容易ぢゃなかったんでせう。」
「えゝ、とても。鉄道院から進行検査があるので請負の方の技師のあせり様ったらありませんや、従って監督は厳しく急ぎますしね、毎日天気でカラッとして却かへって風は冷たいし、朝などは霜が雪のやうでした。そこを砂利を、掘っては、掘っては、積んでは、トロを押したもんです。」
私は、あのすきとほった、つめたい十一月の空気の底で、栗くりの木や樺かばの木もすっかり黄いろになり、四方の山にはまっ白に雪が光り、雫石しづくいし川がまるで青ガラスのやうに流れてゐる、そのまっ白な広い河原を小さなトロがせはしく往いったり来たりし、みんなが鶴嘴つるはしを振り上げたり、シャベルをうごかしたりする景色を思ひうかべました。それからその人たちが赤い毛布でこさへたシャツを着たり、水で凍えないために、茶色の粗羅紗そらしゃで厚く足を包んだりしてゐる様子を眼めの前に思ひ浮べました。
「ほんたうにお容易ぢゃありませんね。」
「なあに、さうやって、やっと積み上ったんです。進行検査にも間に合ったてんで、監督たちもほっとしてゐたやうでした。私どももそのひどい仕事で、いくらか割増も貰もらふ筈はずでしたし、明日からの仕事も割合楽になるといふ訳でしたから、その晩は実は、春木場で一杯やったんです。それから小舎こやに帰って寝ましたがね、いゝ晩なんです、すっかり晴れて庚申かうしんさんなども実にはっきり見えてるんです。あしたは霜がひどいぞ、砂利も悪くすると凍るぞって云ひながら、寝たんです。すると夜中になって、さう、二時過ぎですな、ゴーッと云ふやうな音が、夢の中で遠くに聞えたんです。眼をさましたのが私たちの小屋に三四人ありました。ぼんやりした黄いろのランプの下へ頭をあげたまゝ誰たれも何とも云はないんです。だまってその音のした方へ半分からだを起してほかのものの顔ばかり見てゐたんです。すると俄にはかに監督が戸をガタッとあけて走って入って来ました。
『起きろ、みんな起きろ、今日のとこ崩れたぞ。早く起きろ、みんな行って呉くれ。』って云ふんです。誰も不承不承起きました。まだ眼をさまさないものは監督が起して歩いたんです。なんだ、崩れた、崩れた処へ夜中に行ったって何なぢょするんだ、なんて睡ねむくて腹立ちまぎれに云ふものもありましたが、大抵はみな顔色を変へて、うす暗いランプのあかりで仕度をしたのです。間もなく、私たちは、アセチレンを十ばかりつけて出かけました。水をかけられたやうに寒かったんです。天の川がすっかりまはってしまってゐました。野原や木はまっくろで、山ばかりぼんやり白かったんです。場処へ着いて見ますと、もうすっかり崩れてゐるらしいんです。そのアセチレンの青の光の中をみんなの見てゐる前でまだ石がコロコロ崩れてころがって行くんです。気味の悪いったら。」その人は一寸ちょっと話を切りました。私もその盛られた砂利をみんなが来てもまだいたづらに押してゐるすきとほった手のやうなものを考へて、何だか気味が悪く思ひました。それでもやっと尋ねました。
「それから又工事をやったんですか。」
「やったんです。すぐその場からです。技師がまるで眼を真赤にして、別段な訳もないのに怒鳴ったり、叱しかったりして歩いたんです。滑った砂利を積み直したんです。けれどもどうしたって誰も仕事に実が入りませんや。さうでせう。一度別段の訳もなく崩れたのならいづれ又格別の訳もなしに崩れるかもしれない、それでもまあ仕事さへしてゐれゃ賃金は向ふぢゃ払ひますからね、いくらつまらないと思っても、技師がさうしろって云ふことを、その通りやるより仕方ありませんや。ハッハッハ。一寸ちょっと。」
その工夫の人は立ちあがって窓から顔を出し手をかざして行手の線路をじっと見てゐましたが、俄にはかに下の方へ「よう、」と叫んで、挙手の礼をしました。私も、窓から顔を出して見ましたら、一人の工夫がシャベルを両手で杖つゑにして、線路にまっすぐに立ち、笑ってこっちを見てゐました。それもずんずんうしろの方へ遠くなってしまひ、向ふには栗駒くりこま山が青く光って、カラッとしたそらに立ってゐました。私たちは又腰掛けました。
「今度の積み直しも又八日もかゝつたんですか。」私は尋ねました。
「いゝえ、その時は前の半分もかゝらなかったのです。砂利を運ぶ手数がなかったものですから。その代り乱杭らんぐひを二三十本打ちこみましたがね、昼になってその崩れた工合ぐあひを見ましたらまるでまん中から裂けたやうなあんばいだったのです。県からも人が来てしきりに見てゐましたがね、どうもその理由がよくわからなかったやうでした。それでも四日でとにかくもとの通り出来あがったんです。その出来あがった晩は、私たちは十六人、たき火を三つ焚たいて番をしてゐました。尤もっとも番をするったって何をめあてって云ふこともなし、変なもんでしたが、酒を呑のんで騒いでゐましたから、大して淋さびしいことはありませんでした。それに五日の月もありましたしね。たゞ寒いのには閉口しましたよ。それでも夜中になって月も沈み話がとぎれるとしいんとなるんですね、遠くで川がざあと流れる音ばかり、俄に気味が悪くなることもありました。それでもたうとう朝までなんにも起らなかったんです。次の晩も外の組が十五人ばかり番しましたがやっぱり何もありませんでした。そこで工事はだんだん延びて行って、尤もっともそこをやってゐるうちに向ふの別の丁場では別の組がどんどんやってゐましたからね、レールだけは敷かなくてもまあ敷地だけは橋場に届いたんです。そのうちたうとう十二月に入ったでせう。雪も二遍か降りました。降っても又すぐ消えたんです。ところが、十二月の十日でしたが、まるで春降るやうなポシャポシャ雨が、半日ばかり降ったんです。なあに河の水が出るでもなし、ほんの土をしめらしただけですよ。それでゐて、その夕方に又あの丁場がざあっと来たもんです。折角入れた乱杭もあっちへ向いたりこっちへまがったりです。もうこの時はみんなすっかり気落ちしました。それでも又かといふやうな気分で前の時ぐらゐではなかったのです。その時はもうだんだん仕事が少くなって、又来春といふ約束で人夫もどんどん雫石しづくいしから盛岡もりをかをかかって帰って行ったあとでしたし、第一これから仕事なかばでいつ深い雪がやって来るかわからなかったんですから何だか仕事するっても張りがありませんや。それでも云ひつけられた通り私たちはみんな、さう、みんなで五十人も居たでせうか、あちこちの丁場から集めたんです。崩れた処を掘り起す、それからトロで河原へも行きましたが次の日などは砂利が凍ってもう鶴嘴つるはしが立たないんです。いくら賃銀は貰もらったって、こんなあてのない仕事は厭いやだ、今年はもうだめなんだ、来年神官でも呼んで、よくお祭をしてから、コンクリーで底からやり直せと、まあ私たちは大丈夫のやうなことを云ひながら働いたもんです。それでもたうとう、十二月中には、雪の中で何とかかんとか、もとのやうな形になったんです。おまけに安心なことはその上に雪がすっかり被かぶさったんです。堅まって二尺以上もあったでせう。」
「あゝさうです。その頃です。私の行ったのは。」私は急いで云ひました。
「化物丁場の話をどこでお聞きでした。」
「春木場です。」
「ではあなたのいらしゃったのは、鉄道院の検査官の来た頃です。」
「いや、その検査官かも知れませんよ、私が橋場から戻る途中で、せいの高い鼠ねずみ色の毛糸の頭巾づきんを被って、黒いオーバアを着た老人技師風の人たちや何かと十五六人に会ったんです。」
「天気のいゝ日でしたか。」
「天気がよくて雪がぎらぎらしてました。橋場では吹雪も吹いたんですが。一月の六七日頃ですよ。」
「ではそれだ。その検査官が来ましてね、この化物丁場はよくあちこちにある、山の岩の層が釣合がとれない為に起るって云ったさうですがね、誰たれもあんまりほんとにはしませんや。」
「なるほど。」
汽車が、藤根ふぢねの停車場に近くなりました。
工夫の人は立って、棚たなから帽子をとり、道具を入れた布の袋を持って、扉との掛金を外して停とまるのを待ってゐました。
「こゝでお下りになるんですか。いろいろどうもありがたう。私は斯かう云ふもんです。」
と云ひながら、私は処書ところがきのある名刺を出しました。
「さうですか。私は名刺を持って来ませんで。」その人は云ひながら、私の名刺を腹掛のかくしに入れました。汽車がとまりました。
「さよなら。」すばやくその人は飛び下りました。
「さよなら。」私は見送りました。その人は道具を肩にかけ改札の方へ行かず、すぐに線路を来た方に戻りました。その線路は、青い稲の田の中に白く光ってゐました。そらでは風も静まったらしく、大したあらしにもならないでそのまゝ霽はれるやうに見えたのです。
底本:「新修宮沢賢治全集 第十四巻」筑摩書房
1980(昭和55)年5月15日初版第1刷発行
1983(昭和58)年1月20日初版第4刷発行
入力:林 幸雄
校正:今井忠夫
2003年1月10日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
バキチの仕事
宮沢賢治
「ああそうですか、バキチをご存ぞんじなんですか。」
「知ってますとも、知ってますよ。」
「バキチをご存じなんですか。
小学校でご一緒いっしょですか、中学校でご一緒ですか。いいやあいつは中学校なんど入りやしない。やっぱり小学校ですか。」「兵隊へいたいで一緒です。」
「ああ兵隊で、そうですか、あいつも一等卒いっとうそつでさね、どうやってるかご存じですか。」「さあ知りません。隊で分れたきりですから。」
「ああ、そうですか、そいじゃ私のほうがやっぱり詳くわしく知ってます。この間まで馬喰ばくろうをやってましたがね。今ごろは何をしているか全まったく困こまったもんですよ。」
「どうして馬喰をやめたでしょう。」
「だめでさあ、わっしもずいぶん目をかけました。でもどうしてもだめなんです。あいつは隊をさがってからもとの大工だいくにならないで巡査じゅんさを志願しがんしたのです。」「そして巡査じゅんさをやったんですか。」
「それぁやりました。けれども間もなくやめたんです。」
「どうしてやめたんだろうなあ、何でも隊たいに来る前は、大工でとにかく暮くらしていたと云いうんですが。」
「それゃうそでさあ大工もほんのちょっとです。土方どかたをやめてなったんです。その土方もまたちょっとです。それから前は知りません。土方ばかりじゃありません、飴屋あめやもやったて云いいますよ。」
「巡査をどうしてやめたんです。」「あんな巡査じゃだめでさあ、あのお神明しんめいさんの池ね、あすこに鯉こいが居いるでしょう、県の規則きそくで誰だれにもとらせないんです。ところが、やっぱり夜のうちに、こっそり行くものがあるんです。それぁきっとよく捕とれるんでしょう。バキチはそれをきいたのです。毎晩まいばんお神明さんの、杉すぎのうしろにかくれていて、来るやつを見ていたそうです、そしていよいよ網あみを入れて鯉が十疋ぴきもとれたとき、誰だっこらって出るんでしょう、魚も網も置おいたまま一目散いちもくさんに逃にげるでしょうバキチは笑わらってそいつを持もって警察けいさつの小使室こづかいしつへ帰るんです。」「変へんだねえ、なるほどねえ。」「何でも五回か六回かそんなことがあったそうです。そしたらある日署長しょちょうのとこへ差出人さしだしにんの名の書いてない変な手紙が行ったんです。署長が見たら今のことでしょう、けれども署長しょちょうは笑わらってました。なぜって巡査じゅんさなんてものは実際じっさい月給げっきゅうも僅わずかですしね、くらしに困こまるものなんです。」「なるほどねえ、そりゃそうだねえ。」
「ところがねえ、次つぎが大へんなんですよ、耕牧舎こうぼくしゃの飼牛かいうしがね、結核けっかくにかかっていたんですがある日とうとう死しんだんです。ところが病気びょうきのけだものは死んだら棄すてなくちゃいけないでしょう。けれども何せ売れば二、三百にはなるんです。誰だれだって惜おしいとは思います。耕牧舎でもこっそりそれを売っているらしいというんです。行って見て来いってうわけでバキチが剣けんをがちゃつかせ、耕牧舎へやって来たでしょう。耕牧舎でもじっさい困こまってしまったのです。バキチが入って行きましたらいきなり一疋ぴきの牛を叩たたいてあばれさせました。牛もびっくりしましたね、いきなり外に飛とび出してバキチに突ついてかかったんです。
バキチはすっかりまごついて一目散いちもくさんに警察けいさつへ遁にげて帰ったんです。そして署長のところへ行って耕牧舎では牛の皮かわだけはいで肉と骨ほねはたしかに土に埋うめていましたって報告ほうこくしたんです。ところがそれが知れたでしょう。
町のものもみんな笑わらいました。署長もすっかり怒おこってしまいある朝役所やくしょへ出るとすぐいきなりバキチを呼よび出して斯こう申もうし渡わたしたと云いいます。バキチ、きさまもだめなやつだ、よくよくだめなやつなんだ。もう少し見所みどころがあると思ったのに牛につっかかれたくらいで職務しょくむも忘わすれて遁にげるなんてもう今日限きょうかぎり免官めんかんだ。すぐ服ふくをぬげ。と来たでしょう。バキチのほうでももう大抵たいてい巡査じゅんさがあきていたんです。へえ、そうですか、やめましょう。永々ながながお世話せわになりましたって斯こう云いうんです。そしてすぐ服をぬいだはいいんですが実じつはみじめなもんでした。着物きものもシャツとずぼんだけ、もちろん財布さいふもありません。小使室こづかいしつから出されては寝やすむ家さえないんです。その昼間のうちはシャツとズボン下だけで頭をかかえて一日小使室に居いましたが夜になってからとうとう警部補けいぶほにたたき出されてしまいました。バキチはすっかり悄気切しょげきってぶらぶら町を歩きまわってとうとう夜中の十二時にタスケの厩うまやにもぐり込こんだって云うんです。
馬もびっくりしましたぁね、(おいどいつだい、何の用だい。)おどおどしながらはね起おきて身構みがまえをして斯こうバキチに訊きいたってんです。
(誰だれでもないよ、バキチだよ、もと巡査だよ、知らんかい。)バキチが横木よこぎの下の所ところで腹這はらばいのまま云いました。(さあ、知らないよ、バキチだなんて。おれは一向いっこう知らないよ。)と馬が云いました。」「馬がそう云ったんですか。」「馬がそう云ったそうですよ。わっしゃ馬から聞きやした。(おい、情なさけないこと云うじゃないか、おいらはひどく餓うえてんだ。ちっとオートでも振ふる舞まえよ。)ところがタスケの馬も馬でさあ、面白おもしろがってオペラのようにふしをつけて(なかなかやれないわたしのオート。)だなんてやったもんです。バキチもそこはのんきです。やっぱりふしをつけながら、(お呉くれよ、お呉れよ、お前のオートわたしにお呉れよ。)とうなっていました。そこへ丁度ちょうどわたしが通りかかりました。おい、おい、バキチ、あんまりみっともないざまはよせよ。一体馬を盗ぬすもうってのか。
それとも宿やどがなくなって今夜一晩ひとばんとめてもらいたいと云いうのか。バキチが頭を掻かきやした。いやどっちもだ、けれども馬を盗むよりとまるよりまず第一だいいちに、おれは何かが食いたいんだ。(以下原稿空白)
底本:「ポラーノの広場」角川文庫、角川書店
1996(平成8)年6月25日初版発行
底本の親本:「新校本 宮澤賢治全集」筑摩書房
1995(平成7)年5月
入力:ゆうき
校正:noriko saito
2009年8月23日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
茨海小学校
宮沢賢治
私が茨海ばらうみの野原に行ったのは、火山弾かざんだんの手頃てごろな標本を採るためと、それから、あそこに野生の浜茄はまなすが生えているという噂うわさを、確めるためとでした。浜茄はご承知のとおり、海岸に生える植物です。それが、あんな、海から三十里もある山脈を隔へだてた野原などに生えるのは、おかしいとみんな云いうのです。ある人は、新聞に三つの理由をあげて、あの茨海の野原は、すぐ先頃せんころまで海だったということを論じました。それは第一に、その茨海という名前、第二に浜茄の生えていること、第三にあすこの土を嘗なめてみると、たしかに少し鹹しおからいような気がすること、とこう云うのですけれども、私はそんなことはどれも証拠しょうこにならないと思います。
ところが私は、浜茄をとうとう見附みつけませんでした。尤もっとも私が見附けなかったからと云って、浜茄があすこにないというわけには行きません。もし反対に一本でも私に見当ったら、それはあるということの証拠にはなりましょう。ですからやっぱりわからないのです。
火山弾の方は、はじが少し潰つぶれてはいましたが、半日かかってとにかく一つ見附けました。
見附けたのでしたが、それはつい寄附させられてしまいました。誰たれに寄附させられたのかっていうんですか。誰にって校長にですよ。どこの学校? ええ、どこの学校って正直に云っちまいますとね、茨海狐きつね小学校です。愕おどろいてはいけません。実は茨海狐小学校をそのひるすぎすっかり参観して来たのです。そんなに変な顔をしなくてもいいのです。狐にだまされたのとはちがいます。狐にだまされたのなら狐が狐に見えないで女とか坊ぼうさんとかに見えるのでしょう。ところが私のはちゃんと狐を狐に見たのです。狐を狐に見たのが若もしだまされたものならば人を人に見るのも人にだまされたという訳です。
ただ少しおかしいことは人なら小学校もいいけれど狐はどうだろうということですがそれだってあんまりさしつかえありません。まあも少しあとを聞いてごらんなさい。大丈夫だいじょうぶ狐小学校があるということがわかりますから。ただ呉くれ呉ぐれも云って置きますが狐小学校があるといってもそれはみんな私の頭の中にあったと云うので決して偽うそではないのです。偽でない証拠にはちゃんと私がそれを云っているのです。もしみなさんがこれを聞いてその通り考えれば狐小学校はまたあなたにもあるのです。私は時々斯こう云う勝手な野原をひとりで勝手にあるきます。けれども斯う云う旅行をするとあとで大へんつかれます。殊ことにも算術などが大へん下手になるのです。ですから斯う云う旅行のはなしを聞くことはみなさんにも決して差支さしつかえありませんがあんまり度々たびたびうっかり出かけることはいけません。
まあお話をつづけましょう。なあにほんとうはあの茨いばらやすすきの一杯いっぱい生えた野原の中で浜茄などをさがすよりは、初めから狐小学校を参観した方がずうっとよかったのです。朝の一時間目からみていた方が参考にもなり、又また面白おもしろかったのです。私のみたのは今も云いました通り、午ご后ごの授業です。一時から二時までの間の第五時間目です。なかなか狐の小学生には、しっかりした所がありますよ。五時間目だって、一人も厭あきてるものがないんです。参観のもようを、詳くわしくお話しましょうか。きっとあなたにも、大へん参考になります。
浜茄は見附からず、小さな火山弾を一つ採って、私は草に座すわりました。空がきらきらの白いうろこ雲で一杯でした。茨には青い実がたくさんつき、萱かやはもうそろそろ穂ほを出しかけていました。太陽が丁度空の高い処ところにかかっていましたから、もうおひるだということがわかりました。又じっさいお腹なかも空すいていました。そこで私は持って行ったパンの袋ふくろを背嚢はいのうから出して、すぐ喰たべようとしましたが、急に水がほしくなりました。今まで歩いたところには、一とこだって流れも泉もありませんでしたが、もしかも少し向うへ行ったら、とにかく小さな流れにでもぶっつかるかも知れないと考えて、私は背嚢の中に火山弾を入れて、面倒めんどうくさいのでかけ金もかけず、締革しめかわをぶらさげたまませなかにしょい、パンの袋だけ手にもって、又ぶらぶらと向うへ歩いて行きました。
何べんもばらがかきねのようになった所を抜ぬけたり、すすきが栽うえ込こみのように見える間を通ったりして、私は歩きつづけましたが、野原はやっぱり今まで通り、小流れなどはなかったのです。もう仕方ない、この辺でパンをたべてしまおうと立ちどまったとき、私はずうっと向うの方で、ベルの鳴る音を聞きました。それはどこの学校でも鳴らすベルの音のようで、空のあの白いうろこ雲まで響ひびいていたのです。この野原には、学校なんかあるわけはなし、これはきっと俄にわかに立ちどまった為ために、私の頭がしいんと鳴ったのだと考えても見ましたが、どうしても心からさっきの音を疑うわけには行きませんでした。それどころじゃない、こんどは私は、子供らのがやがや云う声を聞きました。それは少しの風のために、ふっとはっきりして来たり、又俄かに遠くなったりしました。けれどもいかにも無邪気むじゃきな子供らしい声が、呼んだり答えたり、勝手にひとり叫さけんだり、わあと笑ったり、その間には太い底力のある大人の声もまじって聞えて来たのです。いかにも何か面白そうなのです。たまらなくなって、私はそっちへ走りました。さるとりいばらにひっかけられたり、窪くぼみにどんと足を踏ふみこんだりしながらも、一生けん命そっちへ走って行きました。
すると野原は、だんだん茨が少くなって、あのすずめのかたびらという、一尺ぐらいのけむりのような穂を出す草があるでしょう、あれがたいへん多くなったのです。私はどしどしその上をかけました。そしたらどう云うわけか俄かに私は棒か何かで足をすくわれたらしくどたっと草に倒たおれました。急いで起きあがって見ますと、私の足はその草のくしゃくしゃもつれた穂にからまっているのです。私はにが笑いをしながら起きあがって又走りました。又ばったりと倒れました。おかしいと思ってよく見ましたら、そのすずめのかたびらの穂は、ただくしゃくしゃにもつれているのじゃなくて、ちゃんと両方から門のように結んであるのです。一種のわなです。その辺を見ますと実にそいつが沢山たくさんつくってあるのです。私はそこでよほど注意して又歩き出しました。なるべく足を横に引きずらず抜きさしするような工合ぐあいにしてそっと歩きましたけれどもまだ二十歩も行かないうちに、又ばったりと倒されてしまいました。それと一緒いっしょに、向うの方で、どっと笑い声が起り、それからわあわあはやすのです。白や茶いろや、狐の子どもらがチョッキだけを着たり半ズボンだけはいたり、たくさんたくさんこっちを見てはやしているのです。首を横にまげて笑っている子、口を尖とがらせてだまっている子、口をあけてそらを向いてはあはあはあはあ云う子、はねあがってはねあがって叫んでいる子、白や茶いろやたくさんいます。ああこれはとうとう狐小学校に来てしまった、いつかどこかで誰たれかに聴きいた茨海ばらうみ狐小学校へ来てしまったと、私はまっ赤になって起きあがって、からだをさすりながら考えました。その時いきなり、狐の生徒らはしいんとなりました。黒のフロックを着た先生が尖った茶いろの口を閉じるでもなし開くでもなし、眼めをじっと据すえて、しずかにやって来るのです。先生といったって、勿論もちろん狐の先生です。耳の尖っていたことが今でもはっきり私の目に残っています。俄かに先生はぴたりと立ちどまりました。
「お前たちは、又わなをこしらえたな。そんなことをして、折角せっかくおいでになったお客さまに、もしものことがあったらどうする。学校の名誉めいよに関するよ。今日はもうお前たちみんな罰ばっしなければならない。」
狐の生徒らはみんな耳を伏ふせたり両手を頭にあげたりしょんぼりうなだれました。先生は私の方へやって来ました。
「ご参観でいらっしゃいますか。」
私はどうせ序ついでだ、どうなるものか参観したいと云ってやろう、今日は日曜なんだけれども、さっきベルも鳴ったし、どうせ狐のことだからまたいい加減の規則もあって、休みだというわけでもないだろうと、ひとりで勝手に考えました。
「ええ、ぜひそう願いたいのです。」
「ご紹介しょうかいはありますか。」
私はふと、いつか幼年画報に出ていたたけしという人の狐小学校のスケッチを思い出しました。
「画家のたけしさんです。」
「紹介状はお持ちですか。」
「紹介状はありませんがたけしさんは今はずいぶん偉えらいですよ。美術学院の会員ですよ。」
狐の先生はいけませんというように手をふりました。
「とにかく、紹介状はお持ちにならないですね。」
「持ちません。」
「よろしゅうございます。こちらへお出いで下さい。ただ今丁度ひるのやすみでございますが、午后の課業をご案内いたします。」
私は先生の狐について行きました。生徒らは小さくなって、私を見送りました。みんなで五十人は居たでしょう。私たちが過ぎてから、みんなそろそろ立ちあがりました。
先生はふっとうしろを振ふりかえりました。そして強く命令しました。
「わなをみんな解け。こんなことをして学校の名誉に関するじゃないか。今に主謀者しゅぼうしゃは処罰するぞ。」
生徒たちはくるくるはねまわってその草わなをみんなほどいて居おりました。
私は向うに、七尺ばかりの高さのきれいな野ばらの垣根かきねを見ました。垣根の長さは十二間はたしかにあったでしょう。そのまん中に入り口があって、中は一段高くなっていました。私は全くそれを垣根だと思っていたのです。ところが先生が
「さあ、どうかお入り下さい。」と叮寧ていねいに云うものですから、その通り一足中へはいりましたら、全く愕おどろいてしまいました。そこは玄関げんかんだったのです。中はきれいに刈かり込んだみじかい芝生しばふになっていてのばらでいろいろしきりがこさえてありました。それに靴くつぬぎもあれば革かわのスリッパもそろえてあり馬の尾を集めてこさえた払子ほっすもちゃんとぶらさがっていました。すぐ上り口に校長室と白い字で書いた黒札くろふだのさがったばらで仕切られた室へやがありそれから廊下ろうかもあります。教員室や教室やみんなばらの木できれいにしきられていました。みんな私たちの小学校と同じです。ただちがうところは教室にも廊下にも窓のないことそれから屋根のないことですが、これは元来屋根がなければ窓はいらない筈はずですからおまけに室の上を白い雲が光って行ったりしますから、実に便利だろうと思いました。校長室の中では、白服の人の動いているのがちらちら見えます。エヘンエヘンと云っているのも聞えます。私はきょろきょろあちこち見まわしていましたら、先生が少し笑って云いました。
「どうぞスリッパをお召めしなすって。只今ただいま校長に申しますから。」
私はそこで、長靴をぬいで、スリッパをはき、背嚢はいのうをおろして手にもちました。その間に先生は校長室へ入って行きましたが、間もなく校長と二人で出て来ました。校長は瘠やせた白い狐で涼すずしそうな麻あさのつめえりでした。もちろん狐の洋服ですからずぼんには尻尾しっぽを入れる袋もついてあります。仕立賃も廉やすくはないと私は思いました。そして大きな近眼鏡をかけその向うの眼はまるで黄金きんいろでした。じっと私を見つめました。それから急いで云いました。
「ようこそいらっしゃいました。さあさあ、どうぞお入り下さい。運動場で生徒が大へん失礼なことをしましたそうで。さあさあ、どうぞお入り下さい。どうぞお入り。」
私は校長について、校長室へ入りました。その立派なこと。卓の上には地球儀ちきゅうぎがおいてありましたしうしろのガラス戸棚とだなには鶏にわとりの骨格やそれからいろいろのわなの標本、剥製はくせいの狼おおかみや、さまざまの鉄砲てっぽうの上手に泥どろでこしらえた模型、猟師りょうしのかぶるみの帽子ぼうし、鳥打帽から何から何まですべて狐の初等教育に必要なくらいのものはみんな備えつけられていました。私は眼を円くして、ここでもきょろきょろするより仕方ありませんでした。そのうち校長はお茶を注ついで私に出しました。見ると紅茶です。ミルクも入れてあるらしいのです。私はすっかり度胆どぎもをぬかれました。
「さあどうか、お掛かけ下さい。」
私はこしかけました。
「ええと、失礼ですがお職業はやはり学事の方ですか。」校長がたずねました。
「ええ、農学校の教師です。」
「本日はおやすみでいらっしゃいますか。」
「はあ、日曜です。」
「なるほどあなたの方では太陽暦れきをお使いになる関係上、日曜日がお休みですな。」
私は一寸ちょっと変な気がしました。
「そうするとおうちの方ではどうなるのですか。」
狐の校長さんは青く光るそらの一ところを見あげてしずかに鬚ひげをひねりながら答えました。
「左様さよう、左様、至極しごくご尤もっともなご質問です。私の方は太陰暦を使う関係上、月曜日が休みです。」
私はすっかり感心しました、この調子ではこの学校は、よほど程度が高いにちがいない、事によると狐の方では、学校は小学校と大学校の二つきりで、或あるいはこの茨海小学校は、中学五年程度まで教えるんじゃないかと気がつきましたので、急いでたずねました。
「いかがですか。こちらの方では大学校へ進む生徒は、ずいぶん沢山ございますか。」
校長さんが得意そうにまるで見当違ちがいの上の方を見ながら答えました。
「へい。実は本年は不思議に実業志望が多ございまして、十三人の卒業生中、十二人まで郷里きょうりに帰って勤労に従事いたして居ります。ただ一人だけ大谷地おおやち大学校の入学試験を受けまして、それがいかにもうまく通りましたので、へい。」
全く私の予想通りでした。
そこへ隣となりの教員室から、黒いチョッキだけ着た、がさがさした茶いろの狐の先生が入って来て私に一礼して云いいました。
「武田金一郎をどう処罰いたしましょう。」
校長は徐おもむろにそちらを向いてそれから私を見ました。
「こちらは第三学年の担任です。このお方は麻生あそう農学校の先生です。」
私はちょっと礼をしました。
「で武田金一郎をどう処罰したらいいかというのだね。お客さまの前だけれども一寸呼んでおいで。」
三学年担任の茶いろの狐の先生は、恭うやうやしく礼をして出て行きました。間もなく青い格子縞こうしじまの短い上着を着た狐の生徒が、今の先生のうしろについてすごすごと入って参りました。
校長は鷹揚おうようにめがねを外はずしました。そしてその武田金一郎という狐の生徒をじっとしばらくの間見てから云いました。
「お前があの草わなを運動場にかけるようにみんなに云いつけたんだね。」
武田金一郎はしゃんとして返事しました。
「そうです。」
「あんなことして悪いと思わないか。」
「今は悪いと思います。けれどもかける時は悪いと思いませんでした。」
「どうして悪いと思わなかった。」
「お客さんを倒たおそうと思ったのじゃなかったからです。」
「どういう考かんがえでかけたのだ。」
「みんなで障碍物しょうがいぶつ競争をやろうと思ったんです。」
「あのわなをかけることを、学校では禁じているのだが、お前はそれを忘れていたのか。」
「覚えていました。」
「そんならどうしてそんなことをしたのだ。こう云う工合ぐあいにお客さまが度々たびたびおいでになる。それに運動場の入口に、あんなものをこしらえて置いて、もしお客さまに万一のことがあったらどうするのだ。お前は学校で禁じているのを覚えていながら、それをするというのはどう云うわけだ。」
「わかりません。」
「わからないだろう。ほんとうはわからないもんだ。それはまあそれでよろしい。お前たちはこのお方がそのわなにつまずいて、お倒れなさったときはやしたそうだが、又私もここで聞いていたが、どうしてそんなことをしたか。」
「わかりません。」
「わからないだろう。全くわからないもんだ。わかったらまさかお前たちはそんなことしないだろうな。では今日の所は、私からよくお客さまにお詫わびを申しあげて置くから、これからよく気をつけなくちゃいけないよ。いいか。もう決して学校で禁じてあることをしてはならんぞ。」
「はい、わかりました。」
「では帰って遊んでよろしい。」校長さんは今度は私に向きました。担任の先生はきちんとまだ立っています。
「只今ただいまのようなわけで、至って無邪気むじゃきなので、決して悪気があって笑ったりしたのではないようでございますから、どうかおゆるしをねがいとう存じます。」
私はもちろんすぐ云いました。
「どう致いたしまして。私こそいきなりおうちの運動場へ飛び込こんで来て、いろいろ失礼を致しました。生徒さん方に笑われるのなら却かえって私は嬉うれしい位です。」
校長さんは眼鏡めがねを拭ふいてかけました。
「いや、ありがとうございます。おい武村君。君からもお礼を申しあげてくれ。」
三年担任の武村先生も一寸私に頭を下げて、それから校長に会釈えしゃくして教員室の方へ出て行きました。
校長さんの狐きつねは下を向いて二三度くんくん云ってから、新らしく紅茶を私に注ついでくれました。そのときベルが鳴りました。午ご后ごの課業のはじまる十分前だったのでしょう。校長さんが向うの黒塗くろぬりの時間表を見ながら云いました。
「午后は第一学年は修身と護身、第二学年は狩猟しゅりょう術、第三学年は食品化学と、こうなっていますがいずれもご参観になりますか。」
「さあみんな拝見いたしたいです。たいへん面白おもしろそうです。今朝けさからあがらなかったのが本当に残念です。」
「いや、いずれ又またおいでを願いましょう。」
「護身というのは修身といっしょになっているのですか。」
「ええ昨年までは別々でやりましたが、却って結果がよくないようです。」
「なるほどそれに狩猟だなんて、ずいぶん高尚こうしょうな学科もおやりですな。私の方ではまあ高等専門学校や大学の林科にそれがあるだけです。」
「ははん、なるほど。けれどもあなたの方の狩猟と、私の方の狩猟とは、内容はまるでちがっていますからな、ははん。あなたの方の狩猟は私の方の護身にはいり、私の方の狩猟は、さあ、狩猟前業はあなたの方の畜産ちくさんにでも入りますかな、まあとにかくその時々でゆっくりご説明いたしましょう。」
この時ベルが又鳴りました。
がやがや物を言う声、それから「気をつけ」や「番号」や「右向け右」や「前へ進め」で狐の生徒は一学級ずつだんだん教室に入ったらしいのです。
それからしばらくたって、どの教室もしいんとなりました。先生たちの太い声が聞えて来ました。
「さあではご案内を致しましょう。」狐の校長さんは賢かしこそうに口を尖とがらして笑いながら椅子いすから立ちあがりました。私はそれについて室へやを出ました。
「はじめに第一学年をご案内いたします。」
校長さんは「第一教室、第一学年、担任者、武井甲吉」と黒い塗札ぬりふだの下った、ばらの壁かべで囲まれた室に入りました。私もついて入りました。そこの先生は私のまだあわない方で実にしゃれたなりをして頭の銀毛などもごく高尚こうしょうなドイツ刈がりに白のモオニングを着て教壇きょうだんに立っていました。もちろん教壇のうしろの茨いばらの壁には黒板もかかり、先生の前にはテーブルがあり、生徒はみなで十五人ばかり、きちんと白い机デスクにこしかけて、講義をきいて居おりました。私がすっかり入って立ったとき、先生は教壇を下りて私たちに礼をしました。それから教壇にのぼって云いました。
「麻生あそう農学校の先生です。さあみんな立って。」
生徒の狐たちはみんなぱっと立ちあがりました。
「ご挨拶あいさつに麻生農学校の校歌を歌うのです。そら、一、二、三、」先生は手を振ふりはじめました。生徒たちは高く高く私の学校の校歌を歌いはじめました。私は全くよろよろして泣き出そうとしました。誰たれだっていきなり茨海ばらうみ狐小学校へ来て自分の学校の校歌を狐の生徒にうたわれて泣き出さないでいられるもんですか。それでも私はこらえてこらえて顔をしかめて泣くのを押おさえました。嬉しかったよりはほんとうに辛つらかったのです。校歌がすみ、先生は一寸ちょっと挨拶して生徒を手まねで座すわらせ、鞭むちをとりました。
黒板には「最高の偽うそは正直なり。」と書いてあり、先生は説明をつづけました。
「そこで、元来偽というのは、いけないものです。いくら上手に偽をついてもだめなのです。賢い人がききますと、ちゃんと見わけがつくのです。それは賢い人たちは、その語ことばのつりあいで、ほんとうかうそかすぐわかり、またその音ですぐわかり、それからそれを云うものの顔やかたちですぐわかります。ですからうそというものは、ほんの一時はうまいように思われることがあっても、必ずまもなくだめになるものです。
そこでこの格言の意味は、もしも誰かが一つこんな工合のうそをついて、こう云う工合にうまくやろうと考えるとします。そのときもしよくその云うことを自分で繰くり返し繰り返しして見ますと、いつの間にか、どうもこれでは向うにわかるようだ、も少しこう云わなくてはいけないというような気がするのです、そこで云いようをすっかり改めて、又それを心の中で繰り返し繰り返しして見ます、やっぱりそれでもいけないようだ、こうしよう、と考えます。それもやっぱりだめなようだ、こうしようと思います。こんな工合にして一生けん命考えて行きますと、とうとうしまいはほんとうのことになってしまうのです。そんならそのほんとうのことを云ったら、実際どうなるかと云うと、実はかえってうまく偽をついたよりは、いいことになる、たとえすぐにはいけないことになったようでも、結局は、結局は、いいことになる。だからこの格言は又
『正直は最良の方便なり』とも云われます。」
先生は黒板へ向いて、前のにならべて今の格言を書きました。
生徒はみんなきちんと手を膝ひざにおいて耳を尖らせて聞いていましたが、この時一斉いっせいにペンをとって黒板の字を書きとりました。
校長は一寸私の顔を見ました。私がどんな風に、今の講義を感じたか、それを知りたいという様子でしたから、私は五六秒眼めを瞑つぶっていかにも感銘かんめいにたえないということを示しました。
先生はみんなの書いてしまう間、両手をせなかにしょってじっとしていましたがみんながばたばた鉛筆えんぴつを置いて先生の方を見始めますと、又講義をつづけました。
「そこで今の『正直は最良の方便』という格言は、ただ私たちがうそをつかないのがいいというだけではなく、又丁度反対の応用もあるのです。それは人間が私たちに偽をつかないのも又最良の方便です。その一例を挙げますとわなです。わなにはいろいろありますけれども、一番こわいのは、いかにもわなのような形をしたわなです。それもごく仕掛しかけの下手なわなです。これを人間の方から云いますと、わなにもいろいろあるけれども、一番狐のよく捕とれるわなは、昔むかしからの狐わなだ、いかにも狐を捕るのだぞというような格好をした、昔からの狐わなだと、斯こう云うわけです。正直は最良の方便、全くこの通りです。」
私は何だか修身にしても変だし頭がぐらぐらして来たのでしたが、この時さっき校長が修身と護身とが今学年から一科目になって、多分その方が結果がいいだろうと云ったことを思い出して、ははあ、なるほどと、うなずきました。
先生は
「武巣たけすさん、立って校長室へ行ってわなの標本を運んで来て下さい。」と云いましたら、一番前の私の近くに居た赤いチョッキを着たかあいらしい狐の生徒が、
「はいっ。」と云って、立って、私たちに一寸挨拶し、それからす早く茨いばらの壁の出口から出て行きました。
先生はその間黙だまって待っていました。生徒も黙っていました。空はその時白い雲で一杯いっぱいになり、太陽はその向うを銀の円鏡のようになって走り、風は吹ふいて来て、その緑いろの壁はところどころゆれました。
武巣という子がまるで息をはあはあして入って来ました。さっき校長室のガラス戸棚とだなの中に入っていた、わなの標本を五つとも持って来たのです。それを先生の机の上に置いてしまうと、その子は席に戻もどり、先生はその一つを手にとりあげました。
「これはアメリカ製でホックスキャッチャーと云います。ニッケル鍍金めっきでこんなにぴかぴか光っています。ここの環わの所へ足を入れるとピチンと環がしまって、もうとれなくなるのです。もちろんこの器械は鎖くさりか何かで太い木にしばり付けてありますから、実際一遍いっぺん足をとられたらもうそれきりです。けれども誰たれだってこんなピカピカした変なものにわざと足を入れては見ないのです。」
狐の生徒たちはどっと笑いました。狐の校長さんも笑いました。狐の先生も笑いました。私も思わず笑いました。このわなの絵は外国でも日本でも種苗しゅびょう目録のおしまいあたりにはきっとついていて、然しかも効力もあるというのにどう云うわけか一寸不思議にも思いました。
この時校長さんは、かくしから時計を出して一寸見ました。そこで私は、これはもうだんだん時間がたつから、次の教室を案内しようかと云うのだろうと思って、ちょっとからだを動かして見せました。校長さんはそこですっと室へやを出ました。私もついて出ました。
「第二教室、第二年級、担任、武池清二郎」とした黒塗りの板の下がった教室に入りました。先生はさっき運動場であった人でした。生徒も立って一ぺんに礼をしました。
先生はすぐ前からの続きを講義しました。
「そこで、澱粉でんぷんと脂肪しぼうと蛋白質たんぱくしつと、この成分の大事なことはよくおわかりになったでしょう。
こんどはどんなたべものに、この三つの成分がどんな工合ぐあいに入っているか、それを云います。凡およそ、食物の中で、滋養じように富みそしておいしく、また見掛けも大へん立派なものは鶏にわとりです。鶏は実際食物中の王と呼ばれる通りです。今鶏の肉の成分の分析表ぶんせきひょうをあげましょう。みなさん帳面へ書いて下さい。
蛋白質は十八ポイント五パアセント、脂肪は九ポイント三パーセント、含水炭素がんすいたんそは一ポイント二パーセントもあるのです。鶏の肉はただこのように滋養に富むばかりでなく消化もたいへんいいのです。殊ことに若い鶏の肉ならば、もうほんとうに軟やわらかでおいしいことと云ったら、」先生は一寸ちょっと唾つばをのみました、「とてもお話ではわかりません。食べたことのある方はおわかりでしょう。」
生徒はしばらくしんとしました。校長さんもじっと床ゆかを見つめて考えています。先生ははんけちを出して奇麗きれいに口のまわりを拭ふいてから又云いました。
「で一般に、この鶏の肉に限らず、鳥の肉には私たちの脳神経を養うに一番大事な燐りんがたくさんあるのです。」
こんなことは女学校の家事の本に書いてあることだ、やっぱり仲々程度が高い、ばかにできないと私は思いました。先生は又つづけます。
「その鶏の卵も大へんいいのです。成分は鶏の肉より蛋白質は少し少く、脂肪は少し多いのです。これは病人もよく使います。それから次は油揚あぶらあげです。油揚は昔は大へん供給が充分じゅうぶんだったのですけれども、今はどうもそんなじゃありません。それで、実はこれは廃すたれた食物であります。成分は蛋白質が二二パアセント、脂肪が十八ポイント七パアセント、含水炭素が零ゼロポイント九パアセントですが、これは只今ただいまではあんまり重要じゃありません。油揚の代りに近頃ちかごろ盛さかんになったのは玉蜀黍とうもろこしです。これはけれども消化はあんまりよくありません。」
「時間がも少しですから、次の教室をご案内いたしましょう。」校長がそっと私にささやきました。そこで私はうなずき校長は先に立って室へやを出ました。
「第三教室は向うの端はしになって居ります。」校長は云いながら廊下ろうかをどんどん戻りました。さっきの第一教室の横を通り玄関げんかんを越こえ校長室と教員室の横を通ったそこが第三教室で、「第三学年 担任者武原久助」と書いてありました。さっきの茶いろの毛のガサガサした先生の教室なのです。狩猟の時間です。
私たちが入って行ったとき、先生も生徒も立って挨拶あいさつしました。それから講義が続きました。
「それで狩猟に、前業と本業と後業とあることはよくわかったろう。前業は養鶏ようけいを奨励しょうれいすること、本業はそれを捕ること、後業はそれを喰たべることと斯こうである。
前業の養鶏奨励の方法は、だんだん詳くわしく述べるつもりであるが、まあその模範もはんとして一例を示そう。先頃せんころ私が茨窪ばらくぼの松林まつばやしを散歩していると、向うから一人の黒い小倉服を着た人間の生徒が、何か大へん考えながらやって来た。私はすぐにその生徒の考えていることがわかったので、いきなり前に飛び出した。
すると向うでは少しびっくりしたらしかったので私はまず斯う云った。
『おい、お前は私が何だか知ってるか。』
するとその生徒が云った。
『お前は狐きつねだろう。』
『そうだ。しかしお前は大へん何か考えて困っているだろう。』
『いいや、なんにも考えていない。』その生徒が云った。その返事が実は大へん私に気に入ったのだ。
『そんなら私はお前の考えていることをあてて見ようか。』
『いいや、いらない。』その生徒が云った。それが又大へん私の気に入った。
『お前は明後日あさっての学芸会で、何を云ったらいいか考えているだろう。』
『うん、実はそうだ。』
『そうか、そんなら教えてやろう。あさってお前は養鶏の必要を云うがいい。百姓ひゃくしょうの家には、こぼれて砂の入った麦や粟あわや、いらない菜っ葉や何か、たくさんあるんだ。又甘藍キャベジや何かには、青むしもたかる。それをみんな鶏に食べさせる。鶏は大悦おおよろこびでそれをたべる。卵もうむ。大へん得だと斯う云うがいい。』
私が云ったら、その生徒は大へん悦んで、厚く礼を述べて行った。きっとあの生徒は学芸会でそれを云ったんだ。するとみんなは勿論もちろんと思って早速養鶏をはじめる。大きな鶏やひよっこや沢山たくさんできる。そこで我々は早速本業にとりかかると斯う云うのだ。」
私は実はこの話を聞いたとき、どうしてもおかしくておかしくてたまりませんでした。その生徒というのは私の学校の二年生なのです。先頃せんころ学芸会があったのでしたが、その時ちゃんと、狐に遭あったことから何から、みんな話していたのです。ただおしまいが少し違ちがって居りました。それはその生徒の話では
「なんだお前は僕に養鶏をすすめて置いて自分がそれを捕ろうというのか。」と云ったら狐は頭をかかえて一目散に遁にげたというのでした。けれどもそれを私は口に出しては云いませんでした。この時丁度、向うで終業のベルが鳴りましたので、先生は、
「今日はここまでにして置きます。」と云って礼をしました。私は校長について校長室に戻りました。校長は又私の茶椀ちゃわんに紅茶をついで云いました。
「ご感想はいかがですか。」
私は答えました。
「正直を云いますと、実は何だか頭がもちゃもちゃしましたのです。」
校長は高く笑いました。
「アッハッハ。それはどなたもそう仰おっしゃいます。時に今日は野原で何かいいものをお見付けですか。」
「ええ、火山弾かざんだんを見附みつけました。ごく不完全です。」
「一寸ちょっと拝見。」
私は仕方なく背嚢はいのうからそれを出しました。校長は手にとってしばらく見てから
「実にいい標本です。いかがです。一つ学校へご寄附きふを願えませんでしょうか。」と云うのです。私は仕方なく、
「ええ、よろしゅうございます。」と答えました。
校長はだまってそれをガラス戸棚とだなにしまいました。
私はもう頭がぐらぐらして居たたまらなくなりました。
すると校長がいきなり、
「ではさよなら。」というのです。そこで私も
「これで失礼致いたします。」と云いながら急いで玄関を出ました。それから走り出しました。
狐の生徒たちが、わあわあ叫さけび、先生たちのそれをとめる太い声がはっきり後ろで聞えました。私は走って走って、茨海ばらうみの野原のいつも行くあたりまで出ました。それからやっと落ち着いて、ゆっくり歩いてうちへ帰ったのです。
で結局のところ、茨海狐小学校では、一体どういう教育方針だか、一向さっぱりわかりません。
正直のところわからないのです。
底本:「注文の多い料理店」新潮文庫、新潮社
1990(平成2)年5月25日発行
1997(平成9)年5月10日17刷
底本の親本:「新修宮沢賢治全集 第九巻」筑摩書房
1979(昭和54)年7月
入力:土屋隆
校正:noriko saito
2006年11月26日作成
2009年7月24日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
葡萄水
宮沢賢治
(一)
耕平は髪も角刈りで、おとなのくせに、今日は朝から口笛などを吹いてゐます。
畑の方の手があいて、こゝ二三日は、西の野原へ、葡萄ぶだうをとりに出られるやうになったからです。
そこで耕平は、うしろのまっ黒戸棚とだなの中から、兵隊の上着を引っぱり出します。
一等卒の上着です。
いつでも野原へ出るときは、きっとこいつを着るのです。
空が光って青いとき、黄いろなすぢの入った兵隊服を着て、大手をふって野原を行くのは、誰たれだっていゝ気持ちです。
耕平だって、もちろんです。大きげんでのっしのっしと、野原を歩いて参ります。
野原の草もいまではよほど硬くなって、茶いろやけむりの穂を出したり、赤い実をむすんだり、中にはいそがしさうに今年のおしまひの小さな花を開いてゐるのもあります。
耕平は二へんも三べんも、大きく息をつきました。
野原の上の空などは、あんまり青くて、光ってうるんで、却かへって気の毒なくらゐです。
その気の毒なそらか、すきとほる風か、それともうしろの畑のへりに立って、玉蜀黍たうもろこしのやうな赤髪を、ぱちゃぱちゃした小さなはだしの子どもか誰か、とにかく斯かう歌ってゐます。
「馬こは、みんな、居なぐなた。
仔っこ馬まもみんな随ついで行いた。
いまでぁ野原もさぁみしんぢゃ、
草ぱどひでりあめばがり。」
実は耕平もこの歌をききました。ききましたから却って手を大きく振って、
「ふん、一向さっぱりさみしぐなぃんぢゃ。」と云いったのです。
野原はさびしくてもさびしくなくても、とにかく日光は明るくて、野葡萄はよく熟してゐます。そのさまざまな草の中を這はって、真っ黒に光って熟してゐます。
そこで耕平は、葡萄をとりはじめました。そして誰でも、野原で一ぺん何かをとりはじめたら、仲々やめはしないものです。ですから耕平もかまはないで置いて、もう大丈夫です。今に晩方また来て見ませう。みなさんもなかなか忙がしいでせうから。
(二)
夕方です。向ふの山は群青ぐんじゃういろのごくおとなしい海鼠なまこのやうによこになり、耕平はせなかいっぱい荷物をしょって、遠くの遠くのあくびのあたりの野原から、だんだん帰って参ります。しょってゐるのはみな野葡萄の実にちがひありません。参ります、参ります。日暮れの草をどしゃどしゃふんで、もうすぐそこに来てゐます。やって来ました。お早う、お早う。そら、
耕平は、一等卒の服を着て、
野原に行って、
葡萄ぶだうをいっぱいとって来た、いゝだらう。
「ふん。あだりまぃさ。あだりまぃのごとだんぢゃ。」耕平が云ってゐます。
さうですとも、けだしあたりまへのことです。一日いっぱい葡萄ばかり見て、葡萄ばかりとって、葡萄ばかり袋へつめこみながら、それで葡萄がめづらしいと云ふのなら、却かへって耕平がいけないのです。
(三)
すっかり夜になりました。耕平のうちには黄いろのラムプがぼんやりついて、馬屋では馬もふんふん云ってゐます。
耕平は、さっき頬ほっぺたの光るくらゐご飯を沢山喰べましたので、まったく嬉うれしがって赤くなって、ふうふう息をつきながら、大きな木鉢きばちへ葡萄のつぶをパチャパチャむしってゐます。
耕平のおかみさんは、ポツンポツンとむしってゐます。
耕平の子は、葡萄の房を振りまはしたり、パチャンと投げたりするだけです。何べん叱しかられてもまたやります。
「おゝ、青あゑい青あゑい、見める見める。」なんて云ってゐます。その黒光りの房の中に、ほんの一つか二つ、小さな青いつぶがまじってゐるのです。
それが半分すきとほり、青くて堅くて、藍晶石らんしゃうせきより奇麗です。あっと、これは失礼、青ぶだうさん、ごめんなさい。コンネテクカット大学校を、最優等で卒業しながら、まだこんなこと私は云ってゐるのですよ。みなさん、私がいけなかったのです。宝石は宝石です。青い葡萄は青い葡萄です。それをくらべたりなんかして全く私がいけないのです。実際コンネテクカット大学校で、私の習ってきたことは、「お前はきょろきょろ、自分と人とをばかりくらべてばかりゐてはならん。」といふことだけです。それで私は卒業したのです。全くどうも私がいけなかったのです。
いや、耕平さん。早く葡萄の粒を、みんな桶をけに入れて、軽く蓋ふたをしておやすみなさい。さよなら。
(四)
あれから丁度、今夜で三日になるのです。
おとなしい耕平のおかみさんが、葡萄のはひったあの桶を、てかてかの板の間のまん中にひっぱり出しました。
子供はまはりをぴょんぴょんとびます。
耕平は今夜も赤く光って、熱ほてってフウフウ息をつきながら、だまって立って見てゐます。
おかみさんは赤漆塗あかうるしぬりの鉢はちの上に笊ざるを置いて、桶をけの中から半分潰つぶれた葡萄ぶだうの粒を、両手に掬すくって、お握りを作るやうな工合ぐあひにしぼりはじめました。
まっ黒な果汁は、見る見る鉢にたまります。
耕平はじっとしばらく見てゐましたが、いきなり高く叫びました。
「ぢゃ、今年ぁ、こいつさ砂糖入れるべな。」
「罰金取らへらんすぢゃ。」
「うんにゃ。税務署に見めっけらへれば、罰金取らへる。見めっけらへなぃば、すっこすっこど葡ぶん萄酒どしゅ呑のむ。」
「なじょして蔵かぐして置ぐあんす。」
「うん。砂糖入れで、すぐに今夜こんにゃ、瓶びんさ詰めでしむべぢゃ。そして落しの中さ置ぐべすさ。瓶、去年なのな、あったたぢゃな。」
「瓶はあらんす。」
「そだら砂糖持ってこ。喜助ぁ先せんどな持って来たけぁぢゃ。」
「あん、あらんす。」
砂糖が来ました。耕平はそれを鉢の汁の中に投げ込んで掻かきまはし、その汁を今度は布の袋にあけました。袋はぴんとはり切ってまっ赤なので、
「ほう、こいづはまるで牛べごの胆きものよだな。」と耕平が云ひました。そのうちにおかみさんは流しでこちこち瓶を洗って持って来ました。
それから二人はせっせと汁を瓶につめて栓せんをしました。麦酒瓶ビールびん二十本ばかり出来あがりました。「特製御葡萄水」といふ、去年のはり紙のあるのもあります。このはり紙はこの辺で共同でこしらへたのです。
これをはって売るのです。さやう、去年はみんなで四十本ばかりこしらへました。もちろん砂糖は入れませんでした。砂糖を入れると酒になるので、罰金です。その四十本のうち、十本ばかりはほかのうちのやうに、一本三十銭づつで町の者に売ってやりましたが、残りは毎晩耕平が、
「うう、渋、うう、酸っかい。湧わぃでるぢゃい。」なんて云ひながら、一本づつだんだんのんでしまったのでした。
さて瓶がずらりと板の間にならんで、まるでキラキラします。おかみさんは足もとの板をはづして床下の落しに入って、そこからこっちに顔を出しました。
耕平は、
「さあ、いゝが。落すな。瓶の脚揃そろぇでげ。」なんて云ひながら、それを一本づつ渡します。
耕平は、潰し葡萄を絞りあげ、
砂糖を加へ、
瓶びんにたくさんつめこんだ。
と斯かう云ふわけです。
(五)
あれから六日たちました。
向ふの山は雪でまっ白です。
草は黄いろに、をととひなどはみぞれさへちょっと降りました。耕平とおかみさんとは家の前で豆を叩たたいて居をりました。
そのひるすぎの三時頃ころ、西の方には縮れた白い雲がひどく光って、どうも何かしらあぶないことが起りさうでした。そこで
「ボッ」といふ爆発のやうな音が、どこからとなく聞えて来ました。耕平は豆を叩く手をやめました。
「ぢゃ、今の音聴だが。」
「何だべぁんす。」
「きっとどの山が噴火ンしたな。秋田の鳥海山だべが。よっぽど遠ぐの方だよだぢゃい。」
「ボッ。」音がまた聞えます。
「はぁでな、又やった。きたいだな。」
「ボッ。」
「をぉがしな。」
「どごだべぁんす。」
「どごでもいがべ。此処こごまで来なぃがべ。」
それからずうっとしばらくたって、又音がします。
それからしばらくしばらくたってから、又聞えます。
その西の空の眼めの痛いほど光る雲か、すきとほる風か、それとも向ふの柏林かしはばやしの中にはひった小さな黒い影法師か、とにかく誰たれかが斯う歌ひました。
「一昨日をどでな、みぃぞれ降ったれば
すゞらんの実ぃ、みんな赤ぐなて、
雪の支度のしろうさぎぁ、
きいらりきいらど歯ぁみがぐ。」
ところが
「ボッ。」
音はまだやみません。
耕平はしばらく馬のやうに耳を立てて、じっとその方角を聴いてゐましたが、俄にはかに飛びあがりました。
「あっ葡萄酒ぶだうしゅだ、葡萄酒だ。葡ん萄酒はじけでるぢゃ。」
家の中へ飛び込んで落しの蓋ふたをとって見ますと、たしかに二十本の葡萄の瓶びんは、大抵はじけて黒い立派な葡萄酒は、落しの底にながれてゐます。
耕平はすっかり怒って、かるわざの股引ももひきのやうに、半分赤く染まった大根を引っぱり出して、いきなり板の間に投げつけます。
さあ、そこでこんどこそは、
耕平が、そっとしまった葡萄酒は
順序たゞしく
みんなはじけてなくなった。
と斯かう云ふわけです。
どうです、今度も耕平はこの前のときのやうに
「ふん、一向さっぱり当あだり前ぁだんぢゃ。」と云ひますか。云ひはしません。参ったのです。
底本:「新修宮沢賢治全集 第十巻」筑摩書房
1979(昭和54)年9月15日初版第1刷発行
1983(昭和58)年4月20日初版第5刷発行
入力:田代信行
校正:今井忠夫
2003年4月2日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
文語詩稿 一百篇
宮沢賢治
目次
母
岩手公園
選挙
崖下の床屋
祭日〔一〕
保線工手
〔南風の頬に酸くして〕
種山ヶ原
ポランの広場
巡業隊
夜
医院
〔沃度ノニホヒフルヒ来ス〕
〔みちべの苔にまどろめば〕
〔二山の瓜を運びて〕
〔けむりは時に丘丘の〕
〔遠く琥珀のいろなして〕
心相
肖像
暁眠
旱倹
〔老いては冬の孔雀守る〕
老農
浮世絵
歯科医院
〔かれ草の雪とけたれば〕
退耕
〔白金環の天末を〕
早春
来々軒
林館開業
コバルト山地
旱害地帯
〔鐘うてば白木のひのき〕
早池峯山巓
社会主事 佐伯正氏
市日
廃坑
副業
紀念写真
塔中秘事
〔われのみみちにたゞしきと〕
朝
〔猥れて嘲笑あざめるはた寒き〕
岩頸列
病技師〔一〕
酸虹
柳沢野
軍事連鎖劇
峡野早春
短夜
〔水楢松にまじらふは〕
硫黄
二月
日の出前
岩手山巓
車中〔二〕
化物丁場
開墾地落上
〔鶯宿はこの月の夜を雪降るらし〕
公子
〔銅鑼と看版 トロンボン〕
〔古き勾当貞斎が〕
涅槃堂
悍馬〔二〕
巨豚
眺望
山躑躅
〔ひかりものすとうなゐごが〕
国土
〔塀のかなたに嘉莵治かも〕
四時
羅紗売
臘月
〔天狗蕈 けとばし了へば〕
牛
〔秘事念仏の大師匠〕〔二〕
〔廐肥をになひていくそたび〕
黄昏
式場
〔翁面 おもてとなして世経るなど〕
氷上
〔うたがふをやめよ〕
電気工夫
〔すゝきすがるゝ丘なみを〕
〔乾かぬ赤きチョークもて〕
〔腐植土のぬかるみよりの照り返し〕
中尊寺〔一〕
嘆願隊
〔一才のアルプ花崗岩みかげを〕
〔小きメリヤス塩の魚〕
〔日本球根商会が〕
庚申
賦役
〔商人ら やみていぶせきわれをあざみ〕
風底
〔雪げの水に涵されし〕
病技師〔二〕
〔西のあをじろがらん洞〕
卒業式
〔燈を紅き町の家より〕
母
雪袴黒くうがちし うなゐの子瓜食はみくれば
風澄めるよもの山はに うづまくや秋のしらくも
その身こそ瓜も欲りせん 齢とし弱わかき母にしあれば
手すさびに紅き萱穂を つみつどへ野をよぎるなれ
岩手公園
「かなた」と老いしタピングは、 杖をはるかにゆびさせど、
東はるかに散乱の、 さびしき銀は声もなし。
なみなす丘はぼうぼうと、 青きりんごの色に暮れ、
大学生のタピングは、 口笛軽く吹きにけり。
老いたるミセスタッピング、 「去年こぞなが姉はこゝにして、
中学生の一組に、 花のことばを教へしか。」
弧光燈アークライトにめくるめき、 羽虫の群のあつまりつ、
川と銀行木のみどり、 まちはしづかにたそがるゝ。
選挙
(もつて二十を贏かち得んや) はじめの駑馬うまをやらふもの
(さらに五票もかたからず) 雪うち噛める次の騎者
(いかにやさらば太兵衛一族まき) その馬弱くまだらなる
(いなうべがはじうべがはじ) 懼るゝ声はそらにあり
崖下の床屋
あかりを外それし古かゞみ、 客あるさまにみまもりて、
唖の子鳴らす空から鋏。
かゞみは映す崖のはな、 ちさき祠に蔓垂れて、
三日月凍る銀斜子ななこ。
沍いてたつ泥をほとほとと、 かまちにけりて支店長、
玻璃戸の冬を入り来る。
のれんをあげて理髪技士、 白き衣をつくろひつ、
弟子の鋏をとりあぐる。
祭日〔一〕
谷権現の祭りとて、 麓に白き幟たち、
むらがり続く丘丘に、 鼓この音ねの数のしどろなる。
頴花はな青じろき稲むしろ、 水路のへりにたゝずみて、
朝の曇りのこんにやくを、 さくさくさくと切りにけり。
保線工手
狸マミの毛皮を耳にはめ、 シャブロの束に指組みて、
うつろふ窓の雪のさま、 黄なるまなこに泛べたり。
雪をおとして立つ鳥に、 妻がけはひのしるければ、
仄かに笑まふたまゆらを、 松は畳めり風のそら。
〔南風の頬に酸くして〕
南風の頬に酸くして、 シェバリエー青し光芒。
天翔る雲のエレキを、 とりも来て蘇しなんや、いざ。
種山ヶ原
春はまだきの朱あけ雲を
アルペン農の汗に燃し
繩と菩提樹皮マダカにうちよそひ
風とひかりにちかひせり
繞る八谷に劈櫪の
いしぶみしげきおのづから
種山ヶ原に燃ゆる火の
なかばは雲に鎖さるゝ
ポランの広場
つめくさ灯ともす 宵の広場
むかしのラルゴを うたひかはし
雲をもどよもし 夜風にわすれて
とりいれまぢかに 歳よ熟うれぬ
組合理事らは 藁のマント
山猫博士は かはのころも
醸せぬさかづき その数しらねば
はるかにめぐりぬ 射手いてや蠍
巡業隊
霜のまひるのはたごやに、 がらすぞうるむ一瓶の、
酒の黄なるをわかちつゝ、 そゞろに錫の笛吹ける。
すがれし大豆まめをつみ累げ、 よぼよぼ馬の過ぎ行くや、
風はのぼりをはためかし、 障子の紙に影刷きぬ。
ひとりかすかに舌打てば、 ひとりは古きらしゃ鞄、
黒きカードの面反おもぞりの、 わびしきものをとりいづる。
さらにはげしく舌打ちて、 長をさぞまなこをそらしぬと、
楽手はさびしだんまりの、 投げの型してまぎらかす。
夜
はたらきまたはいたつきて、 もろ手ほてりに耐へざるは、
おほかた黒の硅板岩礫イキイシを、 にぎりてこそはまどろみき。
医院
陶標春をつめたくて、 水松いちゐも青く冴えそめぬ。
水うら濁る島の苔、 萱屋に玻璃のあえかなる。
瓶をたもちてうなゐらの、 みたりためらひ入りくるや。
神農像に饌けささぐと、 学士はつみぬ蕗の薹。
〔沃度ノニホヒフルヒ来ス〕
沃度ノニホヒフルヒ来ス、 青貝山ノフモト谷、
荒レシ河原ニヒトモトノ、 辛夷ハナ咲キ立チニケリ。
モロビト山ニ入ラントテ、 朝明ヲココニ待チツドヒ、
或イハ鋸ノ目ヲツクリ、 アルハタバコヲノミニケリ。
青キ朝日ハコノトキニ、 ケブリヲノボリユラメケバ、
樹ハサウサウト燃エイデテ、 カナシキマデニヒカリタツ。
カクテアシタハヒルトナリ、 水音イヨヨシゲクシテ、
鳥トキドキニ群レタレド、 ヒトノケハヒハナカリケリ。
雲ハ経紙ノ紺ニ暮レ、 樹ハカグロナル山山ニ、
梢螺鈿ノサマナシテ、 コトトフコロトナリニケリ。
ツカレノ銀ヲクユラシテ、 モロ人谷ヲイデキタリ、
ココニ二タビ口クチソソギ、 セナナル荷ヲバトトノヘヌ。
ソハヒマビマニトリテ来シ、 木ノ芽ノ数ヲトリカハシ、
アルイハ百合ノ五塊タマヲ、 ナガ大母ニ持テトイフ。
ヤガテ高木モ夜トナレバ、 サラニアシタヲ云ヒカハシ、
ヒトビトオノモ松ノ野ヲ、 ワギ家ノカタヘイソギケリ。
〔みちべの苔にまどろめば〕
みちべの苔にまどろめば、 日輪そらにさむくして、
わづかによどむ風くまの、 きみが頬ちかくあるごとし。
まがつびここに塚ありと、 おどろき離かるゝこの森や、
風はみそらに遠くして、 山なみ雪にたゞあえかなる。
〔二山の瓜を運びて〕
二山の瓜を運びて、 舟いだす酒のみの祖ぢ父ぢ。
たなばたの色紙購ふと、 追ひすがる赤髪けのうなゐ。
ま青なる天弧の下を、 きららかに町はめぐりつ。
ここにして集へる川の、 はてしなみ萌ゆるうたかた。
〔けむりは時に丘丘の〕
けむりは時に丘丘の、 栗の赤葉に立ちまどひ、
あるとき黄なるやどり木は、 ひかりて窓をよぎりけり。
(あはれ土耳古玉タキスのそらのいろ、 かしこいづれの天なるや)
(かしこにあらずこゝならず、 われらはしかく習ふのみ。)
(浮屠らも天を云ひ伝へ、 三十三を数ふなり、
上の無色にいたりては、 光、思想を食めるのみ。)
そらのひかりのきはみなく、 ひるのたびぢの遠ければ、
をとめは餓ゑてすべもなく、 胸なる珞たまをゆさぶりぬ。
〔遠く琥珀のいろなして〕
遠く琥珀のいろなして、 春べと見えしこの原は、
枯草くさをひたして雪げ水、 さゞめきしげく奔るなり。
峯には青き雪けむり、 裾は柏の赤ばやし、
雪げの水はきらめきて、 たゞひたすらにまろぶなり。
心相
こころの師とはならんとも、 こころを師とはなさざれと、
いましめ古りしさながらに、 たよりなきこそこゝろなれ。
はじめは潜む蒼穹に、 あはれ鵞王の影供ぞと、
面さへ映えて仰ぎしを、 いまは酸えしておぞましき、
澱粉堆とあざわらひ、
いたゞきすべる雪雲を、 腐くだせし馬鈴薯とさげすみぬ。
肖像
朝のテニスを慨なげかひて、 額は貢たかし 雪の風。
入りて原簿を閲すれば、 その手砒硫の香にけぶる。
暁眠
微けき霜のかけらもて、 西風ひばに鳴りくれば、
街の燈あかりの黄のひとつ、 ふるへて弱く落ちんとす。
そは瞳まみゆらぐ翁面おきなめん、 おもてとなして世をわたる、
かのうらぶれの贋いか物師、 木藤どうがかりの門かどなれや。
写楽が雲母きらを揉み削こそげ、 芭蕉の像にけぶりしつ、
春はちかしとしかすがに、 雪の雲こそかぐろなれ。
ちひさきびやうや失ひし、 あかりまたたくこの門に、
あしたの風はとどろきて、 ひとははかなくなほ眠るらし。
旱倹
雲の鎖やむら立ちや、 森はた森のしろけむり、
鳥はさながら禍津日を、 はなるとばかり群れ去りぬ。
野を野のかぎり旱割れ田の、 白き空穂のなかにして、
術をもしらに家長たち、 むなしく風をみまもりぬ。
〔老いては冬の孔雀守る〕
老いては冬の孔雀守る、 蒲の脛巾はばきとかはごろも、
園の広場の午后二時は、 湯管くだのむせびたゞほのか。
あるいはくらみまた燃えて、 降りくる雪の縞なすは、
さは遠からぬ雲影の、 日を越し行くに外ならず。
老農
火雲むらがり翔とべば、 そのまなこはばみてうつろ。
火雲あつまり去れば、 麦の束遠く散り映う。
浮世絵
ましろなる塔の地階に、 さくらばなけむりかざせば、
やるせなみプジェー神父は、 とりいでぬにせの赤富士。
青瓊ぬ玉かゞやく天に、 れいろうの瞳をこらし、
これはこれ悪業あく乎か栄光さかえ乎か、 かぎすます北斎の雪。
歯科医院
ま夏は梅の枝青く、 風なき窓を往く蟻や、
碧空そらの反射のなかにして、 うつつにめぐる鑿ぐるま。
浄き衣せしたはれめの、 ソーファによりてまどろめる、
はてもしらねば磁気嵐、 かぼそき肩ををののかす。
〔かれ草の雪とけたれば〕
かれ草の雪とけたれば
裾野はゆめのごとくなり
みじかきマント肩はねて
濁酒をさぐる税務吏や
はた兄弟の馬喰の
鶯いろによそほへる
さては「陰気の狼」と
あだなをもてる三百も
みな恍惚とのぞみゐる
退耕
ものなべてうち訝しみ、 こゑ粗き朋らとありて、
黄の上着ちぎるゝまゝに、 栗の花降りそめにけり。
演奏会リサイタルせんとのしらせ、 いでなんにはや身ふさはず、
豚ゐのこはも金毛となりて、 はてしらず西日に駈ける。
〔白金環の天末を〕
白金環の天末を、 みなかみ遠くめぐらしつ、
大煙突はひさびさに、 くろきけむりをあげにけり。
けむり停まるみぞれ雲、 峡を覆ひてひくければ、
大工業の光景さまなりと、 技師も出でたち仰ぎけり。
早春
黒雲峡を乱れ飛び 技師ら亜炭の火に寄りぬ
げにもひとびと祟むるは 青き Gossan 銅の脈
わが索むるはまことのことば
雨の中なる真言なり
来々軒
浙江の林光文は、 かゞやかにまなこ瞠き、
そが弟子の足をゆびさし、 凛としてみじろぎもせず。
ちゞれ雲西に傷みて、 いささかの粉雪ふりしき、
警察のスレートも暮れ、 売り出しの旗もわびしき。
むくつけき犬の入り来て、 ふつふつと釜はたぎれど、
額ぬか青き林光文は、 そばだちてまじろぎもせず。
もろともに凍れるごとく、 もろともに刻めるごとく、
雪しろきまちにしたがひ、 たそがれの雲にさからふ。
林館開業
凝灰岩タフもて畳み杉植ゑて、 麗姝六七なまめかし、
南銀河と野の黒に、 その〓(「片+戸/甫」)々をひらきたり。
数寄すきの光壁くわうへき更たけて、 千の鱗翅と鞘翅目、
直翅の輩はきたれども、 公子訪へるはあらざりき。
コバルト山地
なべて吹雪のたえまより、 はたしらくものきれまより、
コバルト山地山肌の、 ひらめき酸えてまた青き。
旱害地帯
多くは業にしたがひて 指うちやぶれ眉くらき
学びの児らの群なりき
花と侏儒とを語れども 刻めるごとく眉くらき
稔らぬ土の児らなりき
……村に県あがたにかの児らの 二百とすれば四万人
四百とすれば九万人……
ふりさけ見ればそのあたり 藍暮れそむる松むらと
かじろき雪のけむりのみ
〔鐘うてば白木のひのき〕
鐘うてば白木のひのき、 ひかりぐもそらをはせ交ふ。
凍えしやみどりの縮葉甘藍ケール、 県視学はかなきものを。
早池峯山巓
石絨アスベスト脈なまぬるみ、 苔しろきさが巌にして、
いはかゞみひそかに熟し、 ブリューベル露はひかりぬ。
八重の雲遠くたゝへて、 西東はてをしらねば、
白堊紀の古きわだつみ、 なほこゝにありわぶごとし。
社会主事 佐伯正氏
群れてかゞやく辛夷花樹マグノリア、 雪しろたゝくねこやなぎ、
風は明るしこの郷さとの、 士ひとはそゞろに吝やぶさけき。
まんさんとして漂へば、 水いろあはき日曜どんたくの、
馬を相する漢子をのこらは、 こなたにまみを凝すなり。
市日
丹藤タンドに越ゆるみかげ尾根、 うつろひかればいと近し。
地蔵菩薩のすがたして、 栗を食たうぶる童わらはべと、
縞の粗麻布ジユートの胸しぼり、 鏡欲りするその姉と。
丹藤に越ゆる尾根の上に、 なまこの雲ぞうかぶなり。
廃坑
春ちかけれど坑々の、 祠は荒れて天霧し、
事務所飯場もおしなべて、 鳥の宿りとかはりけり。
みちをながるゝ雪代に、 銹びしナイフをとりいでつ、
しばし閲してまもりびと、 さびしく水をはねこゆる。
副業
雨降りしぶくひるすぎを、 青きさゝげの籠とりて、
巨利を獲るてふ副業の、 銀毛兎に餌すなり。
兎はつひにつぐのはね、 ひとは頬あかく美しければ、
べつ甲ゴムの長靴や、 緑のシャツも着くるなり。
紀念写真
学生壇を並び立ち、 教授助教授みな座して、
つめたき風の聖餐を、 かしこみ呼ぶと見えにけり。
(あな虹立てり降るべしや)
(さなりかしこはしぐるらし)
……あな虹立てり降るべしや……
……さなりかしこはしぐるらし……
写真師台を見まはして、 ひとりに面をあげしめぬ。
時しもあれやさんとして、 身を顫はする学の長をさ、
雪刷く山の目もあやに、 たゞさんとして身を顫ふ。
……それをののかんそのことの、 ゆゑはにはかに推し得ね、
大礼服にかくばかり、 美しき効果をなさんこと、
いづちの邦の文献か、 よく録しつるものあらん……
しかも手練てなれの写真師が、 三秒ひらく大レンズ、
千の瞳のおのおのに、 朝の虹こそ宿りけれ。
塔中秘事
雪ふかきまぐさのはたけ、 玉蜀黍きみ畑漂雪フキは奔りて、
丘裾の脱穀塔を、 ぼうぼうとひらめき被ふ。
歓喜天そらやよぎりし、 そが青き天あめの窓より、
なにごとか女のわらひ、 栗鼠のごと軋りふるへる。
〔われのみみちにたゞしきと〕
われのみみちにたゞしきと、 ちちのいかりをあざわらひ、
ははのなげきをさげすみて、 さこそは得つるやまひゆゑ、
こゑはむなしく息あへぎ、 春は来れども日に三たび、
あせうちながしのたうてば、 すがたばかりは録されし、
下品ざんげのさまなせり。
朝
旱割れそめにし稲沼に、 いまころころと水鳴りて、
待宵草に置く露も、 睡たき風に萎むなり。
鬼げし風の襖子あをし着て、 児ら高らかに歌すれば、
遠き讒誣の傷あとも、 緑青いろにひかるなり。
〔猥れて嘲笑あざめるはた寒き〕
猥れて嘲笑あざめるはた寒き、 凶つのまみをはらはんと
かへさまた経るしろあとの、 天は遷ろふ火の鱗。
つめたき西の風きたり、 あららにひとの秘呪とりて、
粟の垂穂をうちみだし、 すすきを紅く燿かがやかす。
岩頸列
西は箱ヶと毒ドグヶ森、 椀コ、南昌、東根の、
古き岩頸ネツクの一列に、 氷霧あえかのまひるかな。
からくみやこにたどりける、 芝雀は旅をものがたり、
「その小屋掛けのうしろには、 寒げなる山によきによきと、
立ちし」とばかり口つぐみ、 とみにわらひにまぎらして、
渋茶をしげにのみしてふ、 そのことまことうべなれや。
山よほのぼのひらめきて、 わびしき雲をふりはらへ、
その雪尾根をかゞやかし、 野面のうれひを燃し了おほせ。
病技師〔一〕
こよひの闇はあたたかし、 風のなかにてなかんなど、
ステッキひけりにせものの、 黒のステッキまたひけり。
蝕む胸をまぎらひて、 こぼと鳴り行く水のはた、
くらき炭素の燈ひに照りて、 飢饉けかつ供養の巨石おほいし並なめり。
酸虹
鵞黄の柳いくそたび、 窓を掃ふと出でたちて、
片頬むなしき郡長、 酸えたる虹をわらふなり。
柳沢野
焼けのなだらを雲はせて、 海鼠のにほひいちじるき。
うれひて蒼き柏ゆゑ、 馬は黒藻に飾らるゝ。
軍事連鎖劇
キネオラマ、 寒天光のたゞなかに、 ぴたと煙草をなげうちし、
上等兵の袖の上、 また背景の暁あけぞらを、 雲どしどしと飛びにけり。
そのとき角のせんたくや、 まつたくもつて泪をながし、
やがてほそぼそなみだかわき、 すがめひからせ、 トンビのえりを直したりけり。
峡野早春
夜見来よみこの川のくらくして、 斑雪はだれしづかにけむりだつ。
二すぢ白き日のひかり、 ややになまめく笹のいろ。
稔らぬなげきいまさらに、 春をのぞみて深めるを。
雲はまばゆき墨と銀、 波羅蜜山の松を越す。
短夜
屋台を引きて帰りくる、 目あかし町の夜なかすぎ、
うつは数ふるそのひまに、 もやは浅葱とかはりけり。
みづから塗れる伯林青べれんすの、 むらをさびしく苦笑ひ、
胡桃覆へる石屋根に、 いまぞねむれと入り行きぬ。
〔水楢松にまじらふは〕
「水楢松にまじらふは、 クロスワードのすがたかな。」
誰かやさしくもの云ひて、 いらへはなくて風吹けり。
「かしこに立てる楢の木は、 片枝青くしげりして、
パンの神にもふさはしき。」 声いらだちてさらに云ふ。
「かのパスを見よ葉桜の、 列は氷雲に浮きいでて、
なが師も説かん順列を、 緑の毬に示したり。」
しばしむなしく風ふきて、 声はさびしく吐息しぬ。
「こたび県の負債せる、 われがとがにはあらざるを。」
硫黄
猛しき現場監督の、 こたびも姿あらずてふ、
元山あたり白雲の、 澱みて朝となりにけり。
青き朝日にふかぶかと、 小馬ポニーうなだれ汗すれば、
硫黄は歪み鳴りながら、 か黒き貨車に移さるゝ。
二月
みなかみにふとひらめくは、 月魄の尾根や過ぎけん。
橋の燈ひも顫ひ落ちよと、 まだき吹くみなみ風かな。
あゝ梵の聖衆を遠み、 たよりなく春は来くらしを。
電線の喚びの底を、 うちどもり水はながるゝ。
日の出前
学校は、 稗と粟との野末にて、 朝の黄雲に濯はれてあり。
学校の、 ガラス片ひらごとかゞやきて、 あるはうつろのごとくなりけり。
岩手山巓
外輪山の夜明け方、 息吹きも白み競ひ立ち、
三十三の石神に、 米よねを注ぎて奔り行く。
雲のわだつみ洞なして、 青野うるうる川湧けば、
あなや春日のおん帯と、 もろびと立ちてをろがみぬ。
車中〔二〕
稜堀山の巌の稜、 一木きを宙に旋るころ
まなじり深き伯楽はくらくは、 しんぶんをこそひろげたれ。
地平は雪と藍の松、 氷を着るは七時雨、
ばらのむすめはくつろぎて、 けいとのまりをとりいでぬ。
化物丁場
すなどりびとのかたちして、 つるはしふるふ山かげの、
化物丁場しみじみと、 水湧きいでて春寒き。
峡のけむりのくらければ、 山はに円く白きもの、
おそらくそれぞ日ならんと、 親方ボスもさびしく仰ぎけり。
開墾地落上
白髪かざして高清は、 ブロージットと云へるなり。
松の岩頸 春の雲、 コップに小く映るなり。
ゲメンゲラーゲさながらを、 焦げ木はかつとにほふなり。
額を拍ちて高清は、 また鶯を聴けるなり。
〔鶯宿はこの月の夜を雪降るらし〕
鶯宿はこの月の夜を雪降るらし。
鶯宿はこの月の夜を雪降るらし、 黒雲そこにてたゞ乱れたり。
七つ森の雪にうづみしひとつなり、 けむりの下を逼りくるもの。
月の下なる七つ森のそのひとつなり、 かすかに雪の皺たゝむもの。
月をうけし七つ森のはてのひとつなり、 さびしき谷をうちいだくもの。
月の下なる七つ森のその三つなり、 小松まばらに雪を着るもの。
月の下なる七つ森のその二つなり、 オリオンと白き雲とをいたゞけるもの。
七つ森の二つがなかのひとつなり、 鉱石かねなど掘りしあとのあるもの。
月の下なる七つ森のなかの一つなり、 雪白々と裾を引くもの。
月の下なる七つ森のその三つなり、 白々として起伏するもの。
七つ森の三つがなかの一つなり、 貝のぼたんをあまた噴くもの。
月の下なる七つ森のはての一つなり、 けはしく白く稜立てるもの。
稜立てる七つ森のそのはてのもの、 旋り了りてまこと明るし。
公子
桐群に臘の花洽ち、 雲ははや夏を鋳そめぬ。
熱はてし身をあざらけく、 軟風のきみにかぐへる。
しかもあれ師はいましめて、 点竄の術得よといふ。
桐の花むらさきに燃え、 夏の雲遠くながるゝ。
〔銅鑼と看版 トロンボン〕
銅鑼と看版 トロンボン、 孤光燈アークライトの秋風に、
芸を了りてチャリネの子、 その影小くやすらひぬ。
得も入らざりし村の児ら、 叔父また父の肩にして、
乞ふわが栗を喰たうべよと、 泳ぐがごとく競ひ来る。
〔古き勾当貞斎が〕
古き勾当貞斎が、 いしぶみ低く垂れ覆ひ、
雪の楓は暮れぞらに、 ひかり妖しく狎れにけり。
連れて翔けこしむらすゞめ、 たまゆらりうと羽はりて、
沈むや宙をたちまちに、 りうと羽はり去りにけり。
涅槃堂
烏らの羽音重げに、 雪はなほ降りやまぬらし。
わがみぬち火はなほ然へて、 しんしんと堂は埋るゝ。
風鳴りて松のさざめき、 またしばし飛びかふ鳥や。
雪の山また雪の丘、 五輪塔 数をしらずも。
悍馬〔二〕
廐肥こえをはらひてその馬の、 まなこは変る紅べにの竜、
けいけい碧きびいどろの、 天をあがきてとらんとす。
黝き菅藻の袍はねて、 叩きそだたく封介に、
雲ののろしはとゞろきて、 こぶしの花もけむるなり。
巨豚
巨豚ヨークシャ銅の日に、 金毛となりてかけ去れば、
棒をかざして髪ひかり、 追ふや里長のまなむすめ。
日本里長森を出で、 小手をかざして刻を見る、
鬚むしやむしやと物喰むや、 麻布も青くけぶるなり。
日本の国のみつぎとり、 里長を追ひて出で来り、
えりをひらきてはたはたと、 紙の扇をひらめかす。
巨豚ヨークシャ銅の日を、 こまのごとくにかたむきて、
旋れば降くだつ栗の花、 消ゆる里長のまなむすめ。
眺望
雲環かくるかの峯は、 古生諸層をつらぬきて
侏羅紀に凝りし塩岩の、 蛇紋化せしと知られたり。
青き陽遠くなまめきて、 右に亙せる高原は、
花崗閃緑 削剥の、 時代は諸もろに論あげつらふ。
ま白き波をながしくる、 かの峡川と北上は、
かたみに時を異にして、 ともに一度老いしなれ。
砂壌かなたに受くるもの、 多くは酸えず燐多く
洪積台の埴土壌土はにひぢと、 植物群フロラおのづとわかたれぬ。
山躑躅
こはやまつつじ丘丘の、 栗また楢にまじはりて、 熱き日ざしに咲きほこる。
なんたる冴えぬなが紅ぞ、 朱もひなびては酸えはてし、 紅土ラテライトにもまぎるなり。
いざうちわたす銀の風、 無色の風とまぐはへよ、 世紀の末の児らのため。
さは云へまことやまつつじ、 日影くもりて丘ぬるみ、 ねむたきひるはかくてやすけき。
〔ひかりものすとうなゐごが〕
ひかりものすとうなゐごが、 ひそにすがりてゆびさせる、
そは高甲の水車場の、 こなにまぶれしそのあるじ、
にはかに咳し身を折りて、 水こぼこぼとながれたる、
よるの胡桃の樹をはなれ、 肩つゝましくすぼめつゝ、
古りたる沼をさながらの、 西の微光にあゆみ去るなり。
国土
青き草山雑木山、 はた松森と岩の鐘、
ありともわかぬ襞ごとに、 白雲よどみかゞやきぬ。
一石一字をろがみて、 そのかみひそにうづめけん、
寿量の品は神さびて、 みねにそのをに鎮まりぬ。
〔塀のかなたに嘉莵治かも〕
塀のかなたに嘉莵治かも、 ピアノぽろろと弾きたれば、
一、あかきひのきのさなかより、 春のはむしらをどりいづ。
二、あかつちいけにかゞまりて、 烏にごりの水のめり。
あはれつたなきソプラノは、 ゆふべの雲にうちふるひ、
灰まきびとはひらめきて、 桐のはたけを出できたる。
四時
時しも岩手軽鉄の、 待合室の古時計、
つまづきながら四時うてば、 助役たばこを吸ひやめぬ。
時しも赭きひのきより、 農学生ら奔せいでて、
雪の紳士のはなづらに、 雪のつぶてをなげにけり。
時しも土手のかなたなる、 郡役所には議員たち、
視察の件を可決して、 はたはたと手をうちにけり。
時しも老いし小使は、 豚にゑさかふバケツして、
農学校の窓下を、 足なづみつゝ過ぎしなれ。
羅紗売
バビロニ柳掃ひしと、 あゆみをとめし羅紗売りは、
つるべをとりてやゝしばし、 みなみの風に息づきぬ。
しらしら醸す天の川、 はてなく翔ける夜の鳥、
かすかに銭を鳴らしつゝ、 ひとは水み繩を繰りあぐる。
臘月
みふゆの火すばるを高み、 のど嗽ぎあるじ眠れば、
千キロの氷をになひ、 かうかうと水車はめぐる。
〔天狗蕈 けとばし了へば〕
天狗蕈、けとばし了へば、
親方よ、
朝餉とせずや、こゝな苔むしろ。
……りんと引け、
りんと引けかし。
+二八!
その標うちてテープをさめ来!……
山の雲に、ラムネ湧くらし、
親方よ、
雨の中にていつぱいやらずや。
牛
そは一ぴきのエーシャ牛、 夜の地靄とかれ草に、 角をこすりてたはむるゝ。
窒素工場の火の映えは、 層雲列を赤く焦き、
鈍き砂丘のかなたには、 海わりわりとうち顫ふ、
さもあらばあれ啜りても、 なほ啜り得ん黄銅の
月のあかりのそのゆゑに、 こたびは牛は角をもて、
柵を叩きてたはむるゝ。
〔秘事念仏の大師匠〕〔二〕
秘事念仏の大師匠、 元信斎は妻子もて、
北上ぎしの南風、 けふぞ陸穂を播きつくる。
雲紫に日は熟れて、 青らみそめし野いばらや、
川は川とてひたすらに、 八功徳水ながしけり。
たまたまその子口あきて、 楊の梢に見とるれば、
元信斎は歯軋りて、 石を発止と投げつくる。
蒼蠅ひかりめぐらかし、 練肥ダラを捧げてその妻は、
たゞ恩人ぞ導師ぞと、 おのが夫つまをば拝むなり。
〔廐肥をになひていくそたび〕
廐肥をになひていくそたび、 まなつをけぶる沖積層アリビーム、
水の岸なる新墾畑にひばりに、 往来もひるとなりにけり。
エナメルの雲 鳥の声、 唐黍焼きはみてやすらへば、
熱く苦しきその業に、 遠き情事のおもひあり。
黄昏
花さけるねむの林を、 さうさうと身もかはたれつ、
声ほそく唱歌うたひて、 屠殺士の加吉さまよふ。
いづくよりか烏の尾ばね、 ひるがへりさと堕ちくれば、
黄なる雲いまはたへずと、 オクターヴォしりぞきうたふ。
式場
氷の雫のいばらを、 液量計の雪に盛り、
鐘を鳴らせばたちまちに、 部長訓辞をなせるなり。
〔翁面 おもてとなして世経るなど〕
翁面、 おもてとなして世経るなど、 ひとをあざみしそのひまに、
やみほゝけたれつかれたれ、 われは三十ぢをなかばにて、
緊那羅面とはなりにけらしな。
氷上
月のたはむれ薫くゆるころ、 氷は冴えてをちこちに、 さゞめきしげくなりにけり。
をさけび走る町のこら、 高張白くつらねたる、 明治女塾の舎生たち。
さてはにはかに現はれて、 ひたすらうしろすべりする、 黒き毛剃の庶務課長。
死火山の列雪青く、 よき貴人の死蝋とも、 星の蜘蛛来て網はけり。
〔うたがふをやめよ〕
うたがふをやめよ、 林は寒くして、
いささかの雪凍りしき、 根まがり杉ものびてゆるゝを。
胸張りて立てよ、 林の雪のうへ、
青き杉葉の落ちちりて、 空にはあまた烏なけるを。
そらふかく息せよ、 杉のうれたかみ、
烏いくむれあらそへば、 氷霧ぞさつとひかり落つるを。
電気工夫
(直き時計はさま頑かたく、 憎ぞうに鍛へし瞳めは強し)
さはあれ攀ぢる電塔の、 四方に辛夷の花深き。
南風かけつ光の網織れば、 ごろろと鳴らす碍子群、
艸火のなかにまじらひて、 蹄のたぐひけぶるらし。
〔すゝきすがるゝ丘なみを〕
すゝきすがるゝ丘なみを、 にはかにわたる南かぜ、
窪てふ窪はたちまちに、 つめたき渦を噴きあげて、
古きミネルヴァ神殿の、 廃址のさまをなしたれば、
ゲートルきりと頬かむりの、 闘士嘉吉もしばらくは、
萱のつぼけを負ひやめて、 面あやしく立ちにけり。
〔乾かぬ赤きチョークもて〕
乾かぬ赤きチョークもて、 文を抹して教頭は、
いらかを覆ふ黒雲を、 めがねうつろに息づきぬ。
さびしきすさびするゆゑに、 ぬかほの青き善吉ら、
そらの輻射の六月を、 声なく惨と仰ぎたれ。
〔腐植土のぬかるみよりの照り返し〕
腐植土のぬかるみよりの照り返し、 材木の上のちひさき露店。
腐植土のぬかるみよりの照り返しに、 二銭の鏡あまたならべぬ。
腐植土のぬかるみよりの照り返しに、 すがめの子一人りんと立ちたり。
よく掃除せしラムプをもちて腐植土の、 ぬかるみを駅夫大股に行く。
風ふきて広場広場のたまり水、 いちめんゆれてさゞめきにけり。
こはいかに赤きずぼんに毛皮など、 春木ながしの人のいちれつ。
なめげに見高らかに云ひ木流しら、 鳶をかつぎて過ぎ行きにけり。
列すぎてまた風ふきてぬかり水、 白き西日にさゞめきたてり。
西根よりみめよき女きたりしと、 角の宿屋に眼がひかるなり。
かつきりと額を剃りしすがめの子、 しきりに立ちて栗をたべたり。
腐植土のぬかるみよりの照り返しに 二銭の鏡売るゝともなし。
中尊寺〔一〕
七重の舎利の小塔に、 蓋なすや緑の燐光。
大盗は銀のかたびら、 をろがむとまづ膝だてば、
赭のまなこたゞつぶらにて、 もろの肱映えかゞやけり。
手触れ得ず十字燐光、 大盗は礼して没きゆる。
嘆願隊
やがて四時ともなりなんを、 当主いまだに放たれず、
外の面は冬のむらがらす、 山の片面のかゞやける。
二羽の烏の争ひて、 さつと落ち入る杉ばやし、
このとき大気飽和して、 霧は氷と結びけり。
〔一才のアルプ花崗岩みかげを〕
一才のアルプ花崗岩みかげを、 おのも積む孤輪車ひとつわぐるま。
(山はみな湯噴きいでしぞ) 髪赭きわらべのひとり。
(われらみな主ぬしとならんぞ) みなかみはたがねうつ音。
おぞの蟇みちをよぎりて、 にごり谷けぶりは白し。
〔小きメリヤス塩の魚〕
小きメリヤス塩の魚、 藻草花菓子烏賊の脳、
雲の縮れの重りきて、 風すさまじく歳暮るゝ。
はかなきかなや夕さりを、 なほふかぶかと物おもひ、
街をうづめて行きまどふ、 みのらぬ村の家長たち。
〔日本球根商会が〕
日本球根商会が、 よきものなりと販りこせば、
いたつきびとは窓ごとに、 春きたらばとねがひけり。
夜すがら温き春雨に、 風信子華の十六は、
黒き葡萄と噴きいでて、 雫かゞやきむらがりぬ。
さもまがつびのすがたして、 あまりにくらきいろなれば、
朝焼けうつすいちいちの、 窓はむなしくとざされつ。
七面鳥はさまよひて、 ゴブルゴブルとあげつらひ、
小き看護は窓に来て、 あなやなにぞといぶかりぬ。
庚申
歳に七度はた五つ、 庚の申を重ぬれば、
稔らぬ秋を恐かしこみて、 家長ら塚を理をさめにき。
汗に蝕むまなこゆゑ、 昴ばうの鎖の火の数を、
七つと五つあるはたゞ、 一つの雲と仰ぎ見き。
賦役
みねの雪よりいくそたび、 風はあをあを崩れ来て、
萌えし柏をとゞろかし、 きみかげさうを軋らしむ。
おのれと影とたゞふたり、 あれと云はれし業なれば、
ひねもす白き眼して、 放牧のがひの柵をつくろひぬ。
〔商人ら やみていぶせきわれをあざみ〕
商人ら、やみていぶせきわれをあざみ、
川ははるかの峡に鳴る。
ましろきそらの蔓むらに、 雨をいとなむみそさゞい、
黒き砂糖の樽かげを、 ひそかにわたる昼の猫。
病みに恥つむこの郷を、
つめたくすぐる春の風かな。
風底
雪けむり閃めき過ぎて、 ひとしばし汗をぬぐへば、
布づつみになふ時計の、 リリリリとひゞきふるへる。
〔雪げの水に涵されし〕
雪げの水に涵されし、 御料草地のどての上、
犬の皮着てたゞひとり、 菫外線をい行くもの。
ひかりとゞろく雪代の、 土手のきれ目をせな円み、
兎のごとく跳ねたるは、 かの耳しひの牧夫なるらん。
病技師〔二〕
あへぎてくれば丘のひら、 地平をのぞむ天気輪、
白き手巾を草にして、 をとめらみたりまどゐしき。
大寺のみちをこととへど、 いらへず肩をすくむるは、
はやくも死相われにありやと、 粛涼をちの雲を見ぬ。
〔西のあをじろがらん洞〕
西のあをじろがらん洞、 一むらゆげをはきだせば、
ゆげはひろがり環をつくり、 雪のお山を越し申す。
わさび田ここになさんとて、 枯草原にこしおろし、
たばこを吸へばこの泉、 たゞごろごろと鳴り申す。
それわさび田に害あるもの、 一には野馬 二には蟹、
三には視察、四には税、 五は大更の酒屋なり。
山を越したる雲かげは、 雪をそゞろにすべりおり、
やがては藍の松こめや、 虎の斑形を越え申す。
卒業式
三宝または水差しなど、 たとへいくたび紅白の、
甘き澱みに運ぶとも、 鐘鳴るまではカラぬるませじと、
うなじに副へし半巾は、 慈鎮和くわ尚のごとくなり。
〔燈を紅き町の家より〕
燈を紅き町の家より、 いつはりの電話来れば、
(うみべより売られしその子) あわたゞし白木のひのき。
雪の面に低く霧して、 桑の群影ひくなかを、
あゝ鈍びし二重のマント、 銅版の紙片をおもふ。
底本:「新修宮沢賢治全集 第六巻」筑摩書房
1980(昭和55)年2月15日初版第1刷発行
※底本は、1作品が1ページにおさまるように行間を調整している。ただし、このファイルでは、作品の末尾にそのつど
と書き込むことはせず、頁の変わり目ごとに3行をあけた。
※底本は、「作者専用の詩稿用紙に書かれた詩篇を収録し」、多くの詩篇で、詩稿の形式に合わせて上下に二句を配置し、字間スペースなどを調整して下の句の頭が横にそろうように組んである。この形を取っている詩篇に関しては、本ファイルでも、句間を最低全角2字空けとし、下の句の頭を横にそろえた。
入力:junk
校正:今井忠夫
2003年9月4日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
文語詩稿 五十篇
宮沢賢治
いたつきてゆめみなやみし、 (冬なりき)誰ともしらず、
そのかみの高麗の軍楽、 うち鼓して過ぎれるありき。
その線の工事了りて、 あるものはみちにさらばひ、
あるものは火をはなつてふ、 かくてまた冬はきたりぬ。
水と濃きなだれの風や、 むら鳥のあやなすすだき、
アスティルベきらめく露と、 ひるがへる温石の門。
海浸す日より棲みゐて、 たゝかひにやぶれし神の、
二かしら猛きすがたを、 青々と行衛しられず。
雪うづまきて日は温き、 萱のなかなる荼毘壇に、
県議院殿大居士の、 柩はしづとおろされぬ。
紫綾の大法衣、 逆光線に流れしめ、
六道いまは分るらん、 あるじの徳を讃へけり。
温く妊みて黒雲の、 野ばらの藪をわたるあり、
あるいはさらにまじらひを、 求むと土を這へるあり。
からす麦かもわが播けば、 ひばりはそらにくるほしく、
ひかりのそこにもそもそと、 上着は肩をやぶるらし。
さきは夜を截るほとゝぎす、 やがてはそらの菫いろ、
小鳥の群をさきだてて、 くわくこう樹々をどよもしぬ。
醒めたるまゝを封介の、 憤りほのかに立ちいでて、
けじろき水のちりあくた、 もだして馬の指竿とりぬ。
秋立つけふをくちなはの、 沼面はるかに泳ぎ居て、
水ぎぼうしはむらさきの、 花穂ひとしくつらねけり。
いくさの噂さしげければ、 蘆刈びともいまさらに、
暗き岩頸 風の雲、 天のけはひをうかゞひぬ。
打身の床をいできたり、 箱の火鉢にうちゐれば、
人なき店のひるすぎを、 雪げの川の音すなり。
粉のたばこをひねりつゝ、 見あぐるそらの雨もよひ、
蠣売町のかなたにて、 人らほのかに祝ふらし。
氷雨虹すれば、 時計盤たゞに明るく、
病いたつきの今朝やまされる、 青き套門を入るなし。
二限わがなさん、 公きみ 五時を補ひてんや、
火をあらぬひのきづくりは、 神祝かむほぎにどよもすべけれ。
(ばかばかしきよかの邑は、 よべ屯せしクゾなるを)
ましろき指はうちふるひ、 銀のモナドはひしめきぬ。
(いな見よ東かれらこそ、 古き火薬を燃し了へぬ)
うかべる雲をあざけりて、 ひとびと丘を奔せくだりけり。
盆地に白く霧よどみ、 めぐれる山のうら青を、
稲田の水は冽くして、 花はいまだにをさまらぬ。
窓五つなる学校まなびやに、 さびしく学童こらをわがまてば、
藻を装へる馬ひきて、 ひとびと木炭を積み出づる。
たそがれ思量惑くして、 銀屏流沙とも見ゆるころ、
堂は別時の供養とて、 盤鉦木鼓しめやかなり。
頬青き僧ら清らなるテノールなし、 老いし請僧時々に、
バスなすことはさながらに、 風葱嶺に鳴るがごとし。
時しもあれや松の雪、 をちこちどどと落ちたれば、
室ぬちとみに明るくて、 品は四請を了へにけり。
毛布の赤に頭づを縛び、 陀羅尼をまがふことばもて、
罵りかはし牧人ら、 貴きアラヴの種馬の、
息あつくしていばゆるを、 まもりかこみてもろともに、
雪の火山の裾野原、 赭き柏を過ぎくれば、
山はいくたび雲滃の、 藍のなめくぢ角のべて、
おとしけおとしいよいよに、 馬を血馬となしにけり。
そのときに酒代つくると、 夫つまはまた裾野に出でし。
そのときに重瞳の妻めは、 はやくまた闇を奔りし。
柏原風とゞろきて、 さはしぎら遠くよばひき。
馬はみな泉を去りて、 山ちかくつどひてありき。
月の鉛の雲さびに、 みたりあやつり行き過ぎし、
魚や積みけんトラックを、 青かりしやとうたがへば、
松の梢のほのびかり、 霰にはかにそゝぎくる。
こらはみな手を引き交へて、 巨けく蒼きみなかみの、
つつどり声をあめふらす、 水なしの谷に出で行きぬ。
廐に遠く鐘鳴りて、 さびしく風のかげろへば、
小さきシャツはゆれつゝも、 こらのおらびはいまだ来ず。
翔けりゆく冬のフエノール、 ポプラとる黒雲の椀わん。
留学の序を憤り、 中庭にテニス拍つ人。
こぞりてひとを貶おとしつゝ、 わかれうたげもすさまじき、
おのれこよひは暴あれんぞと、 青き瓶袴も惜しげなく、
籾緑金に生えそめし、 代にひたりて田螺ひろへり。
月のほのほをかたむけて、 水杵はひとりありしかど、
搗けるはまこと喰はみも得ぬ、 渋きこならの実なりけり。
さらばとみちを横ぎりて、 束せし廐肥の幾十つら、
祈るがごとき月しろに、 朽ちしとぼそをうかゞひぬ。
まどろむ馬の胸にして、 おぼろに鈴は音をふるひ、
山の焼畑 石の畑、 人もはかなくうまいしき。
人なき山彙やまの二日路を、 夜さりはせ来し酉蔵は、
塩のうるひの茎噛みて、 ふたゝび遠く遁れけり。
萌黄いろなるその頸を、 直くのばして吊るされつ、
吹雪きたればさながらに、 家鴨は船のごとくなり。
絣合羽の巡礼に、 五厘報謝の夕まぐれ、
わかめと鱈に雪つみて、 鮫の黒身も凍りけり。
氷柱かゞやく窓のべに、 「獺」とよばるゝ主幹ゐて、
横めきびしく扉ドアを見る。
赤き九谷に茶をのみて、 片頬ほゝゑむ獺主幹、
つらゝ雫をひらめかす。
狩衣黄なる別当は、 眉をけはしく茶をのみつ。
袴羽織のお百姓、 ふたり斉しく茶をのみつ。
窓をみつめて校長も、 たゞひたすらに茶をのみつ。
しやうふを塗れるガラス戸を、 学童こらこもごもにのぞきたり。
五輪峠と名づけしは、 地輪水輪また火風、
(巌のむらと雪の松) 峠五つの故ならず。
ひかりうづまく黒の雲、 ほそぼそめぐる風のみち、
苔蒸す塔のかなたにて、 大野青々みぞれしぬ。
はんのきの高き梢うれより、 きらゝかに氷華をおとし、
汽車はいまやゝにたゆたひ、 北上のあしたをわたる。
見はるかす段丘の雪、 なめらかに川はうねりて、
天青石アヅライトまぎらふ水は、 百千の流氷ザエを載せたり。
あゝきみがまなざしの涯、 うら青く天盤は澄み、
もろともにあらんと云ひし、 そのまちのけぶりは遠き。
南はも大野のはてに、 ひとひらの吹雪わたりつ、
日は白くみなそこに燃え、 うららかに氷はすべる。
夜をま青き藺むしろに、 ひとびとの影さゆらげば、
遠き山ばた谷のはた、 たばこのうねの想ひあり。
夏のうたげにはべる身の、 声をちゞれの髪をはぢ、
南かたぶく天の川、 ひとりたよりとすかし見る。
あかつき眠るみどりごを、 ひそかに去りて小店さき、
しとみ上ぐれば川音や、 霧はさやかに流れたり。
よべの電燈あかりをそのまゝに、 ひさげのこりし桃の顆みの、
アムスデンジュンいろ紅き、 ほのかに映えて熟るるらし。
きみにならびて野にたてば、 風きららかに吹ききたり、
柏ばやしをとゞろかし、 枯葉を雪にまろばしぬ。
げにもひかりの群青や、 山のけむりのこなたにも、
鳥はその巣やつくろはん、 ちぎれの艸をついばみぬ。
落雁と黒き反り橋、 かの児こそ希ひしものを。
あゝくらき黄泉路よみぢの巌に、 その小き掌てもて得なんや。
木綿ゆふつけし白き骨箱、 哭き喚よぶもけはひあらじを。
日のひかり煙を青み、 秋風に児らは呼び交ふ。
林の中の柴小屋に、 醸し成りたる濁り酒、 一筒汲みて帰り来し、
むかし誉れの神童は、 面青膨れて眼ひかり、 秋はかたむく山里を、
どてら着て立つ風の中。 西は縮れて雲傷み、 青き大野のあちこちに、
雨かとそゝぐ日のしめり、 こなたは古りし苗代の、 刈敷朽ちぬと水黝き、
なべて丘にも林にも、 たゞ鳴る松の声なれば、 あはれさびしと我家の、
門立ち入りて白壁も、 落ちし土蔵の奥二階、 梨の葉かざす窓べにて、
筒のなかばを傾けて、 その歯に風を吸ひつゝも、 しばしをしんとものおもひ、
夜に日をかけて工み来し、 いかさまさいをぞ手にとりにける。
水霜繁く霧たちて、 すすきは濡そほぢ幾そたび、
馬はこむらをふるはしぬ。
(荷繩を投げよはや荷繩)
雉子鳴くなりその雉子、 人なき家の暁を、
歩み漁りて叫ぶらし。
「あな雪か。」屠者のひとりは、 みなかみの闇をすかしぬ。
車押すみたりはうみて、 いらへなく橋板ふみぬ。
「雉なりき青く流れし。」 声またもわぶるがごとき。
落合に水の声して、 老いの屠者たゞ舌打ちぬ。
造園学のテキストに、 おのれが像を百あまり、
著者の原図と銘うちて、 かゝげしことも夢なれやと、
青き夕陽の寒天や、 U字の梨のかなたより、
革の手袋はづしつゝ、 しづにおくびし歩みくる。
ほのあかり秋のあぎとは、 ももどりのねぐらをめぐり、
官つかさの手からくのがれし、 社司の子のありかを知らず。
社殿にはゆふべののりと、 ほのかなる泉の声や、
そのはははことなきさまに、 しらたまのもちひをなせる。
毘沙門の堂は古びて、 梨白く花咲きちれば、
胸疾みてつかさをやめし、 堂守の眼やさしき。
中ぞらにうかべる雲の、 蓋やまた椀まりのさまなる、
川水はすべりてくらく、 草火のみほのに燃えたれ。
ぬさをかざして山つ祇、 舞ふはぶらいの町の書記、
うなじはかなく瓶へいとるは、 峡には一のうためなり。
をさけびたけり足ぶみて、 をどりめぐれるすがたゆゑ、
老いし博士はくしや郡長こほりおさ、 やゝ凄涼のおもひなり。
月や出でにし雪青み、 をちこち犬の吠ゆるころ、
舞ひを納めてひれふしつ、 罪乞ふさまにみじろがず。
あなや否とよ立てきみと、 博士が云へばたちまちに、
けりはねあがり山つ祇、 をみなをとりて消えうせぬ。
川しろじろとまじはりて、 うたかたしげきこのほとり、
病きつかれわが行けば、 そらのひかりぞ身を責むる。
宿世のくるみはんの毬、 干割れて青き泥岩に、
はかなきかなやわが影の、 卑しき鬼をうつすなり。
蒼茫として夏の風、 草のみどりをひるがへし、
ちらばる蘆のひら吹きて、 あやしき文字を織りなしぬ。
生きんに生きず死になんに、 得こそ死なれぬわが影を、
うら濁る水はてしなく、 さゝやきしげく洗ふなり。
風にとぎるゝ雨脚や、 みだらにかける雲のにぶ。
まくろき枝もうねりつゝ、 さくらの花のすさまじき。
あたふた黄ばみ雨を縫ふ、 もずのかしらのまどけきを。
いよよにどよみなみだちて、 ひかり青らむ花の梢うれ。
酒精のかをり硝銀の、 肌膚灼くにほひしかもあれ、
大展覧の花むらは、 夏夜あざらに息づきぬ。
そは牛飼ひの商ひの、 はた鉄うてるもろ人の、
さこそつちかひはぐくみし、 四百の花のラムプなり。
声さやかなるをとめらは、 おのおのよきに票を投げ、
高木検事もホップ噛む、 にがきわらひを頬になしき。
卓をめぐりて会長が、 メダルを懸くる午前二時、
カクタス、ショウをおしなべて、 花はうつゝもあらざりき。
秘事念仏の大師匠、 元真斎は妻子して、
北上岸にいそしみつ、 いまぞ昼餉をしたゝむる。
卓のさまして緑なる、 小松と紅き萱の芽と、
雪げの水にさからひて、 まこと睡たき南かぜ。
むしろ帆張りて酒船の、 ふとあらはるゝまみまぢか、
をのこは三たり舷に、 こちを見おろし見すくむる。
元真斎はやるせなみ、 眼をそらす川のはて、
塩の高菜をひた噛めば、 妻子もこれにならふなり。
楊葉の銀とみどりと、 はるけきは青らむけぶり。
よるべなき水素の川に、 ほとほとと麻苧うつ妻。
驟雨そゝげば新墾にひはりの、 まづ立ちこむるつちけむり。
湯気のぬるきに人たちて、 故なく憤る身は暗し。
すでに野ばらの根を浄み、 蟻はその巣をめぐるころ。
杉には水の幡かゝり、 しぶきほのかに拡ごりぬ。
血のいろにゆがめる月は、 今宵また桜をのぼり、
患者たち廊のはづれに、 凶事の兆を云へり。
木がくれのあやなき闇を、 声細くいゆきかへりて、
熱植ゑし黒き綿羊、 その姿いともあやしき。
月しろは鉛糖のごと、 柱列の廊をわたれば、
コカインの白きかをりを、 いそがしくよぎる医師あり。
しかもあれ春のをとめら、 なべて且つ耐へほゝゑみて、
水銀の目盛を数へ、 玲瓏の氷を割きぬ。
夕陽の青き棒のなかにて、 開化郷士と見ゆるもの、
葉巻のけむり蒼茫と、 森槐南を論じたり。
開化郷士と見ゆるもの、 いと清純とよみしける、
寒天光のうら青に、 おもてをかくしひとはねむれり。
朝日かゞやく水仙を、 になひてくるは詮之助、
あたまひかりて過ぎ行くは、 枝を杖つく村老ヤコブ。
影と並木のだんだらを、 犬レオナルド足織れば、
売り酒のみて熊之進、 赤眼に店をばあくるなり。
さき立つ名誉村長は、 寒煙毒をふくめるを、
豪気によりて受けつけず。
次なる沙弥は顱を円き、 猫毛の帽に護りつゝ、
その身は信にゆだねたり。
三なる技師は徳薄く、 すでに過冷のシロッコに、
なかば気管をやぶりたれ。
最後に女訓導は、 ショールを面に被ふれば、
アラーの守りあるごとし。
僧の妻面膨れたる、 飯盛りし仏器さゝげくる。
(雪やみて朝日は青く、 かうかうと僧は看経。)
寄進札そゞろに誦みて、 僧の妻庫裡にしりぞく。
(いまはとて異の銅鼓うち、 晨光はみどりとかはる。)
「玉蜀黍を播きやめ環にならべ、 開所の祭近ければ、
さんさ踊りをさらひせん。」 技手農婦らに令しけり。
野は野のかぎりめくるめく、 青きかすみのなかにして、
まひるをひとらうちをどる、 袖をかざしてうちをどる。
さあれひんがし一つらの、 うこんざくらをせなにして、
所長中佐は胸たかく、 野面はるかにのぞみゐる。
「いそぎひれふせ、ひざまづけ、 みじろがざれ。」と技手云へば、
種子やまくらんいこふらん、 ひとらかすみにうごくともなし。
うからもて台地の雪に、 部落シユクなせるその杜黝し。
曙人とほつおや、馮のりくる児らを、 穹窿ぞ光りて覆ふ。
残丘モナドノツクの雪の上に、 二すぢうかぶ雲ありて、
誰かは知らねサラアなる、 女ひとのおもひをうつしたる。
信をだになほ装へる、 よりよき生へのこのねがひを、
なにとてきみはさとり得ぬと、 しばしうらみて消えにけり。
たけしき耕の具を帯びて、 羆熊の皮は着たれども、
夜に日をつげる一月の、 干泥のわざに身をわびて、
しばしましろの露置ける、 すぎなの畔にまどろめば、
はじめは額の雲ぬるみ、 鳴きかひめぐるむらひばり、
やがては古き巨人の、 石の匙もて出できたり、
ネプウメリてふ草の葉を、 薬に食めとをしへけり。
吹雪かゞやくなかにして、 まことに犬の吠え集りし。
燃ゆる吹雪のさなかとて、 妖あやしき盽をなせるものかな。
底本:「新修宮沢賢治全集 第六巻」筑摩書房
1980(昭和55)年2月15日初版第1刷発行
※底本は、1作品が1ページにおさまるように行間を調整している。ただし、このファイルでは、作品の末尾にそのつど改ページの注記を書き込むことはせず、頁の変わり目ごとに3行をあけた。
※底本は、「作者専用の詩稿に書かれた詩篇を収録し」、多くの詩篇で、詩稿の形式に合わせて上下に二句を配置し、字間スペースなどを調整して下の句の頭が横にそろうように組んである。この形を取っている詩篇に関しては、本ファイルでも、句間を最低全角2字空けとし、下の句の頭を横にそろえた。
入力:junk
校正:林 幸雄
2002年5月8日作成
2014年5月22日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
病中幻想
宮沢賢治
罪はいま疾やまひにかはり
たよりなくわれは騰りて
野のそらにひとりまどろむ
太虚ひかりてはてしなく
身は水素より軽ければ
また耕さんすべもなし
せめてはかしこ黒と白
立ち並びたる積雲を
雨と崩して堕ちなんを
底本:「新修宮沢賢治全集 第六巻」筑摩書房
1980(昭和55)年2月15日初版第1刷発行
入力:junk
校正:土屋隆
2011年5月14日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
『注文の多い料理店』広告文
宮沢賢治
イーハトヴは一つの地名である。強て、その地点を求むるならばそれは、大小クラウスたちの耕してゐた、野原や、少女アリスガ辿つた鏡の国と同じ世界の中、テパーンタール砂漠の遥かな北東、イヴン王国の遠い東と考へられる。
実にこれは著者の心象中にこの様な状景をもつて実在した
ドリームランドとしての日本岩手県である。
そこでは、あらゆる事が可能である。人は一瞬にして氷雲の上に飛躍し大循環の風を従へて北に旅する事もあれば、赤い花杯の下を行く蟻と語ることもできる。
罪や、かなしみでさへそこでは聖くきれいにかゞやいてゐる。
深い掬の森や、風や影、肉之草や、不思議な都会、ベーリング市迄続々電柱の列、それはまことにあやしくも楽しい国土である。この童話集の一列は実に作者の心象スケツチの一部である。それは少年少女期の終り頃から、アドレツセンス中葉に対する一つの文学としての形式をとつてゐる。
この見地からその特色を数へるならば次の諸点に帰する。
一これは正しいものゝ種子を有し、その美しい発芽を待つものである。而も決して既成の疲れた宗教や、道徳の残澤を色あせた仮面によつて純真な心意の所有者たちに欺き与へんとするものではない。
二これらは新しい、よりよい世界の構成材料を提供しやうとはする。けれどもそれは全く、作者に未知な絶えざる警異に値する世界自身の発展であつて決して畸形に涅ねあげられた煤色のユートピアではない。
三これらは決して偽でも仮空でも窃盗でもない。
多少の再度の内省と分折とはあつても、たしかにこの通りその時心象の中に現はれたものである。故にそれは、どんなに馬鹿げてゐても、難解でも必ず心の深部に於て万人の共通である。卑怯な成人たちに畢竟不可解な丈である。
四これは田園の新鮮な産物である。われらは田園の風と光の中からつやゝかな果実や、青い蔬菜を一緒にこれらの心象スケツチを世間に提供するものである。
注文の多い料理店はその十二巻のセリーズの中の第一冊で先づその古風な童話としての形式と地方色とを以て類集したものであつて次の九編からなる。
───────────────────────────────────────────
1 どんぐりと山猫やまねこ
───────────────────────────────────────────
山猫拝と書いたおかしな葉書が来たので、こどもが山の風の中へ出かけて行くはなし。必ず比較をされなけれはならないいまの学童たちの内奥からの反響です。
───────────────────────────────────────────
2 狼森おいのもりと笊森ざるもりと盗森ぬすともり
───────────────────────────────────────────
人と森との原始的な交渉で、自然の順違二面が農民と与へた永い間の印象です。森に子供らが農具をかくすたびにみんなは「探しに行くぞお」と叫び森は「来お」と答へました。
───────────────────────────────────────────
3 烏からすの北斗ほくと七星せい
───────────────────────────────────────────
戦ふものゝ内的感情です。
───────────────────────────────────────────
4 注文ちうもんの多おほい料理店れうりてん
───────────────────────────────────────────
二人の青年神士が猟に出て路を迷ひ「注文の多い料理店」に入りその途方もない経営者から却つて注文されてゐたはなし。糧に乏しい村のこどもらが都会文明と放恣な階級とに対する止むに止まれない反感です。
───────────────────────────────────────────
5 水仙月すゐせんづきの四日よつか
───────────────────────────────────────────
赤い毛布を被ぎ「カリメラ」の銅鍋や青い焔を考へながら雪の高原を歩いてゐたこどもと「雪婆ンゴ」や雪狼、雪童子とのものがたり。
───────────────────────────────────────────
6 山男やまをとこの四月ぐわつ
───────────────────────────────────────────
四月のかれ草の中にねころんだ山男の夢です。
烏の北斗七星といつしよに、一つの小さなこゝろの種子を有ちます。
───────────────────────────────────────────
7 かしはばやしの夜よ
───────────────────────────────────────────
桃色の大きな月はだん〳〵小さく青じろくなり、かしははみんなざわざわ言ひ、画描きは自分の靴の中に鉛筆を削つて変なメタルの歌をうたふ、たのしい「夏の踊りの第三夜」です。
───────────────────────────────────────────
8 月夜つきよのでんしんばしら
───────────────────────────────────────────
うろこぐもと鉛色の月光、九月のイーハトヴの鉄道線路の内想です。
───────────────────────────────────────────
9 鹿踊しかをどりのはじまり
───────────────────────────────────────────
まだ剖れない巨きな愛の感情です。すゝきの花の向ひ火や、きらめく赤褐の樹立のなかに、鹿が無心に遊んでゐます。ひとは自分と鹿との区別を忘れ、いつしよに踊らうとさへします。
底本:「宮沢賢治全集8」ちくま文庫、筑摩書房
1986(昭和61)年1月28日第1刷発行
2004(平成16)年4月25日第20刷発行
※文中の括弧で囲まれた解説者による注記は省略しました。
入力:土屋隆
校正:noriko saito
2005年2月21日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
注文の多い料理店
宮沢賢治
二人の若い紳士しんしが、すっかりイギリスの兵隊のかたちをして、ぴかぴかする鉄砲てっぽうをかついで、白熊しろくまのような犬を二疋ひきつれて、だいぶ山奥やまおくの、木の葉のかさかさしたとこを、こんなことを云いいながら、あるいておりました。
「ぜんたい、ここらの山は怪けしからんね。鳥も獣けものも一疋も居やがらん。なんでも構わないから、早くタンタアーンと、やって見たいもんだなあ。」
「鹿しかの黄いろな横っ腹なんぞに、二三発お見舞みまいもうしたら、ずいぶん痛快だろうねえ。くるくるまわって、それからどたっと倒たおれるだろうねえ。」
それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちも、ちょっとまごついて、どこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。
それに、あんまり山が物凄ものすごいので、その白熊のような犬が、二疋いっしょにめまいを起こして、しばらく吠うなって、それから泡あわを吐はいて死んでしまいました。
「じつにぼくは、二千四百円の損害だ」と一人の紳士が、その犬の眼まぶたを、ちょっとかえしてみて言いました。
「ぼくは二千八百円の損害だ。」と、もひとりが、くやしそうに、あたまをまげて言いました。
はじめの紳士は、すこし顔いろを悪くして、じっと、もひとりの紳士の、顔つきを見ながら云いました。
「ぼくはもう戻もどろうとおもう。」
「さあ、ぼくもちょうど寒くはなったし腹は空すいてきたし戻ろうとおもう。」
「そいじゃ、これで切りあげよう。なあに戻りに、昨日きのうの宿屋で、山鳥を拾円じゅうえんも買って帰ればいい。」
「兎うさぎもでていたねえ。そうすれば結局おんなじこった。では帰ろうじゃないか」
ところがどうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか、いっこうに見当がつかなくなっていました。
風がどうと吹ふいてきて、草はざわざわ、木の葉はかさかさ、木はごとんごとんと鳴りました。
「どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。」
「ぼくもそうだ。もうあんまりあるきたくないな。」
「あるきたくないよ。ああ困ったなあ、何かたべたいなあ。」
「喰たべたいもんだなあ」
二人の紳士は、ざわざわ鳴るすすきの中で、こんなことを云いました。
その時ふとうしろを見ますと、立派な一軒いっけんの西洋造りの家がありました。
そして玄関げんかんには
RESTAURANT
西洋料理店
WILDCAT HOUSE
山猫軒
という札がでていました。
「君、ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けてるんだ。入ろうじゃないか」
「おや、こんなとこにおかしいね。しかしとにかく何か食事ができるんだろう」
「もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか」
「はいろうじゃないか。ぼくはもう何か喰べたくて倒れそうなんだ。」
二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸せとの煉瓦れんがで組んで、実に立派なもんです。
そして硝子がらすの開き戸がたって、そこに金文字でこう書いてありました。
「どなたもどうかお入りください。決してご遠慮えんりょはありません」
二人はそこで、ひどくよろこんで言いました。
「こいつはどうだ、やっぱり世の中はうまくできてるねえ、きょう一日なんぎしたけれど、こんどはこんないいこともある。このうちは料理店だけれどもただでご馳走ちそうするんだぜ。」
「どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。」
二人は戸を押おして、なかへ入りました。そこはすぐ廊下ろうかになっていました。その硝子戸の裏側には、金文字でこうなっていました。
「ことに肥ふとったお方や若いお方は、大歓迎だいかんげいいたします」
二人は大歓迎というので、もう大よろこびです。
「君、ぼくらは大歓迎にあたっているのだ。」
「ぼくらは両方兼ねてるから」
ずんずん廊下を進んで行きますと、こんどは水いろのペンキ塗ぬりの扉とがありました。
「どうも変な家うちだ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。」
「これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。」
そして二人はその扉をあけようとしますと、上に黄いろな字でこう書いてありました。
「当軒は注文の多い料理店ですからどうかそこはご承知ください」
「なかなかはやってるんだ。こんな山の中で。」
「それあそうだ。見たまえ、東京の大きな料理屋だって大通りにはすくないだろう」
二人は云いながら、その扉をあけました。するとその裏側に、
「注文はずいぶん多いでしょうがどうか一々こらえて下さい。」
「これはぜんたいどういうんだ。」ひとりの紳士は顔をしかめました。
「うん、これはきっと注文があまり多くて支度したくが手間取るけれどもごめん下さいと斯こういうことだ。」
「そうだろう。早くどこか室へやの中にはいりたいもんだな。」
「そしてテーブルに座すわりたいもんだな。」
ところがどうもうるさいことは、また扉が一つありました。そしてそのわきに鏡がかかって、その下には長い柄えのついたブラシが置いてあったのです。
扉には赤い字で、
「お客さまがた、ここで髪かみをきちんとして、それからはきもの
の泥どろを落してください。」
と書いてありました。
「これはどうも尤もっともだ。僕もさっき玄関で、山のなかだとおもって見くびったんだよ」
「作法の厳しい家だ。きっとよほど偉えらい人たちが、たびたび来るんだ。」
そこで二人は、きれいに髪をけずって、靴くつの泥を落しました。
そしたら、どうです。ブラシを板の上に置くや否いなや、そいつがぼうっとかすんで無くなって、風がどうっと室の中に入ってきました。
二人はびっくりして、互たがいによりそって、扉をがたんと開けて、次の室へ入って行きました。早く何か暖いものでもたべて、元気をつけて置かないと、もう途方とほうもないことになってしまうと、二人とも思ったのでした。
扉の内側に、また変なことが書いてありました。
「鉄砲と弾丸たまをここへ置いてください。」
見るとすぐ横に黒い台がありました。
「なるほど、鉄砲を持ってものを食うという法はない。」
「いや、よほど偉いひとが始終来ているんだ。」
二人は鉄砲をはずし、帯皮を解いて、それを台の上に置きました。
また黒い扉がありました。
「どうか帽子ぼうしと外套がいとうと靴をおとり下さい。」
「どうだ、とるか。」
「仕方ない、とろう。たしかによっぽどえらいひとなんだ。奥に来ているのは」
二人は帽子とオーバーコートを釘くぎにかけ、靴をぬいでぺたぺたあるいて扉の中にはいりました。
扉の裏側には、
「ネクタイピン、カフスボタン、眼鏡めがね、財布さいふ、その他金物類、
ことに尖とがったものは、みんなここに置いてください」
と書いてありました。扉のすぐ横には黒塗りの立派な金庫も、ちゃんと口を開けて置いてありました。鍵かぎまで添そえてあったのです。
「ははあ、何かの料理に電気をつかうと見えるね。金気かなけのものはあぶない。ことに尖ったものはあぶないと斯こう云うんだろう。」
「そうだろう。して見ると勘定かんじょうは帰りにここで払はらうのだろうか。」
「どうもそうらしい。」
「そうだ。きっと。」
二人はめがねをはずしたり、カフスボタンをとったり、みんな金庫のなかに入れて、ぱちんと錠じょうをかけました。
すこし行きますとまた扉とがあって、その前に硝子がらすの壺つぼが一つありました。扉には斯こう書いてありました。
「壺のなかのクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。」
みるとたしかに壺のなかのものは牛乳のクリームでした。
「クリームをぬれというのはどういうんだ。」
「これはね、外がひじょうに寒いだろう。室へやのなかがあんまり暖いとひびがきれるから、その予防なんだ。どうも奥には、よほどえらいひとがきている。こんなとこで、案外ぼくらは、貴族とちかづきになるかも知れないよ。」
二人は壺のクリームを、顔に塗って手に塗ってそれから靴下をぬいで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら喰べました。
それから大急ぎで扉をあけますと、その裏側には、
「クリームをよく塗りましたか、耳にもよく塗りましたか、」
と書いてあって、ちいさなクリームの壺がここにも置いてありました。
「そうそう、ぼくは耳には塗らなかった。あぶなく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人はじつに用意周到しゅうとうだね。」
「ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところでぼくは早く何か喰べたいんだが、どうも斯うどこまでも廊下じゃ仕方ないね。」
するとすぐその前に次の戸がありました。
「料理はもうすぐできます。
十五分とお待たせはいたしません。
すぐたべられます。
早くあなたの頭に瓶びんの中の香水をよく振ふりかけてください。」
そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。
二人はその香水を、頭へぱちゃぱちゃ振りかけました。
ところがその香水は、どうも酢すのような匂においがするのでした。
「この香水はへんに酢くさい。どうしたんだろう。」
「まちがえたんだ。下女が風邪かぜでも引いてまちがえて入れたんだ。」
二人は扉をあけて中にはいりました。
扉の裏側には、大きな字で斯う書いてありました。
「いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。
もうこれだけです。どうかからだ中に、壺の中の塩をたくさん
よくもみ込んでください。」
なるほど立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、こんどというこんどは二人ともぎょっとしてお互にクリームをたくさん塗った顔を見合せました。
「どうもおかしいぜ。」
「ぼくもおかしいとおもう。」
「沢山たくさんの注文というのは、向うがこっちへ注文してるんだよ。」
「だからさ、西洋料理店というのは、ぼくの考えるところでは、西洋料理を、来た人にたべさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして、食べてやる家うちとこういうことなんだ。これは、その、つ、つ、つ、つまり、ぼ、ぼ、ぼくらが……。」がたがたがたがた、ふるえだしてもうものが言えませんでした。
「その、ぼ、ぼくらが、……うわあ。」がたがたがたがたふるえだして、もうものが言えませんでした。
「遁にげ……。」がたがたしながら一人の紳士はうしろの戸を押おそうとしましたが、どうです、戸はもう一分いちぶも動きませんでした。
奥の方にはまだ一枚扉があって、大きなかぎ穴が二つつき、銀いろのホークとナイフの形が切りだしてあって、
「いや、わざわざご苦労です。
大へん結構にできました。
さあさあおなかにおはいりください。」
と書いてありました。おまけにかぎ穴からはきょろきょろ二つの青い眼玉めだまがこっちをのぞいています。
「うわあ。」がたがたがたがた。
「うわあ。」がたがたがたがた。
ふたりは泣き出しました。
すると戸の中では、こそこそこんなことを云っています。
「だめだよ。もう気がついたよ。塩をもみこまないようだよ。」
「あたりまえさ。親分の書きようがまずいんだ。あすこへ、いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう、お気の毒でしたなんて、間抜まぬけたことを書いたもんだ。」
「どっちでもいいよ。どうせぼくらには、骨も分けて呉くれやしないんだ。」
「それはそうだ。けれどももしここへあいつらがはいって来なかったら、それはぼくらの責任だぜ。」
「呼ぼうか、呼ぼう。おい、お客さん方、早くいらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。お皿さらも洗ってありますし、菜っ葉ももうよく塩でもんで置きました。あとはあなたがたと、菜っ葉をうまくとりあわせて、まっ白なお皿にのせるだけです。はやくいらっしゃい。」
「へい、いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラドはお嫌きらいですか。そんならこれから火を起してフライにしてあげましょうか。とにかくはやくいらっしゃい。」
二人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙屑かみくずのようになり、お互にその顔を見合せ、ぶるぶるふるえ、声もなく泣きました。
中ではふっふっとわらってまた叫さけんでいます。
「いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いては折角せっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へい、ただいま。じきもってまいります。さあ、早くいらっしゃい。」
「早くいらっしゃい。親方がもうナフキンをかけて、ナイフをもって、舌なめずりして、お客さま方を待っていられます。」
二人は泣いて泣いて泣いて泣いて泣きました。
そのときうしろからいきなり、
「わん、わん、ぐゎあ。」という声がして、あの白熊しろくまのような犬が二疋ひき、扉とをつきやぶって室へやの中に飛び込んできました。鍵穴かぎあなの眼玉はたちまちなくなり、犬どもはううとうなってしばらく室の中をくるくる廻まわっていましたが、また一声
「わん。」と高く吠ほえて、いきなり次の扉に飛びつきました。戸はがたりとひらき、犬どもは吸い込まれるように飛んで行きました。
その扉の向うのまっくらやみのなかで、
「にゃあお、くゎあ、ごろごろ。」という声がして、それからがさがさ鳴りました。
室はけむりのように消え、二人は寒さにぶるぶるふるえて、草の中に立っていました。
見ると、上着や靴くつや財布さいふやネクタイピンは、あっちの枝えだにぶらさがったり、こっちの根もとにちらばったりしています。風がどうと吹ふいてきて、草はざわざわ、木の葉はかさかさ、木はごとんごとんと鳴りました。
犬がふうとうなって戻もどってきました。
そしてうしろからは、
「旦那だんなあ、旦那あ、」と叫ぶものがあります。
二人は俄にわかに元気がついて
「おおい、おおい、ここだぞ、早く来い。」と叫びました。
簔帽子みのぼうしをかぶった専門の猟師りょうしが、草をざわざわ分けてやってきました。
そこで二人はやっと安心しました。
そして猟師のもってきた団子だんごをたべ、途中とちゅうで十円だけ山鳥を買って東京に帰りました。
しかし、さっき一ぺん紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯にはいっても、もうもとのとおりになおりませんでした。
底本:「注文の多い料理店」新潮文庫、新潮社
1990(平成2)年5月25日発行
1997(平成9)年5月10日17刷
初出:「イーハトヴ童話 注文の多い料理店」盛岡市杜陵出版部・東京光原社
1924(大正13)年12月1日
入力:土屋隆
校正:noriko saito
2005年1月26日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
『注文の多い料理店』序
宮沢賢治
わたしたちは、氷砂糖をほしいくらいもたないでも、きれいにすきとおった風をたべ、桃ももいろのうつくしい朝の日光をのむことができます。
またわたくしは、はたけや森の中で、ひどいぼろぼろのきものが、いちばんすばらしいびろうどや羅紗らしゃや、宝石いりのきものに、かわっているのをたびたび見ました。
わたくしは、そういうきれいなたべものやきものをすきです。
これらのわたくしのおはなしは、みんな林や野はらや鉄道線路やらで、虹にじや月あかりからもらってきたのです。
ほんとうに、かしわばやしの青い夕方を、ひとりで通りかかったり、十一月の山の風のなかに、ふるえながら立ったりしますと、もうどうしてもこんな気がしてしかたないのです。ほんとうにもう、どうしてもこんなことがあるようでしかたないということを、わたくしはそのとおり書いたまでです。
ですから、これらのなかには、あなたのためになるところもあるでしょうし、ただそれっきりのところもあるでしょうが、わたくしには、そのみわけがよくつきません。なんのことだか、わけのわからないところもあるでしょうが、そんなところは、わたくしにもまた、わけがわからないのです。
けれども、わたくしは、これらのちいさなものがたりの幾いくきれかが、おしまい、あなたのすきとおったほんとうのたべものになることを、どんなにねがうかわかりません。
大正十二年十二月二十日
底本:「注文の多い料理店」新潮文庫、新潮社
1990(平成2)年5月25日発行
1997(平成9)年5月10日17刷
初出:「イーハトヴ童話 注文の多い料理店」盛岡市杜陵出版部・東京光原社
1924(大正13)年12月1日
入力:土屋隆
校正:noriko saito
2005年1月26日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
『注文の多い料理店』新刊案内
宮沢賢治
イーハトヴは一つの地名である。しいて、その地点を求もとむるならば、それは、大小クラウスたちの耕たがやしていた、野原のはらや、少女アリスがたどった鏡かがみの国と同じ世界せかいの中、テパーンタール砂漠さばくのはるかな北東、イヴン王国の遠い東と考えられる。
じつにこれは著者の心象中に、このような状景じょうけいをもって実在じつざいしたドリームランドとしての日本岩手県である。
そこでは、あらゆることが可能かのうである。人は一瞬いっしゅんにして氷雲ひょううんの上に飛躍ひやくし大循環だいじゅんかんの風を従したがえて北に旅たびすることもあれば、赤い花杯はなさかずきの下を行く蟻ありと語かたることもできる。
罪つみや、かなしみでさえそこでは聖きよくきれいにかがやいている。
深ふかい椈の森や、風や影かげ、肉之草や、不思議ふしぎな都会とかい、ベーリング市まで続つづく電柱でんちゅうの列れつ、それはまことにあやしくも楽しい国土である。この童話集の一列は実に作者の心象スケッチの一部いちぶである。それは少年少女期きの終おわりごろから、アドレッセンス中葉ちゅうように対たいする一つの文学としての形式けいしきをとっている。
この見地からその特色を数えるならば次の諸点に帰する。
一 これは正しいものの種子しゅしを有ゆうし、その美うつくしい発芽はつがを待まつものである。しかもけっして既成きせいの疲つかれた宗教しゅうきょうや、道徳どうとくの残滓ざんしを、色あせた仮面かめんによって純真じゅんしんな心意しんいの所有者しょゆうしゃたちに欺あざむき与あたえんとするものではない。
二 これらは新しい、よりよい世界せかいの構成材料こうせいざいりょうを提供ていきょうしようとはする。けれどもそれは全まったく、作者に未知みちな絶たえざる驚異きょういに値あたいする世界自身じしんの発展はってんであって、けっして畸形きけいに捏こねあげられた煤色すすいろのユートピアではない。
三 これらはけっして偽いつわりでも仮空でも窃盗せっとうでもない。
多少たしょうの再度さいどの内省ないせいと分析ぶんせきとはあっても、たしかにこのとおりその時心象しんしょうの中に現あらわれたものである。ゆえにそれは、どんなに馬鹿ばかげていても、難解なんかいでも必かならず心の深部しんぶにおいて万人ばんにんの共通きょうつうである。卑怯ひきょうな成人せいじんたちに畢竟ひっきょう不可解ふかかいなだけである。
四 これは田園でんえんの新鮮しんせんな産物さんぶつである。われらは田園の風と光の中からつややかな果実かじつや、青い蔬菜そさいといっしょにこれらの心象スケッチを世間せけんに提供するものである。
注文の多い料理店はその十二巻かんのセリーズの中の第一冊だいいっさつでまずその古風こふうな童話どうわとしての形式けいしきと地方色とをもって類集るいしゅうしたものであって次つぎの九編へんからなる。
目次と…………その説明
(中略、ここに「注文ちゅうもんの多い料理店りょうりてん」の中扉なかとびらのカットを挿入そうにゅうしてある)
1 どんぐりと山猫
山猫拝やまねこはいと書いたおかしな葉書はがきが来たので、こどもが山の風の中へ出かけて行くはなし。必かならず比較ひかくをされなければならないいまの学童がくどうたちの内奥ないおうからの反響はんきょうです。
2 狼森と笊森、盗森
人と森との原始的げんしてきな交渉こうしょうで、自然しぜんの順違じゅんい二面にめんが農民に与あたえた永ながい間の印象いんしょうです。森が子供こどもらや農具のうぐをかくすたびに、みんなは「探さがしに行くぞお」と叫さけび、森は「来こお」と答えました。
3 烏の北斗七星
戦たたかうものの内的感情ないてきかんじょうです。
4 注文の多い料理店
二人の青年紳士しんしが猟りょうに出て路みちを迷まよい、「注文ちゅうもんの多い料理店りょうりてん」にはいり、その途方とほうもない経営者けいえいしゃからかえって注文されていたはなし。糧かてに乏とぼしい村のこどもらが、都会文明とかいぶんめいと放恣ほうしな階級かいきゅうとに対たいするやむにやまれない反感はんかんです。
5 水仙月の四日
赤い毛布ケットを被かつぎ、「カリメラ」の銅鍋どうなべや青い焔ほのおを考えながら雪の高原を歩いていたこどもと、「雪婆ゆきばンゴ」や雪狼ゆきオイノ、雪童子ゆきわらすとのものがたり。
6 山男の四月
四月のかれ草の中にねころんだ山男の夢ゆめです。烏からすの北斗七星ほくとしちせいといっしょに、一つの小さなこころの種子しゅしを有もちます。
7 かしわばやしの夜
桃色ももいろの大きな月はだんだん小さく青じろくなり、かしわはみんなざわざわ言いい、画描えかきは自分の靴くつの中に鉛筆えんぴつを削けずって変へんなメタルの歌をうたう、たのしい「夏の踊おどりの第だい三夜」です。
8 月夜のでんしんばしら
うろこぐもと鉛色なまりいろの月光、九月のイーハトヴの鉄道線路てつどうせんろの内想ないそうです。
9 鹿踊りのはじまり
まだ剖わかれない巨おおきな愛あいの感情かんじょうです。すすきの花の向むかい火や、きらめく赤褐せっかつの樹立こだちのなかに、鹿しかが無心むしんに遊あそんでいます。ひとは自分と鹿との区別くべつを忘わすれ、いっしょに踊おどろうとさえします。
底本:「注文の多い料理店」角川文庫、角川書店
1996(平成8)年6月25日改訂新版発行
1997(平成9)年5月25日改訂4版発行
※「(中略、~)」は編集者による注記です。創作的表現にはあたらないと判断し、底本通りとしました。
※底本の「地方名」を「地方色」に改めるにあたっては「宮沢賢治全集8」(ちくま文庫、1986)、「注文の多い料理店」(新潮文庫、1990)を参照しました。
※傍点は原文(初版本刊行時の広告ちらし)で赤刷りされた文字を表します。
入力:土屋隆
校正:noriko saito
2005年2月21日作成
2005年5月21日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
中尊寺〔二〕
宮沢賢治
白きそらいと近くして
みねの方鐘さらに鳴り
青葉もて埋もる堂の
ひそけくも暮れにまぢかし
僧ひとり縁にうちゐて
ふくれたるうなじめぐらし
義経の彩ある像を
ゆびさしてそらごとを云ふ
底本:「新修宮沢賢治全集 第六巻」筑摩書房
1980(昭和55)年2月15日初版第1刷発行
※〔〕付きの表題は、底本編集時におぎなわれたものです。
入力:junk
校正:土屋隆
2011年5月14日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
台川
宮沢賢治
〔もうでかけましょう。〕たしかに光がうごいてみんな立ちあがる。腰こしをおろしたみじかい草。かげろうか何かゆれている。かげろうじゃない。網膜もうまくが感かんじただけのその光だ。
〔さあでかけましょう。行きたい人だけ。〕まだ来ないものは仕方しかたない。さっきからもう二十分も待まったんだ。もっともこのみちばたの青いいろの寄宿舎きしゅくしゃはゆっくりして爽さわやかでよかったが。
これからまたここへ一遍いっぺん帰って十一時には向むこうの宿やどへつかなければいけないんだ。「何処どごさ行ぐのす。」そうだ、釜淵かまぶちまで行くというのを知らないものもあるんだな。〔釜淵まで、一寸ちょっと三十分ばかり。〕
おとなしい新らしい白、緑みどりの中だから、そして外光の中だから大へんいいんだ。天竺木綿てんじくもめん、その菓子かしの包つつみは置おいて行ってもいい。雑嚢ざつのうや何かもここの芝しばへおろしておいていい行かないものもあるだろうから。
「私はここで待ってますから。」校長だ。校長は肥ふとってまっ黒にいで立ちたしかにゆっくりみちばたの草、林の前に足を開ひらいて投なげ出している。
〔はあ、では一寸行って参まいります。〕木の青、木の青、空の雲は今日も甘酸あまずっぱく、足なみのゆれと光の波なみ。足なみのゆれと光の波。
粘土ねんどのみちだ。乾かわいている。黄色だ。みち。粘土。
小松こまつと林。林の明暗めいあんいろいろの緑。それに生徒せいとはみんな新鮮しんせんだ。
そしてそうだ、向うの崖がけの黒いのはあれだ、明らかにあの黒曜石こくようせきの dyke だ。ここからこんなにはっきり見えるとは思わなかったぞ。
よしうまい。
〔向むこうの崖がけをごらんなさい。黒くて少し浮うき出した柱はしらのような岩があるでしょう。あれは水成岩すいせいがんの割われ目に押おし込こんで来た火山岩です。黒曜石です。〕ダイクと云いおうかな。いいや岩脈がんみゃくがいい。〔ああいうのを岩脈といいます。〕わかったかな。
〔わかりましたか。向うの崖に黒い岩が縦たてに突つき出ているでしょう。
あれは水成岩のなかにふき出した火成岩ですよ。岩脈ですよ。あれは。〕
ゆれてるゆれてる。光の網あみ。
〔この山は流紋凝灰岩りゅうもんぎょうかいがんでできています。石英粗面岩せきえいそめんがんの凝灰岩、大へん地味ちみが悪わるいのです。赤松あかまつとちいさな雑木ぞうきしか生はえていないでしょう。ところがそのへん、麓ふもとの緩ゆるい傾斜けいしゃのところには青い立派りっぱな闊葉樹かつようじゅが一杯いっぱい生はえているでしょう。あすこは古い沖積扇ちゅうせきせんです。運はこばれてきたのです。割合わりあい肥沃ひよくな土壌どじょうを作っています。木の生え工合ぐあいがちがって見えましょう。わかりましょう。〕わかるだろうさ。けれどもみんな黙だまって歩いている。これがいつでもこうなんだ。さびしいんだ。けれども何でもないんだ。
後うしろで誰だれかこごんで石ころを拾ひろっているものもある。小松ばやしだ。混こんでいる。このみちはずうっと上流じょうりゅうまで通っているんだ。造林ぞうりんのときは苗なえや何かを一杯つけた馬がぞろぞろここを行くんだぞ。
〔志戸平しどたいらのちかく豊沢とよさわ川の南の方に杉すぎのよくついた奇麗きれいな山があるでしょう。あすことこことはとても木の生え工合や較くらべにも何にもならないでしょう。向むこうは安山岩あんざんがんの集塊岩しゅうかいがん、こっちは流紋凝灰岩です。石灰せっかいや加里カリや植物養料しょくぶつようりょうがずうっと少いのです。ここにはとても杉なんか育そだたないのです。〕うしろでふんふんうなずいているのは藤原清作ふじわらせいさくだ。あいつは太田おおただからよくわかっているのだ。
〔尤もっとも向うの杉すぎのついているところは北側きたがわでこっちは南と東です。その関係かんけいもありますがそうでなくてもこっちは北側でも杉やひのきは生はえません。あすこの崖がけで見てもわかります。この山と地質ちしつは同じです。ただ北側なため雑木ぞうきが少しはよく育そだってます。〕いいや駄目だめだ。おしまいのことを云いったのは結局けっきょく混雑こんざつさせただけだ。云わないでおけばよかった。それでもあの崖はほんとうの嫩わかい緑みどりや、灰はいいろの芽めや、樺かばの木の青やずいぶん立派りっぱだ。佐藤箴さとうかんがとなりに並ならんで歩いてるな。桜羽場さくらはばがまた凝灰岩ぎょうかいがんを拾ひろったな。頬ほおがまっ赤かで髪かみも赭あかいその小さな子供こども。
雲がきれて陽ひが照てるしもう雨は大丈夫だいじょうぶだ。さっきも一遍いっぺん云ったのだがもう一度いちどあの禿はげの所ところの平ひらべったい松まつを説明せつめいしようかな。平ったくて黒い。影かげも落おちている。どこかであんなコロタイプを見た。及川おいかわやなんか知ってるんだ。よすかな。いいや。やろう。
〔さあ、いいですか。あすこに大きな黄色の禿はげがあるでしょう。あすこの割合わりあい上のあたりに松が一本生えてましょう。平ったくてまるで潰つぶれた蕈きのこのようです。どうしてあんなになったんですか。土壌どじょうが浅あさくて少し根ねをのばすとすぐ岩石でしょう。下へ延のびようとしても出来ないでしょう。横よこに広がるだけでしょう。ところが根と枝えだは相関現象そうかんげんしょうで似にたような形になるんです。枝も根のように横にひろがります。桜さくらの木なんか植うえるとき根を束たばねるようにしてまっすぐに下げて植えると土から上の方も箒ほうきのように立ちましょう。広げれば広がります。〕
「そんだ。林学でおら習ならった。」何と云いったかな。このせいの高い眼めの大きな生徒せいと。
坂さかになったな。ごろごろ石が落おちている。
「先生この石何て云うのす。」どうせきまってる。
〔凝灰岩。流紋りゅうもん凝灰岩だ。凝灰岩の温泉おんせんの為ために硅化けいかを受うけたのだ。〕
光が網あみになってゆらゆらする。みんなの足並あしなみ。小松の密林みつりん。
「釜淵かまぶちだら俺おらぁ前になんぼがえりも見だ。それでも今日も来た。」
うしろで云っている。あの顔の赤い、そしていつでも少し眼が血走ってどうかすると泣ないているように見える、あの生徒せいとだ。五内川ごないかわでもないし、何と云ったかな。
けれどもその語ことばはよく分っているぞ。よくわかっているとも。
巨礫きょれきがごろごろしている。一つ欠かいて見せるかな。うまくいった。パチンといった。〔これは安山岩あんざんがんです。上流かみの方から流ながれてきたのです。〕
すっと歩き出せ。関せきさんだ。「この石は安山岩であります。上流から流れてきたのです。」まねをしている。堀田ほっただな。堀田は赤い毛糸のジャケツを着きているんだ。物ものを言う口付くちつきが覚束おぼつかなくて眼めはどこを見ているかはっきりしないで黒くてうるんでいる。今はそれがうしろの横よこでちらっと光る。
そこの松林まつばやしの中から黒い畑はたけが一枚まい出てきます。
(ああ畑も入ります入ります。遊園地ゆうえんちには畑もちゃんと入ります)なんて誰だれだったかな、云いっていた、あてにならない。こんな畑を云うんだろう。おれのはもっとずっと上流の北上きたかみ川から遠くの東の山地まで見はらせるようにあの小桜こざくら山の下の新らしく墾ひらいた広い畑を云ったんだ。
「全体ぜんたいどごさ行ぐのだべ。」
「なあに先生さ従ついでさぃ行げばいいんだじゃ。」また堀田だな。前の通りだ。うしろで黄いろに光っている。みんな躊躇ちゅうちょしてみちをあけた。おれが一番さきになる。こっちもみちはよく知らないがなあにすぐそこなんだ。路みちから見えたら下りるだけだ。防火線ぼうかせんもずうっとうしろになった。
〔あれが小桜山だろう。〕けわしい二つの稜りょうを持もち、暗くらくて雲かげにいる。少し名前に合わない。けれどもどこかしんとして春の底そこの樺かばの木の気分はあるけれどもそれは偶然性ぐうぜんせいだ。よくわからない。みちが二つに岐わかれている。この下のみちがきっと釜淵かまぶちに行くんだ。もうきっと間違まちがいない。
小松こまつだ。密みつだ。混こんでいる。それから巨礫きょれきがごろごろしている。うすぐろくて安山岩だ。地質調査ちしつちょうさをするときはこんなどこから来たかわからないあいまいな岩石ものに鉄槌かなづちを加えてはいけないと教えようかな。すぐ眼めの前を及川おいかわが手拭てぬぐいを首くびに巻まいて黄色の服ふくで急いそいでいるし、云いおうかな。けれどもこれは必要ひつようがない。却かえって混雑こんざつするだけだ。とにかくひどく坂さかになった。こんな工合ぐあいで丁度ちょうどよく釜淵かまぶちに下りるんだ。遠くで鳥も鳴いているし。下の方で渓たにがひどく鳴っている。ことによるとここらの下が釜淵だ。一寸ちょっとのぞいてみよう。
黒い松まつの幹みきとかれくさ。みんなぞろぞろ従ついてくる。渓が見える。水が見える。波なみや白い泡あわも見える。ああまだ下だ。ずうっと下だ。釜淵は。ふちの上の滝たきへ平たいらになって水がするする急いで行く。それさえずうっと下なのだ。
この崖がけは急でとても下りられない。下に降おりよう。松林だ。みちらしく踏ふまれたところもある。下りて行こう。藪やぶだ。日陰ひかげだ。山吹やまぶきの青いえだや何かもじゃもじゃしている。さきに行くのは大内おおうちだ。大内は夏服の上に黄色な実習服じっしゅうふくを着きて結むすびを腰こしにさげてずんずん藪をこいで行く。よくこいで行く。
急にけわしい段だんがある。木につかまれ木は光る。雑木ぞうきは二本雑木が光る。
「じゃ木さば保たご附つくこなしだじゃぃ。」誰だれかがうしろで叫さけんでいる。どういう意味いみかな。木にとりつくと弾はね返かえってうしろのものを叩たたくというのだろうか。
光って木がはねかえる。おれはそんなことをしたかな。いやそれはもうよく気をつけたんだ。藪だ。もじゃもじゃしている。大内はよくあるく。
崖がけだ。滝たきはすぐそこだし、ここを下りるより仕方しかたない。さあ降りよう。大内はよく降りて行く。急だぞ。この木は少し太すぎる。灰はいいろだ。急だぞ、草、この木は細いぞ、青いぞあぶないぞ。なかなか急だ。大丈夫だいじょうぶだ。この木は切ってあるぞ。〔ほう、〕そこはあんまり急だ。
おりるのか。仕方ない。木がめまぐるしいぞ。「一人落おぢればみんな落ぢるぞ。」誰かうしろで叫んでいる。落ちてきたら全まったくみんな落ちる。大内がずうっと落ちた。
河原かわらまで行ってやっととまった。
おれはとにかく首尾しゅびよく降おりた。
少し下へさがり過すぎた。瀑たきまで行くみちはない。
凝灰岩ぎょうかいがんが青じろく崖と波なみとの間に四、五寸すん続つづいてはいるけれどもとてもあすこは伝つたって行けない。それよりはやっぱり水を渉わたって向むこうへ行くんだ。向うの河原は可成かなり広いし滝たきまでずうっと続いている。
けれども脚あしはやっぱりぬれる。折角せっかくぬらさないためにまわり道して上から来たのだ、飛石とびいしを一つこさえてやるかな。二つはそのまま使つかえるしもう四つだけころがせばいい、まずおれは靴くつをぬごう。ゴム靴によごれた青の靴下か。〔一寸ちょっと待まって、今渡わたるようにしますから。〕
この石は動うごかせるかな。流紋岩りゅうもんがんだかなりの比重ひじゅうだ。動くだろう。水の中だし、アルキメデス、水の中だし、動く動く。うまくいった。波なみ、これも大丈夫だいじょうぶだ。大丈夫。引率いんそつの教師が飛石をつくるのもおかしいがまたえらい。やっぱりおかしい。ありがたい。うまくいった。
ひとりが渡る。ぐらぐらする。あぶなく渡る、二人がわたる。
もう一つはどれにするかな もう四人だけ渡っている。飛石の上に両りょうあしを揃そろえてきちんと立って四人つづいて待まっているのは面白おもしろい。向うの河原のを動かそう。影かげのある石だ。
持もてるかな。持てる。けれども一番いちばん波の強いところだ。恐おそらく少し小さいぞ。小さい。波が昆布こんぶだ、越こして行く。もう一つ持って来よう。こいつは苔こけでぬるぬるしている。これで二つだ。まだぐらぐらだ。も一つ要いる。小さいけれども台にはなる。大丈夫だ。おれははだしで行こうかな。いいややっぱり靴ははこう。面倒めんどうくさい靴下はポケットへ押おし込こめ、ポケットがふくれて気持きもちがいいぞ。
素すあしにゴム靴ぐつでぴちゃぴちゃ水をわたる。これはよっぽどいいことになっている。前にも一ぺんどこかでこんなことがあった。去年きょねんの秋だ。腐植質フィウマスの野原のたまり水だったかもしれない。向むこうに黒いみちがある。崖がけの茂しげみにはいって行く。これが羽山はやまを越こえて台に出でるのかもわからない。帰りに登のぼるとしようかな。いいや。だめだ。曖昧あいまいだしそれにみんなも越えれまい。
「先生、この石何す。」一かけひろって持もっている。〔ふん。何だと思います。〕「何だべな。」〔凝灰岩ぎょうかいがんです。ここらはみんなそうですよ。浮岩質ふがんしつの凝灰岩。〕
みんなさっきはあしをぬらすまいとしたんだが日が照てるし水はきれいだし自分でも気がつかず川にはいったんだ。
もうずんずん瀑たきをのぼって行く。cascade だ。こんな広い平たいらな明るい瀑はありがたい。上へ行ったらもっと平らで明るいだろう。けれども壺穴つぼあなの標本ひょうほんを見せるつもりだったが思ったくらいはっきりはしていないな。多少失望しつぼうだ。岩は何という円くなめらかに削けずられたもんだろう。水苔みずごけも生はえている。滑すべるだろうか。滑らない。ゴム靴の底そこのざりざりの摩擦まさつがはっきり知れる。滑らない。大丈夫だいじょうぶだ。さらさら水が落おちている。靴はビチャビチャ云いっている。みんないい。それにみんなは後からついて来る。
苔がきれいにはえている。実じつに円く柔やわらかに水がこの瀑のところを削けずったもんだ。この浸蝕しんしょくの柔らかさ。
もう平らだ。そうだ。いつかもここを溯のぼって行った。いいや、此こ処こじゃない。けれどもずいぶんよく似にているぞ。川の広さも両岸りょうがんの崖、ところどころの洲すの青草。もう平らだ。みんな大分溯ったな。
〔ここをごらんなさい。岩石の裂さけ目に沿そって赤く色が変かわっているでしょう。裂け目のないところにも赤い条すじの通っているところがあるでしょう。この裂け目を温泉おんせんが通ったのです。温泉の作用で岩が赤くなったのです。ここがずうっとつちの底そこだったときですよ。わかりますか。〕
だまっている。波なみがうごき波が足をたたく。日光が降ふる。この水を渉わたることの快こころよさ。菅木すがきがいるな。いつものようにじっとひとの目を見つめている。
〔ここをごらんなさい。岩に裂さけ目があるでしょう。ここを温泉おんせんが通って岩を変質へんしつさせたのです。風化ふうかのためにもこう云いう赤い縞しまはできます。けれどもここではほかのことから温泉の作用ということがわかるのです。〕
ずいぶん上流じょうりゅうまで行った。実際じっさいこんなに川床かわどこが平たいらで水もきれいだし山の中の第一流だいいちりゅうの道路どうろだ。どこまでものぼりたいのはあたりまえだ。
向むこうの岸きしの方にうつろう。
「先生この岩何す。」千葉ちばだな。お父さんによく似にている。〔何に似てます。何でできてますか。〕だまっている。〔わかりませんか。礫岩れきがんです。礫岩です。凝灰質礫岩ぎょうかいしつれきがん。〕及川おいかわだな。〔いいですか。これは温泉おんせんの作用ですよ。この裂け目を通った温泉のために凝灰岩が変質へんしつを受うけたんです。〕
みんなわかるんだな。これは。向うにも一つ滝たきがあるらしい。うすぐろい岩の。みんなそこまで行こうと云うのか。草原があって春木も積つんである。ずいぶん溯のぼったぞ。ここは小さな段だんだ。
「ああ云う岩のすき間のごと何て云うのだたべな。習ならったたんとも。」
〔やっぱり裂け目です。裂け目でいいんです。〕習ったというのは節理せつりだな。節理なら多面ためん節理、これを節理と云うわけにはいかない。裂罅れっかだ。やっぱり裂け目でいいんだ。壺穴つぼあなのいいのがなくて困こまるな。少し細長いけれどもこれで説明せつめいしようか。elongatedpot-hole〔ここがどうしてこう掘ほれるかわかりますか。石ころ、礫がこれを掘るのです。そら水のために礫がごろごろするでしょう。だんだん岩を掘るでしょう。深ふかいところが一層いっそう深くなるはずです。もっと大きなのもあります。〕
日光の波、日光の波、光の網あみと、水の網。
「ほこの穴あなこまん円けじゃ。先生。」
ああいい、これはいい標本ひょうほんだ。こいつなら持もってこいだ。
〔さあ、見て下さい。これはいい標本です。そら。この中に石ころが入ってましょう。みんな円くなってるでしょう。水ががりがり擦こすったんです。そら。〕
実じつにいい礫れきだ。まっ白だ。まん円だ水でぬれている。取とってしまった。誰だれかがまた掻かき廻まわす。もうない。あとは茶色だし少し角もある。ああいいな。こんなありがたい。あんまり溯のぼる。もう帰ろう。校長もあの路みちの岐わかれ目で待まっている。
〔ほう。戻もどれ。ほう。〕向むこうの崖がけは明るいし声はよく出ない。聞えないようだ。市野川いちのかわやぐんぐんのぼって行く。〔ほう、〕「戻れど。お。」「戻れ。」
向いた向いた。一人向けばもういい。川を戻るよりはここからさっきの道へのぼったほうがいい、傾斜けいしゃもゆるく丁度ちょうどのぼれそうだ。〔みんなそこからあの道へ出ろ。〕
手を振ふったほうがわかるな。わかったわかったわかったようだ。市野川が崖の上のみちを見ている。
うしろの滝たきの上で誰だれか叫さけんでいる。大竹おおたけだ。「おら荷物にもつ置おいてきたがらこっちがら行ぐ。」よかろう。〔よおし。〕もう大竹が滝をおりて行く。すばやいやつだ。二、三人またついて行く。それからも一人おくれてひどく心配しんぱいそうに背中せなかをかがめて下りていく。斉藤貞一さいとうていいちかな。一寸ちょっとこっちを見たところには栗鼠りすの軽かるさもある。ほんとうに心配なんだ。かあいそう。
市野川やみんながぞろぞろ崖をみちの方へ上って行くらしい。
そうすればおれはやっぱり川を下ったほうがいいんだ。もしも誰か途中とちゅうで止っていてはわるい。尤もっとも靴下くつしたもポケットに入っているし必かならず下らなければならないということはない、けれどもやっぱりこっちを行こう。ああいい気持きもちだ。鉄槌かなづちをこんなに大きく振って川をあるくことはもう何年ぶりだろう。波なみが足をあらい水はつめたく陽ひは射さしている。
「先生ぁ、ずいぶん足ぁ早ぃな。」富手とみてかな、菅木すがきかな、あんなことを云いっている。足が早いというのは道をあるくときの話だ。ここも平たいらで上等じょうとうの歩道なのだ。ただ水があるばかり。
「先生、あの崖がけのどご色変かわってるのぁ何してす。」簡かんだ。崖の色か。
〔あれは向むこうだけは土が落おちたんです。滑すべって。〕
うん。あるある。これが裂罅れっかを温泉おんせんの通った証拠しょうこだ。玻璃蛋白石はりたんぱくせきの脈みゃくだ。
〔ここをごらんなさい。岩のさけ目に白いものがつまっているでしょう。これは温泉から沈澱ちんでんしたのです。石英せきえいです。岩のさけ目を白いものが埋うめているでしょう。いい標本ひょうほんです。〕みんなが囲かこむ。水の中だ。
「取とらえなぃがべが。」「いいや、此こ処ここのまんまの標本だ。」
「それでも取らえなぃがべが。」〔取ってみますか。取れます。〕
中々面倒めんどうだ。
「先生こっちにもっと大きなのあるんす。」あるある。これならネストと云いってもいい。これなら取れる。ハムマアの尖とがった方ではだめだ。平ひらたい方は……。
水がぴちゃぴちゃはねる。そっちの方のものが逃にげる、ふん。
〔水がはねますか。やっぱりこっちでやるかな。〕
白く岩に傷きずがついた。二所ふたところついた。
とれる。とれた。うまい。新鮮しんせんだ。青白い。
緑簾石りょくれんせきもついている。そうじゃないこれは苔こけだ。〔いいですか。これは玻璃蛋白石です。温泉から沈澱したのです。晶洞しょうどうもあります。小さな石英の結晶けっしょうです。持もっておいでなさい。〕
誰だれだ崖がけの上で叫さけんでいるのは。
「先生。おら河童捕かっぱどりしたもや。河童捕り。」藤原健太郎ふじわらけんたろうだ。黒の制服せいふくを着きて雑嚢ざつのうをさげ、ひどくはしゃいで笑わらっている。どうしていまごろあんな崖の上などに顔を出したのだ。
「先生。下りで行ぐべがな。先生。よし、下りで行ぐぞ。」
〔うん。大丈夫だいじょうぶ。大丈夫だ。〕おりるおりる。がりがりやって来るんだな。ただそのおしまいの一足だけがあぶないぞ。裸はだかの青い岩だし急きゅうだ。
〔おおい。もう少し斜ななめにおりろ。〕おりるおりる。どんどん下りる。もう水へ入った。〔どうしたのです。〕「先生。河童捕りあんすた。ガバンも何も、すっかりぬらすたも。」〔どこで。……〕
もう下ろう。滝たきに来た。下りているものもある。水の流ながれる所ところは苔こけは青く流れない所は褐色かっしょくだ。みんなこわごわ下りて来る。水の流れる所は大丈夫滑すべらないんだ。〔水の流れるところをあるきなさい。水の流れるところがいいんです。〕
あれは葛丸くずまる川だ。足をさらわれて淵ふちに入ったのは。いいや葛丸川じゃない。空想くうそうのときの暗くらい谷だ。どっちでもいい。水がさあさあ云いっている。「いいな。あそごの水の跳はね返かえる処ところよ。」
うん、いい早池峯山はやちねさんの七折ななおりの滝たきだってこんなのの大きなだけだろう。
もうみんなおりる。おれもおりる。たった一人あとからやって来る人がある。こわそうだ。
〔水の流れるところをあるくんです。水の流れる所を歩くんですよ。〕
そうだ。そうだ。いい気持きもちだ。
底本:「イーハトーボ農学校の春」角川文庫、角川書店
1996(平成8)年3月25日初版発行
底本の親本:「新校本 宮澤賢治全集」筑摩書房
1995(平成7)年5月
入力:ゆうき
校正:noriko saito
2010年9月5日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
田園迷信
宮沢賢治
十の蜂舎の成りしとき
よき園成さば必らずや
鬼ぞうかがふといましめし
かしらかむろのひとありき
山はかすみてめくるめき
桐むらさきに燃ゆるころ
その農園の扉を過ぎて
苺需めしをとめあり
そのひとひるはひねもすを
風にガラスの点を播き
夜はよもすがらなやましき
うらみの歌をうたひけり
若きあるじはひとひらの
白銅をもて帰れるに
をとめしづかにつぶやきて
この園われが園といふ
かくてくわりんの実は黄ばみ
池にぬなはの枯るゝころ
をみなとなりしそのをとめ
園をば町に売りてけり
底本:「新修宮沢賢治全集 第六巻」筑摩書房
1980(昭和55)年2月15日初版第1刷発行
入力:junk
校正:土屋隆
2011年5月14日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
電車
宮沢賢治
第一双の眼めの所有者
(むしゃくしゃした若い古物商。紋付と黄の風呂敷ふろしき)
第二双の眼の所有者
(大学生。制服制帽。大きなめがね。灰色ヅックの提鞄さげかばん)
第一双の眼(いや、いらっしゃい、今日は。よいお天気でございます。)
第二双の眼(何を哂わらってやがるんだ。)
(失礼いたしました。へいへい。えゝと、あなたさまはメフィストさんのご子息さん。今日はどちらへ。)
(何だ失敬な。)
(あ、左様で。あ、左様でございましたか。
これはどうもまことに失礼いたしました。たいへん飛び乗りがお上手でいらっしゃいます。)
(まだ何か云いってるのかい。失敬ぢゃないか。)
(さうさう。あなたはメフィストさんとはアウエルバッハ以来お仲がよろしくないのですな。ついおなりがそっくりなもんですから、まあちょっと相似形、さやう、ごく複雑な立体の相似形といふやうにお見受けいたしたもんですから。いや、どうもまことに失礼いたしました。)
(気を付けろ。間抜けめ。何だそのにやけやうは。)
(へいへい。なあにどうせ私などはへいへい云ふやうにできてるんですから。いや。それにしてもたゞ今は又もやとんだ無礼をはたらきました。ひらにひらにご容赦と。ところでお若いのにそのまん円な赤い硝子ガラスのべっ甲めがねはいかがでせうか。いかゞなもんでございませう。な。)
(気持ちの悪いやつだな。この眼鏡めがねかい。この眼鏡かい。おれは乱視だから仕方ないさ。)
(あっ、ああ、なる程乱視。乱視でしたか。いや、それならば仕方ござんせん。なるほど、なるほど。とにかくしかしそれにしてもと、あんまりお帽子の菱ひしがたが神経質にまあ一寸ちょっと詩人のやうに鋭く尖とがっていささかご人体にんていにかゝはりますが、)
(えい、畜生まだ何か云ってやがる。何だ、きさまの眼玉は黄いろできょろきょろまるで支那しなの犬のやうだ。ははあおれはドイツできさまの悪口を云ってやる。判わかるかい。
〝〔Was fu:r ein Gesicht du hast !〕〟おや。)
"(何だと。〝〔Nein, mein Ju:ngling, sage moch einmal, was fu:r ein Gesicht du machst !〕〟"
そっちの方で判るかい。おまへのやうな人道主義者は斯かう云ふもんだ。hast では落第だよ。)
(ふん。支那人と思ったらドイツとのあひの子かい。)